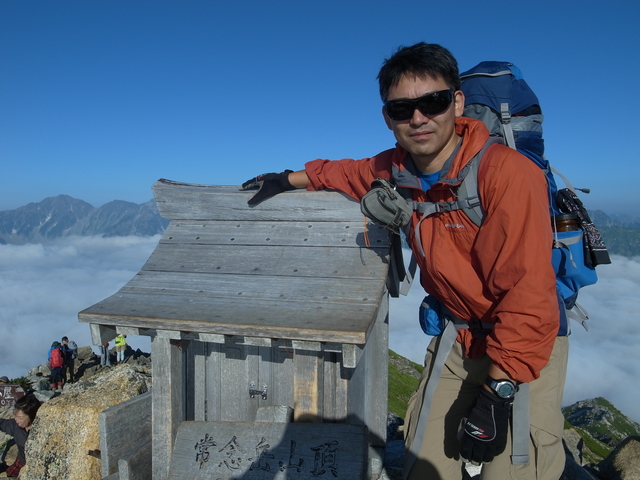世の中には、不条理な話があリますよね。
それで、暗いタイプの不条理な話と、明るいタイプの不条理な話があります。
暗いのは、カフカなんかがよく書いています。突然、虫になったり、いきなり裁判にかけられたり。
こっちはあんまり好きではないです。気が滅入ってくる。
でも、明るい不条理の話は、なんとなく滑稽なので、けっこう好きです。
では、ここで不条理を定義しておきましょう。
不条理とは、物事の筋道が通らず、予想外の方向にいくことです。
明るい不条理の小説を、ちょっと紹介しましょう。手元に本がなくて、うろ覚えですが。
夜中に寝てるのに、しつこく電話がなっている。何だと思って、起きて電話をとる。
「〇〇というところに住んでいる〇〇という者ですが、ラーメンを持ってきて、ガチャン」
女が勝手にそれだけ言って、電話を切ってしまう。
なんだよ。うちはラーメン屋じゃないんだよ。間違えてるじゃん電話番号。
あの人、あそこの通りの角の〇〇さんだよな。
まてよ、棚にラーメンがあるな、彼はそう思った。
それで、彼は台所に行って、ラーメンをせっせと作りはじめた。
話の筋としては、間違い電話なんだから、無視するのが普通です。
しかし、彼はラーメン屋でもないのに、自分でラーメンを作って持っていこうとしている。
ここが予想外の行動です。
もう一つ、「傘で私の頭を叩くのが習慣の男がいる」という題の小説です。
この短編小説は、控えめに言っても、最高です。マジで笑えます。
アルゼンチンの作家、フェルナンド・ソレンティーノの小説で、「SUDDEN FICTION 世界編」という超短編小説集にあります。
冒頭を紹介しましょう。
傘で私の頭を叩くのが習慣の男がいる。
男が傘で頭を叩きはじめてから、今日できっかり五年になる。はじめはとても我慢がならなかった。いまはもう慣れてしまった。
男の名前は知らない。私が知っているのは、彼が平凡な男で、無地の背広を着ていて、こめかみのあたりに白髪が見えはじめ、これといって特徴のない顔をしているということだ。
彼との出会いは、五年前のある蒸し暑い朝にさかのぼる。
パレルモ公園のベンチに座って、木陰でのんびり新聞を読んでいてときのことだった。
突然、何かが自分の頭に触れるのを私は感じた。それがこの、いま私がこうしてこれを書いているあいだも、機械的に、無表情に傘で私の頭を殴りつづけている男だったのである。
そのはじめての朝、私はカッとなって後ろをふり向いた。男はそのまま平然と私を叩きつづけた。
君、気でも狂ったのかね、と私は男に言った。彼は私の言葉が耳に入らぬ様子だった。
次に警官を呼ぶぞと脅した。だが男は一向に動じる気配もなく、相変わらず同じ動作をくりかえした。
私は立ち上がり、男の顔に一発思いっ切りお見舞いした。
明らかに彼はやわな男である。そう断言できるのは、いかに怒りの念に燃えたぎっていたとはいえ、私のパンチはそんなに強くないからだ。にもかかわらず、小さなうめき声を立てて、男は地面に崩れ落ちた。
そして、ただちに、懸命に力をふりしぼる様子で、男は立ち上がり、再び傘で私の頭を叩きはじめた、男は鼻血を出していた。私はその瞬間、私はなぜか彼が気の毒になってしまった。
こういう感じで、男は殴られて鼻血を出しても、走って逃げても、何をしても追ってきて傘で頭を叩き続けます。男は何も食べず、眠らず頭を叩き続けます。
ほんとおかしな話です。それで、最後のところです。
その反面、最近思ったのだが、彼に叩かれなくては、私はもはや生きていけないのではあるまいか。
あの恐ろしい予感がしばしば私を襲う。その頻度は増える一方だ。
すなわち、もしかするとこの男は私が彼をもっとも必要とするときに、いなくなってしまうのではあるまいか。
そうなれば、私は、かくも安らかな眠りを与えてくれる、あの柔らかな傘の打撃を感じることがなくなるだろう。
そう思うと気が滅入る。言いようもなく気が滅入るのである。
僕は不条理の中にある滑稽さのようなものを、すごく愛しています。
筋道の通らない変な状況のときに、それを受け入れて、とにかく笑い飛ばすのが、生きていくための技なんです。
とにかく、笑いましょう。怒ったりイライラしたらだめですよ。
死ぬなんてもってのほかです。