随分前に義母がブランデーで付けた梅酒(梅ブランデーって言うの?)を作ったと分けてくれました。
梅酒は何度も漬けているけど、甘いお酒の苦手な義父母は結局飲み切れず、古酒の消費で飽きてしまうのが悩みの種だったそうです。
義父母宅の庭に梅の木があるので、毎年いくらか梅が採れるので、少量でも簡単にできる梅酒を小瓶で作る事が多かったそうです。例年通り作っても飽きて古酒が増えるだけだろうと思った義母は教えてもらったのでブランデーで仕込んだ所、意外にも風味が良く、ン年物の梅酒が多々あるけれどそれとも違った味わいで、たまに飲むにはいいかな?と思ったとの事。
話の種に私もご相伴にあずかったのですが、なかなかのお味。義母曰く「分量も適当だし、お酒もあまったブランデーを使っただけだから」との事ですが、とっても気に入った私をみて「いくらか手をつけちゃったけれど、良かっら持って行って」と瓶ごとプレゼント。
下戸なので、そんなにジャンジャンはのめませんが、頂いてからチビチビと楽しませてもらったのを良く覚えています。
しかし最近、義父母宅の梅の木がそろそろ寿命なのか?どうも調子が悪いのです。結実すれば勿体ないので梅シロップや梅酒で使おうと思わずにはいられない義母からすると肩の荷が下りた感じかもしれませんが、結実そのものの数が激減し、結実しても虫食いだらけだったり小粒過ぎたりキズが多かったりで使えそうなのがほんの数粒という事も多々なんだとか。
「本当に寿命なのかどうかわからないけれど、落葉の始末も大変なので最近では特に短く刈り込んでいる事も手伝っているんじゃないかしら?」と義母は言っていました。なるほど・・・・老齢の2人暮らしなので、立木の世話は結構大変なのでしょう、他にも樹木は色々あるので、それらを順番に世話するとなると、短く刈り込みたくもなりますよね(^^;)お察しします。
そんな訳で、以前は黙っていても義父母宅に多種あった古梅酒も近年とうとう底をつきました。元々義父母は大して飲まないので大目にできた年はお友達などにおすそ分けしたりしていたから、残数は残り少なかったのですが、それでも何本も瓶に詰め直したものが戸棚に入ってましたが、今は見当たりません。
在庫もなければ新しいのも作らないので、最近私は梅酒に出会う事がなくなりました。
生前私の母は毎年何十キロと梅を漬けていました、しかし梅酒はあまりお好み(母も甘いの苦手^^;)でなかったようで、いくつかつけたのを見たことはあるのですが、ストックは殆ど見たことがなかったな~
毎年何十キロと大きな梅を馴染みの八百屋さんに注文して漬けるのですが、梅干しは時間と手間がかかる割に消費スピードがイマイチ・・・・結局実家には山ほど梅干しがありました。
母は片手間に
紫蘇ジュース
梅シロップ
カリカリ梅
小梅
梅酢
梅エキス(何か黒いヤツ)
梅サワー(ですかね?)
等々、色々手をだしたのですが、家族に人気だったのが梅シロップ(梅ジュース)でした。
家族は梅干しを食べる習慣がないので(お弁当用に使う位だった)梅干しの8割は母の知人友人に振舞われていました。しかし梅シロップだけは、作った傍から無くなるという盛況ぶり、私もよく飲みました(^^)
結婚してからは、母の気まぐれで少し作ったから~と梅干しとともに送られてくる事がありましたが、母はあまり好きじゃないせいか、リクエストが出ないと進んで作ってはくれなかったな~
カリカリ梅は私の好物だったので、1年おき位に送ってくれました。母のカリカリ梅は大粒の3L玉で作るので1つでとっても食べごたえがあるんです(^^;)出来立て直ぐは酸味が程よいので何個でも食べられるのですが、食感はそのままなのに何故かつかりが深くなると酸味が刺激的になります・・・・それはそれで美味しいのですが、最初のように何個も!とは行かなくなるのが非常に惜しい。
その為、食べ残しがあると翌年の新物からドンドン消費されて古株が残ってしまうので、毎年作っても前年の残りがある時は断っていました。その為、大体1年おき位のペースで我が家に届いていたのです。梅干しもそうなんだよね~(^^;)同居人も食卓で食べるという習慣がないので、お弁当にいれるとか調理に使うとかしないと本当に減らないんです、母の梅は美味しいんですが、減塩だからか?非常に酸味が強く、しかも大粒なので1個食べると満足してしまうんですよ(^^;)
母が亡くなってからも我が家には母の梅がずっとありました。冷蔵庫の専用スペースに小分けにして保存していたんです。
実家には大瓶で年代物が随分あったのですが、そんな大瓶は私では消化できないので、小瓶のものを密閉容器に移して持ち帰りました。その量でさえ、消化に数年かかりました、だって完全に無くなったのが去年の事でしたもん。
美味しい季節の風物詩、ありがとうございました(-人-)
そんな思い出を振り返っちゃう程、我が家ではここ数年梅加工品が見当たらなくなりました。
金柑が梅干し好き(母似か?)なので時折頼まれて市販の梅干しを買う位ですね~
でも、梅干しは母のようには作れる気がしないのですが、梅シロップや梅酒位なら私でもできるかな?と思ったので、ちょっとチャレンジしてみる事に。
本当は梅酒と梅シロップを小瓶で2つ位でいいかな?と思っていたのですが・・・・・母の梅加工品は金柑の記憶にもハッキリと残っているそうで、梅シロップを是非作ってほしい!と言われました。
その昔、一度だけ下処理して冷凍した実を義母にもらって梅シロップは作った事があります。一番面倒な所を義母がしてくれて私は瓶を消毒して砂糖と交互に瓶詰しただけだったんですが(^^;)それでも作った事になるんでしょうかね?
でも義母は簡単だから、次回はチャレンジしてみてね(^^)なんて言ってくれたんですが、当時は放っておいても梅加工品は何かしら届くのが普通だったし、既に梅干しやカリカリ梅なども保存に苦労していた位だったので、梅の実を購入してまでチャレンジする気にはなれませんでした。
でも今は梅加工品のストックは一切ございません!
今チャンレジしなくて、いつやるの?って事で迷う前に既成事実~とばかりに瓶を購入しました。
↓借用画像・深謝(-人-)

現居のキッチンは収納が少ないので、冷暗所を確保するのも中々難しいです(^^;)
床下収納はあるのですが、実はあまりそこに食品をストックするのは私が好まないので、できればキッチンカウンター等の引出しに収納したかったので、このようなスリム型を選びました。これなら完成後冷蔵庫に(冷蔵庫には入る余地は多々あるんですよ)入れる事もできるので、熟成期間だけ置く場所を確保すれば何とかなる!というのも私好みでした。
これは私が愛用しているスナップウェア(現フレッシュロック)のメーカーであるタケヤ化学さんからでている樹脂製の梅酒瓶です。軽量で丈夫だそうなので、チビで手の小さな私でも扱いやすそうな気がしました。
樹脂製なので熱湯消毒できないのが難ですが、アルコール消毒すればいいので、多分大丈夫(^^)
1本1.6リットルなので、2本買えばいいかな?とおもっていたのですが、漬かると目減りしますが、漬け始めは梅も氷砂糖もゴロゴロしているので、念のため3本購入。
果たしてこれでどの位できるのでしょうか?というか無事完成するのかな?
長くなったので、次回へ続きます。次回は梅の分量等を覚書として記載したいです。
梅酒は何度も漬けているけど、甘いお酒の苦手な義父母は結局飲み切れず、古酒の消費で飽きてしまうのが悩みの種だったそうです。
義父母宅の庭に梅の木があるので、毎年いくらか梅が採れるので、少量でも簡単にできる梅酒を小瓶で作る事が多かったそうです。例年通り作っても飽きて古酒が増えるだけだろうと思った義母は教えてもらったのでブランデーで仕込んだ所、意外にも風味が良く、ン年物の梅酒が多々あるけれどそれとも違った味わいで、たまに飲むにはいいかな?と思ったとの事。
話の種に私もご相伴にあずかったのですが、なかなかのお味。義母曰く「分量も適当だし、お酒もあまったブランデーを使っただけだから」との事ですが、とっても気に入った私をみて「いくらか手をつけちゃったけれど、良かっら持って行って」と瓶ごとプレゼント。
下戸なので、そんなにジャンジャンはのめませんが、頂いてからチビチビと楽しませてもらったのを良く覚えています。
しかし最近、義父母宅の梅の木がそろそろ寿命なのか?どうも調子が悪いのです。結実すれば勿体ないので梅シロップや梅酒で使おうと思わずにはいられない義母からすると肩の荷が下りた感じかもしれませんが、結実そのものの数が激減し、結実しても虫食いだらけだったり小粒過ぎたりキズが多かったりで使えそうなのがほんの数粒という事も多々なんだとか。
「本当に寿命なのかどうかわからないけれど、落葉の始末も大変なので最近では特に短く刈り込んでいる事も手伝っているんじゃないかしら?」と義母は言っていました。なるほど・・・・老齢の2人暮らしなので、立木の世話は結構大変なのでしょう、他にも樹木は色々あるので、それらを順番に世話するとなると、短く刈り込みたくもなりますよね(^^;)お察しします。
そんな訳で、以前は黙っていても義父母宅に多種あった古梅酒も近年とうとう底をつきました。元々義父母は大して飲まないので大目にできた年はお友達などにおすそ分けしたりしていたから、残数は残り少なかったのですが、それでも何本も瓶に詰め直したものが戸棚に入ってましたが、今は見当たりません。
在庫もなければ新しいのも作らないので、最近私は梅酒に出会う事がなくなりました。
生前私の母は毎年何十キロと梅を漬けていました、しかし梅酒はあまりお好み(母も甘いの苦手^^;)でなかったようで、いくつかつけたのを見たことはあるのですが、ストックは殆ど見たことがなかったな~
毎年何十キロと大きな梅を馴染みの八百屋さんに注文して漬けるのですが、梅干しは時間と手間がかかる割に消費スピードがイマイチ・・・・結局実家には山ほど梅干しがありました。
母は片手間に
紫蘇ジュース
梅シロップ
カリカリ梅
小梅
梅酢
梅エキス(何か黒いヤツ)
梅サワー(ですかね?)
等々、色々手をだしたのですが、家族に人気だったのが梅シロップ(梅ジュース)でした。
家族は梅干しを食べる習慣がないので(お弁当用に使う位だった)梅干しの8割は母の知人友人に振舞われていました。しかし梅シロップだけは、作った傍から無くなるという盛況ぶり、私もよく飲みました(^^)
結婚してからは、母の気まぐれで少し作ったから~と梅干しとともに送られてくる事がありましたが、母はあまり好きじゃないせいか、リクエストが出ないと進んで作ってはくれなかったな~
カリカリ梅は私の好物だったので、1年おき位に送ってくれました。母のカリカリ梅は大粒の3L玉で作るので1つでとっても食べごたえがあるんです(^^;)出来立て直ぐは酸味が程よいので何個でも食べられるのですが、食感はそのままなのに何故かつかりが深くなると酸味が刺激的になります・・・・それはそれで美味しいのですが、最初のように何個も!とは行かなくなるのが非常に惜しい。
その為、食べ残しがあると翌年の新物からドンドン消費されて古株が残ってしまうので、毎年作っても前年の残りがある時は断っていました。その為、大体1年おき位のペースで我が家に届いていたのです。梅干しもそうなんだよね~(^^;)同居人も食卓で食べるという習慣がないので、お弁当にいれるとか調理に使うとかしないと本当に減らないんです、母の梅は美味しいんですが、減塩だからか?非常に酸味が強く、しかも大粒なので1個食べると満足してしまうんですよ(^^;)
母が亡くなってからも我が家には母の梅がずっとありました。冷蔵庫の専用スペースに小分けにして保存していたんです。
実家には大瓶で年代物が随分あったのですが、そんな大瓶は私では消化できないので、小瓶のものを密閉容器に移して持ち帰りました。その量でさえ、消化に数年かかりました、だって完全に無くなったのが去年の事でしたもん。
美味しい季節の風物詩、ありがとうございました(-人-)
そんな思い出を振り返っちゃう程、我が家ではここ数年梅加工品が見当たらなくなりました。
金柑が梅干し好き(母似か?)なので時折頼まれて市販の梅干しを買う位ですね~
でも、梅干しは母のようには作れる気がしないのですが、梅シロップや梅酒位なら私でもできるかな?と思ったので、ちょっとチャレンジしてみる事に。
本当は梅酒と梅シロップを小瓶で2つ位でいいかな?と思っていたのですが・・・・・母の梅加工品は金柑の記憶にもハッキリと残っているそうで、梅シロップを是非作ってほしい!と言われました。
その昔、一度だけ下処理して冷凍した実を義母にもらって梅シロップは作った事があります。一番面倒な所を義母がしてくれて私は瓶を消毒して砂糖と交互に瓶詰しただけだったんですが(^^;)それでも作った事になるんでしょうかね?
でも義母は簡単だから、次回はチャレンジしてみてね(^^)なんて言ってくれたんですが、当時は放っておいても梅加工品は何かしら届くのが普通だったし、既に梅干しやカリカリ梅なども保存に苦労していた位だったので、梅の実を購入してまでチャレンジする気にはなれませんでした。
でも今は梅加工品のストックは一切ございません!
今チャンレジしなくて、いつやるの?って事で迷う前に既成事実~とばかりに瓶を購入しました。
↓借用画像・深謝(-人-)

現居のキッチンは収納が少ないので、冷暗所を確保するのも中々難しいです(^^;)
床下収納はあるのですが、実はあまりそこに食品をストックするのは私が好まないので、できればキッチンカウンター等の引出しに収納したかったので、このようなスリム型を選びました。これなら完成後冷蔵庫に(冷蔵庫には入る余地は多々あるんですよ)入れる事もできるので、熟成期間だけ置く場所を確保すれば何とかなる!というのも私好みでした。
これは私が愛用しているスナップウェア(現フレッシュロック)のメーカーであるタケヤ化学さんからでている樹脂製の梅酒瓶です。軽量で丈夫だそうなので、チビで手の小さな私でも扱いやすそうな気がしました。
樹脂製なので熱湯消毒できないのが難ですが、アルコール消毒すればいいので、多分大丈夫(^^)
1本1.6リットルなので、2本買えばいいかな?とおもっていたのですが、漬かると目減りしますが、漬け始めは梅も氷砂糖もゴロゴロしているので、念のため3本購入。
果たしてこれでどの位できるのでしょうか?というか無事完成するのかな?
長くなったので、次回へ続きます。次回は梅の分量等を覚書として記載したいです。



















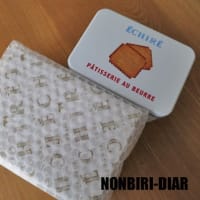
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます