意外と簡単!? 食卓が華やぐ、りんごの飾り切り4選

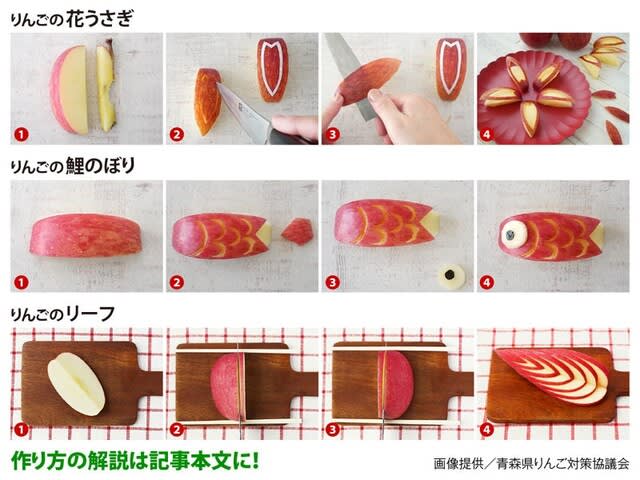
花うさぎの作り方
(1)8等分にしてから芯を切り取る
(2)皮を花びら型に切り抜く
(3)お尻の方からヘタの方に向かって8割皮をむいてストップし、切り抜いた部分を取り出す
(4)完成。切り抜いた部分も花びら型なので、飾ると華やかに
鯉のぼり
(1)花うさぎと同様、8等分してから芯を切り取り、横向きに置く
(2)ナイフの刃先を使い、エラとうろこの形に切り取り、ひらがなの「く」の字に深さ2mm程度の切込みを入れ、皮を取り除く。これが尾になる
(3)薄く切ったりんごを丸く型抜きし、そこに海苔を丸く切ってのせて目玉にする
(4)完成。王林などを混ぜるとぐっとかわいくなる
リーフ
(1)りんごを縦1/4に切ってまな板の上に置く
(2)りんごの上下に割り箸を置く。割り箸はりんごを切り落とさないようにするため。5mm幅でナイフを入れ、割り箸にあたるところまで切る
(3)切ったらりんごを90度転がし、反対側も同様に左右対称に切る、を繰り返す
(4)全部切れたら同じ幅に少しずつずらして完成
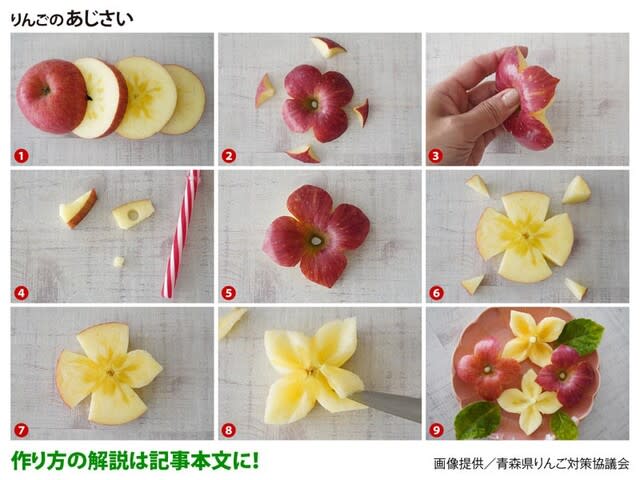
(1)りんごを横に4等分する。
(2)軸がついている方とお尻の方をV字に4ヵ所切り取る。
(3)花びらの先が尖がるように整える。
(4)りんごの端材をスライスしストローでくり抜く
(5)中心部にストローなどでくりぬいた果肉をのせる。
(6)果肉の方を4ヵ所V字に切り取る。
(7)4つの花びらの先が尖がるようにナイフで切り取る。
(8)刃先で花びらの中をえぐるように切り取り、芯の部分に4と同様にくりぬいた果肉をのせる。
(9)あじさいのように並べて完成。



























