特別展覧会「japan 蒔絵」
~ 宮殿を飾る・東洋の燦めき ~
*会場:サントリー美術館(会期終了)
*会期:2008年12月23日~2009年1月26日
<mimifukuから一言。>
まず、
・ジャパン(Japan)の語源となる、
・ジパング(Zipangu)について調べてみましょう。
*ジパング(Zipangu):広辞苑より
マルコポーロの「東方見聞録」にCipanguとして日本に擬定された地名。
中国の東1500カイリの海中で<黄金に富む>と表記されている。
<ジャパン>はこの語から転じたもの。
実際にマルコ・ポーロ(1254年~1324年)は、
日本には渡来していないと言う説が有力なようで、
中国やモンゴルで伝え聞いた噂として、
海の向こうの日本のことを知ったと考えられています。
<日本が黄金の国>とされるのは、
現在の歴史学では通説となっている当時の豊富な日本の金の埋蔵量ではなく、
おそらく当時完成されていた障壁や工芸に施された金の加工技術の輝きでしょう。
マルコポーロは1274年から~1294年頃に元~中国を旅したとされ、
1274年、1281年と2度に渡る蒙古襲来の時代以前の日本美術の成立を、
学習すれば<黄金の国>の意味を理解できるでしょう。
・岩手:中尊寺金色堂の建立=1124年。
・京都:三十三間堂の千手観音=1164年創建。
・奈良~平安~鎌倉へと続く蒔絵技法の確立。
・平安仏画や経典、歌集に散りばめられた金砂子や截金の技法。
・金泥による文字や絵画の表現。
・鎧、兜等、武具にまで使用された金工芸。
さらに文化遺産に乏しく確証はありませんが、
・金糸を使った衣装や、
・金箔が施された屏風などが、
多く制作されていたのではないかと考えられます。
<少ない資源を細工し全面に塗布・装飾された黄金の世界>
それはまさに<黄金の国>として諸外国の方々の目に映ったのではないか?
その中で世界の目が日本の美として注目したのが蒔絵の技法。
漆、または漆器を<Japan>とする解釈もありますが、
私は、
漆工芸の多彩さと蒔絵装飾の持つ順応性(多様性)こそが、
西欧にとっての輸入品<ジャパン>の語源ではないかと考えていますし、
西欧人の持つ強いイメージ、
<黄金の国:ジパング>の幻想を具現化したのも、
多くの金細工を制作した日本の職人達の技術だと感じます。
逆に言えばシルクロードの時代から続く東洋貿易を越えて、
<西洋に直接輸出された最初の日本の技術こそが蒔絵(漆工芸)>
なのではないかと考えています。
つまり、
中国から持ち込まれた漆の技術(水に弱い木の性質を保護する技術)が、
我国で成熟し日本人の美意識に応じた装飾嗜好(主として権力者の意図)が、
金細工技術の向上につながり日本独自のオリジナル性を高めていった。
その技術は、
日本に於ける最初の輸出産業品として大航海時代のヨーロッパに紹介され、
為替や貨幣が確立されていない時代の世界貿易の交換品(物々交換)として、
交換され世界へ流通していく。
オリジナリティの高い日本の精密細工技術は、
大航海時代以後のヨーロッパでも変わらず高く評価され、
“日本の産業技術に対する高い信頼と評価は、
その後の世界の工場としての日本の未来を暗示していた”
のかも知れない。
そんな風に展覧会に目を向けると違った見方ができますし、
情報のない当時の国際社会の中で、
地名や人種としての日本(Japan)に対する認識よりも、
中国(China=チャイナ)の陶器同様に、
西欧人にとっての輸入産業品(としての日本の技術)こそが、
Japanであったと推測することも容易です。
つまり、
<Japanの言葉の持つ真の意味=高度な産業技術。>
以上は、私の独断的な見解ですが、
この展覧会でその推測を遠からず感じることができるでしょう。
・Japan(ジャパン=漆工芸)の語源を探ると同時に、
・輸出大国日本の起源(ルーツ)を探る旅。
私は京都国立博物館で既にこの展覧会を見ています。
決して最上級の技術を駆使した蒔絵工芸の傑作
~武家の調度品や明治の細密精緻な工芸品等~
が揃っているわけではないですが、
可愛い小物やヨーロッパの王室を飾った別注の調度品の数々。
また、
大航海時代のキリスト教と日本工芸とのかかわりや
江戸時代の町人文化の豊かさも知る機会になると思います。
そんな展覧会です。
お正月は1月2日から開館されているようなので、
お時間があれば、ぜひご覧ください。
<関連記事>
*さよなら京都国立博物館(平常館:建て替え)~2008年12月~
→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/49fafdbaf0f33099445b591d2ce252e6
~下記、サントリー美術館ホームページより転載。
日本の漆工芸は世界的に名高く、
陶磁器を“china”と呼ぶように漆器が“japan”と呼ばれたことが、
その浸透ぶりを象徴しています。
特に、
金銀を用いて漆黒の地をきらびやかに飾る蒔絵(まきえ)は、
桃山時代にはじめて来日したヨーロッパの人々を魅了し、
特注品が作られるほどになりました。
海外での蒔絵の人気はその後も途絶えることなく、
遠く東洋からもたらされた贅沢な品として珍重され、
フランス王妃マリー・アントワネットら王侯貴族は競って蒔絵を求め、
宮殿を飾りました。
本展ではフランスのヴェルサイユ宮殿美術館などが所蔵する、
アントワネットのコレクションをはじめ、
イギリスの貴族の館バーリーハウス、
スウェーデン王室、
ザクセン公アウグスト強王ゆかりの宮殿など、
ヨーロッパ各地に残された貴重なコレクションに、
国内で所蔵される国宝、重要文化財を含む名品の数々を加えた、
約240件の優品を一堂に集めて展示します。
日本で生まれ西洋人を魅了した繊細で華麗な黄金の美。
蒔絵の歴史をグローバルな視点から見つめる初めての大規模な展覧会です。
※作品保護のため、会期中展示替えを行います。
第1章:中世までの日本の蒔絵。
日本で独自に発展した漆工芸・蒔絵は、
極めて膨大な手間を要するため大変高価なもので、
16世紀までは寺社や貴族など一部の特権階級のための調度品でした。
ここでは、
10世紀から16世紀にかけての国宝、重要文化財を含む優品で、
輸出漆器誕生以前の蒔絵の歴史を辿ります。
第2章:西洋人が出会った蒔絵。
~ 高台寺蒔絵 ~
桃山時代。
豪壮好みの武将たちは内装を金碧障壁画で彩り、
柱や框(かまち)、調度品を蒔絵で飾りました。
新興の武士たちの需要に応えそれまで蒔絵を施されることのなかった、
日用の膳椀類や建築部材を絢爛かつ手早く作るよう工夫したのが、
「高台寺蒔絵」です。
ポルトガル人が種子島に漂着し、
日本が初めて西洋世界と出会ったちょうどこの頃、
来日した西洋人が目の当たりにした「高台寺蒔絵」の美。
すなわち、
黒漆の面に金粉を蒔くことで文様を浮かび上がらせる、
勇壮絢爛な漆黒と黄金の美をご覧いただきます。
第3章:大航海時代が生み出した蒔絵。
~ 南蛮漆器 ~
16世紀後半に「南蛮人」と呼ばれるポルトガル人やスペイン人が来日しました。
キリスト教の宣教師たちや大航海時代にアジア各地に貿易拠点を築き、
寄港地それぞれの工芸技術で宗教用具や家具を作らせていた商人たちは、
蒔絵の美しさに魅了され漆職人たちに祭礼具や家具を注文しました。
彼らが着目したのは、
当時の日本であまり作られていなかった貝を磨いて貼り付ける「螺鈿」という技法。
蒔絵の装飾に螺鈿を加えより豪華な漆器を作らせました。
南蛮人と日本文化の交流により誕生したのが、
最初の輸出漆器である「南蛮漆器」です。
第4章:絶対王政の宮殿を飾った蒔絵。
~ 紅毛漆器 ~
17世紀の江戸幕府の鎖国政策により、
ヨーロッパ諸国ではオランダの東インド会社だけが、
長崎出島での交易を許されました。
それに伴い輸出漆器の様式も変化します。
すきまなく蒔絵と螺鈿で器面を埋め尽くした「南蛮漆器」から、
黒漆の余白を生かした絵画的表現の蒔絵へ。
この新しいスタイルの蒔絵は、
オランダ人を「紅毛人」と呼んだことに由来し「紅毛漆器」と呼ばれます。
ヨーロッパの王侯貴族は彼らの富と権力の象徴として競って蒔絵を集め、
蒔絵を一部に組み込んだバロックやロココ様式の家具が、
ヨーロッパで作られるようになりました。
第5章:蒔絵の流行と東洋趣味。
蒔絵が貴族の居室を飾るようになった背景には、
後に「シノワズリ」と呼ばれることになる東洋趣味の流行がありました。
ヨーロッパにはない異文明の物事・風俗
~それらは“東洋”としてひとまとめにされていました~
に対して抱いた憧れや好奇心が18世紀のロココ趣味と融合したのです。
シノワズリの流行は自らの装飾美術の伝統に東洋を組み入れ、
さらに自らが思い描いた東洋風のイメージをもとに商品を発注することで、
東洋の様式に変化をもたらすことにも発展したのです。
第6章:王侯のコレクションと京の店先。
フランス国王ルイ16世王妃マリー・アントワネットは、
たいへんな蒔絵のファンでした。
質・量ともにヨーロッパ随一を誇るアントワネットの蒔絵コレクションの中には、
輸出用の注文品ではなく上質でありながらも、
京の店先で選ばれ買われたと考えられるものもあります。
本展では特別に、
それらが伝わるヴェルサイユ宮殿美術館、ギメ美術館所蔵の小品とあわせて、
スウェーデン王室、ザクセン公アウグスト強王ゆかりの宮殿、
イギリス貴族の館バーリーハウスなどに伝わる同種の小品コレクションを、
一堂に展示します。
日本にほとんど残っていないまるでタイムカプセルのように、
ヨーロッパで大切に伝えられてきた貴重な小品をお楽しみください。
第7章:そして万国博覧会。
産業革命を遂げたイギリスでは、
19世紀半ばに登場した新興ブルジョワジーが、
絶対王政期の東洋趣味を手本とした蒔絵を愛好し、
亡命貴族が手放した17、18世紀の作品や、
万国博覧会に出品された作品などを購入しました。
折りしも日本では、
幕藩体制が滅び蒔絵師の仕事が激減していました。
このとき活路となったのが300年にわたって開拓されてきた、
蒔絵の海外需要であり、
新しい需要者に向けて技術の粋を集めた、
精細な作品が輸出されることになったのです。










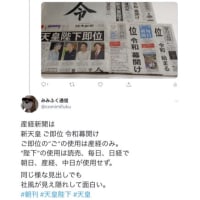

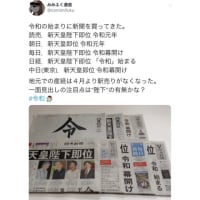

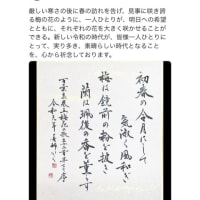
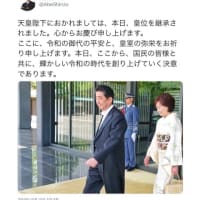



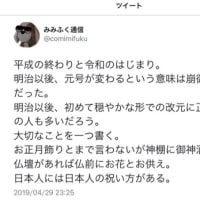







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます