日曜美術館
『写真家:セバスチャン・サルガド』
~極限に見た生命の美しさ~
放送局 :NHK教育/デジタル教育1
放送日 :2010年 1月17日(日)
放送時間 :午後8時~午後8時45分(放送終了)
放送局 :NHK教育/デジタル教育1
放送日 :2009年12月 6日(日)
放送時間:午後8時~午後8時45分(放送終了)
番組HP→ http://www.nhk.or.jp/nichibi/weekly/2009/1129/index.html
<mimifukuから一言>
セバスチャン・サルガド。
その名前する聞いたことのない人が殆どだと思います。
サルガドの写真が美術に当たるかどうかにも疑問を感じます。
例えばメープルソープのように作画を意図とした耽美表現や、
マン・レイの時代の創作写真黎明期の作品群などは、
実験的で美術作品としての評価は高まるばかりです。
セバスチャン・サルガド。
ロバート・キャパ、アンリ・カルティエ・ブレッソン、エリオット・アーウィット。
著名な報道カメラマン達を多数所属した写真家集団:マグナムに在籍する、
現役のカメラマン。
最も世間で知られている写真は、
1991年の湾岸戦争の折にクウェートの破壊された油田地帯で撮影された、
一連の写真群は誰もが一度は目にしたことがあるのではないかと感じます。
1993年に東京国立近代美術館で開催された、
『人間の大地:労働』展を観に行った記憶があります。
<消えいく肉体労働>とのタイトルとは裏腹に、
失意の目をし疲れきった様子の被写体の人物。
報道写真にありがちな悲劇の瞬間ではないのですが、
貧しさの中で懸命に働く姿やタコ部屋を思い浮かべる強制労働の実態。
昨年ブームになった『蟹工船』のワンシーンを髣髴させるような途上国の現状。
写真集『人間の大地・労働』(サルガードと表記)は、
岩波書店から大型本として出版され、
その中でサルガド自身が、
「世界人口の中で一握りの人間(先進国)が大量消費をし、
その他の大勢(途上国)の人々が消費する可能性が絶たれながらも、
厳しい労働条件の中で毎日毎夜働いている。」
と語っています。
サルガドの写真集『人間の大地・労働』が物語っているものは、
「労働の歴史(社会発展の歴史)は厳しい肉体労働の歴史であり、
現状(1990年頃)の途上国の実態は総べての先進国の過去の姿であり、
産業革命の発達は“消えゆく肉体労働”に寄与した。」
さらに、
「肉体労働の歴史は同時に絶えず危険と背中合わせに存在し、
途上国に於ける過酷な労働は多くの場合に詐取をともない、
幸せになるべき人間達に幸せになるチャンスは与えられない。」
そんな風に感じられました。
2009年10月24日~12月13日まで東京恵比寿の東京都写真美術館では、
現在のセバスチャン・サルガドを知ることのできるアフリカ展を開催中。
今回の日曜美術館はその展覧会の開催に合わせた特別企画。
番組ではサルガド自身が出演しインタビューに答えます。
21世に入り急速に発達したデジタル処理される写真技術の進化や、
気軽に誰もが報道(プチ)カメラマンになれるデジタル映像社会の中で、
本物(求道者)のカメラマンが写真を通して伝えたいと願うことは何か?
悲しみや失意の中に見出すことのできる人間の尊厳。
番組タイトルの“極限に見た生命の美しさ”は、
人が生きる証(あかし)としての労働の尊さ。
そんなことが表現されているのではないかと思います。
写真家サルガドが捉えた“瞬間の切り取り=途上国の実態”と、
戦前・戦後の日本でも実際に存在した危険な労働や貧困との共通点。
戦後の日本や途上国での何もない環境の中で“たくましく生きる姿勢”と、
有り余った商品の中で目標もなく“鬱々とする病める先進国”の実態。
そんなことが感じられればと考えています。
<番組内容と感想>
番組は制作年代順の作品ごとに紹介されました。
第1章:「SAHEL(大干ばつ)」
第2章:「WORKERS(労働者)」
第3章:「EXODUS(脱出)」
第4章:「GENESIS(起源)」
私が放送前に記述した文書は、
「WORKERS」について。
「SAHEL」については断片しか知りませんし、
「EXODUS」や「GENESIS」の認識はありませんでした。
「EXODUS」でのルワンダの悲劇については、
ニュース・ソースとしての記憶しかありませんし、
「GENESIS」については活動すら知りませんでした。
“サルガドの作品は悲惨な状況も神々しい絵画のような美しさで切り取る。”
とNHKの番組紹介で記入されており当初意味が理解できませんでした。
「EXODUS」。
番組が進行するに連れて鑑賞者の目に入り込む光の表現に、
サルガドの写真が持つ絵画性を感じるのだろうと気付きました。
ただし番組中サルガド自身が触れているように、
問題を告発するための報道写真に作画意識は不要だと語っています。
「GENESIS」。
2004年から撮影が始まった起源を探る旅。
人物ではなく自然を対象にした風景写真の数々には、
これまでの報道写真にはないアート性を感じます。
私のお気に入りはゴリラの正面写真。
まるで肖像画のように静止したゴリラの表情に、
人間との共通性を感じない人はいないでしょう。
GENESIS=生命の起源。
環境の変化と地球生命体の関わり。
サルガドは、
「(地球上の)すべての生命の尊厳を尊重することが大切です。
人間が生かされていることを自覚せずに他の生命を疎んじるなら、
いつの日か地球から見放されることでしょう。」
の言葉で番組を締めました。
<サルガドが語った印象的な言葉>
*荒木経惟:写狂人の旅/アラーキーと歩く4日間。
→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/86cad3dc01f1f2afb20a5eb134e8f748
~以下NHKホームページより記事転載。
*写真にはそれ自体に力があります。
言葉(日常会話)で訴えかけるには翻訳が必要ですが、
写真は言葉を必要としない誰もが理解できる、
統一した言語を持っています。
*私達フォト・ジャーナリストは、
告発するために活動しています。
報道カメラマンとジャーナリストの違いは、
問題の瞬間を撮影するだけでなく、
告白すべき対象の場で実際に滞在し、
生活を共にすることで、
問題点を洗い出します。
*難民達と共に生活し長い時間撮影している中で、
自然が放つ一瞬の光が偶然に写し出される事があります。
しかし、
私は光が表現する美しさについて何も感じてはいません。
自然が放つ光が人間の尊厳を浮き彫りにするのです。
光は世界中のあらゆる国で存在するのです。
劇的(ドラマチック)な悲劇は写真家が作り出すものではなく、
そこにある自然が作り出すのです。
*尊厳とはどんな状況下でも人として生きていること。
悲惨に見える難民達にも生きる豊かさがあります。
ここに写し出された人々は、
誰かが死んだらその人のために嘆き悲しみ
苦しんでいる人がいれば皆が助け合うのです。
逆に都会で暮らす民の貧しさに孤独や孤立があります。
そのことの方が悲惨かもしれません。
<関連記事>
*巨匠たちの肖像:写真家・土門拳~仏を睨む目~
→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/2cd8159db9d06052202dbd9f7fef7a75
世界的報道写真家:セバスチャン・サルガド。
1944年ブラジルに生まれ。
経済学を学んだ後1973年に写真家に転身。
アフリカの干ばつや飢餓、世界の労働者の実態、移民や難民などを、
経済学者ならではの分析力と地球規模の視点でとらえてきた。
サルガドの作品は、
悲惨な状況も神々しい絵画のような美しさで切り取る。
『私はどんな過酷な状況の中でも生きようとする人間の尊厳を撮っているのだ』
被写体と一体となり寄り添うようにカメラを向けるサルガドは、
絶望の果てには必ず希望があることを伝えている。
現在、
サルガドは自ら最後のライフワークと位置づける、
「GENESIS(起源)」の撮影に取り組んでいる。
地球創生のころと変わらぬような無垢(むく)な自然の姿を探し、
生命の起源をたどるという挑戦。
環境問題に警鐘を鳴らし未来に生きる人々へのメッセージでもある。
番組では、
30年以上撮り続けてきたアフリカの作品を中心に、
「WORKERS(労働者)」
「EXODUS(脱出)」など代表作を紹介。
交流のあった元国連難民高等弁務官事務所・緒方貞子さんの、
インタビューなどを交えて紹介する。
【ゲスト】 写真家:セバスチャン・サルガド
【キャスター】姜 尚中、中條 誠子










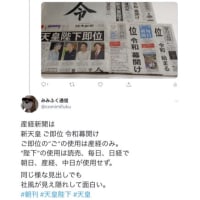

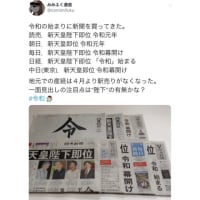

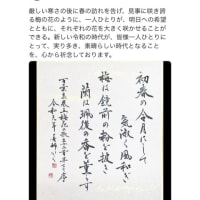
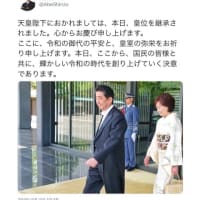



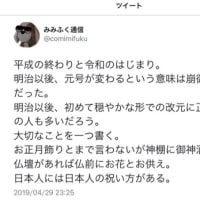






告発するために活動しています。
報道カメラマンとジャーナリストの違いは、
問題の瞬間を撮影するだけでなく、
告白すべき対象の場で実際に滞在し、
生活を共にすることで、
問題点を洗い出します。
ロバート・キャパは報道カメラマンで、サルガドはジャーナリストと言う事でしょうか?
コメントありがとうございます。
サルガド自身が語った言葉は私も強く印象に残りました。
おそらくサルガドが言いたかったのは、
“真実を知る最良の方法はその場で生活すること。”
なのだと感じます。
悲惨な瞬間を切り取り世界に発信することで問題提起をする。
報道カメラマンに必要なことは、
決定的瞬間をいち早く大衆に伝達すること。
その前後の背景やそれに至った説明は、
カメラマンの仕事ではなく記者の仕事。
ジャーナリズムが伝達する本質には、
<報道・解説・論評等>があります。
・報道は目の前で起きたことを客観的に伝えることであり、
速度性が求められます。
・解説はその伝達事項の成り立ちや背景を解り易く大衆に説明。
・論評は伝達事項について、
報道媒体やジャーナリストが自分達の意見を述べること。
写真(や映像)は伝達事項の証明(証拠)としての役割が高く、
日本の新聞やテレビ等の主要媒体は読者(視聴者)が、
不愉快に感じる悲惨な事実の実写を自主規制していますし、
亡くなった方やご家族の気持ちに配慮があります。
~数字追求のための配慮不足も指摘できますが…。
雑誌などでは悲惨な現場を生々しく写し出されることも多く、
真実の瞬間を求める読者の気持ちに応えることで、
部数を伸ばす戦略も見られます。
掲載される写真の中には興味本位ではなく、
ジャーナリズムの本質を感じるものも多くあります。
サルガドが語る“共に生活する”ことは、
写真が持つ“瞬間的な切り取り”だけに真実を求めるのではなく、
難民と暮らしを共にすることで貧困と困難の本質に迫る。
例えば大きな自然災害が起きると、
衝撃的な映像が数々とテレビ画面に映し出されます。
生死の瞬間に人々は注目しますし、
災害の悲惨さを大きく伝えることが、
最善の問題提起と考えられるからです。
しかし大きな災害の後の生活。
その事が災害地で暮らす人々にとっての大きな問題であり、
瞬間の後の復興への道筋や借金問題や大黒柱を失った悲しみ。
ジャーナリズムとは、
大衆が関心を示す瞬間後の問題点を丁寧に救い上げることに通じます。
サルガドがフォト・ジャーナリストとしての誇りを語っているのは、
問題点の本質は瞬間では終わらないことを伝えるためなのでしょう。
例えば職業カメラマンは決定的瞬間を求めることに情熱を傾けるあまり、
問題の背景や様々な人々の立場を反故にして撮影することもあると感じます。
それは同時にお金と引き換える事が目的手段となり、
パパラッチのような人達も多く排出しました。
“決定的な瞬間”はブレッソンの有名な言葉ですが、
本質的なジャーナリズムに決定的な瞬間などありません。
そのことをサルガドは伝えたかったのではないか?
そんなことを感じます。
「ロバート・キャパは報道カメラマンで、
サルガドはジャーナリストと言う事でしょうか?」
の疑問に答える解答は持ちえません。
しかしサルガドが写真を通じて、
“瞬間後の真実(長い道のり)を追究している”
だろう事は想像できます。
ロバート・キャパにしても、
滞在時間は短いもののあらゆる戦地に赴き、
自分の命と引き換えに真実を伝えるために奔走した事実。
キャパの生き方に、
“戦争ジャーナリストとしての使命”
を感じることもできるでしょう。
「ロバート・キャパは報道カメラマンで、
サルガドはジャーナリストと言う事でしょうか?」
それは見る者の判断に委ねられると思います。