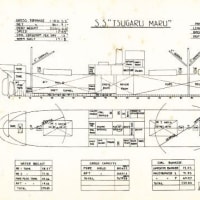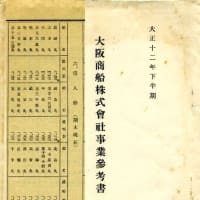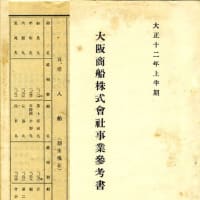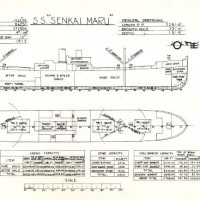今年は3回、長距離フェリーを目的に大阪湾を訪れている。日の出の早い季節には、クリアな画像は望めないもの
の、早朝の入港船を押さえたい。その時は、入港船の一段落した後、葭屋橋と毛馬閘門を訪れた。

フェリーきたきゅうしゅう(名門大洋フェリー) 133389 / JPBR、9,476G/T、鋼、1991(H3).12、佐伯重工業
ネット動画に、淀川を遡航する外輪汽船の映像がある。曳船として活躍する姿を捉えていて、煙突を傾け橋梁を
潜るという、思いもよらぬ貴重な映像に目を見張った。昭和一桁中半頃と思われる。毎日のように眺めては、タ
イムトラベルを楽しんでいる。淀川水系の外輪汽船は、画像を見慣れた利根川水系の船と、印象を異にする。



この鶏卵紙写真の中央部には、甲板室上に操舵室のある外輪汽船3隻を確認できる。手がかりは片隅にプリン
トされている「IOSIYABASI in TSUKIJI」 と、「築地 葭屋橋 舩塲ノ東北隅ニ在リ料店客舎河岸ニ満チ斿人常ニ絶
エズ」 と記された文言。「築地」とあることから、記録地は東京築地。「愉快丸」(東京湾汽船)など、低い橋梁を
潜らない外輪汽船は甲板室上に操舵室を設けているため、船は航洋型外輪汽船と誤解した。
築地のIOSIYA橋を調べる内に勘違いに気付いた。大阪にも築地はあった。「IOSIYA」 は記されていた「葭屋」
と判った。
伏見と大坂を結んだ蒸気船の、大坂側乗り場は八軒家にあった。現在の京阪電車天満橋駅の北側にあたる。
その下流に今も葭屋橋はある。淀川を航行した外輪汽船は、折返しの間、大川から東横堀川の分流する葭屋
橋界隈に係留されたようである。『船名録』の「大坂東区京橋」は、八軒家船着場のあった町名。
築地は当初「蟹島築地」と呼ばれ、遊興地を形成していた。蟹島遊郭は天明4(1784)葭屋庄七らによって設け
られ、「葭屋橋」は遊郭への通路として架橋された。外輪汽船の背後に見える三階建の建築物は遊郭なのか。
妙なところに梯子が掛けられている。鶏卵紙写真の解像度の高さに驚嘆させられる。

鶏卵紙写真に近い角度を探し、天神橋上から葭屋橋を望んでみた。葭屋橋と今橋は東詰で接している。右手奥
に見えるのは難波橋。


ひまわり(大阪水上バス) 135953、54G/T、鋼、1998(H10).01、杢兵衛造船所
大阪水上バスの運航する「ひまわり」は、グルメ・ミュージック船と銘打っている。外輪汽船を模したシックな装いは好ま
しい。外輪部分のデザインは、嘗ての淀川蒸気船を参考にしたと思われる。数年前の秋の撮影。
江戸期より、京都~大坂間の旅客は主に「三十石船」という旅客船が担っていた。『日本の船・和船編』による
と、乗組員4名、旅客定員28名。下りは流れに乗って棹さして大坂を目指したが、京都へ上るには、棹で遡航出
来る区間以外の9個所に「綱引道」があり、大変な労力をかけて上ったと云う。京都側船着場は伏見にあった。
淀川に最初に登場した蒸気船は、1870(M3)柴田(大坂)による「鳩丸」「水竜丸」らしい。高額の運賃に客足は伸
びなかったのか、1873(M6)に休業する。安藤半兵衛は2隻の譲渡を受け、曳船業を開業した。人力に頼っていた
川舟を曳航し、輸送単価を下げたことが当たった。旅客や貨物は蒸気船にシフトし、経営は安定した。
それを見て後へ続く者は続出した。『M18汽船表』に初記載される船は、1884(M17).03設立の澱江汽船会社3隻
(第一安全丸、第二安全丸、光陽丸)と、大坂澱江汽船会社1隻(伏見丸)。1885(M18)には夜間航行も認められ、
就航船は更に増加した。その間の1877(M10).02.05、京都駅~神戸駅間の官設鉄道は営業を開始たものの、運
賃は高額であり、淀川蒸気船は賑わった。
『M21船名録』掲載12隻の定繋港を確認すると、京都側・大坂側夫々の船主が判る。
■京都府下伏見--大坂澱江汽船会社系
第一伏見丸(四方卯之助)M16.04
第二伏見丸(木村榮次郎)M17.11
第三伏見丸(大島源三郎)M18.02
運貨丸(木村平七)M19.07
大坂丸(津田太郎兵衛)M18.01
改進丸(中路八兵衛)M18.03
■大坂東区京橋--澱江汽船会社系
第一安全丸(手塚平右衛門)M12.04
第二安全丸(老村亦次郎)M15.06
六盛丸(秋岡弥平衛)M16.06
牧方丸(鈴木六平)M18.03
第五運輸丸(大島佐七)M16.09
第六運輸丸(大島佐七)M17.04
過当競争排除を目的に、京都府・大阪府の介入により淀川汽船会社は設立された。設立は1887(M20)と1888
(M21).06との二説がある。船名録を見る限り1887(M20)と考えられる。前掲12隻に「新淀川丸」を加えた13隻が
当初の陣容。ここに最初の天下統一が成った。
直ぐに対抗勢力は現れるもので、南方一族の「英丸」「第二英丸」が参入して来た。淀川汽船会社にとって、続
いて現れた「第一京阪丸」(池山小三郎→森島儀三郎)M22.04と、「長安丸」(柏谷忠七)M24.08は、強敵となっ
た。森島は役所の指導により協定に応じたが、柏谷忠七は「長安丸」M24.08に続いて「第二長安丸」M25.04、
「第三長安丸」M26.04、「第四長安丸」M26.12と次々に船腹を増やし、対決姿勢を強めた。
『船名録』に拠ると、淀川水系の外輪汽船の最多在籍年は1893(M26)~1894(M27)。淀川汽船株式会社8隻、柏
谷忠七4隻、森島儀三郎2隻、南方英夫1隻の、計15隻を確認できる。
1895(M28)伏見~京都駅間に、京都電気鉄道により我が国最初の電車運転は開始された。
1896(M29)大阪汽船曳船は「第一此花丸」「第二此花丸」の2隻を建造し、参入した。この大阪汽船曳船は、吹田
庄兵衛らによって設立されたという大二曳船と、どのような関係なのか。1901(M34)所有者は大阪汽船曳船から
大二曳船に変わっている。
1899(M32).04の時刻表を見ると、淀川汽船「大阪八軒家~牧方~八幡~淀~伏見」航路は、上下各7便設定さ
れている。所要時間は、下り3時間に対し、遡航する上りは7時間を要している。
淀川汽船株式会社は徐々に所有船を減らし、遂に1902(M35)渡邊永助に所有船4隻を譲渡して解散した。渡邊
永助は、淀川汽船と競合した「柏谷義一」「大二曳船」二社と協定し、経営の安定を図っている。
1905(M38)~1908(M41)にかけ、中島豊吉は「柏谷・橋本」「大二曳船」所有船を買収した。社名を中島運送部と
し、渡邊永助と協定した。
1910(M43).04.15京阪電気鉄道は天満橋~五条を開業した。この開業により、旅客は激減し、以後、淀川の外
輪汽船の活躍は曳船業(石炭などの貨物輸送)に限られていく。
次の変化は1914(T3)に訪れた。渡邊永助は所有船3隻を中島豊吉に売却。ここに二回目の天下統一は成った。
中島は淀川運送株式会社を設立し、所有船7隻は同社名義となった。
第三長安丸 4533 / JCPT、133G/T、木、1893(M26).09、林政七(伏見)
攝津丸 6960 / JCTB、150G/T、木、1893(M26).12、林政七(伏見) ←渡邊
近畿丸 6961 / JCTD、132G/T、木、1896(M29).12、尼賀又兵衛(大阪) ←渡邊
近江丸 6970 / JCTK、143G/T、木、1894(M27).10、林政七(伏見) ←渡邊
長安丸 6971 / JCTL、132G/T、木、1891(M24).08、平野龍太郎(伏見)
宇治丸 10342 / LBQC、113G/T、木、1907(M40).04、尼賀又兵衛(大阪)
大正丸 15833 / MDNG、78G/T、木、1913(T02).01、尼賀又兵衛(大阪)
『船名録』で追いかけていくと不思議なことに気付く。船舶番号は変わり、新たに登簿されているが、汽機、汽
罐の製造者・年月から「宇治丸」は「第貳此花丸」、「大正丸」は「第一此花丸」の後身と見られる。単に汽機、
汽罐の流用ばかりでなく、船殻も締め直しを行い、再利用したと見られる。
の、早朝の入港船を押さえたい。その時は、入港船の一段落した後、葭屋橋と毛馬閘門を訪れた。

フェリーきたきゅうしゅう(名門大洋フェリー) 133389 / JPBR、9,476G/T、鋼、1991(H3).12、佐伯重工業
ネット動画に、淀川を遡航する外輪汽船の映像がある。曳船として活躍する姿を捉えていて、煙突を傾け橋梁を
潜るという、思いもよらぬ貴重な映像に目を見張った。昭和一桁中半頃と思われる。毎日のように眺めては、タ
イムトラベルを楽しんでいる。淀川水系の外輪汽船は、画像を見慣れた利根川水系の船と、印象を異にする。



この鶏卵紙写真の中央部には、甲板室上に操舵室のある外輪汽船3隻を確認できる。手がかりは片隅にプリン
トされている「IOSIYABASI in TSUKIJI」 と、「築地 葭屋橋 舩塲ノ東北隅ニ在リ料店客舎河岸ニ満チ斿人常ニ絶
エズ」 と記された文言。「築地」とあることから、記録地は東京築地。「愉快丸」(東京湾汽船)など、低い橋梁を
潜らない外輪汽船は甲板室上に操舵室を設けているため、船は航洋型外輪汽船と誤解した。
築地のIOSIYA橋を調べる内に勘違いに気付いた。大阪にも築地はあった。「IOSIYA」 は記されていた「葭屋」
と判った。
伏見と大坂を結んだ蒸気船の、大坂側乗り場は八軒家にあった。現在の京阪電車天満橋駅の北側にあたる。
その下流に今も葭屋橋はある。淀川を航行した外輪汽船は、折返しの間、大川から東横堀川の分流する葭屋
橋界隈に係留されたようである。『船名録』の「大坂東区京橋」は、八軒家船着場のあった町名。
築地は当初「蟹島築地」と呼ばれ、遊興地を形成していた。蟹島遊郭は天明4(1784)葭屋庄七らによって設け
られ、「葭屋橋」は遊郭への通路として架橋された。外輪汽船の背後に見える三階建の建築物は遊郭なのか。
妙なところに梯子が掛けられている。鶏卵紙写真の解像度の高さに驚嘆させられる。

鶏卵紙写真に近い角度を探し、天神橋上から葭屋橋を望んでみた。葭屋橋と今橋は東詰で接している。右手奥
に見えるのは難波橋。


ひまわり(大阪水上バス) 135953、54G/T、鋼、1998(H10).01、杢兵衛造船所
大阪水上バスの運航する「ひまわり」は、グルメ・ミュージック船と銘打っている。外輪汽船を模したシックな装いは好ま
しい。外輪部分のデザインは、嘗ての淀川蒸気船を参考にしたと思われる。数年前の秋の撮影。
江戸期より、京都~大坂間の旅客は主に「三十石船」という旅客船が担っていた。『日本の船・和船編』による
と、乗組員4名、旅客定員28名。下りは流れに乗って棹さして大坂を目指したが、京都へ上るには、棹で遡航出
来る区間以外の9個所に「綱引道」があり、大変な労力をかけて上ったと云う。京都側船着場は伏見にあった。
淀川に最初に登場した蒸気船は、1870(M3)柴田(大坂)による「鳩丸」「水竜丸」らしい。高額の運賃に客足は伸
びなかったのか、1873(M6)に休業する。安藤半兵衛は2隻の譲渡を受け、曳船業を開業した。人力に頼っていた
川舟を曳航し、輸送単価を下げたことが当たった。旅客や貨物は蒸気船にシフトし、経営は安定した。
それを見て後へ続く者は続出した。『M18汽船表』に初記載される船は、1884(M17).03設立の澱江汽船会社3隻
(第一安全丸、第二安全丸、光陽丸)と、大坂澱江汽船会社1隻(伏見丸)。1885(M18)には夜間航行も認められ、
就航船は更に増加した。その間の1877(M10).02.05、京都駅~神戸駅間の官設鉄道は営業を開始たものの、運
賃は高額であり、淀川蒸気船は賑わった。
『M21船名録』掲載12隻の定繋港を確認すると、京都側・大坂側夫々の船主が判る。
■京都府下伏見--大坂澱江汽船会社系
第一伏見丸(四方卯之助)M16.04
第二伏見丸(木村榮次郎)M17.11
第三伏見丸(大島源三郎)M18.02
運貨丸(木村平七)M19.07
大坂丸(津田太郎兵衛)M18.01
改進丸(中路八兵衛)M18.03
■大坂東区京橋--澱江汽船会社系
第一安全丸(手塚平右衛門)M12.04
第二安全丸(老村亦次郎)M15.06
六盛丸(秋岡弥平衛)M16.06
牧方丸(鈴木六平)M18.03
第五運輸丸(大島佐七)M16.09
第六運輸丸(大島佐七)M17.04
過当競争排除を目的に、京都府・大阪府の介入により淀川汽船会社は設立された。設立は1887(M20)と1888
(M21).06との二説がある。船名録を見る限り1887(M20)と考えられる。前掲12隻に「新淀川丸」を加えた13隻が
当初の陣容。ここに最初の天下統一が成った。
直ぐに対抗勢力は現れるもので、南方一族の「英丸」「第二英丸」が参入して来た。淀川汽船会社にとって、続
いて現れた「第一京阪丸」(池山小三郎→森島儀三郎)M22.04と、「長安丸」(柏谷忠七)M24.08は、強敵となっ
た。森島は役所の指導により協定に応じたが、柏谷忠七は「長安丸」M24.08に続いて「第二長安丸」M25.04、
「第三長安丸」M26.04、「第四長安丸」M26.12と次々に船腹を増やし、対決姿勢を強めた。
『船名録』に拠ると、淀川水系の外輪汽船の最多在籍年は1893(M26)~1894(M27)。淀川汽船株式会社8隻、柏
谷忠七4隻、森島儀三郎2隻、南方英夫1隻の、計15隻を確認できる。
1895(M28)伏見~京都駅間に、京都電気鉄道により我が国最初の電車運転は開始された。
1896(M29)大阪汽船曳船は「第一此花丸」「第二此花丸」の2隻を建造し、参入した。この大阪汽船曳船は、吹田
庄兵衛らによって設立されたという大二曳船と、どのような関係なのか。1901(M34)所有者は大阪汽船曳船から
大二曳船に変わっている。
1899(M32).04の時刻表を見ると、淀川汽船「大阪八軒家~牧方~八幡~淀~伏見」航路は、上下各7便設定さ
れている。所要時間は、下り3時間に対し、遡航する上りは7時間を要している。
淀川汽船株式会社は徐々に所有船を減らし、遂に1902(M35)渡邊永助に所有船4隻を譲渡して解散した。渡邊
永助は、淀川汽船と競合した「柏谷義一」「大二曳船」二社と協定し、経営の安定を図っている。
1905(M38)~1908(M41)にかけ、中島豊吉は「柏谷・橋本」「大二曳船」所有船を買収した。社名を中島運送部と
し、渡邊永助と協定した。
1910(M43).04.15京阪電気鉄道は天満橋~五条を開業した。この開業により、旅客は激減し、以後、淀川の外
輪汽船の活躍は曳船業(石炭などの貨物輸送)に限られていく。
次の変化は1914(T3)に訪れた。渡邊永助は所有船3隻を中島豊吉に売却。ここに二回目の天下統一は成った。
中島は淀川運送株式会社を設立し、所有船7隻は同社名義となった。
第三長安丸 4533 / JCPT、133G/T、木、1893(M26).09、林政七(伏見)
攝津丸 6960 / JCTB、150G/T、木、1893(M26).12、林政七(伏見) ←渡邊
近畿丸 6961 / JCTD、132G/T、木、1896(M29).12、尼賀又兵衛(大阪) ←渡邊
近江丸 6970 / JCTK、143G/T、木、1894(M27).10、林政七(伏見) ←渡邊
長安丸 6971 / JCTL、132G/T、木、1891(M24).08、平野龍太郎(伏見)
宇治丸 10342 / LBQC、113G/T、木、1907(M40).04、尼賀又兵衛(大阪)
大正丸 15833 / MDNG、78G/T、木、1913(T02).01、尼賀又兵衛(大阪)
『船名録』で追いかけていくと不思議なことに気付く。船舶番号は変わり、新たに登簿されているが、汽機、汽
罐の製造者・年月から「宇治丸」は「第貳此花丸」、「大正丸」は「第一此花丸」の後身と見られる。単に汽機、
汽罐の流用ばかりでなく、船殻も締め直しを行い、再利用したと見られる。