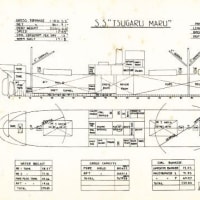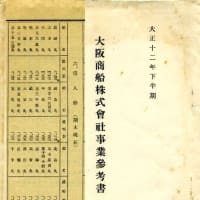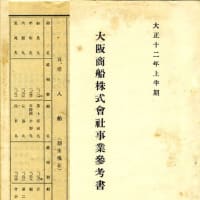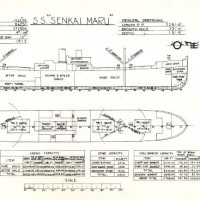雲伯地方へ商船として初来港した蒸気船は、久留米藩「千歳丸」(買積船)であった。日本郵船「青龍丸」
の前身である。沿岸航路船の境港寄港は、1876(M09)郵便汽船三菱会社の大阪~日本海沿岸諸港~
函館航路から始り(境支社設置は1878.02.18)、1884(M17)大阪商船による第12本線(大阪~境航路)
開設、1905(M38).04阪鶴鉄道による舞鶴~境航路開設と続き、山陰本線の延伸に伴い衰退した。
内海航路最初の蒸気船は、M8宍道湖に登場した外輪船「波濤丸」という。明治末から大正の絵葉書全盛
期、この地方の港を記録した画像に、菱形の煙突マークを付けた合同汽船の小型客船が、数多く記録された。
合同汽船はその名のとおり、船主の「合同」により1907(M40).05.06設立された船社。ご多分に漏れず、
ここにも競合船社による激しい貨客の争奪戦があった。先頃、数隻の船名が読み取れたことから、合同汽
船設立の頃を楽しむことができた。

「第貳加茂川丸」と確認できたのはこの画像で、記録されたのは美保関。米子汽船が前川留吉(大阪)に
発注し、1906(M39)年に建造された。加茂川(旧加茂川)は米子市内中心部を流れ、中海にそそぐ河川。
9904 / JVGR、58G/T、1906(M39)、前川留吉(大阪)

この船影は、前掲画像と甲板室の配置や舷門の位置、ポールドの間隔が一致する。「第貳加茂川丸」と見ら
れる。

「米」の文字をデザインした煙突マークを纏う、米子汽船当時の画像もある。船首部装飾の中心に社章が付く。
船名は6文字であり、文字の輪郭から「第壹加茂川丸」と推測している。『松江安来の100年』には米子
汽船が二隻並ぶ鮮明な画像が掲載され、その右手は「第貳加茂川丸」、左手はこの「第壹」と異り、「錦江
丸」の何れかと思われる。
M41版船名録に掲載される米子汽船の所有船(6隻)は次のとおり。1903(M36)から毎年一隻を建造している。
5559 / JFMG 第壹米子丸 M24.04 57G/T 前川留吉(大阪)
6181 / JKHC 第貳米子丸 M26.09 75G/T 前川留吉(大阪)
8712 / JRDK 第壹錦江丸 M36.08 57G/T 前川留吉(大阪)
8983 / JNDW 第貳錦江丸 M37.04 58G/T 前川留吉(大阪)
9573 / JTLP 第壹加茂川丸 M38.04 60G/T 前川留吉(大阪)
9904 / JVGR 第貳加茂川丸 M39.02 58G/T 前川留吉(大阪)


中央で船尾を見せているのは「第壹米子丸」、何故か満船飾となっている。米子汽船の煙突マークは付けてい
ない。右手の汽船は工部省に似た「エ」の社旗、左手は「品」の字を塗りつぶしたように見える。キャプションに
「鉄道連絡船」とあり、連絡を示すため「工部省旗」そのものか? 松江汽船の「エ」と見たのだが。
合同汽船の社章が見えないことから、合併前の明治30年代末期、貨客争奪華やかなりし頃の光景と思われる。
米子汽船合資会社は坂口平兵衛により1891(M24).02設立され、米子~松江及び宍道湖に就航した。当時、既
に中島伊八による汽船航路があり、就航当初から競合することになった。坂口家は江戸時代より綿仲買と醤油
製造を営み、平兵衛の代に米子汽船をはじめ多くの企業を創業し、米子経済界を主導した人物である。

右手に見えるのが「第貳加茂川丸」で、合同汽船の煙突マークとなっている。左側の汽船は合併に参加しなかっ
た社と思われ、前掲左側で「品」の社旗を掲げた船と同一船である。
各社入り乱れていた頃、貨客の争奪は激しく、運賃のダンピングや景品に手拭いを配布したり、宣伝にチンドン屋
も繰り出した。客引きの余り、時には鉄拳の飛ぶこともあったと記録される。各社の疲弊著しいものがあった。
1907(M40).05.06、航路事業者を統合して合同汽船株式会社が創立した。仲介したのは米子の並河理二郎。初代
社長に就任した。
M41版船名録(M40.12.31現在)は合併後の編纂であるが、所有者欄は旧船主名となっている。船主は次のとおり。
中島虎之助(6隻) <中島汽船部>
米子汽船(6隻)
松江汽船(8隻)
星野合名会社(1隻)
益尾吉太郎他(1隻) <米子深浦港汽船組合>
大正となってから中海汽船が参入し、競合が再燃するも、合同汽船には敵わなかったようだ。中海汽船には、
もと陸軍省「豊城丸」6517 / JPHVが来ている。興味深い船と云えば、合同汽船には中島虎之助を経て、もと
尼崎伊三郎「幸崇敬丸」1322 / HJPNが在籍した。それとは知らず、見ているのかも知れない。

就航エリアに多くの観光地を擁する合同汽船には、多数の航路案内図が残されている。案内図を見ると、松江を
起点とする航路は、夫々「美保関線」(急行便/各港便あり)、安来・米子方面は「東航路」、恵曇・小境方
面は「西航路」と呼称されたようだ。中海干拓で大根島は陸続きとなり、合同汽船は1980(S55).09.30終航を
迎えた。今、大橋川から宍道湖にかけて、次の旅客船が活躍している。

「はくちょう」白鳥観光 1987(S62)、16G/T、上原造船所(西ノ島)

「はくちょうⅡ」白鳥観光 1995(H7)、19G/T、上原造船所(西ノ島)

「矢田の渡し」矢田渡船観光 1998(H10)、4.9G/T
の前身である。沿岸航路船の境港寄港は、1876(M09)郵便汽船三菱会社の大阪~日本海沿岸諸港~
函館航路から始り(境支社設置は1878.02.18)、1884(M17)大阪商船による第12本線(大阪~境航路)
開設、1905(M38).04阪鶴鉄道による舞鶴~境航路開設と続き、山陰本線の延伸に伴い衰退した。
内海航路最初の蒸気船は、M8宍道湖に登場した外輪船「波濤丸」という。明治末から大正の絵葉書全盛
期、この地方の港を記録した画像に、菱形の煙突マークを付けた合同汽船の小型客船が、数多く記録された。
合同汽船はその名のとおり、船主の「合同」により1907(M40).05.06設立された船社。ご多分に漏れず、
ここにも競合船社による激しい貨客の争奪戦があった。先頃、数隻の船名が読み取れたことから、合同汽
船設立の頃を楽しむことができた。

「第貳加茂川丸」と確認できたのはこの画像で、記録されたのは美保関。米子汽船が前川留吉(大阪)に
発注し、1906(M39)年に建造された。加茂川(旧加茂川)は米子市内中心部を流れ、中海にそそぐ河川。
9904 / JVGR、58G/T、1906(M39)、前川留吉(大阪)

この船影は、前掲画像と甲板室の配置や舷門の位置、ポールドの間隔が一致する。「第貳加茂川丸」と見ら
れる。

「米」の文字をデザインした煙突マークを纏う、米子汽船当時の画像もある。船首部装飾の中心に社章が付く。
船名は6文字であり、文字の輪郭から「第壹加茂川丸」と推測している。『松江安来の100年』には米子
汽船が二隻並ぶ鮮明な画像が掲載され、その右手は「第貳加茂川丸」、左手はこの「第壹」と異り、「錦江
丸」の何れかと思われる。
M41版船名録に掲載される米子汽船の所有船(6隻)は次のとおり。1903(M36)から毎年一隻を建造している。
5559 / JFMG 第壹米子丸 M24.04 57G/T 前川留吉(大阪)
6181 / JKHC 第貳米子丸 M26.09 75G/T 前川留吉(大阪)
8712 / JRDK 第壹錦江丸 M36.08 57G/T 前川留吉(大阪)
8983 / JNDW 第貳錦江丸 M37.04 58G/T 前川留吉(大阪)
9573 / JTLP 第壹加茂川丸 M38.04 60G/T 前川留吉(大阪)
9904 / JVGR 第貳加茂川丸 M39.02 58G/T 前川留吉(大阪)


中央で船尾を見せているのは「第壹米子丸」、何故か満船飾となっている。米子汽船の煙突マークは付けてい
ない。右手の汽船は工部省に似た「エ」の社旗、左手は「品」の字を塗りつぶしたように見える。キャプションに
「鉄道連絡船」とあり、連絡を示すため「工部省旗」そのものか? 松江汽船の「エ」と見たのだが。
合同汽船の社章が見えないことから、合併前の明治30年代末期、貨客争奪華やかなりし頃の光景と思われる。
米子汽船合資会社は坂口平兵衛により1891(M24).02設立され、米子~松江及び宍道湖に就航した。当時、既
に中島伊八による汽船航路があり、就航当初から競合することになった。坂口家は江戸時代より綿仲買と醤油
製造を営み、平兵衛の代に米子汽船をはじめ多くの企業を創業し、米子経済界を主導した人物である。

右手に見えるのが「第貳加茂川丸」で、合同汽船の煙突マークとなっている。左側の汽船は合併に参加しなかっ
た社と思われ、前掲左側で「品」の社旗を掲げた船と同一船である。
各社入り乱れていた頃、貨客の争奪は激しく、運賃のダンピングや景品に手拭いを配布したり、宣伝にチンドン屋
も繰り出した。客引きの余り、時には鉄拳の飛ぶこともあったと記録される。各社の疲弊著しいものがあった。
1907(M40).05.06、航路事業者を統合して合同汽船株式会社が創立した。仲介したのは米子の並河理二郎。初代
社長に就任した。
M41版船名録(M40.12.31現在)は合併後の編纂であるが、所有者欄は旧船主名となっている。船主は次のとおり。
中島虎之助(6隻) <中島汽船部>
米子汽船(6隻)
松江汽船(8隻)
星野合名会社(1隻)
益尾吉太郎他(1隻) <米子深浦港汽船組合>
大正となってから中海汽船が参入し、競合が再燃するも、合同汽船には敵わなかったようだ。中海汽船には、
もと陸軍省「豊城丸」6517 / JPHVが来ている。興味深い船と云えば、合同汽船には中島虎之助を経て、もと
尼崎伊三郎「幸崇敬丸」1322 / HJPNが在籍した。それとは知らず、見ているのかも知れない。

就航エリアに多くの観光地を擁する合同汽船には、多数の航路案内図が残されている。案内図を見ると、松江を
起点とする航路は、夫々「美保関線」(急行便/各港便あり)、安来・米子方面は「東航路」、恵曇・小境方
面は「西航路」と呼称されたようだ。中海干拓で大根島は陸続きとなり、合同汽船は1980(S55).09.30終航を
迎えた。今、大橋川から宍道湖にかけて、次の旅客船が活躍している。

「はくちょう」白鳥観光 1987(S62)、16G/T、上原造船所(西ノ島)

「はくちょうⅡ」白鳥観光 1995(H7)、19G/T、上原造船所(西ノ島)

「矢田の渡し」矢田渡船観光 1998(H10)、4.9G/T