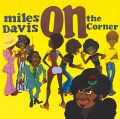最初の出会いは、糸井重里との共作(競作?)「夢で会いましょう」でした。
当時、ちょっとばかりペンギニスト本読んでいて、糸井重里につられて読んだのですが「この村上春樹って鋭いなぁ」と思い、そこから初期3部作に浸りました。
(とはいえ、いきなり「羊」から入ったもので、「ねずみ」というのが何者か、なかなかわかりませんでした)
そこから一気に、短編集、「世界の終わり/ハードボイルドワンダーランド」「ノールウェイの森」と突き進み、「ダンス・ダンス・ダンス」を数ページ読んで突然村上春樹が読めなくなりました。長編も、短編も、エッセーも、翻訳物もとにかく村上春樹のいっさいを読む事ができなくなりました。過剰摂取によるアレルギーみたいなものだったのかもしれません。
読めなくなった、けど、気にはなるわけで、新刊が出ると、本屋で眺める事はしました。でも、買う事はありませんでした。
やっと、なぞの村上春樹アレルギーを、「読みたい」という意志が克服したのが「アフター・ダーク」。
ところが「東京奇譚集 」はこれまた、過剰反応で手に取らず、なぜか「意味がなくてはスイングはない 」なんて買ってしまいました。この本、村上春樹度が薄いのかもしれません。
こういうブログやっているので、音楽の紹介の方法に興味があったという事もあります。村上春樹が好きなミュージシャン/演奏家について、好きなように料理したこの本。じっくり時間かけて紹介するのって、いいなぁ、と思いつつもそんな余裕があるはずも無く。なにか一つ、ちゃんと文献とかあたってからブログ書いてみようかな。大変相だけど。
で、「意味がなくてはスイングはない」ですが、実のところ迷いました、買うかどうか。
なぜならば、紹介しているミュージシャンが、僕がカバーしていた範囲と全く違う。とうか知らない。かろうじて、ブルース・スプリングスティーン(でもアルバム通しで聞いた事ない)と「SMiLE」で気になっていたブライアン・ウィルソンぐらい。
もっとも、知っているミュージシャンだったら、わざわざ村上春樹に解説してもらうまでもないですよね。でも、自分でも知っているミュージシャンを村上春樹がどう料理するのかは、知りたいですよね。知らないミュージシャンであってもあの「夢で会いましょう」の村上春樹が、どう料理して紹介してくれるのかが楽しみですよね。
つまり、紹介しているミュージシャンを知っていても知らなくても、結論はおなじ、村上春樹がどのような魅力を伝えてくれるか、それが楽しみ。だったら、買ってみるしかない。なんとも自己正当化のための理論ではありますが・・・
12月25日のSMiLE / Brian Wilsonから読み始めているので(電車の中で眠りながら読んだとはいえ、1ヶ月というのは長いですね)それ以前のものと変化があったとすれば、この本の影響のはず。うーん、影響されていても、筆の力が全然及んでませんね。

当時、ちょっとばかりペンギニスト本読んでいて、糸井重里につられて読んだのですが「この村上春樹って鋭いなぁ」と思い、そこから初期3部作に浸りました。
(とはいえ、いきなり「羊」から入ったもので、「ねずみ」というのが何者か、なかなかわかりませんでした)
そこから一気に、短編集、「世界の終わり/ハードボイルドワンダーランド」「ノールウェイの森」と突き進み、「ダンス・ダンス・ダンス」を数ページ読んで突然村上春樹が読めなくなりました。長編も、短編も、エッセーも、翻訳物もとにかく村上春樹のいっさいを読む事ができなくなりました。過剰摂取によるアレルギーみたいなものだったのかもしれません。
読めなくなった、けど、気にはなるわけで、新刊が出ると、本屋で眺める事はしました。でも、買う事はありませんでした。
やっと、なぞの村上春樹アレルギーを、「読みたい」という意志が克服したのが「アフター・ダーク」。
ところが「東京奇譚集 」はこれまた、過剰反応で手に取らず、なぜか「意味がなくてはスイングはない 」なんて買ってしまいました。この本、村上春樹度が薄いのかもしれません。
こういうブログやっているので、音楽の紹介の方法に興味があったという事もあります。村上春樹が好きなミュージシャン/演奏家について、好きなように料理したこの本。じっくり時間かけて紹介するのって、いいなぁ、と思いつつもそんな余裕があるはずも無く。なにか一つ、ちゃんと文献とかあたってからブログ書いてみようかな。大変相だけど。
で、「意味がなくてはスイングはない」ですが、実のところ迷いました、買うかどうか。
なぜならば、紹介しているミュージシャンが、僕がカバーしていた範囲と全く違う。とうか知らない。かろうじて、ブルース・スプリングスティーン(でもアルバム通しで聞いた事ない)と「SMiLE」で気になっていたブライアン・ウィルソンぐらい。
もっとも、知っているミュージシャンだったら、わざわざ村上春樹に解説してもらうまでもないですよね。でも、自分でも知っているミュージシャンを村上春樹がどう料理するのかは、知りたいですよね。知らないミュージシャンであってもあの「夢で会いましょう」の村上春樹が、どう料理して紹介してくれるのかが楽しみですよね。
つまり、紹介しているミュージシャンを知っていても知らなくても、結論はおなじ、村上春樹がどのような魅力を伝えてくれるか、それが楽しみ。だったら、買ってみるしかない。なんとも自己正当化のための理論ではありますが・・・
12月25日のSMiLE / Brian Wilsonから読み始めているので(電車の中で眠りながら読んだとはいえ、1ヶ月というのは長いですね)それ以前のものと変化があったとすれば、この本の影響のはず。うーん、影響されていても、筆の力が全然及んでませんね。