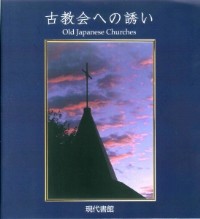読みかけの本です。
この本と出会ったのは、去年の4月。
文庫本の新刊コーナーに並んでいた。
この表紙と

帯にあった城山三郎の文字に惹かれた。
城山三郎、亡くなったのが去年の3月だから、本当に亡くなって出た本、ということになります。
作者のナンシー・ウッド。
解説にると、アメリカのニュー・メキシコ州の自然の中で、ネイティブアメリカンの様に暮らし、ネイティブアメリカンのように考えるアメリカ人だそうです。
「今日は死ぬのにもってこいの日」という著書もあるので、どこかでご覧になったこともあるかと思います。
さて。
「今日という日は贈りもの」の方ですが、これは1月から12月までの月(moon)のお話。
お話というより、毎月毎に例えば
6月 トウモロコシの穂が出る月
7月 太陽の家の月
とタイトルがつけられて、各月ごとに「瞑想」という単文と詩が続くという構成。
例えば7月の瞑想は「7月に月が通るのは、情熱という道」とタイトルが付けられて、そのあとに詩が3編続きます。
非常に短い詩集なので、文庫の最後に原文が載っています。
翻訳前のオリジナルを読むこともできるので、1冊で2度おいしい、という感じの文庫です。
詩集なので、時間が空いたときにあちこちをパラパラとめくって読んでいるのですが、昨日出会ったのは「Spirit Brothers」という詩。
「魂の兄弟たち」
私たちはみな一つ。
人間とハチドリ
野生馬とイタチ
飼い猫と赤尾タカ
バファローと犬
コーテと白尾ウサギ
人間の魂と動物の魂は
理解という
共通の根から出ている。
人間の夢と動物の夢は
私たちの尊い母なる大地の
限りない地平線を共有している。
人間の魂と動物の魂は
空の円が大地の円と
出会うところで一つになる。
この聖なる空間に宇宙の意味がある。
そして宇宙の意味とは
葉におく露
水の上の光のダンス
二匹の犬の会話
ハチドリの飛ぶ様
それ以上のことではない。

城山三郎とナンシー・ウッドの間で交わされた書簡が掲載されています。
城山三郎からの最初の手紙の中で、非常な辺鄙な土地に暮らしていて不便はないか、という意味の質問が投げかけられていました。
ナンシー・ウッドからの返信には「私には不便という言葉の意味が分かりません。ここには私の暮らしに必要なすべてのものがあります」という回答を記していました。
自然の中で、鳥や動物たちと暮らす。
言うのは簡単だと思いますが、実行するには、今普通に持っている価値観を改めないとできないのではないかと思います。
本当は、今すぐにでも始めなくては行けないのでしょうけど、
そこまでの勇気があるか、わかりません。
----
にほんブログ村へ登録しました。

この本と出会ったのは、去年の4月。
文庫本の新刊コーナーに並んでいた。
この表紙と

帯にあった城山三郎の文字に惹かれた。
城山三郎、亡くなったのが去年の3月だから、本当に亡くなって出た本、ということになります。
作者のナンシー・ウッド。
解説にると、アメリカのニュー・メキシコ州の自然の中で、ネイティブアメリカンの様に暮らし、ネイティブアメリカンのように考えるアメリカ人だそうです。
「今日は死ぬのにもってこいの日」という著書もあるので、どこかでご覧になったこともあるかと思います。
さて。
「今日という日は贈りもの」の方ですが、これは1月から12月までの月(moon)のお話。
お話というより、毎月毎に例えば
6月 トウモロコシの穂が出る月
7月 太陽の家の月
とタイトルがつけられて、各月ごとに「瞑想」という単文と詩が続くという構成。
例えば7月の瞑想は「7月に月が通るのは、情熱という道」とタイトルが付けられて、そのあとに詩が3編続きます。
非常に短い詩集なので、文庫の最後に原文が載っています。
翻訳前のオリジナルを読むこともできるので、1冊で2度おいしい、という感じの文庫です。
詩集なので、時間が空いたときにあちこちをパラパラとめくって読んでいるのですが、昨日出会ったのは「Spirit Brothers」という詩。
「魂の兄弟たち」
私たちはみな一つ。
人間とハチドリ
野生馬とイタチ
飼い猫と赤尾タカ
バファローと犬
コーテと白尾ウサギ
人間の魂と動物の魂は
理解という
共通の根から出ている。
人間の夢と動物の夢は
私たちの尊い母なる大地の
限りない地平線を共有している。
人間の魂と動物の魂は
空の円が大地の円と
出会うところで一つになる。
この聖なる空間に宇宙の意味がある。
そして宇宙の意味とは
葉におく露
水の上の光のダンス
二匹の犬の会話
ハチドリの飛ぶ様
それ以上のことではない。

城山三郎とナンシー・ウッドの間で交わされた書簡が掲載されています。
城山三郎からの最初の手紙の中で、非常な辺鄙な土地に暮らしていて不便はないか、という意味の質問が投げかけられていました。
ナンシー・ウッドからの返信には「私には不便という言葉の意味が分かりません。ここには私の暮らしに必要なすべてのものがあります」という回答を記していました。
自然の中で、鳥や動物たちと暮らす。
言うのは簡単だと思いますが、実行するには、今普通に持っている価値観を改めないとできないのではないかと思います。
本当は、今すぐにでも始めなくては行けないのでしょうけど、
そこまでの勇気があるか、わかりません。
----
にほんブログ村へ登録しました。