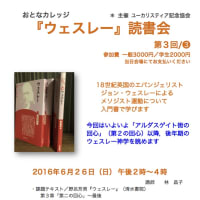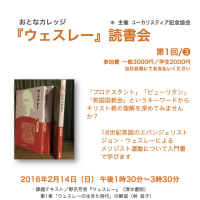ツイッターを始めて数週間、この間で実感したこと。
1.大物な人たちの、リアルタイムな動きの分かり度がなかなかすごい。
2.つぶやくのを聞きたい人が必ずしもツイッターをしているとは限らない。いや、むしろ、ツイッターをしている個人って、かなり限られているのでは。これはブログも同じか。
3.この人ならば是非フォローしたいという人でも、1日に何度もツイートが送られてくると結構しんどくなって結局フォローできない。
ここまでは、ごく平凡な感想である。でも次のことは、ちょっとした発見かも。
たとえば政治家にとって、こういったメディアを通じて主張したり活動をアピールすることはとても好都合だと思う。オバマ大統領にとってのツイッターとか、小沢一郎氏にとってのニコ動とか。それで、ツイートしているその有名人、それって本当に本人なの?という世間の疑問に対して、本人かどうかは電話で確認を行っているとTwitter社側が答えていたのをどこかで読んだ記憶がある。
それでも、である。やっぱり、「本人なの?」という疑念を捨て去ることができないんだなあ。だってだって。
敬愛するコメディアン俳優のローワン・アトキンソンが、「フォロー、ありがと」なんて個人宛にメッセージをくれるなんて。ありがたいお言葉を届けてくださるダライラマに、こちらから直に返信ができてしまうなんて。その他にも、本来であればとっても遠い世界に生きる人々とダイレクトに交信できるのである。
ベネディクト16世とかカンタベリー大主教とか、こういう方々はツイートしないのかな。まあ、ラテン語でやられたらいやだけど。一般の社会では、某組織のお偉いさんに連絡を取ろうとしても、総務課で事務処理されてしまうのがせいぜいなのに、ツイッターでは本人ダイレクトにこちらの言葉が届いているということになっているわけだわね。すごい世の中になったものだ。
しがない庶民としては、「わーい、こんなえらい人と交信できたよ!」とまんまと喜ぶ……わけがないでしょう。自動返信システムなり秘書なり代理人なり、何かしらのダミー的存在が本人の名でツイート活動しているに違いないと、いくらなんでもそう思いますわ。
しかし、そう思いながらもやはり楽しいのである。いかにも本人その人が、そうであるようにして語る言葉を聞くのはいいものだ。しかもその言葉は、あながち本人からまるっきり乖離しているわけでもないはずであり、いやむしろ、その言葉の多くは、本当にご本人が呟いているのかもしれないのである。
近年の聖書研究の成果によって、従来パウロによって書かれたと思われていた手紙が実はそうではなかった、パウロとは別の人物が、パウロの「名をかたって」書いた文書であるということが明らかになったものが、新約聖書の中にはいくつかある(テモテ1,2やテトスとか、牧会書簡とよばれる書のこと)。別の言い方をすれば、人々は2000年近くもの間、それらの手紙に書かれた言葉が、パウロ本人によって語られたものであると信じてきたのである。
そうであるような牧会書簡をどう評価するかという神学上の問題はともかくとして、それらがパウロによる言葉として、歴史上、さまざまなドラマを形成してきたという事実が私には興味深い。E・H・カー『歴史とは何か』から始まり、その後、大福先生のもとでR・ブルトマンの解釈学を学んだ私にとっては、この書簡がパウロのものかどうかという真偽に関心をもつ聖書学よりも、それらのドラマ(実存史)のもつ意味を考える研究の方がずっと楽しいのである。
私もこっそり、大福先生の「名をかたって」何かを発表しちゃおーかなー、いつか。でも、あまりのレベルの違いから、すぐバレるだろう。おあとがよろしいようで。
1.大物な人たちの、リアルタイムな動きの分かり度がなかなかすごい。
2.つぶやくのを聞きたい人が必ずしもツイッターをしているとは限らない。いや、むしろ、ツイッターをしている個人って、かなり限られているのでは。これはブログも同じか。
3.この人ならば是非フォローしたいという人でも、1日に何度もツイートが送られてくると結構しんどくなって結局フォローできない。
ここまでは、ごく平凡な感想である。でも次のことは、ちょっとした発見かも。
たとえば政治家にとって、こういったメディアを通じて主張したり活動をアピールすることはとても好都合だと思う。オバマ大統領にとってのツイッターとか、小沢一郎氏にとってのニコ動とか。それで、ツイートしているその有名人、それって本当に本人なの?という世間の疑問に対して、本人かどうかは電話で確認を行っているとTwitter社側が答えていたのをどこかで読んだ記憶がある。
それでも、である。やっぱり、「本人なの?」という疑念を捨て去ることができないんだなあ。だってだって。
敬愛するコメディアン俳優のローワン・アトキンソンが、「フォロー、ありがと」なんて個人宛にメッセージをくれるなんて。ありがたいお言葉を届けてくださるダライラマに、こちらから直に返信ができてしまうなんて。その他にも、本来であればとっても遠い世界に生きる人々とダイレクトに交信できるのである。
ベネディクト16世とかカンタベリー大主教とか、こういう方々はツイートしないのかな。まあ、ラテン語でやられたらいやだけど。一般の社会では、某組織のお偉いさんに連絡を取ろうとしても、総務課で事務処理されてしまうのがせいぜいなのに、ツイッターでは本人ダイレクトにこちらの言葉が届いているということになっているわけだわね。すごい世の中になったものだ。
しがない庶民としては、「わーい、こんなえらい人と交信できたよ!」とまんまと喜ぶ……わけがないでしょう。自動返信システムなり秘書なり代理人なり、何かしらのダミー的存在が本人の名でツイート活動しているに違いないと、いくらなんでもそう思いますわ。
しかし、そう思いながらもやはり楽しいのである。いかにも本人その人が、そうであるようにして語る言葉を聞くのはいいものだ。しかもその言葉は、あながち本人からまるっきり乖離しているわけでもないはずであり、いやむしろ、その言葉の多くは、本当にご本人が呟いているのかもしれないのである。
近年の聖書研究の成果によって、従来パウロによって書かれたと思われていた手紙が実はそうではなかった、パウロとは別の人物が、パウロの「名をかたって」書いた文書であるということが明らかになったものが、新約聖書の中にはいくつかある(テモテ1,2やテトスとか、牧会書簡とよばれる書のこと)。別の言い方をすれば、人々は2000年近くもの間、それらの手紙に書かれた言葉が、パウロ本人によって語られたものであると信じてきたのである。
そうであるような牧会書簡をどう評価するかという神学上の問題はともかくとして、それらがパウロによる言葉として、歴史上、さまざまなドラマを形成してきたという事実が私には興味深い。E・H・カー『歴史とは何か』から始まり、その後、大福先生のもとでR・ブルトマンの解釈学を学んだ私にとっては、この書簡がパウロのものかどうかという真偽に関心をもつ聖書学よりも、それらのドラマ(実存史)のもつ意味を考える研究の方がずっと楽しいのである。
私もこっそり、大福先生の「名をかたって」何かを発表しちゃおーかなー、いつか。でも、あまりのレベルの違いから、すぐバレるだろう。おあとがよろしいようで。