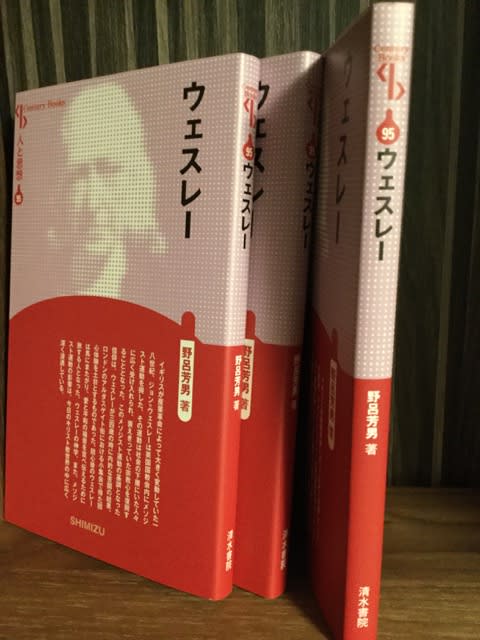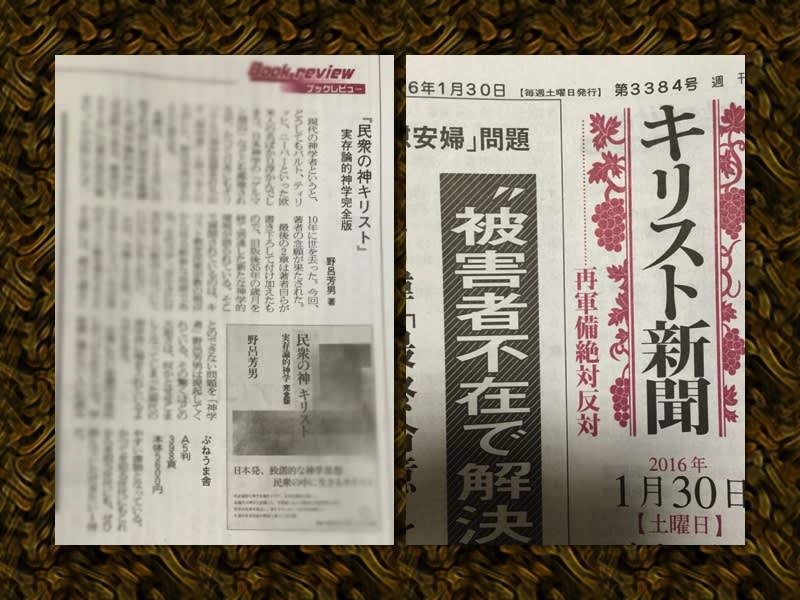特別講座 「マスター英文法」6月18日(日)開講
〜本気モードの英文法講座です
講座内容
英文法、参考書を読んでも授業で説明されても何かピンとこない、実際に問題が解けないという方々へ。それは今までの学習では、英文法の単元ごとの学習に終始していて、システム全体の理解が欠けているからです。まさに「木を見て森を見ず」ですね。本講座では、「木」としての単元理解と、それらを結びつけ「森」を理解する俯瞰的な視野を養います。ベテラン講師が、少人数クラスでじっくりと、あなたの英文法力向上のお手伝いします。
①〜③回
英文法総論:動詞を中心に、時制、各品詞の性質、基本文型など、英文法の根幹を学びます。
④〜⑥回
英文法各論:「態」から「仮定法」まで、中学〜高校で扱う英文法の単元を網羅的に学びます。
対象
・大学受験を目指している社会人&受験生
・TOEICなどの英語系資格試験でReading スコア向上を目指す方
・この機会に一気に英語力を上げたい方
高校生以上の方が対象です。
日程
①6/18, ②6/25, ③7/2, ④7/9, ⑤7/23, ⑥7/30 計6回、全て日曜日午後 13時〜16時30分
会場
東京都中央区(各回、会場が異なります)
受講費
¥60,000
・前半①〜③のみの参加も可能です。(受講費は半額です。)
・前半①〜③を受講した方に限り、④以降は選択的な受講も可能です。(¥10,000/1回)①〜③未受講の場合、④以降の選択受講はできません。
教材
オリジナルプリントと『フォレスト』(桐原書店)
その他、受講生の状況により、復習や今後の学習について個別にアドバイスします。
担当講師は、普段は大企業、官公庁などでさまざまな英語ニーズに対する人材を養成する英語講師をしています。指導歴の長いベテランです。(林昌子)
《講師よりメッセージ》講師自身、日々の生活の中で「読む・聞く・書く・話す」英語を駆使しながら研究生活を送っていますが、文法がよく分からずに英語力がつくとは到底考えられません。例えるとすれば、自動車を運転するのにマニュアル教本や道交法の知識がなくても車の運転ができる、というくらい無謀なことだと思います。
英語ができるようになるのに「文法なんて必要ない」という方には向きません。内容がぎっしり詰まっているので、結構ハードな講座です。本気の方だけ、お越しください。少数精鋭で、アットホームな雰囲気の中、このひと月半で英語力アップを目指す方、ぜひお待ちしております!
お問合せはこちらからどうぞ。
〜本気モードの英文法講座です
講座内容
英文法、参考書を読んでも授業で説明されても何かピンとこない、実際に問題が解けないという方々へ。それは今までの学習では、英文法の単元ごとの学習に終始していて、システム全体の理解が欠けているからです。まさに「木を見て森を見ず」ですね。本講座では、「木」としての単元理解と、それらを結びつけ「森」を理解する俯瞰的な視野を養います。ベテラン講師が、少人数クラスでじっくりと、あなたの英文法力向上のお手伝いします。
①〜③回
英文法総論:動詞を中心に、時制、各品詞の性質、基本文型など、英文法の根幹を学びます。
④〜⑥回
英文法各論:「態」から「仮定法」まで、中学〜高校で扱う英文法の単元を網羅的に学びます。
対象
・大学受験を目指している社会人&受験生
・TOEICなどの英語系資格試験でReading スコア向上を目指す方
・この機会に一気に英語力を上げたい方
高校生以上の方が対象です。
日程
①6/18, ②6/25, ③7/2, ④7/9, ⑤7/23, ⑥7/30 計6回、全て日曜日午後 13時〜16時30分
会場
東京都中央区(各回、会場が異なります)
受講費
¥60,000
・前半①〜③のみの参加も可能です。(受講費は半額です。)
・前半①〜③を受講した方に限り、④以降は選択的な受講も可能です。(¥10,000/1回)①〜③未受講の場合、④以降の選択受講はできません。
教材
オリジナルプリントと『フォレスト』(桐原書店)
その他、受講生の状況により、復習や今後の学習について個別にアドバイスします。
担当講師は、普段は大企業、官公庁などでさまざまな英語ニーズに対する人材を養成する英語講師をしています。指導歴の長いベテランです。(林昌子)
《講師よりメッセージ》講師自身、日々の生活の中で「読む・聞く・書く・話す」英語を駆使しながら研究生活を送っていますが、文法がよく分からずに英語力がつくとは到底考えられません。例えるとすれば、自動車を運転するのにマニュアル教本や道交法の知識がなくても車の運転ができる、というくらい無謀なことだと思います。
英語ができるようになるのに「文法なんて必要ない」という方には向きません。内容がぎっしり詰まっているので、結構ハードな講座です。本気の方だけ、お越しください。少数精鋭で、アットホームな雰囲気の中、このひと月半で英語力アップを目指す方、ぜひお待ちしております!
お問合せはこちらからどうぞ。