3月の初めに知人が何気なく話題にして帰られた『あの図書館の彼女たち』(3/7記)。
早速書店に走り、勢い込んで読み始めたものの、翻訳の文章に慣れないせいか半分ほどは展開を読むだけに追われた。個人の名前が定着し始め、ドイツ軍がパリに侵攻してくるあたりから引き込まれていく。
多くの文学書のタイトルが、その一節が、文中に組みこまれ、引用され、なかなか洒落ていると感じることも多かった。

戦時中のパリの物語と言うと、ナチスに対抗するレジスタンスの人々を思い浮かべる人も少なくない。しかし、実際に地下活動に加わったのはごくわずかだ。多くの市民は日々の生活を過ごすだけで精一杯で、自分たちに危害が加えられるのではないかと怯え、疑心暗鬼にかられていた。ナチスに売り渡そうとする密告が横行していたことも、今ではよく知られている。(「解説」)
「(非常時ばかりでなく、何気ない日常生活においても)異なる文化的背景を持つ者どうしが出会ったとき、偏見や先入観に邪魔されずに意思疎通ができるかどうかで、きっと世界は大きくちがってくるだろう。他者を受け入れることで、それは相手を理解し、自分の気持ちもわかってもらい、思ってもいなかった幸せを招くことができるかもしれない。
パリの住人やアメリカ図書館に出入りする人々、そしてモンタナ州の少女リリーなど、オディールを巡る人々の悲喜こもごものエピソードに、そんなチャールズ(作者)の想いがうかがえる。(「訳者あとがき」)
「わたしが本書を書いた目的は、第二次世界大戦の歴史の中の、このほとんど知られていない章を読者と分け合い、登録者を助けるためにナチスに抵抗した勇気ある司書たちの声を記録し、文学への愛を共有するためだった。
いかに私たちが互いに助け合い、邪魔し合うのかと言うだけではなく、わたしたちの在り方を決める人間関係を探求したかった。
言葉は、他者に対して開いたり閉じたりできるゲートだ。わたしたちが読んだ本、互いに話す物語、自分に言い聞かせる物語がそうであるように、単語を使ってわたしたちは知覚を形成する。
外国人職員と図書館の登録者は、“敵性外国人”とみなされて、拘留された者もいた。ユダヤ人登録者は図書館に入ることを許されず、多くはのちに収容所で殺された。ある友人は、第二次世界大戦の時代の物語を読むことによって、人は自分だったらどうしただろうと自問したいのだと言った。
わたしとしては、図書館と学習がすべての人に許され、人々を尊厳と情熱を持って扱えるような状態を確保するために、自分たちに何ができるかというほうが、もっといい問いかけだと思う。」(「著者の覚書」)
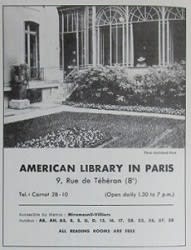
1939年、20歳でアメリカ図書館の司書に採用されたオディール。1983年、オディールはアメリカのモンタナ州に住んでいた。隣家の12歳の少女リリーと出会い、良き隣人として友人として歳の差を超えた関係が紡がれる。
人は過ちを犯す。図書館の仕事を放りだし、オディールがアメリカに「逃げた」わけも明らかになった。
コロンビア大学への入学が決まったリリーに、オディールはパリ行きの航空券と絵葉書が入った封筒を渡した。葉書には、「 “リリーへ。夏のために、愛をこめて” パリ 」とあり、アメリカ図書館と白い服の女性が映っていた。
「パリのアメリカ図書館 毎日開館」の文字と。 -これが結びだった。
リリーが心から願ったオディールとマーガレットにとってのハッピーエンド。リリーにとっても「思ってもいなかった幸せ」が訪れた。
二人の心の底にあった思いが、切れたかに見えた縁をつないでいたのだ。
早速書店に走り、勢い込んで読み始めたものの、翻訳の文章に慣れないせいか半分ほどは展開を読むだけに追われた。個人の名前が定着し始め、ドイツ軍がパリに侵攻してくるあたりから引き込まれていく。
多くの文学書のタイトルが、その一節が、文中に組みこまれ、引用され、なかなか洒落ていると感じることも多かった。

戦時中のパリの物語と言うと、ナチスに対抗するレジスタンスの人々を思い浮かべる人も少なくない。しかし、実際に地下活動に加わったのはごくわずかだ。多くの市民は日々の生活を過ごすだけで精一杯で、自分たちに危害が加えられるのではないかと怯え、疑心暗鬼にかられていた。ナチスに売り渡そうとする密告が横行していたことも、今ではよく知られている。(「解説」)
「(非常時ばかりでなく、何気ない日常生活においても)異なる文化的背景を持つ者どうしが出会ったとき、偏見や先入観に邪魔されずに意思疎通ができるかどうかで、きっと世界は大きくちがってくるだろう。他者を受け入れることで、それは相手を理解し、自分の気持ちもわかってもらい、思ってもいなかった幸せを招くことができるかもしれない。
パリの住人やアメリカ図書館に出入りする人々、そしてモンタナ州の少女リリーなど、オディールを巡る人々の悲喜こもごものエピソードに、そんなチャールズ(作者)の想いがうかがえる。(「訳者あとがき」)
「わたしが本書を書いた目的は、第二次世界大戦の歴史の中の、このほとんど知られていない章を読者と分け合い、登録者を助けるためにナチスに抵抗した勇気ある司書たちの声を記録し、文学への愛を共有するためだった。
いかに私たちが互いに助け合い、邪魔し合うのかと言うだけではなく、わたしたちの在り方を決める人間関係を探求したかった。
言葉は、他者に対して開いたり閉じたりできるゲートだ。わたしたちが読んだ本、互いに話す物語、自分に言い聞かせる物語がそうであるように、単語を使ってわたしたちは知覚を形成する。
外国人職員と図書館の登録者は、“敵性外国人”とみなされて、拘留された者もいた。ユダヤ人登録者は図書館に入ることを許されず、多くはのちに収容所で殺された。ある友人は、第二次世界大戦の時代の物語を読むことによって、人は自分だったらどうしただろうと自問したいのだと言った。
わたしとしては、図書館と学習がすべての人に許され、人々を尊厳と情熱を持って扱えるような状態を確保するために、自分たちに何ができるかというほうが、もっといい問いかけだと思う。」(「著者の覚書」)
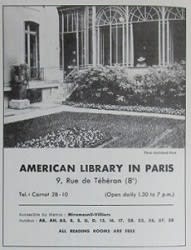
1939年、20歳でアメリカ図書館の司書に採用されたオディール。1983年、オディールはアメリカのモンタナ州に住んでいた。隣家の12歳の少女リリーと出会い、良き隣人として友人として歳の差を超えた関係が紡がれる。
人は過ちを犯す。図書館の仕事を放りだし、オディールがアメリカに「逃げた」わけも明らかになった。
コロンビア大学への入学が決まったリリーに、オディールはパリ行きの航空券と絵葉書が入った封筒を渡した。葉書には、「 “リリーへ。夏のために、愛をこめて” パリ 」とあり、アメリカ図書館と白い服の女性が映っていた。
「パリのアメリカ図書館 毎日開館」の文字と。 -これが結びだった。
リリーが心から願ったオディールとマーガレットにとってのハッピーエンド。リリーにとっても「思ってもいなかった幸せ」が訪れた。
二人の心の底にあった思いが、切れたかに見えた縁をつないでいたのだ。















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます