[写真]第46回衆院選の開票状況を見つめる岡田克也副総理、2012年12月16日午後10時過ぎ、ザ・プリンスパークタワー東京、宮崎信行撮影。
民主党は2012年12月19日(水)、第46回総選挙の解党寸前的大惨敗の後、初めての両院議員総会を開きました。場所は党本部内ホール。ホールと言っても自民党本部、社民党本部のホールと違って2階席はありません。普通の会社で言えば「大会議室」です。この場所で両院議員総会を開くのは、2009年7月21日の衆議院解散直後の両院議員総会以来3年半ぶり。政権の宴を終え、あの暑い夏の前に戻りました。
第2次野党期最初の総会と言うことで、昔のような談論風発政党に戻り、小選挙区で2連勝した長野1区の篠原孝さんが口火を切り、輿石東幹事長ら執行部が決めた22日投開票に異論を唱えました。その後も一部産別出身非改選参院議員を除き、相次いで、もっと時間をかけ、落選者、地方議員、党員サポーター、連合らと総括しながら、選挙をすべしとの声が上がり、日程感については1月の定期党大会(例年は1月中旬だが通常国会の日程からして1月下旬も)での新代表選出が発言者の大勢をしめました。
野田佳彦代表・総理は「敗軍の将、兵を語らず」と短く挨拶し、深々とおじぎ。しかし拍手も合いの手もなく、この辺は、第1次与党期民主党と変わっていない点で、いずれにしろ、表現下手、建設的提案が少ない両院議員総会でしたが、「民主党らしさ」の復活は感じました。
これに関連して、有力代表候補者周辺は「総括と代表選は別ではないか」として、代表選をしたうえで、新代表の下で総括し、参院選に臨むとのスケジュール感を提示。総括と代表選を混同した発言者が多いとして、「だから駄目なんだ」とコメントしました。
◇
岡田克也副総理は敗戦確定後では初めて記者会見を2012年12月18日(火)開き、民主党の今後の方向性について、「(2012)マニフェストで書かれた方向性というのは、私はそのまま引継がれていく」としたうえで、「この党には昔から二つの路線があったんですね。一つは改革路線(略)もともと民主党は改革ということを掲げていた政党なんですよね。もう一つは、ヨーロッパでいう社民的路線ですね、どちらかというと大きな政府というか、国がより重要な役割を果たすべきだと。この二つの路線がありました」として、「これをどうやって融合していくかと、私もこれは二つは矛盾するものでは必ずしもないと思うんですね。今の財政状況を見れば、様々な改革なくして本当に必要な人にきちんと生活を保障していくということもできませんし、この改革路線とヨーロッパの社民的な路線、人に優しいというか、そういう路線をいかに融合させていくかというが、私は民主党の大きな課題ではないか」との考えを示しました。これは、岡田副総理、枝野幸男経産相ら3人がまとめ立党大会で採択した「私たちの基本理念」にも明らかなところです。
副総理退任後、野党議員として取り組みたい政策については「一つは、やはり子ども・子育てというか、あるいは働く女性が子育てがきちんと両立できる、そういう社会を作っていくということが一つです(略) それからもう一つはオープンガバメントという形、これもある意味では行政事業レビューシートを作って行政事業レビューをやったとかですね、そういったことがここの一環でありますが、そういった、より開かれた広い意味でのオープンガバメントということを進めていくという、この二つは政策的にさらに深めたいし、将来の民主党の政策の柱にしていきたい」と語りました。
初当選時に所属した衆院厚生委員(現・厚生労働委員)から22年。子ども・子育て新システムすなわち幼保一体化。そして、「配偶者控除から児童手当へ」の民主党路線をつきつめる。これは自民党が配偶者控除を大きくしようとしていることと、真っ向から対立する概念であり、イデオロギー対立に近いものがあり、ぶれないパラダイム設計が必要です。そして、納税者の理解と、有権者への説得の努力、方法が必要です。

それと、第1次野党期執行部や外相として実績を挙げた情報公開に加えて、行政刷新相として政権途中から参画した、仕分けの力を前に進めたいとの考えで、各府省への行政事業レビューシートの運営などを外野から取り組んでみたいということになります。配属委員会としては、衆院厚生労働委員、衆院内閣委員ということになるでしょう。過去の議事録からすると、岡田さんは内閣委員を務めたことはないで、行政刷新相としてことし答弁する中で興味を持ったのかもしれません。
ところで、岡田さんの「選挙は最終的には自分の責任です。総理がいろいろな思いを込めて決断したことについて、それを理由に自分は負けたんだと言うのは、私は議員のとるべき態度ではないというふうに思います。そういう、みんな執行部や他人の責任にしちゃうというところは改めないと、この党は再生できないと私は思います」との発言について、1990年自民党非世襲初当選の仲間(現在は参院議員)が、翌日の両院議員総会で、名指しをさけながらマイクを持って岡田発言を暗に批判しました。閣僚になれず下野した悔しさは分かります。しかし、彼に言いたいのはひと言。「だから駄目なんだよ」。
とにかく、ビシバシと私たちが鍛え直さないといけないようです。来夏の参院選まで、カネはないけど、時間はある、ビシバシと鍛えてそれで駄目なら初めてあきらめがつくというものです。民主党をあきらめないことが日本をあきらめないことにつながります。
なお、衆院小選挙区で2回連続して落選した総支部長は次の衆院選で公認しないという民主党の内規、ツーアウトルールについて、「それは次の執行部が考えることですから、私の今の立場で何か言うことではないというふうに思います。ただ、ツーアウトルールというのは、小沢さんになって大分覆されたんですね。我々のときにそういうことで、総支部長を外した人が小沢代表のもとで復活したりということが結構ありましたので、今、党としてそういう考え方を今もとっているのかどうかというのは判然としないところはありますよね」と語り、見直しに柔軟な姿勢を示唆しました。
岡田克也副総理は2012年(平成24年)11月9日(金)午後3時からの定例閣議後記者会見で、同週に今期限りの引退を表明した永年在職議員が、1997年12月の新進党解党の際に、小沢一郎氏が幹事長(故人)、国対委員長(現・民主党議員)、政調会長(現・自民党議員)に加えて創価学会系トップだった総務会長、公明系重鎮の両院議員総会長らが知らない間に解党(分党)手続きを進めていたとの証言が飛び出したことについて、「もう昔の話ですから、私はちゃんと説明しろというふうに議員総会では申し上げたのですが、もう今となってはちょっと説明されても、今さらという感じがしますね」と語りました。
神崎武法総務会長、近江巳記夫両院議員総会長の知らないところで分党手続きを進めていたのなら、小沢一郎氏が支持団体の一つ、創価学会(秋谷栄之助会長=当時)や連合(鷲尾悦也会長=当時)に無断で財産を処分したことは確実。
小沢一郎氏については、経世会(自民党竹下派)の残余財産を引き継いだ改革フォーラム21(自民党羽田派)・新生党、新進党、さらには自由党の残余財産を指定政治資金管理団体のみならず、自らの側近・秘書を代表者として届け出た政治団体の繰越金や土地(名義は小沢一郎氏)として私物化している疑惑があり、納得ある説明はいまだにありませんし、謝罪もありません。
[お知らせ1]
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。取材資金にもなりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせ2]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。他メディアにはない国会審議を中心とした政治の流れをこのブログで伝えていきます。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]
http://www.kantei.go.jp/jp/fukusouri/press/ http://regimag.jp/b/sample/list/?blog=65
おはようございます。
さあいよいよ、今週から第181臨時国会のスタートです。
あの暑い夏の総選挙から3年2ヶ月。第45期衆議院、民主党第1次与党期においては、最後の秋の臨時国会になります。
天高く馬肥ゆる秋。
今月の内閣改造では、安住淳幹事長代行、鉢呂吉雄選挙対策委員長、中川正春財務委員長の「岡田3人衆」が、党の存亡をかけた「80日間世界一周」に飛び立ちました。
もし、民主党政権がダメになったらどうするか。それはまだ野党時代、あの暑い夏の総選挙のさいちゅうに、岡田さんが語っています。
政権交代ある政治を根付かせる。二大政党がともにお互いをチェックし、権力、しがらみ、情報を交代させることによって国民の手に政治を取り戻す。あの日(1993年6月18日、宮澤解散)から始まった試みです。
その試みは、いったん潰えました。言うまでもありません。1997年12月28日、小沢一郎氏による新進党解党の暴挙によってです。そして、2009年8月25日、民主党本部8階の役員室で再び暴挙が起きました。それは、岡田克也幹事長が作成した、第45回衆院選勝利から第22回参院選までの300日間の日程表である「岡田300日プラン」をあろうことか、与党権力の私物化をねらっていた小沢一郎氏が回収し、代表・鳩山由紀夫が黙認した事件です。まさに一度裏切る人間は二度裏切る。
これにより、鳩山代表が首相官邸に引っ越した後に、民主党本部の留守番は、国民が選んだ岡田幹事長ではなく、悪の枢軸・小沢一郎氏となりました。民主党政権への信頼は失墜しました。ナント300日の間に、内閣支持率が80%から20%に真っ逆さまに落ちました。憲政史上最大の右下がり。第22回参院選で我が党は比例代表では得票数・議席数とも断然トップとなりましたが、選挙区では得票率1位ながら、議席数は自民党に大きく負けました。自公は改選過半数に迫りました。
それでも、政権交代ある政治のメリットは、この3年2ヶ月間、どぶさらいの汚泥に目を背けながらも、多くの日本国民が理解するようになりました。政権交代ある政治は、体感では風向きの関係で回り回っているように感じますが、前に進みました。
野党一筋15年。自民党同期当選の福田康夫さん、細田博之さん、同じ経世会の佐田玄一郎さんらに大きく遅れて初入閣した岡田さんですが、外相、副総理と当選7回生の59歳にしては大きすぎる官職を歴任しました。そして、閣議・閣僚懇談会の議事録作成と30年後の公開、製薬・医療機器の規制緩和と薬事法と新医療機器法の分割・改正、そして、JAの金融・葬祭事業などの廃止も含めた見直し、農地の宅地転用の規制強化、農業委員会の制度見直しなど、「平成の農地改革・農民解放」という大きなテーマにかかわっています。とても勇気のある政治家だと考えます。
[写真]当選7回生、59歳の副総理、2012年3月23日、首相官邸ホームページ内副総理の記者会見から。
民主党政権は事業仕分けで歳出を削り、「控除から手当てへ」の税制改正で租税特別措置を削りました。これにより、次の選挙では特定業界からの支持を受けづらくなり、今までの与党の強み(しめつけ)を使えなくなりました。それは必定であり、民主党がしなければならなかったことです。
安住淳幹事長代行は2012年10月19日(金)の定例記者会見で「幹事長と、私と、選対委員長の3人で、それぞれの選挙区を抜き打ち的に歩きます」と述べました。そして「任期を考えると、もともとの民主党の支持団体と地元の議員の間で、どのようになっているかの確認したい」としています。逆風の選挙こそ、足腰の強さが求められ、そして、頼りになるのは雨天の友です。衆議院小選挙区の特質を理解しないで、もともとの支持団体ではないJA農協と交わったり、野党時代は招待状をくれなかった各種行事であいさつして地元周りと称するような議員は落選すればいい。裏切り者です。
議員仕分けが必要になってきます。鉢呂選対委員長は、新しい公募から能力ある新人を擁立しようとしています。元自由党副党首、中井洽議員(三重1区)も自ら今期限りの引退を表明しました。
岡田さんは23日の記者会見で野田総理の発言を巡る受け止め方について、「それを勝手に一部のメディアは3条件というふうに伝えているということです。もちろん議員の中にもそういうふうに受け取って、発言している方はいらっしゃるわけですが、それは間違いであるということを伝えている、私は申し上げているわけです」と述べ、最近顕著なメディアが誤解し、議員が誤解し、メディアが報じるという誤解の拡大再生産に警鐘を鳴らしています。伝言ゲームがきちんとできるかどうかは、選挙や政治活動の基本であり、新聞をスマートフォンで読んで、そのまま信じるような一部議員には消えてもらわないと、次の有事でも脚を引っ張りかねません。
東日本大震災で、この国は大きな歴史の転換期を迎えました。岡田幹事長は震災の時に、1期生にこう言いました。「こういうときこそ人は見られている」。その後の日本政治はご存知の通り、第177通常国会の6月1日に小沢一郎氏にそそのかされる格好で、自公が菅内閣不信任案を提出し、否決されました。それから1年経って、またしても小沢一郎氏が暗躍し、社会保障と税の一体改革法案の衆院採決を迎えましたが、可決に成功しました。そして、8月29日(水)には自公を批判する野田内閣問責決議が参院で可決しました。これも政党助成法の関係で早期解散は困る小沢氏の差し金で、3度騙された谷垣禎一さんは自民党総裁を追われました。ケミストリーの合う、宏池会・谷垣総裁の失脚は残念でしたが、3度も小沢に騙されるようでは、リアル首相として外交は任せられません。私は思いました。「こういうときこそ人は見られている」と。
小沢一郎を倒さなければなりません。小沢グループ新党「国民の生活が第一」を根絶やしにしなければなりません。小沢一郎を亡き者にして、それで二大政党の定着は終わりではありません。80年前の二大政党制が失敗したと我が物顔で言う人間がいますが、まったくの勉強不足です。80年前の失敗はすべてテロリズムです。例えば立憲政友会に限定しても、初代党首の伊藤博文、3代党首の原敬、4代党首の高橋是清、6代党首の犬養毅が暗殺されています。2代党首の西園寺公望は元老として暗躍し、5代党首の田中義一は首相在任中に板垣征士郎・石原完爾による満州侵略を防げなかったので、いわば暗殺されるまでもなかったのです。大正デモクラシーの二大政党が官僚(陸軍省)に権力を奪われたのはテロリズムが最大の要因であり、政争にその責を負うのは本質を捉える能力のない歴史家にすぎません。人間の一生は重い荷物を背負って、遠い道を行くようなものです。岡田さんは政権交代ある政治の前に立ちはだかった「衆参ねじれ」に対して、「例え狭い道(ナローパス)でも前に進む」「走りながら考える」として、辞任3条件と3党合意にもとづき、平成23年度特例公債法を成立させました。そして、毎年総理が特例公債法という人質の交換条件として辞任する連鎖を経つために、第180通常国会では会期末を9月8日に設定して、「特例公債法案が成立しないと11月に財源が枯渇する」という論法を打ち出し、総理を救いました(「淳が総理を神隠し」)。第181臨時国会では、3代目参議院の天皇・自民党の脇雅史・参院国対委員長が所信表明を本会議の議題にしないことにしました。でもそれもいいのではないでしょうか。小泉純一郎首相(清和会自民党総裁)も「(施政方針)演説を衆参で2回でやるのは無駄なので改善してほしい」と国対に告げ、参議院の反発を招きました。
新しい時代の幕開けです。
新生党羽田内閣が倒されたとき、次の総選挙で与党になれると思っていました。甘かった。牛丼一筋80年ならぬ野党一筋15年。しかし、その間、一瞬たりとも、与党になったらどうするという観点を持ち続けた。それが岡田さんです。ですから、2009年5月の民主党代表選で岡田さんが当選していれば、2011年3月11日以降の日本の姿は変わっていたかもしれません。ひょっとしたら、原子力発電所が爆発することはなかったかもしれません。まあ、それは詮無いことなので、やめておきましょう。
2007年8月のブログ開設からしばらくは、羽田孜再登板をあきらめて、新生党最年少の岡田首相をめざしていることは、ずっとこのブログでは隠してきました。それが思いの外、2009年5月という早いタイミングで岡田さんが代表選に出馬。当ブログは説明不足のまま、岡田首相に向けてダッシュすることになり、政治ブログランキング2位だったのが、「応援クリックが激減する」という何とも陰湿なイジメにあい、ランキングを退会しました。8月政権交代。もともとリスクヘッジからブログを止めるとしていましたが、鳩山代表が岡田幹事長を更迭し、新進党解党者・小沢一郎氏を幹事長にするという暴挙をみて、ブログを再開。足がすくんで物が言えぬようになった政治家と支持者、私はこの時誰が足がすくんで物が言えなくなったか、一生忘れないと思いますが、それを横目に、2010年6月に小沢を引きずり降ろすことに成功。野党内野党(民主党副代表)を密かに応援してから、2年10ヶ月でついに与党内与党へと。そこから歴史の流れが速くなり、さらに「3・11」でジェットコースター状態になり、ついには、2年4ヶ月間、与党内与党のもっとも官邸に近いブログとなりました。書けないことも増えました。その割に、書いておかないと気が済まないことが増えて、文章量は圧倒的に多くなりました。与党というのは何もかも驚くことばかりでした。たとえナローパスでも、第45期衆議院を最後の最後まで走り抜けなければなりません。
まっすぐに、ひたむきに。そこから逃げるのではなく、この国が好きだからこそ、ロングロングウェイ。例えナローパスでもロングロングウェイ。次の次のそのまた次の選択のために、二大政党政治の完成に向けて、第181回臨時国会も全力で駆け抜けていく所存です。
岡田かつやの可能性への挑戦は、まだスタートラインに着いたばかりです。
[お知らせ]
衆議院解散はいつか。その答えはこの日程表にある。会員制ブログ(月840円)。
今後の政治日程 by 下町の太陽
国会傍聴取材の活動資金にもなりますので、ご協力をお願いします。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
国会での審議を中心に地道な政治報道を続けられるようご支援をお願いします。
[お知らせおわり]
tag http://www.kantei.go.jp/jp/fukusouri/press/ http://regimag.jp/b/sample/list/?blog=65
[写真]タンザニアを訪れた岡田克也外相、2010年5月3日。
岡田克也外相が2010年5月の大型連休を活用して視察した、タンザニアの住友化学の蚊帳工場が第19回読売国際協力賞を受賞しました。2012年10月23日(火)付の読売新聞1面で発表され、特集面が組まれています。
岡田さんは衆議院議員としてのブログ「岡田かつやTALK-ABOUT」の2010年5月11日付「アフリカ訪問(3)―現場に行って初めて見えるものがある」のなかで、「まず、第1に行きましたのが、タンザニアの蚊帳工場です」「非常に効果があって、マラリアによる死亡が半分になったという国がいくつか出てきました」「そういった素晴らしい技術を日本の企業が提供しているというだけではなくて、このタンザニアの蚊帳工場では、合わせて6000名の雇用を作り出しています」「いずれにしても、私は、日本の企業が頑張っている姿を嬉しく思いました」と感想をつづっています。
岡田さんのブログは、現在衆議院議員としてはきわめて珍しく、コメント欄が開設されていますが、ハンドルネーム「いいちこ」さんから「蚊帳技術が外国にしっかりと定着した事は、とっても嬉しいです。でも、蚊が触れただけで死んでしまうような殺虫剤を糸に混ぜて、それを人間が使用して、身体に害は無いのでしょうか?小さい子が謝って端っこを口に入れたりしても大丈夫なのかなぁ・・・などと、ちょっと心配してしまいました」 とのコメントが寄せられました。
この後、住友化学の米倉弘昌会長は経団連会長に就任しました。
読売新聞によると、この「殺虫剤が練り込まれた蚊帳」は「オリセットネット」と呼ぶそうで、同社は1985年頃から開発。同社の研究員、伊藤高明さんが、マラリアの流行でアフリカを中心に年間100万人が亡くなっていることを知り、マラリア撲滅をライフワークにすることを決心。洗濯しても殺虫剤が落ちにくくしたり、寝苦しくならないよう通気性を高めたりして開発に成功しました。ただ、売れるかどうか見通しは立たなかったそうですが、タンザニアで青年海外協力隊員としてマラリアにかかった経験がある川崎秀二部長が背中を押しました。2003年にタンザニア企業に技術を無償提供し、2005年に現地企業と住友化学の合弁企業を設立。岡田さんの2010年のブログでは、6000人の雇用となっていますが、きょうづけの読売では、7000人の雇用を生み出しているそうです。
現地リポートによると、タンザニア・マガディニ村のティパイ・ワガディコ村長は、「SUMITOMOの名前は、誰でも知っている」と、高く評価したそうです。
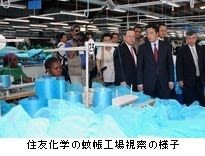
[写真]タンザニアの住友化学の蚊帳工場を訪れた岡田外相、2010年5月、岡田かつやTALK-ABOUTから。
これとは別に、先の通常国会の衆議院社会保障と税の一体改革特別委員会の審議でもタンザニアの日本人が紹介されています。元外交官で公明党の遠藤乙彦さん(第45期衆議院で勇退)が、2012年5月31日、「今、タンザニアで、もう援助の時代は終わってビジネスの時代になって、非常に活性化して成長も進んでいる中で、日本からやってきた三十歳の若者がビジネスで非常に大きな成功をおさめて脚光を浴び、有名人になっている、タンザニア政府からいろいろな助言まで求められるぐらいの存在になっているということであります。沖縄出身の男性らしいんですが、24歳のときにタンザニアに定着して、そこでビジネスに開眼して、今や、5年間で41社を立ち上げ、100人以上の従業員を使い、何と年商300億という話を聞きまして、通称タンザニアのプータロー君というように呼ばれているそうなんですが、ドロップアウトしたような青年でも、国際的に活躍して、実際にそういった起業家精神を発揮して成功している例もあるわけであります」と紹介しています。
一方、岡田さんのブログには、ハンドルネーム「レイ」さんが次のような具体的提案を寄せています。「孤児である子達が大きくなった時、教育を十分に生かして、悲しい思いをせずに暮らせるようになっていればいいなあ、、と思います。それから、岡田さんのお話にあった、アフリカの大地に広がる、日本と同じ田んぼの風景、をふと思い浮かべてみて、そういえばアフリカでお米を作る、、というのは一体どういうことかな?という疑問がわきました」「それで少し今調べてみたら、色々分かりました。まず、アフリカでもお米の需要が今はとても高くなっていること、(祖先が東南アジア人であるマダガスカルの人たちは、もともと主食がお米なのだそうですが)、ネリカ米という、アジアイネとアフリカイネを掛け合わせた、アフリカの環境にあったお米ができて、生産が十分にできるようになったこと、また、お米に関する優れた技術・支援のノウハウを日本が持っていることなどがあるのだそうですね。なるほど、、と思いました!アフリカでもお米の消費が増えた理由の一つに、調理が簡単、ということがあるらしいのですが、確かにテレビでみたところ、トウモロコシの粉をお鍋の中でこねるのは、力が要りそうで大変そうでした、、。でも美味しそうだし、立派な食文化として、これからも主食の座を守っていってもらいたい気持ちです!」
ということで、冒頭の写真は、タンザニアの大規模水田を見る岡田外相。規制制度改革で、JA潰しを狙っているとされる岡田さんですが、別段海外から安い輸入米で日本を席巻するようなせこい人ではありません。
読売国際協力賞は、読売新聞創刊120周年を記念して1994年に創設。選考委員は、「佐藤謙・世界平和研究所理事長」ら5人。
まあ、読売新聞ももっと、岡田さんの活動を中立公正に報道して欲しいものですね。
それはさておき、岡田克也59歳。極端な新自由主義者との観測もありますが、「今思い切って国を開かないと日本は潰れる」と公言する岡田さん。日本のセールスマンとして、世界の中のJAPANへ。岡田克也の可能性への挑戦はまだまだ続きます。
[お知らせ]
衆議院解散はいつか。その答えはこの日程表にある。会員制ブログ(月840円)。
今後の政治日程 by 下町の太陽
国会傍聴取材の活動資金にもなりますので、ご協力をお願いします。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
国会での審議を中心に地道な政治報道を続けられるようご支援をお願いします。
[お知らせおわり]
tag http://www.kantei.go.jp/jp/fukusouri/press/ http://regimag.jp/b/sample/list/?blog=65
田中けいしゅう法相(田中慶秋法相)が、ヤクザ(指定暴力団稲川会)の息子の仲人を務めたと報じた三文雑誌「週刊新潮」の報道について、岡田克也副総理は発売翌日の2012年10月12日(金)の定例記者会見で「30年前の事件だし、しかも後から知ったと言うことで、私は何か辞めなければいけないような問題ではないと思います」と述べ、自民党の安倍晋三総裁の辞任要求を退けました。
自民党(自由民主党)の安倍晋三総裁は発売当時の11日、「私はまだその記事をよく読んでいないんですが」と断ったうえで、「法的な問題点も含めて、どのような問題があるのか。(ヤクザと法相は)どれくらい深い関係か」「法務大臣は法律の番人でありますから、その基本のところが分かっていないとなれば、どう対応していくかということは考えなくてはならない」とし、田中法相の辞任を要求する考えを示唆していました。
[画像]ヤクザと田中法相の関係について、「法務大臣は法律の番人」と主張した自民党の安倍晋三総裁=自民党ウェブサイト内動画をスクリーンショット。
稲川会は、戦後横浜港の利権を乗っ取ろうとしたところ、地元港湾荷役のエース「藤木組」(現・藤木企業)が死守し、旧三菱財閥(日本郵船)、旧三井財閥(三井物産)との共同出資会社「三協」を設立。ヤクザを横浜港から排除しました。藤木さんは、三菱地所「横浜ランドマークタワー」の10階にスタジオがあり、最上階297メートルから電波を出している神奈川県、横浜市出資の第3セクター「FM横浜(横浜エフエム放送)」の実質の創業者です。FM横浜はサラ金のCMを流さない優良放送局として知られます。
稲川会は官官接待の街関内(かんない)のみかじめ料や、伊勢佐木町のバカラ賭博開帳で糊口をしのいできました。すなわち、神戸港における山口組と違い、稲川会は「負け組ヤクザ」でしかありません。関内は官官接待問題ですたれ、伊勢佐木町は松坂屋が閉店するなど、稲川会がいる街は滅びる傾向があります。稲川会は生活に困っているから、三文雑誌の取材に応じたのでしょう。ヤクザが雑誌で話して法相が辞任する事態になれば、せっかく経済的に困窮しているヤクザに再び利権を与えることになりかねません。
ヤクザは百害あって一利無し。いや、三利ありと申し上げましょう。それは、警察と読売新聞と三文雑誌(週刊新潮・週刊大衆・大阪スポーツ)のメシの種である。それ以外は、何一つ、付加価値を生みません。ヤクザがいて喜ぶのは、傍流警察官と読売新聞社会部と三文雑誌だけです。ヤクザは日本にしかいません。だから、警察庁・テレビ・新聞が「暴力団員」と表現するのは不自然で、世界と同じく「(ジャパニーズ)ヤクザ」と呼ぶべきです。ヤクザは日本の恥です。ヤクザは社会の屑です。
ヤクザは日本の閉鎖性の裏返しです。
ヤクザは完全に消し去るべきです。
ヤクザは河原に集めて、油をかけて、灰にすべきです。
これがホントの「暴ハイ(暴排)」です。
私は数年以上ヤクザを見かけた認識がありません。高利貸しの衰退で、ヤクザは虫の息です。今こそ稲川会、住吉会、工藤会をはじめとして山口組も含めてヤクザをつぶすべきです。自民党東京都連も住吉会、稲川会、国粋会をつぶす活動をすべきです。ヤクザと政治家の関係について、民主党閣僚の姿勢を自民党が正面から追及するのも第181臨時国会の重要な議題となりそうです。政党に関係なく、日本のために、自民党の徹底的な攻撃を期待したいところです。
tag http://www.kantei.go.jp/jp/fukusouri/press/ http://regimag.jp/b/sample/list/?blog=65
このエントリー記事の本文は以上です。
平成24年9月14日付の経済産業省の定例幹部人事(通常国会閉会に伴い発令)で、次官級の経済産業審議官を務めていた岡田秀一(おかだ・ひでいち)さんが経産省を退職しました。すでに1年前から1年後輩の事務次官が誕生していましたが、岡田さんの退職で昭和51年(1976年)4月1日、通産省入省組は36年半たって全員同省をさったことになります。城山三郎さんが通産省を描いた小説『官僚たちの夏』が出版された後、最初の入省となった昭和51年入省組でしたが、だれ一人事務次官になれませんでした。
通産省昭和51年入省組は入省4年後に第2次オイル・ショックという国難を経験しました。このとき、通産省(資源エネルギー庁)石油部計画係長だった岡田克也副総理は、「イラン・イラク戦争とか、第2次オイルショックのときでしたので、大変忙しくしてましたので、マージャンをやる暇なかったのですが、楽しく仕事をさせていただきました」とその感想を述べています。
岡田秀一さんは小泉純一郎首相誕生と同時に首相官邸に出向し、首相秘書官を務めました。小泉内閣メールマガジンの発刊は「総裁選公約達成第1号」として多くの登録者を得て、飯島勲・政務秘書官の「ワイドショー政治」とともに、日本の「9・11」、2005年9月11日の第44回衆議院議員選挙の小泉圧勝をもたらしました。このとき、野党第1党で惨敗した民主党代表が岡田克也さんでした。
そして「3・11」では、細野哲弘・資源エネルギー庁長官、寺坂信昭・原子力安全・保安院長が通産省・経産省の長年の原子力政策について、情報隠蔽体質があったことを激しく批判され、昨夏退職しました。
一方、大分県知事に通産省出身者の名物知事(平松守彦前知事)が生まれて以降、通産官僚・管区経済産業局長経験者は知事の人材供給源となりました。初の女性大阪府知事、沖縄県知事もそうですが、昭和51年入省組では、富山県出身の高橋はるみさんが経産局長を務めた北の大地・北海道に渡り、北海道知事になり、ガンも乗り越え3期目(任期は2015年統一地方選まで)に入っています。
『官僚たちの夏』では、ラストシーンで主人公が新聞記者から「ケガしても突っ走るような世の中は、もうそろそろ終わりや。通産省そのものがそんなこと許さなくなってきている」と言われるシーンがあります。第180国会の3月8日の衆院予算委員会では、自民党の小池百合子さんが「かつて城山三郎さんが「官僚たちの夏」で、当時の商工省の活躍……(発言する者あり)当時。もう通産省になっていましたか。その事務次官までされた方ではありますけれども、あのころと経産省の役割そのものがもう変わってきているんじゃないだろうかと思うんですよ」と言及しています。この人物は、三木武夫通産相のころに通産事務次官をつとめた佐橋滋さんを描いていることになりますが、佐橋さんは1975年の小説でも、2012年の国会でも「時代遅れ」と指摘されたことになります。
時代遅れを指摘された「官僚たちの夏」1期生は時代の変化に激しく職業人生を左右される運命の子となりました。そのなかで、「同期入省は1人しか次官になれない」という鉄の掟のなかで、優秀な人材が潰れていった気がします。同期入省は1人しか次官になれないという霞が関のルールは、戦前にはなく、広田弘毅・吉田茂という戦争を挟んで外相・首相を務めた2人は同期入省11人で2人とも外務事務次官を務めています。事務次官は吉田、広田の順で、大臣・総理は広田、吉田の順でした。
この2人について、同じく城山三郎さんが広田の人生を描いた『落日燃ゆ』では「2人は同期というだけでなく、語学好きのいわゆる能吏タイプでなく、どこか国士風なところが似通っているのか、ふしぎによく気が合い、機会があるごとに、吉田が広田を訪ねてきて話し込む仲であった」と書いています。このように「同期から事務次官は1人」というルールがなかった時代には、同期同士が国策を話し込むというシーンがあったようです。そして、『落日燃ゆ』は、極東国際軍事裁判(東京裁判)の判決を受けて、1948年12月23日午前0時20分、広田弘毅が巣鴨プリズンでA級戦犯として絞首刑を執行されるラストシーンで・・・終わりません。その同じ日の夜、少数与党の第2次吉田内閣が野党による内閣不信任案の提出と可決を受けて、現行憲法下最初の衆議院解散(なれあい解散)に打って出て、吉田民自党が単独で269議席(占有率57・7%)で地滑り的圧勝(第24回総選挙)を収め、長期政権の土台を気付いたことと対比させたうえで、「「日本を滅ぼした長州の憲法」の終焉を告げる総選挙でもあった」との一文で終わります。このしめくくりの一文は小説全体を通すと違和感がありますが、城山さんの本音が込められたことがよく分かります。それを主人公の広田と同期の吉田首相の活躍と対比させて描いたことになります。
吉田茂は戦後初の国葬となり、大勲位。広田家は遺骨(他の軍人と一緒になったもの)の受け取りを拒否し無縁仏の状態となり、霊は靖国神社に合祀されていますが、広田家が参拝したことはないようです。東条英機、松岡洋右、白取敏彦ら英霊を殺した人が合祀されているという奇妙な神社になってしまったのが、今の靖国神社です。
このように同期で1人事務次官というルールは終わりを告げるときが来ています。現在も国土交通省、総務省など橋本行革の合併省庁では同期が事務次官になるようになりましたが、採用時点での同期がその省で事務次官になるという事例はまでないと思います。
吉田、広田の2人はいまでも名前が残っています。しかし、「同期1人事務次官」のルールにより、具体的に日の目を見なかった人材の名前というのは、私は知りません。その役所の人は、「あの人」と噂するかも知れませんが、世間では誰も知らない名前です。埋もれてしまった人材の名前というのは残らないんです。
そして、そもそも経済産業省という役所が必要あるのかどうかというところまで私たちは検討しなければならない時期にあります。それはずっと前からそうでした。通商行政は戦前のように外務省に戻し、職員も移管する。原子力行政は文部科学省・環境省に移す。特許庁は内閣府外局にして、文部科学省文化庁の人も入れる。中小企業行政は自治体に移管する。これほど、時代によって自らの存在意義を自ら作って、性質が変わってきた役所は他にありません。それは自民党と経団連の癒着政治(財界の男妾)をエスコートしてきた論功行賞。そして橋本行革を支えた人が通産省出身だったことの論功行賞です。それに経産官僚は悪く言えばチャラい、良く言えば織田信長系の人が多い。いろいろな役所にいけば、良い触媒になります。省としての一体的な維持にこだわるべきでありません。
国家の構成員はすべて、歴史という法廷に立たされたときに、ひるむ生き方をしてはいけません。私益と国益がなるべく一致する生き方をしていると、人生というものは、まあなんとかなるものです。
[お知らせ]
衆議院解散はいつか。その答えはこの日程表にある。会員制ブログ(月840円)。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできますので、気軽に登録してみてください。取材資金にもなりますので、ご協力をお願いします。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
「新党結成」の煽り報道で食べている既存メディアは恥を知れ。国権の最高機関である国会を中心に地道に、本質を見抜いた政治報道を続けられるようご支援をお願いします。
[お知らせおわり]
tag http://www.kantei.go.jp/jp/fukusouri/press/
[写真]野田総理、岡田副総理。
首相官邸前では、毎週金曜日夕方に「再稼働反対、ドンドンドドドン」という抗議運動があります。関西電力の大飯原子力発電所の再起動に反対するデモです。昔の革マル派などの組織とは違い、実行委員会をのぞけば、明らかに参加者は個人で、初老の夫婦や、若者など、おそらく1万人以上が首相官邸前で「ドンドンドドドン」とやっています。私がこの抗議運動(デモ)を意識するようになったのは、6月8日(金)で、衆院議員会館でいろいろと話して、総理の午後6時からの記者会見をラジオで聞きながら帰宅の途につくと、総理の演説の音声が外から聞こえてきます。ハンドマイクで総理の演説を拡声し、ひと言ひと言につっこみを入れる参加者。その総理の演説の声が、第2次世界大戦開戦にあたり国民の結集を呼びかけるジョージ6世の演説と重なる面があり、何とも言えぬ重たい気持ちになりました。
岡田克也副総理は、2012年7月13日の定例記者会見でデモに機動隊が動員されていることについて「機動隊の皆さんは、何か事故が起こらないように、けが人が出たりとか、そういうことが起こらないように御努力いただいているというふうに思います。それは当然必要なことであろうというふうに思います」として、若き機動隊員の諸君に経緯を払いました。すばらしい警備ぶりだと思います。例えば、デモ参加者に「こんにちは」と声をかける係。あるいは、上司というよりも金曜デモ警備の先輩が後輩に教えるときに、「首相官邸とか内閣府とかから職員が出てくるけど、地下鉄の駅に行きたいっていう奴が必ずいるから通しちゃって」と初めてのデモ警備に緊張感を隠しきれない警察官。日本の秩序を守るすばらしい若者たちです。
岡田さんは言葉を続けて、「それから、ここでデモに加わる皆さんの気持ちもそれはそれでよく分かりますので、いろんな自らの考え方を何らかの形で表現したいと思っておられる方が国会議事堂周辺、あるいは官邸周辺にお集まりになるということは、これは一つの意思表示ですから、それについて私がいいとか、悪いとかということではないと思います。ある意味では、それは当然の権利だというふうに思います。」と述べ、デモ参加者の気持ちも分かるし、意思表示は当然だとの考えを示しました。
羽田内閣総辞職による下野から18年、新進党結党から17年。やっと昨年9月から、新進党三羽がらす(野田佳彦首相、藤村修官房長官、今年1月から岡田克也副総理)が官邸をやるようになったのに、この苦難の連続はなんでしょう。一体改革の採決を翌週に控えた6月22日(金)には、副総理会見で「宮崎さんいい質問しましたね」とお世辞を言ってもらった後に、「火の用心」のために赤坂議員宿舎に向かい、その途中で首相官邸前を通りました。このとき、「原子力の火を消すな」というプラカードを見て、デモに反対している人をみました。そして、さらにデモ隊は「笑点のテーマ」を流して反対派を妨害。何なんだこれは。しかし、新進党勢が官邸をやっている中での、この我が国の歴史に例を見ない事象に、その後も、「再稼働反対ドンドンドドドオン」という太鼓の音が耳から離れることはありませんでした。
しかし、1年前ならいざしらず、今の私は「こんなに大変なら、官邸は自民党さんにやってもらった方がいいかな」という気がまったくしなくなりましたね。官邸を背負うことの重荷はずっしり感じますが、投げ出して自民党にやってもらおうという気持ちは持たなくなった。それだけでも、私の中での政権交代の成果です。いずれにしろ、1年で選挙ですから。
政権を担うという重荷を分かち合いながら前に進む。それが新進党結党の志です。第1次民主党結党メンバーの中には、後ろから鉄砲を撃つような奴もいますが、所詮は「与党でもない野党でもないゆ党」です。もちろん第1次民主党のメンバーにも、安住淳財務相、玄葉光一郎外相、枝野幸男経産相、古川元久経財相ら優れたメンバーもいます。
「日本の海が荒れている・・・」新進党結党大会冒頭の詩人の句です。どんな苦境でも、野田官邸の正しさは歴史が評価します。前に進むしかありません。新進党結党の志と団結心があれば、どんな苦難でも乗り越えられます。
最後に、総理の大飯原発再稼働についての記者会見をつけますので、歴史法廷の判断材料にしていほしいと考えます。
[野田佳彦首相2012年6月8日(金)記者会見(首相官邸ホームページ)から引用はじめ]
【野田総理冒頭発言】
本日は大飯発電所3、4号機の再起動の問題につきまして、国民の皆様に私自身の考えを直接お話をさせていただきたいと思います。
4月から私を含む4大臣で議論を続け、関係自治体の御理解を得るべく取り組んでまいりました。夏場の電力需要のピークが近づき、結論を出さなければならない時期が迫りつつあります。国民生活を守る。それがこの国論を二分している問題に対して、私がよって立つ、唯一絶対の判断の基軸であります。それは国として果たさなければならない最大の責務であると信じています。
その具体的に意味するところは2つあります。国民生活を守ることの第1の意味は、次代を担う子どもたちのためにも、福島のような事故は決して起こさないということであります。福島を襲ったような地震・津波が起こっても、事故を防止できる対策と体制は整っています。これまでに得られた知見を最大限に生かし、もし万が一すべての電源が失われるような事態においても、炉心損傷に至らないことが確認をされています。
これまで1年以上の時間をかけ、IAEAや原子力安全委員会を含め、専門家による40回以上にわたる公開の議論を通じて得られた知見を慎重には慎重を重ねて積み上げ、安全性を確認した結果であります。勿論、安全基準にこれで絶対というものはございません。最新の知見に照らして、常に見直していかなければならないというのが東京電力福島原発事故の大きな教訓の一つでございました。そのため、最新の知見に基づく30項目の対策を新たな規制機関の下での法制化を先取りして、期限を区切って実施するよう、電力会社に求めています。
その上で、原子力安全への国民の信頼回復のためには、新たな体制を一刻も早く発足させ、規制を刷新しなければなりません。速やかに関連法案の成案を得て、実施に移せるよう、国会での議論が進展することを強く期待をしています。
こうした意味では、実質的に安全は確保されているものの、政府の安全判断の基準は暫定的なものであり、新たな体制が発足した時点で安全規制を見直していくこととなります。その間、専門職員を要する福井県にも御協力を仰ぎ、国の一元的な責任の下で、特別な監視体制を構築いたします。これにより、さきの事故で問題となった指揮命令系統を明確化し、万が一の際にも私自身の指揮の下、政府と関西電力双方が現場で的確な判断ができる責任者を配置いたします。
なお、大飯発電所3、4号機以外の再起動については、大飯同様に引き続き丁寧に個別に安全性を判断してまいります。
国民生活を守ることの第2の意味、それは計画停電や電力料金の大幅な高騰といった日常生活への悪影響をできるだけ避けるということであります。豊かで人間らしい暮らしを送るために、安価で安定した電気の存在は欠かせません。これまで、全体の約3割の電力供給を担ってきた原子力発電を今、止めてしまっては、あるいは止めたままであっては、日本の社会は立ち行きません。
数%程度の節電であれば、みんなの努力で何とかできるかもしれません。しかし、関西での15%もの需給ギャップは、昨年の東日本でも体験しなかった水準であり、現実的には極めて厳しいハードルだと思います。
仮に計画停電を余儀なくされ、突発的な停電が起これば、命の危険にさらされる人も出ます。仕事が成り立たなくなってしまう人もいます。働く場がなくなってしまう人もいます。東日本の方々は震災直後の日々を鮮明に覚えておられると思います。計画停電がなされ得るという事態になれば、それが実際に行われるか否かにかかわらず、日常生活や経済活動は大きく混乱をしてしまいます。
そうした事態を回避するために最善を尽くさなければなりません。夏場の短期的な電力需給の問題だけではありません。化石燃料への依存を増やして、電力価格が高騰すれば、ぎりぎりの経営を行っている小売店や中小企業、そして、家庭にも影響が及びます。空洞化を加速して雇用の場が失われてしまいます。そのため、夏場限定の再稼働では、国民の生活は守れません。
更に我が国は石油資源の7割を中東に頼っています。仮に中東からの輸入に支障が生じる事態が起これば、かつての石油ショックのような痛みも覚悟しなければなりません。国の重要課題であるエネルギー安全保障という視点からも、原発は重要な電源であります。
そして、私たちは大都市における豊かで人間らしい暮らしを電力供給地に頼って実現をしてまいりました。関西を支えてきたのが福井県であり、おおい町であります。これら立地自治体はこれまで40年以上にわたり原子力発電と向き合い、電力消費地に電力の供給を続けてこられました。私たちは立地自治体への敬意と感謝の念を新たにしなければなりません。
以上を申し上げた上で、私の考えを総括的に申し上げたいと思います。国民の生活を守るために、大飯発電所3、4号機を再起動すべきというのが私の判断であります。
その上で、特に立地自治体の御理解を改めてお願いを申し上げたいと思います。御理解をいただいたところで再起動のプロセスを進めてまいりたいと思います。
福島で避難を余儀なくされている皆さん、福島に生きる子どもたち。そして、不安を感じる母親の皆さん。東電福島原発の事故の記憶が残る中で、多くの皆さんが原発の再起動に複雑な気持ちを持たれていることは、よく、よく理解できます。しかし、私は国政を預かるものとして、人々の日常の暮らしを守るという責務を放棄することはできません。
一方、直面している現実の再起動の問題とは別に、3月11日の原発事故を受け、政権として、中長期のエネルギー政策について、原発への依存度を可能な限り減らす方向で検討を行ってまいりました。この間、再生可能エネルギーの拡大や省エネの普及にも全力を挙げてまいりました。
これは国の行く末を左右する大きな課題であります。社会の安全・安心の確保、エネルギー安全保障、産業や雇用への影響、地球温暖化問題への対応、経済成長の促進といった視点を持って、政府として選択肢を示し、国民の皆様との議論の中で、8月をめどに決めていきたいと考えております。国論を二分している状況で1つの結論を出す。これはまさに私の責任であります。
再起動させないことによって、生活の安心が脅かされることがあってはならないと思います。国民の生活を守るための今回の判断に、何とぞ御理解をいただきますようにお願いを申し上げます。
また、原子力に関する安全性を確保し、それを更に高めていく努力をどこまでも不断に追及していくことは、重ねてお約束を申し上げたいと思います。
私からは以上でございます。
【質疑応答】
(内閣広報官)
それでは、質疑に移ります。
指名された方は、まず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。
それでは、どうぞ。
(記者)
読売新聞の望月です。
総理、今週は4日に引き続いて2度目の会見となり、御苦労様です。
福井県知事の要望に応じられて、今回の会見に至られたのだと思いますけれども、先ほどの会見で、要するに夏場の電力需要を乗り切るためだけでなく、日本の経済、エネルギー安全保障上も原子力が重要な電源であるという認識をお示しになられたのだと思いますが、そうしますと、丁寧に御検討されるとおっしゃいましたが、大飯以降の他の原発の再稼働のスケジュール感について、どのようにお考えになられるのか。
あるいは今、おっしゃられましたが、中長期のエネルギーの割合を政権としてどのように考えられるのか。8月をめどにまとめられるとおっしゃいましたけれども、今現在、2030年の原子力の割合などが議論になっていて、総理の今のお話ですと、これはゼロにはできないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。また、その場合、40年の廃炉ルールなどには齟齬が出てこないのかも含めて教えていただければと思います。
(野田総理)
最初は会見の意義みたいなところだと思いますけれども、福井県知事のみならず、福井県民の思いを重く受け止めつつ、今日は国民の生活を守るという観点から、再起動は必要であるという私の考え方を基本的に御説明したいという意味での会見をさせていただきました。
再起動の安全性、必要性については、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、当面の夏場の需給だけの問題ではなくて、これはエネルギー安全保障であるとか、あるいは国民生活や経済への影響、特に国民生活、経済への影響で言うならば、これは電力価格が高騰することによって国民の負担が増えてはいけないんですが、そういうことを抑制しなければいけない等々の観点、日本の経済、社会全体の安定ということを考えての判断であるということであります。
大飯以外のスケジュールのお話でございますけれども、これは大飯と同様に、スケジュールありきではいかなる再起動も考え得ません。引き続き、丁寧に個別に安全性を判断していくというプロセスをたどっていきたいと思います。
最後に、中長期のエネルギーの割合の話が出ましたけれども、ちょうど今日のエネルギー・環境会議が行われまして、その選択肢についての中間整理を行わせていただきました。こうした中間整理なども踏まえまして、国民的な議論を行いながら、御指摘があったとおり、8月をめどに国民が安心できるエネルギーの構成、ベストミックスというものを打ち出していきたいと考えております。
(内閣広報官)
それでは、次の方どうぞ。
佐藤さん、どうぞ。
(記者)
日本テレビの佐藤です。
原発も非常に重要ですけれども、消費税関連の一体改革、関連法案も大詰めですので、こちらをお伺いしたいのですが、今日、修正協議が始まり、15日までに合意を目指すということで、総理の決意を改めてお伺いしたいというのが1点。
自民党の石原幹事長は、社会保障面の最低保障年金については、国民会議を設置して、そこで議論をしてもよいとおっしゃっております。この国民会議についての総理の御見解をお伺いしたいと思います。
最後にもう一点ですが、法案を成立させるには会期の延長も避けられないと思いますが、総理の頭の中にある会期の延長幅、これは9月の代表選挙を超えるような大幅な会期延長も想定されているのかどうか。その見解を伺いたいと思います。
(野田総理)
まず、今日から本格的な修正協議がスタートをいたしました。この協議については、昨年からの課題でありまして御要請をしてまいりましたけれども、自民党、公明党、やはり国民のために結論を出さなければいけない重要な課題だと御認識をいただき、こうした協議に応じていただいたことに感謝を申し上げたいと思いますし、加えて、この改革の方向について御賛同いただいているその他の会派の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。
これは、先送りのできない課題であります。したがいまして、今、会期は6月21日まででございますので、それまでに当然のことながらG20に私は行かせていただきたいと思います。この世界経済が不透明な状況の中で、日本としての立場は明確に打ち出さなければいけません。
そういうことを考えると今日も協議の場で御議論があったと思いますけれども、15日までの間に決着をつけるべく、最大限の努力をされるということでございますので、そうしたスケジュール感の中で真摯な議論が行われること、そして成案を得ることを強く期待したいと思います。
そこで、石原幹事長の話もございましたけれども、要は法案としては7本出しています。その7本について協議に基づいて私どもは成立をさせたいと思います。その上で中長期に関わる問題をどうするかという議論も当然あると思いますが、その道筋をどうつくり出すかということは、先ほど御提起のあった国民会議の問題もそこに含まれると思いますけれども、そういうものも含めて結論が得られるような議論を期待したいと思います。
会期の問題は、これはこの一体改革だけではなくて政治改革の問題とか、この6月21日までの間に、何としてもその他の法案も成立を目指さなければいけないものがたくさんございます。まずはそこでできるだけ多く御提出をしている法案であるとか、あるいは結論を出さなければいけないテーマについて結論を出すことに今はベストを尽くす段階であって、その後の幅の問題を現段階で申し上げる段階ではないと思います。
(内閣広報官)
それでは、次の方。
それでは、浜田さん、どうぞ。
(記者)
ロイター通信の浜田と申します。
長期的な将来の脱原発依存を実現する上で、原発事業の体制は従来どおり国策民営が望ましいのか、電力会社から原発を切り離して国が事業に関与する体制に移行すべきなのか、原発の事業体制の見直しに関する議論の必要性、検討の必要性について総理のお考えをお聞かせください。
(野田総理)
事業体制について、現時点で今政府として何らかの方向性を持っているわけではございません。その事業体制を考える前に、その前にやるべきことがあると思っております。それが先ほど来御議論というか御指摘もいただいておりますけれども、8月をめどにまとめようとする、まさに中長期の国民が安心できるエネルギー政策の在り方、そこをまず決めていくことが大事ではないかと思いますし、これは国民各層のさまざまな御議論もいただきながらまとめていきたいというふうに思います。
(内閣広報官)
それでは、時間が来ておりますので、最後の質問とさせていただきます。
それでは、七尾さん、どうぞ。
(記者)
ニコニコの七尾です。よろしくお願いします。
本日、先ほど行われた国会事故調で福島第一原発事故の際の政府対応の問題点が幾つか改めて浮き彫りになりました。そこで御質問なのですが、原子力規制組織の法案に関わります、今、国会で審議しており議論が進んでいる中で、原発事故の際の総理の指示権の在り方や必要性について改めてお聞かせください。
(野田総理)
政府事故調、そして、今、御指摘いただいた国会事故調、そういうところから出てくる御指摘というものを真摯に受け止めて、二度と去年のような事故を起こさないための対策を講じていくということが何よりも基本だと思いますし、そこから出てくる御意見は真摯に受け止めたいと思います。
その上で、今、与野党間で議論をしている新たな規制の組織の話の中で、総理大臣の権限のところ、今、議論をやっている最中だと思います。かなり煮詰まってきているのではないかという報告を受けております。ここで折り合うことができれば1つの合意形成が大きく前進できるのではないかと思いますので、その動きを今注視しているところでございます。
(内閣広報官)
それでは、時間がまいりましたので、これで総理会見を終わります。どうもありがとうございました。
(野田総理)
どうもありがとうございました。
[引用おわり]
[お知らせ]
衆議院解散の日程を別ブログで解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。
あおり、扇動のない国会審議を日めくり式につづっていく政治報道をしています。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
政権交代ある二大政党政治の実現に向けて、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]
[画像]「59歳、59歳、と何度も言われるとうれしくありません」・・・首相官邸ホームページ内動画からキャプチャ。
おめでとうございます。
2012年7月14日(土)、岡田克也さんは59歳の誕生日。
7月13日(金)の定例記者会見で、当ブログが「59歳は還暦の一年前」「岡田さんが尊敬する織田信長の人生は48年、縁のある孫文の人生は58年だった」と指摘すると、「意図がよく分かりません」「あまり59歳、59歳と言われるとうれしくありません」としながら、
「これからの一年は激動の一年だということだと思います。衆院選も参院選もあるということですから、日本の政治にとっても、民主党にとっても。そういうなかを、国民のみなまさに理解をいただきながら政権交代という歴史的なできごとがあって、その成果を国民に伝わり、それを深めていく一年にしたい」と語りました。
第21期参議院は2013年7月29日に任期を迎えますが、公職選挙法(公選法)第32条は「参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終わる日の前30日以内に行う」「通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない」となっており、2013年7月14日の還暦は、選挙戦のさなかに迎える可能性が極めて高くなっています。
岡田さんは「大変な時期であることは間違いありません。世界経済にとっても、非常に厳しい状況だし、国内は大震災があり、原発問題もあったということですから。その数年、与党であったということは何らかの巡り合わせですけど、その中で責任を果たさなければなりません」と語りました。

[写真]偉大な(偉大過ぎる?)両親、岡田卓也さん、岡田保子さん、日経新聞「私の履歴書」から。
[写真]恵まれた幼児期。
[写真]物憂げだった東大法学部学生時代。
[画像]36歳で非世襲ながら自民党公認で初当選=NHK映像から。
[画像]初当選と同時に「これから20年、30年かけて今の初心を忘れずに」=フジテレビ。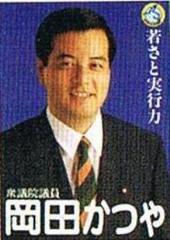
[写真]「若さと行動力 衆議院議員 岡田かつや」という自民党にありがちな抽象的なキャッチフレーズ。

[画像]第20回参院選の報道、日経新聞、2004年7月。
岡田さんは、土井たか子さん以来の自民党以外で参院改選第1党の大勝利を呼び込んだ党首です。どうもこの印象はない人が多いようで、まあテレビの見過ぎですとしか言いようがありません。
1990年、ベルリンの壁崩壊後初の第39回衆院選に初出馬したときは苦戦したものの、渡部恒三自治大臣が応援演説にかけつけ、「岡田君を当選させてもらえば、みなさんの要望は私が責任をもって実現する」と応援演説し、集まった自治会長たちの期待感が一挙に高まった(「政権交代」68ページ)そうですが、先日は、衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会の法案可決の打ち上げで、恒三さんから「20年間付き合っていて初めておごってもらった」と言われたと明かしています(7月6日の定例記者会見)。

[写真]15年越しの政権交代を実現したものの、与党して東日本大震災という未曾有の国難に遭遇。渡部恒三さんと。
岡田さんは記者会見での「これから何年間政治家をやるのか」との質問に「それは私が決めることではなく、有権者が決めることですよね」と当たり前すぎるけど、最近の政治家が分かっていない原則を話した上でこう語りました。
「長くやればいいとは思っていません」。
[画像]59歳の副総理になっても、走り続ける。
[お知らせ]
衆議院解散の日程を別ブログで解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。
あおり、扇動のない国会審議を日めくり式につづっていく政治報道をしています。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
政権交代ある二大政党政治の実現に向けて、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]
民主党、自民党、公明党は15日(金)の3党合意に向けて、社会保障と税の一体改革関連3領域7法案の修正を進めています。税制分科会の自民党実務者は町村信孝さん。第45期衆議院では、北海道5区で落選し、比例北海道で復活当選しましたが、その議席をかなぐり捨てて、北海道5区の補欠選挙で圧勝したので、現在は当選10回生、二ケタになっています。
イヤミなマッチー。
第45期衆議院の50人委員会で自民党理事の配分は2人だけ。攻撃的なマッチーは自民党第2次野党期最初の予算委筆頭理事として、次席理事に先輩の加藤紘一さんを従え、イヤミぶりを発揮。先陣を切って自ら質問に立ち、「これ以上質問できませんな」といすに座り審議拒否しようとしたところ、加藤次席理事が第一委員室にいないことに気付きました。場内協議をする理事がいないので、あわてて質問を続けるという野党慣れしていない場面もありました。
衆議院社会保障と税の一体改革特別委員会(中野寛成委員長)でも、理事の座は伊吹文明元幹事長と逢沢一郎前国対委員長の谷垣禎一総裁と仲が良い2人組にとられました。町村さんは委員として審議を見ていました。自民党税制調査会は会長が野田毅さんで、伊吹さん、町村さんは顧問です。野田毅さんも一体改革特別委員を務めていますが、3党修正の実務者の座は、町村さんが取りました。このレイヤー(3党協議税制分科会)は、衆参ねじれ(第45期衆議院・第21期22期参議院)以降、民主党の藤井裕久、公明党の斉藤鉄夫、自民党の野田毅の各党税調会長の指定席でした。ただ、これは新進党トリオなので、会期末の「ハプニング解散」も期待して、イヤミなマッチーが自民党実務者になったんだと思います。
副総理の岡田克也さんは、2012年6月8日(金)の定例記者会見で、通産省時代に町村さんの部下として2回働いたことがあることを明かしました。町村さんは昭和44年(1969年)入省、岡田さんは昭和51年(1976年)入省。
岡田さんが24歳のころ、産業政策調査課で、杉山弘課長(後に事務次官)のもと、町村信孝課長補佐、岡田克也総括係長として、直属の上司、部下の関係だったとしました。このときは河本敏夫通産大臣で、「名目GDP7%成長」をかかげて、その経済政策の立案に関わったとしています。新成長戦略の「名目3%成長、実質2%成長」に四苦八苦の今では考えられない時代です。
やはり余裕のある時代だったようで、岡田さんは「大変マージャンのお好きな課長だったので、課長さん命令の下、マージャンのメンツを揃えるのも私の重要な仕事だった」と述べました。
「もう一回はもう少し時間が経って、(資源エネルギー庁)石油部というところで私が計画係長、町村さんが石油企画官という、これはラインは一緒ではないのです。我々は総括ラインで、町村さんはもう一つ違うラインだったので、同じ部屋の中で仕事をした、同じ課の中でということです。このときもイラン・イラク戦争とか、第2次オイルショックのときでしたので、大変忙しくしてましたので、マージャンをやる暇なかったのですが、楽しく仕事をさせていただきました」と語りました。
岡田さんは11年前、当選4回生のころ、朝日新聞の早野透編集委員のインタビューについて次のように答えています。(朝日新聞社 1冊の本 8月号政治家の本棚「世界の名著に線を引き引きトライ」早野 透 Hayano Toru 朝日新聞編集委員から)
[引用はじめ]
(前略)それが終わって第二次オイルショックで石油を扱って、緊急事態法制をつくったり、灯油とかガソリンの配給切符をつくって倉庫に仕舞い込んだりね。
◎―――そんな事態まで行ってたんでしたっけねえ。
岡田――そうです。あんまり表に出しませんでしたけど。
◎―――珍しい話だな、それ。
岡田――第二次オイルショックの役所の対応は、隠れた成功物語だと僕は思いますけどね。情報開示をしなかったと言われればそれまでなんですが、「大丈夫」だと言い続けながら配給のための法律とかの案は全部つくって、かなり忙しかった。かなり厳しい実態をそう大きな混乱なく乗り切ったんですね。(後略)
[引用おわり]
朝日新聞の有名な政治記者だった早野透さんが知らないほど、第2次石油危機(オイルショック)は瀬戸際まで行っていたということになります。世界的には、「オイルショック」とはこちらの第2次(1979年)のことの方をさすのですが、我が国では1973年の第1次オイルショックをさすことが多いでしょう。きょうの日経新聞2面にもヨドバシカメラの取締役・店長が「33年間、売り場に立っているけど、今が一番苦しい。オイルショックの時よりひどいね」と語っていますが、このオイルショックも第1次を念頭に置いているのでしょう。もちろん、過去33年間で一番苦しいのですから、第1次も第2次も含めてということでしょうが。
岡田さんは著書『政権交代-この国を変える』のなかで、石油部計画係長のころ、「いたずらに買い占め騒動を起こさせないために、秘密厳守が徹底され、石油行政に関して報道されることはほとんどなかった」「当時、この配給制度のことを知っていたのは、通産省でも限られたスタッフだけだったはずだ」「このときの大きな国家的試練をさしたる混乱なく乗り切った当時の通産省の対応は、情報開示をしなかったという批判はまぬがれないとしても、秘められた大きな成功物語だったと思う。こうした経験から私は、緊急事態において、国民の生活を守る最後の砦であることを実感していた」。
私はオイルショックについては記憶にないので、今の国難とどう違うのか、質問してみました。
岡田さんは次のように答えました。
[記者会見録から引用はじめ]
(記者)
すみません。
2度目の石油部石油課のときは、例のオイルショックで、石油の配給切符を実は印刷していたと、そのころですね。
(岡田副総理)
ええ、そうですね。
(記者)
あのとき、かなり国難だったと思いますが、当時の国難と比べて、今どんな時代状況だと思われますか。
(岡田副総理)
それは比較は難しいですけれどもね。ただあれは一時的なショックで、今は財政など見ると、もう少し重い、風邪にかかったのではなくて、肺炎みたいな感じではないですか、今は。相当思い切って、時間をかけないと治癒しないということではないかと思います。
[引用おわり]
[岡田克也公式ホームページから引用はじめ]
朝日新聞社 1冊の本 8月号
政治家の本棚 62
岡田克也氏 おかだ かつや
衆議院議員
民主党政調会長
元通産省企画調査官
1953年7月14日生まれ
◎インタビュー:早野 透 Hayano Toru 朝日新聞編集委員
「世界の名著」に線を引き引きトライ
◎―――昭和二十八年生まれでしょう。戦争の傷跡はほぼどうやら癒えてきた時代ですよね。
岡田――たまに家族で名古屋の動物園に連れていってもらったりというのが楽しみだったんです。まだ引揚者みたいな人が地下道なんかに並んでいて、非常に印象に残っていますね。戦争の傷跡というとそれぐらいですね。
◎―――育った三重県四日市市は?
岡田――「四日市」ですからね、もとは商業の町です。戦後、旧海軍廠の跡にコンビナートができた産業都市で、「発展する若い町」というイメージだったんですが、小学生の頃に公害問題が顕在化して、同級生でぜんそくに悩んでいた人もいたし、後に亡くなった人もいました。「公害の町」というイメージをいまだに引きずっていますよね、もういまはないんですけれども。
◎―――父上のジャスコはその頃もう動き出したんですか。
岡田――もともと呉服屋を二百年ぐらい続けてきた家が戦後、売るものがなかったものですから、何でも売るようになって地方百貨店だったんですね。
◎―――戦後社会的発展のなかにいたわけですな。小学校は。
岡田――地元の中部西小学校から中部中学校です。父もそうだし、私の子どもも同じですけどね。
◎―――その頃は、本なんかは。
岡田――小学三年生のときに交通事故に遭いまして、骨折して二カ月ぐらい入院したんですよ。田舎で交通事故ってそんなに多くなかったですからテレビニュースになりました。そのときに読んだのが『シートン動物記』とか『ファーブル昆虫記』。
◎―――勉強家でしたか。
岡田――母親に言わせると、学校では優等生のふりをしていた、家では違ったと言うんです。僕、三人兄弟の真ん中なものですから、かなり生存競争は厳しかった。男三人の真ん中というのは『次郎物語』と同じ構図なんですね。だから『次郎物語』って好きだったんです。でもまあ、小・中学校は地方都市でわりと暢気に過ごしましたね。
◎―――学校の生徒会なんかは。
岡田――小学校のときは生徒会長とかに立候補して百七対百で当選した記憶がありますね。
◎―――接戦だな、こりゃ。
岡田――ええ、負けた相手は後期の生徒会長をやりました。中学校はテニスクラブでかなり熱心にやりましたので、立候補しませんでした。
◎―――勉強は?
岡田――いやなものはいやなんですね。やらないんですよね。覚えるのが非常に苦手なものですから。社会とか得意じゃなかった。英語はもう不得意でしたね。
◎―――現在の民主党政調会長ぶりとはぜんぜん違うじゃないですか、それは。
岡田――中学校で英語で「5」だったのは一年生の一学期だけで、ずっと「4」だったですね。僕、家の都合で高校から大阪に行ったんですよ。中学校の友だちが「岡田が東大へ行くとは思わなかった」って言いますから。
◎―――大阪教育大付属池田高校ですね。
岡田――父が大阪で新しく会社を合併してつくる、それがジャスコなんです。兄は高校三年生で、弟が小学六年生だったものですから、きりが悪いから一年間待つ。「おまえはどうするか」と言われて「それじゃ大阪へ行くか」と。国立大学ですから受験も公立より早かった。それに受かれば北野高校を受けようかと思っていたんですが、通った途端に面倒くさくなってそこは受験しませんでした。一年間は大阪で父親と二人で生活して、父も半分くらいしかいませんでしたから、多少自炊みたいなことをして。一年は寂しかったですね。高校は紛争で二カ月ぐらい閉じちゃうし。
◎―――どうしてですか。
岡田――大学紛争の生き残りが高校に来て叱咤激励した。三年生に西川ってのがいましてね、後に「ハーグ事件」を起こした、あれは赤軍派ですか。ある日学校に行ったら閉まってて、封鎖ですね。私は田舎から出てきた一年生で、目が回るような、よくわからないような......。
◎―――バリケードつくったり、閉じこもっていたりしてたわけですか。
岡田――そうですね。学校の授業はやっていなかった。授業がないから集まって討論です、僕らは反対派ですけどね。三年生になって、日本史の先生が「君らが紛争のときに言ったような受験教育一辺倒の授業は私はしない」って宣言して、「私は近代しか教えないから、明治より昔は君たち自身で教科書を読んで勉強しろ」って言って、大学レベルの授業をやってくれたんですよね。いま同級生が集まると、「あの授業がいちばん印象深い」という話になりますね。
◎―――その頃は勉強はどうでした?
岡田――一年生は勉強しなかったし、成績はよくなかった。二年生はスランプで最悪でしたね。四十人でずうっと三十番台でしたものね。三年生になって心を入れ替えて勉強したということですね。
◎―――なるほどねえ。その頃は少しは記憶に残っている本はありますか。
岡田――あまり読んでいないですね。いろいろ考えごとはしてたような記憶はあるんですが。ともかく大学に滑り込みセーフでした。
◎―――何か本番に強いんだなあ。
岡田――わりと私、頑固ですので、例えば歴史なんかも「絶対おれは年号は覚えないぞ」って決意しましたので、一つも年号は覚えなかったんですね。
◎―――なんでそんな......。
岡田――「そういう無意味なことを強いる教育はおかしい」と。私、東大へ行きたかった理由って、東大の過去問を見ると、年号が出なかったというのが大きかったんです(笑)。うちは代々早稲田で、「なぜ官学なぞに行くのか」っていって怒られたんですが。
◎―――しかし、変わった決意だな。普通は「まあ年号も覚えとこう」というふうになっちゃうけれど。何か自分で方針を立てて実行するという感じがその頃からあったのかしら。
岡田――そうかもしれませんね。
◎―――東京ではまた一人でしょう。
岡田――賄い付きの下宿でしたので食事つき。当時、大学紛争の自主ゼミみたいなものがまだ残っていたんです。折原浩先生のもとで僕らはマックス・ウェーバーを読んでいたんですけれども。『職業としての政治』とか『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』、わからないなりに印象を受けて。自主ゼミでしたので単位にはたぶんならなかったんじゃなかったかなと思うんですが。
あと、佐藤誠三郎さんがアメリカから帰ってきた新進気鋭の政治学者で、まだ三十代だと思うんですね。彼のゼミは毎週、四、五冊読まされるんです。
◎―――佐藤誠三郎さんは官界、学界のいろんなところに弟子がいますね。
岡田――当時、エズラ・ヴォーゲルの本なんかを読みました。彼が日本に来たときに書いたものかな、『日本の新中間階級』。ぜんぜん有名じゃなかったんですけど、後に『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を書きました。のちに私のハーバード留学のときの先生です。あと、ロナルド・ドーア。
◎―――そのへんの学統がつながっているわけか。
岡田――「世界の名著」ってありましたよね。それでキルケゴールとかパスカルとかデカルトとか、全く歯が立ちませんでしたが、何か一生懸命トライしていた時代ですね。小説もずいぶん読みましたけれども、ドストエフスキーがいちばん。最近『カラマーゾフの兄弟』を読み直してみようかなと思ったんですが、全く読めなかった。感受性がたぶんなくなっているんだと思うんですけど。一、二年生は本の虫だった。「世界の名著」などいま読み返すと線があちこちに引いてある。でも、なぜそこに線を引いたのかが全くわからなくて(笑)。小林陽太郎さんの日本アスペンのエグゼクティブ・セミナーというのがありまして、おもに企業人が古典を読む研修なんですね。二年ぐらい前に参加したんです。「週に一時間は読んだほうがいいよ」とそのときアドバイス受けたんですが、なかなかね。
◎―――就職は。
岡田――司法試験は落ちました。もう二度と受ける気がしませんでした。
◎―――あれもめちゃめちゃ記憶しなくちゃいけないからなあ。通産省に入られてどんなことをしていたんですか。
岡田――最初は、中小企業政策。二年目で法律をつくれと言われてから、役所時代はわりと法律をつくることが多かったですね。
◎―――法律をつくるのは、見込みのある若手にやらせる仕事でしょう、霞が関全体を掴むために。
岡田――まあ、各省折衝など一通りありますからね。三年目、四年目はマクロ経済の担当で、福田内閣の河本敏夫通産大臣の頃ですね。課長が杉山弘さんって後の次官、最近、電源開発社長を辞めました。課長補佐が町村信孝自民党幹事長代理で、私が係長。麻雀とかずいぶん遊びましたけど、当時のマクロ経済の勉強、いま役に立っていますね。それが終わって第二次オイルショックで石油を扱って、緊急事態法制をつくったり、灯油とかガソリンの配給切符をつくって倉庫に仕舞い込んだりね。
◎―――そんな事態まで行ってたんでしたっけねえ。
岡田――そうです。あんまり表に出しませんでしたけど。
◎―――珍しい話だな、それ。
岡田――第二次オイルショックの役所の対応は、隠れた成功物語だと僕は思いますけどね。情報開示をしなかったと言われればそれまでなんですが、「大丈夫」だと言い続けながら配給のための法律とかの案は全部つくって、かなり忙しかった。かなり厳しい実態をそう大きな混乱なく乗り切ったんですね。大平首相の「東京サミット」のときですよ。
◎―――その後は。
岡田――機械情報産業局で、いま資源エネルギー庁長官の河野博文さんが企画官で、その下でコンピューター・ソフトウェアの法的保護の問題をやっていました。アメリカが著作権で保護するというのに、われわれが異論を唱えた。富士通、日立事件とかありましてね、IBMのソフトウェアを盗んでいたとかいう事件です。われわれは「著作権法では保護が厚すぎる。独自の法律をつくるんだ」と壮大な構想だったんですが、最後はアメリカ議会を抱き込んだIBMにこてんこてんにやられちゃったんです。いろいろ議論して面白かったけれど、そこで私は若干ナショナリスティックになったんです。それが終わって、アメリカに一年間行ってこいと言われて、ハーバードのヴォーゲルのもとで過ごしたんですね。しかし英語不得意ですから......。
◎―――どうなりました?
岡田――悲惨だったですねえ(笑)。最初の一カ月間、語学研修のときは地獄ですね。三十代になって行くのはしんどいですね。当時、家内と二人でしたから、家はソニーの盛田昭夫さんの話にならって、少し大きめの部屋を借りて、そこへいろんな人を呼びましたね。竹中平蔵も来たことがあるんですよ。みんな食べ物を持ち寄るときに、彼がちらし寿司を持ってきたのを家内が覚えていて、「竹中さんの顔をテレビで見るたびにちらし寿司を思い出す」と。彼は当時、日本開発銀行から来ていた。
◎―――いまの時代を背負う人たちの梁山泊でもあったわけだな。
岡田――僕がアメリカで買った家具は慶応の島田晴雄さんに売って帰ってきたんです。アメリカにいるときに、「ああ、政治もなかなかいいな」と。そのとき初めて「政治家にひょっとしたらなろう」と思った。それまでは全くそういう気持ちはありませんでしたので。
◎―――なんでそう思ったんですかね。
岡田――当時、レーガン大統領の時代ですよね。まあ、日本よりは政治家は尊敬されていますよね。政治への参加意識もあるし、それはハーバード、ボストンという独特の雰囲気はあったかもしれませんが、政治家が、あるいは政治が世の中を動かしているという、これは日本ではなかった新鮮な驚きですよね。
◎―――日本ではとりわけ派閥抗争の時代でしたからね。
岡田――それで帰国して、地元の四日市出身の山本幸雄先生と最初は喧嘩するつもりで地元へ帰っていたりしていたんですね。通産省を辞めて、選挙まで一年八カ月ぐらいでしたね。途中で山本先生の後継となりました。山本先生、党を変わってもずうっと応援演説してくれています。
◎―――それで当選。このときはしかし、自民党竹下派でしたね。いきなり政治改革と竹下派分裂がやってきた。
岡田――私、自民党総務会で亀井静香氏と取っ組み合いして新聞に載ったりしました。先頭切って小沢一郎氏擁護で自民党を出て新生党に行きました。
◎―――だけど、のちに新進党を小沢さんが解党したときに、岡田さんが反対する激しい演説をぶたれていましたね。
岡田――ビラ配りまでしましてね。「解党はおかしい」って。あれが小沢さんとの決別だったんですね。解党はもったいなかったですね。その前に羽田孜・小沢一郎の闘いがあって、私は母親と父親が喧嘩して、その子どもみたいな状況でした。なんとか仲直りさせようと思ったんですけど、だめでしたね。そこで二大政党に行くコースが逸れました。
◎―――そして民主党をつくる。
岡田――それから三年。僕はわりと落ち着いて、政局からは少し身をおいて、政策の勉強を中心にしてきたつもりなんですが、自分なりの基本的考え方の形が取れてきたので、少し政局のほうもと思ってはいるんですけどね。
◎―――「小泉ブーム」が出てきちゃって民主党は......。
岡田――僕は政権を取りに行ける党だと思っています。政策面では、自民党を超えたと思っているんです。小泉さんが出てきたのは、従来の自民党に対して国民は「ノー」と言ったということなのです。次の衆院選挙は本当に政権を取りにいく選挙になると思いますね。
◎対談後記◎
岡田克也氏は民主党のポスト「鳩菅」のエースである。衆院予算委員会での小泉内閣への岡田氏の質問は緻密で幅広い政策知識を身につけていて、一種の余裕さえうかがわせた。 ウェーバーを読み、「世界の名著」にトライし、エズラ・ヴォーゲルに学んだ岡田氏のたどった道を聞けば、かつての野党にありがちな反体制といったおもむきは全くない。それはかえって日本政治でのこだわりのない政権交代の可能性を期待させる。(早野)
[引用おわり]
[お知らせ1]
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。取材資金にもなりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせ2]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。他メディアにはない国会審議を中心とした政治の流れをこのブログで伝えていきます。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
ご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]
[画像]第44回衆院選民主党マニフェストから。
副総理の岡田克也さんは2012年5月21日(月)行政刷新会議(野田佳彦議長)の「規制・制度改革に関する分科会」を「力強く進めるためにバージョンアップ」して、「規制・制度改革委員会」(岡素之委員長)を設置しました。地方自治法などに設置根拠がある「農業委員会」や、農協法や農林中央金庫法などに基づく「JA全農(農業協同組合、農協)」やJAバンクの存在そのものを含めた改革を視野にみすえて、5月31日に農業ワーキングチームを設置しました。「規制」とはすなわち「法律と政令・省令」のことです。農業委員会などは存在そのものが「規制」(法律と政令・省令)ですから、その存在そのものが「仕分け」の対象になると考えられます。国民の意見を集約して、政治を国民の手に取り戻す、政権交代ある二大政党政治の醍醐味といえるでしょう。
ちなみに、「規制・制度改革委員会設置」「農業ワーキングチーム設置」は日経新聞がベタ記事で報じただけで、他の新聞には載っていないようです。
規制・制度改革委員会は、「農業委員会、JA、農業生産法人」をテーマにするほか、今後は「医療の自由診療と混合診療」もテーマにする方針。まずは社会保障と税の一体改革を実現して、年金の最低保障機能を強化し、子育て世代の負担を軽減。そのうえで、「ちょっと乱暴な副総理」として自民党政権の支持基盤に切り込み、農家や患者にやさしい、「岡田克也流やさしい新自由主義」がさあいよいよ幕が開けます。
日本再生のためには、例え狭い道でも、前に進むしかありません。私も全力で、まっすぐにひたむきに、追いかけていきます。
今後は農業生産法人をやりやすくすることで、高齢の農家が農地を宅地に変えずに、農地のまま農業生産法人に託し、JAローンを肩代わりしてもらったり、毎月賃料を受けながら先祖代々の田畑を残すことが可能になるような改革を目指している、と私は考えています。もともと直接支払いは岡田克也さんのマニフェストから登場した政策。小沢一郎代表により「農業者戸別所得補償」に改称しましたが、直接支払いを下支えにして、集荷業としてのJAなどの権限(規制)を和らげ、「平成の農民解放(農地解放)」を実現したい考えだろうと忖度しています。
JAバンクも80兆円の貯金を元にした資材融資や住宅ローン、営農ローンのほか、農業共済・医療共済が生き物として回っていますから、廃止するわけにはいきませんが、今のままで良いというわけではありません。ユニバーサル・サービスのゆうちょ銀行が農業融資に参入するなどの競争、すなわち機会の均等、すなわち自由が必要です。
規制・制度改革委員会の事務局は、副総理室がある首相官邸ではなく、行政刷新大臣室がある内閣府別館に設置しました。行政刷新会議事務局と自らの大臣室に隣接したフロアに規制・制度改革委員会の事務局室を設けました。機能の集約で、心を一つにスピードアップし、残り1年となった衆院任期中に規制改革を進める考え。
内閣府は部署ごとに建物が分かれており「たこの八ちゃん」と揶揄されてきました。2000年の橋本行革で内閣府が発足して以来、政治家本人の命令で、事務局と庁舎の模様替えが実施されたのは初めての可能性が高く、真の政治主導が始まった可能性があります。
岡田さんは5月22日(火)の記者会見で「この新たな委員会の事務局について、行政刷新会議事務局と現在離れた場所にありますので、同じ庁舎内に集約をするということを決め、昨日から新たな執務室で業務を開始したところでございます。その関係で、皆さんにはこちらに会見の場所を変わっていただいたということでございます」と述べました。
TPP(トランス・パシフィック・パートナーシップ)との関係については「TPPに直接関係はありません」と断言。そのうえで、「しかし、今、日本の農業について、より生産性を高める。あるいは競争条件を整備すると、そういった問題意識で取り組んでいるところでございます」と答えました。
岡田さんは昨年8月4日の記者会見で当ブログの「パナソニックがサンヨーの白物家電部門をハイアールに売却するとか、トヨタが関東自動車工場を完全子会社化するといった話があります。わが国ではそれぞれの業種で有力企業の数が他国に比べて多いとされており、事業再編・企業再編が必要だとされているが、どのようにお考えでしょうか」との質問に次のように答えています。
「それは企業の話ですので、あまり政治のレベルでどうこう言うことではないと思います。ただ、国際的に見れば、やはり企業の数はそういった自動車・電機はじめ多いのは事実で、ある程度の集約化は避けられないのではないかと思います。見通しの問題としてですね。そういうときに、ただ単に足し合わせるだけではなくて、一定の集約化がなされなければ、これは厳しい国際競争を勝ち抜くための再編の意味がありませんから、「1+1」が2になるのではなくて、「1+1」が1.5とか1.7になることによって競争力がかえって増すと、そういう再編・集約が望ましいのではないかと思います。サンヨーの件も、そういう観点で私はよく理解できるところであります」
「1+1」が1.5や1.7になるというのは、固定費の圧縮を意味しており、固定費の主要な部分は人件費です。このやりとりでも明らかなように岡田さんは新自由主義的な経済観を強く持っていると考えられます。しかし、「あまり政治のレベルでどうこう言うことではない」とも述べており、企業の戦略そのものに政府があまりタッチすべきではないという岡田流新しい自由主義にも思えます。岡田さんは政治キャリアを衆院厚生委員から振り出しにしたことから明らかなように、、年金を初めとする社会保障の最低保障機能の強化に取り組んでおり、現在、社会保障と税の一体改革法成立に全力を尽くしているのはご存じの通りです。いわば、社会的公正を重視する「社会自由主義」に近いのかもしれません。まあ、学術的なことは私、分かりませんので、「岡田流やさしい自由主義」「あたらしい自由主義」で日本再生、という表現にさせていただきます。
信なくば立たず。自民党政権での規制改革委員長を務めたオリックスの宮内義彦社長・会長は、電力自由化を実現すると同時に、自らの会社が応札するという暴挙を犯しました。第166通常国会の2007年3月5日の参院予算委員会で渡辺喜美・内閣府規制改革担当大臣(当時は自民党)は、次のように答弁し、宮内義彦さんを批判しています。
「これは規制改革というのは一体だれのためにやるのかと、それは国民のためにやるんですよ。規制改革が一部業界のためとか、そんなことで行われるわけじゃないんです。したがって、委員の方々はそれだけ高い公共心をお持ちのはずなんです。これだけ、これだけ国会で批判を受けて、自分の会社のために、自分の業界のために提案をするような、そんな委員は今はいませんよ。(発言する者あり)前の、先ほど、先ほど御指摘の委員の方、お二人とも今は委員ではございません、ついでながら」。

[写真]小池百合子環境大臣(自民党)主催のクールビズ・ファッションショーで気取る自民党政権の規制緩和委員長、宮内義彦オリックス会長。
このように規制改革を経営者に頼むと、その人が会社の利益に動く可能性があります。岡田さんは住友商事会長の岡素之さんを委員長に選びました。果たして、岡さんは公益のためにやってくれるのでしょうか。私は岡さんという人物をまったく知りません。ただ、岡田さんが選んだんだから、大丈夫かな、という気はしております。
[写真]岡田克也さんの指名で民主党政権で内閣府規制制度改革委員長を務める岡素之・住友商事会長(同社ホームページ)。
日本のこの19年間の経済低迷は、デフレではありません。国力が落ちているのです。そんなこと、分かってるんでしょ、みなさん?
規制とは既得権益者のためにあるのではありません。規制とは、公務員の仕事を増やすためにあるのです。仮に震災前に規制改革が出来ていれば、がれきの処理率が1年間で6%ということはなかったでしょう。私たちは自分の脚で立ち上がって、未来をつくらねばならないのです。
例えば、下の2枚の写真。ともに金子洋一・候補(現参院議員)を応援する岡田さんの姿です。しかし、この写真には大きな違いがあります。左の写真は衆院三重5区の民主党公認法補としての金子さん。右の写真は参院神奈川選挙区の民主党公認候補としての金子さんです。自らが定めた「2回ルール」すなわち小選挙区で2回連続で落選した候補者は次の衆院選で民主党公認候補としないという原理原則を適用して、政治家への道をいったん閉ざされた金子さんが、自ら神奈川県連の公募に応募して、勝ち得た2度目のチャンス。岡田さんはしっかりとその背中を押しています。それが岡田流やさしい自由主義です。

[写真]左は金子洋一さんのブログから、右は筆者撮影。
日本をあきらめない。そのためには、走れる人は走りましょう。走れない人は大丈夫。生活保護や最低保障機能を強化した年金があります。僕らを見守ってください。80年前、日本は関東大震災と大恐慌でじり貧がどか貧になりました。今、私たちはリーマンショックと東日本大震災でじり貧がどか貧になりました。80年前、私たちは国際連盟を脱退し、大東亜共栄圏建設に邁進する暴挙に出て、一度滅びました。今、私たちは国際連合の一員として日米同盟を維持し、TPPの事前交渉に参加しています。
日本をあきらめない。そのためには思い切って国を開かなければいけない。なぜ開かなければならないか。理由は簡単です。開かないと国がつぶれるからです。それだけ。じり貧から抜け出すには、徹底した自由貿易論者である野田佳彦総理、岡田克也副総理を先頭に世界に打って出なければいけません。私たちにはそれができる人材が一定以上そろっています。やさしさ(社会保障と税の一体改革)と新自由主義(規制改革による自由な日本)の両立が必要です。
さあいよいよ、そのときが来ました。さあ勇気を出して。みんな一緒なら、ほら、きっと飛べるよ。攻撃は最大の防御。日本をあきらめない。そのためには、まっすぐに、ひたむきに、思い切って外に出る。日本を前に進めましょう。日本は再生します。絶対に大丈夫です。安心してください。
[お知らせ1]
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。取材資金にもなりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせ2]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。他メディアにはない国会審議を中心とした政治の流れをこのブログで伝えていきます。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]
建国以来、未曾有の国難のなか、歴史の流れが速くなっています。
安住財務大臣は29日の閣議後記者会見で、今週2012年6月1日(金)から、東京と上海で日本円と中国人民元の直接取引を始めると発表しました。三菱東京、みずほ、三井住友の3つのメガバンクも発表しました。

[写真]2012年(平成24年)6月1日(金曜日)からの日本円と中国人民元の直接取引開始を発表する安住淳財務大臣、2012年5月29日のお昼のNHKニュースから。
29日朝の読売新聞は警視庁公安部が外国人登録証を不正に更新した可能性がある中国大使館の1等書記官に対して、出張要請したと報じました。玄葉外相は日中関係について「なんとも言いようがない。状況把握してから言いたい」と述べました。1等書記官は中国人民解放軍のスパイ組織の構成員とみられます。中華人民共和国スパイのわが国での立件は同国成立後の60年間で初めてと思われます。在東京中国大使館のスポークスマンは1等書記官は今月任期切れで帰国しているとしており、事態の長期化は必至。
[写真]2012年5月29日に発覚した中国大使館員のスパイ容疑にかかわる外国人登録証の不正更新疑惑の報道を受けて、日中外交について見通しを語る玄葉光一郎外相、NHKニュースウォッチ9から。
さらに、松下政経塾に海外インターンとして入塾した経緯があるとしました。ちなみに、野田佳彦首相、松原仁・国家公安委員長、玄葉光一郎・外相は3人とも松下政経塾出身。日本国内で過激派(共産主義者)が絶滅寸前になったことで、仕事量が減っていると思われる公安警察(警察庁警備局長と47都道府県の公安部・警備課による任意のネットワーク)が存在感を発揮しようとしている可能性があります。昨年の臨時国会(第179回国会)では、NHK入り審議で、参院自民党議員が質問した団体について、警察庁警備局長が「警察としましては、警察法第二条に定められた公共の安全と秩序の維持という責務を果たすため、御指摘の団体を含め極左暴力集団の動向には重大な関心を有しているところであります」と従来にない踏み込んだ答弁をしています。これも公安警察が定員維持を目指しているのかもしれません。
政治の世界では、絶対に親友はできません。赤坂や銀座で飲めば飲むほど、将来傷つく地雷が増えるだけ。国会議員の名刺は、現在でももてますから、異業種交流会でも行った方がマシです。政界の義兄弟もしかり。竹下登さんと金丸信さんは義兄弟です。比喩ではなく、本当に子ども同士が結婚しています。しかし、経世会は「竹下首相再登板」をめざす竹下系と「小沢首相」をめざす金丸系に分かれ、分裂しました。民主党内で鳩山由紀夫さんが、羽田孜さん・小沢一郎さん・岡田克也さんら「新生党」系列の議員との交流が少ないのは、鳩山さんだけが経世会竹下系だったからです。
岡田克也さんは実社会でも3兄弟ですが、政界では、岡田克也副総理(7期58歳)、玄葉光一郎外相(6期48歳)、安住淳財務相(5期50歳)が岡田3兄弟です。冒頭の写真のように昨年の第177通常国会では、幹事長、政調会長、国対委員長として、震災を乗り切り、3党合意をつくり、民主党が与党になってから初めての成果のある国会を作り上げました。野田佳彦首相(民主党代表)をつくり、ホッとした表情でしたが、その後、3人とも閣僚となり、まさに歴史の激動のなか、運命の人になっています。
[写真]実の岡田3兄弟、左側の眼光が鋭いのが克也さん。
昨年は3党合意を作り上げた政界の岡田3兄弟ですが、小沢グループの反発があり、輿石東幹事長に交代しました。しかし、小沢グループに配慮して起用されたその輿石幹事長は、特例公債法案の成立に向けた3党協議をしている気配がなく、国際的な日本(Japan)の経済・財政リスクは高まっています。現在、長期金利が低くなっているのは、「引き潮」に過ぎないと見るのが妥当です。
その一方、野田佳彦首相側近は、9月の民主党代表選挙に向けて、岡田3兄弟が何か仕掛けるのではないかという疑心暗鬼があるようです。しかし、岡田3兄弟は国の安定を損ねるようなことをするような人たちでは絶対にありません。100%あり得ない邪推です。むしろ、そのような邪推をする野田首相側近に、総理と心中する心構えのありやなしやを問いたい。
運命の人、岡田3兄弟。
国難の中、その肩にのしかかる重荷は積み重なるばかり。
東大卒、上智大卒、早大卒。
官僚出身、県議出身、マスコミ出身。
実父が立派な人という共通点はありますが、育ちは違う。竹下金丸義兄弟と違い、志のみでつながった義兄弟。
そもそも玄葉外相が明治維新以来初めてのミッションスクール(キリスト教系教会設立の大学)出身の外相というのが、以下にこの国が人材をつぶしてきたかの裏返しです。
to be , or not to be.that is the question.(生きるべきか死ぬべきかそれが問題だ)。
ハムレットのせりふですが、板挟みになる必要はありません。なぜなら答えは「to be」、「生きる」ことしか政治家としての選択肢はないからです。
岡田3兄弟とともに、日本を前に進めましょう。
大丈夫。歴史の証人になれたと思えば、ラッキーです。国は生き続けます。
ほら、前を向いて。みんな一緒ならきっと走れるよ。岡田3兄弟の背中を強く押して、歴史の作り手になりましょう。政治を国民の手に取り戻しましょう。
円・人民元、直接取引=東京、上海で来月1日から―国内大手銀が参入表明(時事通信) - goo ニュース
2012年5月29日(火)11:53
(時事通信)
安住淳財務相は29日の閣議後記者会見で、東京、上海両市場で円と中国の通貨・人民元を直接交換する取引を6月1日に開始すると表明した。現在の円・元の取引はほぼ全量、ドルを仲介しており、為替手数料が余分にかかっている。直接交換によりコストが削減されるため、日中貿易の拡大につながる。みずほ銀行など国内大手銀行は29日、円・元取引に参入すると発表した。
安住財務相は「第三国通貨(ドル)を介さないことで、手数料削減や(ドル相場変動に伴う)決済リスクを低減する効果がある」と強調した。
安住財務相は「第三国通貨(ドル)を介さないことで、手数料削減や(ドル相場変動に伴う)決済リスクを低減する効果がある」と強調した。
[時事通信社]
スパイ中国書記官、玄葉外相「思い出せない」(読売新聞) - goo ニュース
警視庁公安部がウィーン条約で禁じられた商業活動をしていたとされる在日中国大使館の1等書記官に出頭要請した問題は、政界に波紋を広げた。
松原国家公安委員長は29日の閣議後の記者会見で、「捜査内容については答えを差し控える」としながらも、「中国の対日工作には重大な関心を払っていて、情報収集、分析に努めるとともに、違法行為については厳正な取り締まりを行う」と述べた。
玄葉外相も記者会見で、「今朝新聞で知り、(関係課から)事情を聞いている。警視庁からの要請を受けて、外務省の職員が在京中国大使館に対応したと認識している」と明らかにした。
ただ、日中関係への影響については「なんとも言いようがない。状況把握してから言いたい」と述べるにとどめた。自身が通った松下政経塾に1等書記官が一時在籍していたことについても、「顔も名前も思い出せない。(自分とは)一回りくらい違うので、訪ねてきたことがあるのかどうかすら分からない」と話した。
[お知らせ1]
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。取材資金にもなりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせ2]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。他メディアにはない国会審議を中心とした政治の流れをこのブログで伝えていきます。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]
岡田克也副総理は2012年5月18日(金)の定例記者会見で「特例公債法案が通らないということが金利に影響を及ぼさないように注意深く進めていかなければいけない」と述べ、新年度入りから特例公債(赤字国債)が発行できない状態が続いていることが、長期金利(日本国債の表面価格と連動)の変動を最小限にするため、政府(財務省理財局)がオペレーションしていく考えを示しました。
そのうえで、「(衆議院・財務金融)委員会で議論しておられることですので、今の段階で政府が何か口を出さないほうが結果はいいというふうに思います。むしろ一般論として言えば、なるべく早く成立をさせていただきたい」と述べ、平成24年度の特例公債を発行する法案(赤字国債発行法案、第180国会閣法2号)を早く成立させるよう、国会に求めました。
衆院の社会保障と税の一体改革特別委員会(中野寛成委員長)にかかっている3領域7法案や、内閣委員会のマイナンバー法案などの「一体改革大綱」の法案との採決の関連性については、「ええ、もちろん、これは別の法案ですから、そういう意味では別のものです」とし、連動しないとの考えを示しました。昨年は8月9日の3党合意(民自公の幹事長、政調会長、実務者の合計9人)文書にもとづき、8月26日(金)の参院本会議で成立し、その夕、菅直人首相が退陣を表明しました。
ことしはギリシャ再選挙や、フランス新大統領のEUとの新政策、さらに日本国内の銀行の資金運用手段の手詰まり感などから、特例公債の発行への需要が変化したり、ヘッジファンドなどが日本国益を損ねるような相場への仕掛けをしてくる可能性は否定できず、与野党・衆参を問わず「決められる政治」への脱却が全国会議員に求められています。
まあここまで書くと、書いている本人も緊張感を覚えるわけですが、とはいえ、経済も社会も「支え合い」であり、相互依存は高まるばかりですから、まあなんとかなるものです。
記者会見での記者(筆者)との一問一答は次の通り。
[岡田副総理記者会見(5月18日)要旨から引用はじめ]
(前略)
(問)フリーランスの宮崎ですが、特例公債法案についてお伺いいたします。というのは、長期金利のほうが下がっておりまして、今週0.815%ぐらいをつけているときもあります。まだこの時間ですとニューヨークも開いたばかりの時間ですので、一般的な話なのですけれども、今、報道されているのは第322回新発国債10年もので、これは5月10日の発行ですから、当然建設国債です。赤字国債は発行できるわけありませんから、まだ現時点では。2.3兆円発行されるということで、今年の建設国債は、今、当初では6兆円ぐらいのはずですので、もう2.3兆円も発行するのかという気がいたします。
お伺いしたいことは、長期金利が低いか高いか、あるいは表面価格が安いか高いかではなく、いずれにしろ変化が激しいのは好ましくないというのは間違いないと思います。ちょっとヨーロッパのことはなかなか難しくて分かりませんが、衆議院で現在留め置かれている特例公債法案、審議のほうはかなり積み上がっております。採決しようと思えば、審議時間のほうはもうほぼあると思うのですけれども、この特例公債法案に関して、政府のお立場から国会に対してどうお願いされますでしょうか。
(答)委員会で議論しておられることですので、今の段階で政府が何か口を出さないほうが結果はいいというふうに思います。むしろ一般論として言えば、なるべく早く成立をさせていただきたいということですが、真摯に各党間で議論が行われているということですから、それを見守りたいというふうに思っています。
(問)今回の一体改革の法案のほうとの審議というのは、これは別のものだとお考えでしょうか。
(答)ええ、勿論、これは別の法案ですから、そういう意味では別のものです。
(問)ある程度、これは最後ですけれども、長期金利には今注目はされているところでしょうか。
(答)特例公債法案が通らないということが金利に影響を及ぼさないように注意深く進めていかなければいけないと、そしてなるべく迅速に結論を出していただきたいというふうに思っています。
[引用おわり]
[お知らせ1]
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。取材資金にもなりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせ2]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。他メディアにはない国会審議を中心とした政治の流れをこのブログで伝えていきます。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]
みんなの党政調会長の浅尾慶一郎さん、2012年5月13日放送のNHK日曜討論画面から。
2012年5月13日のNHK日曜討論は「社会保障と税の一体改革」について、各党税制調査会長らが出演しました。藤井裕久・民主党税調会長、野田毅・自民党税調会長、斉藤鉄夫・公明党税調会長ら結党から解党までの3年間、新進党に在籍した民自公税調会長トリオらが登場。藤井さんが「前回の消費税引き上げ(を決めたの)は、勘違いされているが、橋本内閣ではなく、社民党の村山内閣だ」と指摘しました。
この中で、浅尾慶一郎・みんなの党政調会長が歳入庁構想について、看過できない発言がありました。初めに私の考えを述べれば、国税庁と日本年金機構を統合して歳入庁をつくるべきですが、内閣府に置くのは反対です。厚生年金に関しては、零細企業主の負担を軽減し、求人をためらうことがないように、労使折半のあり方を見直したり、加入するかしないかのパート労働者の自由をつくるのがいいでしょう。なお歳入庁の創設は、2009年第45回衆院選鳩山マニフェストには書いてありましたが、2010年第22回参院選菅マニフェストには書いていないと思います。
浅尾・政調会長は番組最初の発言で、「社会保障と税の一体改革と言っても単なる増税案だと思う」「まず簡単にできるのは民主党自身が選挙の際にマニフェストで言っていた徴収面の改革」「社会保険料と税の徴収は今は別々になっていますけれど、歳入庁をつくるということは、民主党、マニフェストのときに言っていました。で、私たち(みんなの党は)歳入庁をつくると、現在(社会)保険料の徴収漏れで10兆円の徴収漏れがあると(試算をしている)。そもそもマニフェストで言っていたのだから自分のところで試算をすべきなんですね。我々がした試算にいろいろとケチをつけるんじゃなくて、あくまでも試算をしないというのは英語で言うとチキンというか、臆病者というか、私は逃げていると思いますかね」。
浅尾さんは英語がうまいのですが、NHKで「チキン」なんて言っちゃダメですよ。あの80年代アメリカを代表する映画「バック・トゥー・ザ・フューチャー」3部作があまり地上波テレビで放送されないのも、それが理由なんですよ。私もあの映画で初めてその言葉を覚えましたが、どんなに英語が流ちょうでも、テレビで「チキン」というようでは、TOEICもTOEFLも零点です。
第180通常国会でのこの議論の経緯を如実に表しているのが、次の動画です。2月22日の衆院予算委員会の議事録を探したらまだ上がっていないので、衆議院インターネット審議中継のビデオライブラリを撮影して、次の動画をつくってみました。ご覧下さい。
チキンはどっちだ!
野党議員の質問が「冒頭、大臣にお願いがあります」から始まったのは、記憶がありません。
浅尾さん、ずいぶんオドオドしていますが、どうしたんですか? なんかあったんですか?(笑)
で、何があったか。
浅尾さんは、2月1日の衆院予算委員会(4次補正の審議)で「きょうはちょっと、これはかなり数字が入った話ですから、衆議院の調査室に詳細なものもつくってもらったものがあります、国民年金の未納率も入れて。結果としては、数字としては、十二兆というのは数字は変わりません。変わりませんので、ぜひ、検討するというんだったら、政府の側でも未加入の人を入れたらどうなるかという試算をやってみたらいいじゃないですか」と語っています。
2月10日の同委(当初予算の審議)でも「前回も申し上げましたが、私の試算は衆議院の調査室にやっていただいております。ですので、政府は政府として、こっちは立法府として、立法府の調査室にお願いした数字で十二兆ぐらいの数字が出てきておりますから、そういうふうにおっしゃるのであれば、政府が前提を置いて数字を出していただきたいと思います。まず、そのことを伺いたいと思います」。
その後、上の動画のように2月22日の予算委員会で「ご説明したい」ということになりました。
3月7日の衆院内閣委員会の一般質疑では自民党の竹本直一さんからも質問があり、岡田さんは「今、浅尾委員もおられますが、十兆円というのは、私はかなり過大ではないかというふうには思っております」と答弁。その後、質問に立った浅尾さんは「冒頭、先ほど委員会での質疑の中で岡田副総理が私の名前を出していただいたので、前々からお願いをさせていただいている、お願いをする筋の話でもないんですが、こちらが出した試算について説明に伺うということになっておりまして、残念ながら、その日は、どうも新聞報道によると、自民党の方々との増税案の協議ということで、中止になってしまったということであります。増税をする前に、民主党自身が歳入庁をつくるということも言っておりましたし、数字が違うというなら違うで結構です、しかし、取り漏れがあることは事実ですから、その試算。いわゆる取り漏れがあるというのは不良債権になっているところだと思いますので、その不良債権隠しをするのではなくて、政府自身としても試算をしていただきたいと思いますし、ぜひその時間をとっていただきたいということを申し上げたいと思いますが、何かあれば」と質問。岡田さんは「浅尾委員にお時間をいただきながら、ちょっと都合でお会いできなくなりましたので、改めて時間をというふうに思っております。事務方から事前に説明を受けたんですが、私なりに納得できないところがありまして、再度検討を事務方にお願いしておりますので、私なりに納得をした上でお会いした方がいいかなというふうに思っています」と答弁しています。
そして、きょう5月13日のNHK日曜討論では「10兆円ぐらい」と数字を出した上で、「試算をしない政府はチキン」発言。みんなの党はいい加減にしてほしい。自民党、公明党のような責任野党がいる一方、もっともらしいことを言って、経済学に疎い方々を騙すペテン師政党に私には思えます。
さて、衆議院規則第56条は、衆議院調査局長の予備的調査などの国政調査に関して定めています。調査局長の下には「予算調査室」など、常任・特別委員会ごとに調査室が置かれています。スタッフは、ほとんどが衆議院採用の職員ですが、関連する官庁の官僚が1人ほど出向している調査室もあります。ところが、参議院規則にはこの「調査局の予備的調査」の定めはありません。そもそも参議院には「調査局」という組織がありません。委員会ごとの調査室は衆院同様にあります。この辺が参院では2期11年務めながらも、衆議院では1期生である浅尾さんがスタッフの使い方の勘違いにつながっている可能性があると思います。
みんなの党が第180通常国会で使う数字はどれもこれもいい加減。大変な無責任野党、ペテン師です。浅尾政調会長は衆院本会議でも席を離れる時間が多いように見受けられます。新自由主義を否定する者ではありませんが、楽して儲けようというみんなの党の心根は極めて残念です。
浅尾さんには、岡田さんが最初に代表選挙に出馬したときに民社協会を代表して推薦人になったころの澄んだ瞳を取り戻して欲しい。当分、民自公3党路線で行くしかないでしょう。
[国会議事録から引用はじめ]
平成二十四年二月一日(水曜日) 平成二十三年度一般会計補正予算(第4号)
平成二十三年度特別会計補正予算(特第4号)
(前略)
○浅尾委員 実は、この歳入庁というものの最大のメリットは、今パネルに出しましたけれども、国税庁というのは全国に一体どれぐらいの法人があるかという情報を全部持っているんです。なぜ持っているかというと、法務局に登記した情報が全て国税庁に行っているので、その情報を持っている。
結果として、毎年、これは平成二十一年の数字ですけれども、二百七十三万一千七百六十八法人が赤字であっても申告している。赤字であっても申告しているということは、そこで働いている人の給与の源泉徴収についてはちゃんと納められていますよということなんです。ですから、給与についての所得税はちゃんと入ってきている。
一方で、法人は全て厚生年金に加入をする義務があるんですが、昔の社会保険庁、今の日本年金機構はまだこの法人データというのは持っていません。持っていない結果、聞くと、大体どれぐらいの法人が加入しているんですかと言うと、答えはわからない。ただ、わかるのは、百七十五万事業所が加入していると。
この事業所というのは、支店や工場も一事業所でカウントしますから、ですから、百七十五万事業所ということは、多分、八十万法人ぐらいしか厚生年金に加入していない。歳入庁をつくれば、二百七十三万一千七百六十八法人とこの八十万ぐらいの推計の法人数とが一発でわかるじゃないですか。しかも、それは私が言っているわけじゃなくて、民主党自身がマニフェストで約束したことだから、それはさっさと、税と社会保障の一体改革というんだったら、社会保険の保険料徴収の部分の改革の一丁目一番地だと思いますよ。
なおかつ、どれぐらいの徴収漏れがあるかというのを推計してみました。推計してみると、民間の給与所得者というのが五千三百八十八万四千人、厚生年金の被保険者というのは三千四百二十四万八千人ということなんですが、これは、いろいろな計算式を置いていくと、年金の保険料だけで六兆六百七十五億円。健康保険も一緒ですから、大体十二兆円ぐらい毎年毎年の徴収漏れがあるということなので、まず、歳入庁をつくれば未加入の法人というのはすぐなくなると思いますが、すぐなくならないというんだったら、なぜなくならないのか、それをお答えいただきたいと思います。そのことについて、これは一体改革相に聞いた方がいいかもしれないですね。
○岡田国務大臣 まず、歳入庁につきましては、我々は、社会保障・税一体改革の素案の中で、「歳入庁の創設による、税と社会保険料を徴収する体制の構築について直ちに本格的な作業に着手する。」というふうに整理をしております。したがって、歳入庁に関して検討を早急に開始したいというふうに考えているところであります。
浅尾さんの御指摘は、渡辺議員が本会議でも述べられたところですが、非常におもしろい話だと思いました。ただ、逆に言いますと、その差額はお示しされた資料によりますと六兆円ぐらいということになるわけですが、六兆円がすぐ入ってくるのならいいんですが、現実にどれだけ中小企業でそれにたえ得る企業があるのだろうか、そういうこともあわせ考えていかないと、机上の計算だけになってしまうのかな、そういうふうに受けとめた次第です。
○浅尾委員 今の岡田大臣の答弁は一つ問題があると私は思います。財政的にたえられるかどうかという話と、じゃ、法律違反を大臣として放置していいかどうかという話は、別の次元の話なんじゃないかなと。
つまりは、加入する義務もありますし、今でも、日本年金機構は職権で加入を命じられるんですよ。加入を命じられるけれども、基本的にはやっていないことが相当多いので、それは、もしそうだとするならば、中小企業については保険料を減免するというようなことを政策的にやらないと、法治国家としてはおかしいということになりますが、その点はどう思われますか。
○岡田国務大臣 今のお話で私がどこまで理解しているかですが、給与所得者が五千三百八十八万人いる、これは、厚生年金の対象になる正規の社員がこれだけいるということなんでしょうか。
○浅尾委員 実は、会社が税務署に申告するときに、五百万円以上については、いわゆる個人の住民票のデータも含めて税務署に出します。五百万円以下の人については何人という人数を出しますが、それは月額報酬八万八千円以上の人ということになっています。そして、厚生年金の対象というのは九万八千円というのが標準報酬月額なので、じゃ、一万円の間に二千何百万人もいるかというような話もあります。
もしそういうふうにおっしゃるんであれば、きょうはちょっと、これはかなり数字が入った話ですから、衆議院の調査室に詳細なものもつくってもらったものがあります、国民年金の未納率も入れて。結果としては、数字としては、十二兆というのは数字は変わりません。変わりませんので、ぜひ、検討するというんだったら、政府の側でも未加入の人を入れたらどうなるかという試算をやってみたらいいじゃないですか。(後略)
平成二十四年二月十日(金曜日)
(前略)
○浅尾委員 みんなの党の浅尾慶一郎です。
きょうは、きょうもと言った方がいいかもしれません、社会保障の問題について中心的にお話をさせていただきたいというふうに思いますが、たまたまきょう発売の月刊誌の文芸春秋に、私が書きました、年金制度改革あるいは社会保障改革によって、消費税増税と匹敵する、あるいはそれ以上の財源が出てくるという論文をお載せいたしました。ぜひ総理にも、年金とか医療、特に保険の部分というのは非常に複雑になっておりますので、大変お忙しいと思いますが、今そのコピーをお配りさせていただいておりますので、お時間のあるときに、そちらの方もお読みいただけると大変ありがたいというふうに思います。
そのことを申し上げさせていただきまして、まずは、歳入庁をつくったら、これはいろいろな試算が出てくると思いますが、あらあら十二、三兆のお金ができますよということをこの間、提言させていただきました。それに対して、岡田副総理の答弁、あるいはその後のテレビでのコメントを見ておりますと、答弁ではこういうふうに言っておられます、「現実にどれだけ中小企業でそれにたえ得る企業があるのだろうか、そういうこともあわせ考えていかないと、机上の計算だけになってしまうのかな、」と。
これは、実は先般の委員会でも申し上げましたけれども、法治国家としてはいかがなものか。つまりは、国民年金についてもさまざま未納の問題がありますが、これは、政府の立場からいえば、払ってください、企業の未加入に対しては加入してくださいということを呼びかけるべき立場でありまして、それが、払えないというのであれば、別途制度をつくるというのがあるべき立場だということだと思います。
まず総理に、憲法が定めます法のもとの平等と、それから、現在多くの企業が、実際の法人数に対しては恐らく、恐らくというか間違いなく過半数、恐らく三分の二ぐらいが厚生年金に未加入であるという事実に基づいて、法のもとの平等と歳入庁の構想についてどういうふうに考えておられるか、総理に伺いたいと思います。
○岡田国務大臣 前回、委員とはこの問題を議論させていただきました。
いろいろな前提、仮定に立ってやっておられる話で、その後、私も少し調べさせていただいて、全体で十二兆円、厚生年金保険料、健康保険の保険料合わせて、それが未収だという委員の御指摘ですが、私は、それは相当過剰に計算されている、過大に計算されているというふうに考えております。そこのところを少し議論させていただきたいというふうに思っています。
○浅尾委員 前回も申し上げましたが、私の試算は衆議院の調査室にやっていただいております。ですので、政府は政府として、こっちは立法府として、立法府の調査室にお願いした数字で十二兆ぐらいの数字が出てきておりますから、そういうふうにおっしゃるのであれば、政府が前提を置いて数字を出していただきたいと思います。まず、そのことを伺いたいと思います。(後略)
衆院内閣委員会 第2号 平成24年3月7日(水曜日)
大臣所信聴取に対する一般質疑
(前略)
○竹本委員 実は、これは民主党政権だけのせいではないので、私もこの問題を担当したことがあるんですけれども、やはり、当時から未納率を下げるというのは極めて難しい問題でありました。しかし、完全に一〇〇%徴収というのは、今の制度ではなかなか難しいというふうに思います。
ですから、仮にきちんと税を徴収できるようになりますと十兆円程度の増収、こうなるわけでありまして、今回、民主党が考えている、政府が考えている消費税値上げで十三兆円ぐらいでしょうから、ほとんど一%分の消費税値上げで済むという話にもなるわけであります。
だから、やはり徴収をきちんとやるにはどうすればいいか。そうなると、やはり歳入庁をつくってやれという話にもなりますが、歳入庁をつくるかどうかという問題について、副総理の、岡田さんの考えを聞きたいと思います。
○岡田国務大臣 今、浅尾委員もおられますが、十兆円というのは、私はかなり過大ではないかというふうには思っております。その議論はまた改めて、必要があれば御説明したいというふうに考えております。
つまり、例えば厚生年金の保険料について言えば、厚生年金に加入することが免除されている事業者もございますので、そういったことをきちんとカウントしたときに十兆ということにはならないのではないかというふうに思っております。
さて、御指摘の歳入庁ですが、先般、私のもとに検討するためのチームをつくりまして、検討作業、これは、大綱の閣議決定を受けて検討作業を開始したところでございます。
今後、その作業チームにおきまして、一つは、国民年金保険料などの納付率向上にどの程度つながるのか、それから社会保険行政、税務行政全般の効率性確保に資するか、今後導入が見込まれるマイナンバー、給付つき税額控除、新年金制度等にとってふさわしい体制か、そういった視点を踏まえて検討を進めてまいりたいというふうに思います。
私の方としては、春ごろ、四月ごろに全体のイメージ的なものだけでもまず中間的に報告してもらいたいというふうに指示を出しているところでございます。
(中略)
○荒井委員長 次に、浅尾慶一郎君。
○浅尾委員 みんなの党の浅尾慶一郎です。
冒頭、先ほど委員会での質疑の中で岡田副総理が私の名前を出していただいたので、前々からお願いをさせていただいている、お願いをする筋の話でもないんですが、こちらが出した試算について説明に伺うということになっておりまして、残念ながら、その日は、どうも新聞報道によると、自民党の方々との増税案の協議ということで、中止になってしまったということであります。
増税をする前に、民主党自身が歳入庁をつくるということも言っておりましたし、数字が違うというなら違うで結構です、しかし、取り漏れがあることは事実ですから、その試算。いわゆる取り漏れがあるというのは不良債権になっているところだと思いますので、その不良債権隠しをするのではなくて、政府自身としても試算をしていただきたいと思いますし、ぜひその時間をとっていただきたいということを申し上げたいと思いますが、何かあれば。
○岡田国務大臣 浅尾委員にお時間をいただきながら、ちょっと都合でお会いできなくなりましたので、改めて時間をというふうに思っております。
事務方から事前に説明を受けたんですが、私なりに納得できないところがありまして、再度検討を事務方にお願いしておりますので、私なりに納得をした上でお会いした方がいいかなというふうに思っています。
(後略)
[引用おわり]
[お知らせ1]
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。取材資金にもなりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせ2]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。他メディアにはない国会審議を中心とした政治の流れをこのブログで伝えていきます。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]
[写真]岡田克也さん、2011年6月28日、宮崎信行撮影。
大震災イヤーとなった平成23年(2011年)の岡田克也さんの政治資金収支報告書 は、政治資金管理団体(岡田かつや後援会)がの収入が1億3199万2283円で前年と比べて33%減少、額にして6451万円の減収と大幅に苦戦したことが分かりました。
総支部長をつとめる「民主党三重県第3区総支部」は8683万0795円。後援会と総支部の総計、岡田さんの場合は団体間のやりとりがないものと思われるので「純計」と考えられますが、これは2億1882万円で、前年比22%減少となりました。
岡田克也さんが公式ホームページで公開した「政治資金収支報告書の要旨」の平成23年(1月1日~12月31日)分で分かりました。公開は平成24年5月8日付。
これについて、金庫番(国会事務所長)は、「支援者の企業様が経費節減。こちらも経費節減をして何とか食いつないだ」と語りました。
単式簿記なので、前年からの繰越金はすべて収入に計上されます。複式簿記ならば前年の資産の部に計上され、内部留保となります。この点が政治資金収支報告書と企業会計の違いです。ただし、政治家の場合は繰越金が政治的資源なので、単式簿記でいいのかもしれません。
減収のおおきな要因。前年(2010年の外相時代)は、帝国ホテルに泊まって岡田外相のあいさつを聴き国会見学をするバスツアーを連続して催し、1939人の参加を得ました。自分たちが育てた岡田さんが与党になりいきなり外務大臣で帝国ホテルに夫婦で泊まってという「最高の冥土の土産」(失礼ですかね・・・)ということで、「5635万円の売り上げ」を記録しました。とはいえ、「旅行代理店もだいぶ頑張ってくれて」ナント2・9万円でしたので、旅行代理店への支払いは5281万円で、写真代・飲み物代を含めてトントンでした。この事業がそっくり消えていますので、この分は減収になります。
しかし、岡田さんの場合は2010年→2011年の繰越金が後援会で5493万円、総支部が4434万円だったのに、2011年→2012年への繰越金は後援会が5284万円、総支部が4580万円となっており、トータルでは微減となりました。いずれにしろ、最大の目的は第46回総選挙への備えですから、不安を残す格好となりました。三重3区(四日市の三滝川より北川、川越町、菰野町など三重郡、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡)の方だけでなく、全国のみなさん、岡田克也(岡田かつや)さんの背中を押してください。
総支部での獲得党員は182人(前年は195人)、サポーターは1065人(前年は1258人)にとどまりました。登録月となる5月は、党本部幹事長在任中ですので、率先垂範ができなかったと言わざるを得ません。ただし、当時の党規約では、西暦・平成とも下1ケタ奇数の年は代表選がないので、サポーターが減る傾向がありました。金庫番によると、「震災後の混乱(や党勢の不振)よりも、不況の影響がイチバン強かった」とのことです。
[画像]千葉・幕張の党大会で与党幹事長としてスタートした岡田克也さんの2011年だったが、経費節減圧力の折、献金・パーティー・サポーターとも減収となった、2011年1月13日、民主党ホームページ内動画からキャプチャ。
総支部への個人献金は23人・824万円(前年は33人・863万円)、企業献金は224社・2085万円(前年は247社・2250万円)、団体献金は1団体2万円(前年は1団体3万円)。かつて与党幹事長になって、献金が減った議員はいるのでしょうか。まさに「仕分けの民主党」。
自らが差配した政党助成金の支部交付金は1000万円と他の衆院議員と同額と思われます。
そして稼ぎ頭である後援会主催の政治資金パーティーは7349万円の売り上げ。前年の9004万円から大幅に落ち込み、1億円割れが続きました。金庫番は「毎年回っているから分かるが、景気の影響で、企業の経費節減が相当厳しかった」とふりかえっています。そこで「やはり開催コストがかかるので」(金庫番)、パーティー開催を例年通りの四日市・津・名古屋・東京・大阪の5会場に戻しました。前年は神戸にも進出し8会場に拡大していました。開催会場を絞り、400万円の支出を削減。パーティーの収益率を高めました。
後援会への個人での最高寄付金額者は50万円でした。前の年の100万円の方はいませんでした。
なかなか、苦しいですね。政治資金は景気先行指標。私自身も何とか経費節減でやっていかないといけないなあと、私自身も感じました。
他の政治家の政治資金収支報告書はこれから6ヶ月以上先の、11月末に総務省または都道府県選挙管理委員会の48カ所のいずれかで公開されます。
首を長くして待って、比較しましょう。
[お知らせ]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。他メディアにはない国会審議を中心とした政治の流れをこのブログで伝えていきます。質素倹約に努めていますが、交通費などがかかります。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。取材資金にもなりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせおわり]
岡田克也さんが2012年1月13日に初めて(官僚時代を含む)官邸入りしてから100日間が経ちました。各省からの出向官僚で構成される「チーム岡田」は「省益より国益」に目が向き、歴史に残る一体改革特別委員会での4領域11法案の審議入りを前に、巡航速度に乗ったことが分かりました。岡田さんと一緒に官邸入りした岡田腹心が明らかにしました。
岡田腹心は東大法学部卒の37歳で、政策担当秘書試験8期生。政権交代をかける第45回総選挙直前には、極秘裏に鳩山由紀夫代表(ネクスト首相)の名代として、ワシントンを民主党政調職員と2人で訪れています。
腹心は、1年1日間の外務大臣時代は、「大臣と2人で孤立するアウェイ感がありましたね」としました。外務省は最近まで採用が他の省と別試験で人事交流が少ない閉鎖的かつ組織文化が独特な官庁です。しかし、内閣官房および内閣府はほとんどが各省からの出向者のため、「そういったな孤立感はまったくありませんね」としました。
内閣官房や内閣府の職員はある意味、「二重スパイ」です。出身省と内閣官房・内閣府との間に相互に情報を流通させるのが仕事です。要は国益に向いているか、省益に向いているか。これがすべてです。腹心は「現時点では」との条件付きで、「みんな国益を見ている」と断言。一体改革法案を仕上げれば、これは歴史に名を残します。
岡田副総理に関しては、日本郵政株式会社の総務・人事部次長が自らのご家来衆である「内閣官房行革実行本部事務局参事官」の併任辞令を受けていたことを把握していないという「官邸のお化け」事件がありました。
[3月9日の岡田副総理記者会見の要旨から引用はじめ]
(記者)
フリーランスの宮崎信行と申します。
内閣官房の人事についてお伺いします。
日本郵政株式会社の総務・人事部次長が内閣官房行政改革実行本部事務局の参事官に併任する辞令が出ています。これは3月1日付で、私は昨日付のインターネット官報を見て気づいたのですが、ちなみにこの方は元々総務官僚だと思うのですけれども、この併任人事に関して、岡田さんは認識されていらっしゃいましたでしょうか。日本郵政の人事部副部長が併任で在籍のまま内閣官房の行革実行本部の事務局の参事官になっているのですけれども。
(岡田副総理)
まだ私は報告は受けておりません。
(記者)
報告を受けておられないということで、これが官邸の怖さだと思うのですね。外務省ではこういうことはなかったと思います。行革実行本部は本部長は総理ですし、本部長代行が岡田副総理、副本部長で財務大臣と総務大臣と藤村官房長官となります。
内閣官房は本来主務大臣は官房長官だと思いますけれども、こういったところで郵政の次長が元々総務官僚なのですけれども、日本郵政の社長と副社長は御存じのように元々財務官僚の方ですから、例えば郵政の本社に行ったら、上司から報告を求められたらどうするのだと、その場合その方の国益と会社の利益、一致することはあり得ませんから、私は民間企業の経営も見たことがありますけれども、この方は国益のために働くのでしょうか。
というか、そもそも行革担当大臣や公務員制度改革担当大臣が認識しないでこういう人事が昨日付の官報でも発表されている現状をどのように思われますか。
(岡田副総理)
一定レベル以上でないと、それは私のところには上がってこないということです。いずれにしても、何か日本郵政の人間が行革本部に来ることが問題だというふうには私は認識してないのですね。特に今具体的な懸案があるわけでは、何か緊張関係があるわけではありませんので。
(記者)
でしたら、併任でなくて、例えば採用してもいいのではないですか。要するに、こういうことが内閣官房で人事が続くと、どこかでこういった人事を連鎖を断たないと、どの党のどなたが官邸の主になっても、同じことが続くように私は思います。
(岡田副総理)
私は問題だというふうには認識しておりません。何かあれば報告は受けてみたいと思いますが。
[引用終わり]
ただ、この併任職員の「W氏」ですが、岡田腹心によると、現時点では国益のために働いているとのことです。
このほかにも4月13日の記者会見では「公務員制度改革というのは一体何かということです。本来、この話も総務省の話なのですね。しかし、私は行革全体を見る立場にありますから、私の下で総務省にも御協力いただいて、この問題をやってきているということで、必ずしも公務員制度改革担当ということでこれをやっているわけではない、そういうふうに御理解ください」と述べています。
このように、内閣官房と内閣府と総務省行革3局(行政管理局、行政評価局、人事・恩給局)の関係に、岡田さんですら戸惑っていることが伺えます。この点は第180通常国会の冒頭で、第4次補正予算(案)の基本的質疑で、参院自民党のトップバッターが切り込んできたところです。政策よりもまずは人を動かす。それが民主党に求められていることです。
鳩山由紀夫首相は「故人献金」で、政策秘書と公設秘書を官邸に連れて行けなくなりました。そこで、平野博文官房長官が経産省出身の弁護士を連れてきました。経産省出身の弁護士ということで会社の顧問弁護士としての収入が多く、総理政務秘書官になって年収が半減したとも言われています。そもそも鳩山さんにとっては他人のうえ、平野さんが連れてきたので切るわけにもいかない。しかもこの人は「小沢一郎さんのスパイだ」という説が鳩山グループ内に流れて、官邸崩壊となりました。その後、菅直人首相は党職員を政務秘書官にして、常に鞄をその秘書官に持たせました。総理秘書官のかばん持ちは政務と事務の秘書官が基本的に日替わり、ないしは会合の案件により順繰りで持つという慣行を破りました。これはこれで、過渡期において意味があったと私は考えています。野田佳彦首相は再び順繰りに鞄を持たせています。岡田副総理もこれまで、重さ17キログラムと言われる手提げ鞄ないしはハンドバッグを常に自分で持っていましたが、副総理になってからは秘書官に持たせるケースが増えています。
最高のリーダーは1ミリたりともぶれてはいけません。いよいよ来週から「一体改革特別委員会」のスタートです。本会議でも趣旨説明と代表質問が行われる予定です。チーム岡田は歴史に名を残すチャンスです。私はチーム岡田を全面的に応援します。そして、国益より省益をめざす官僚が局長級に一部いるのならば、「岡田をうつなら俺をうて」。私が松尾伝蔵になります。岡田が決めたらどこまでも。まっすぐに、ひたむきに岡田さんとともに一体改革関連法を成立させる。余裕がない震災後日本ですが、私は後世のためにリンゴの木を植える。小沢一郎さんが無罪だろうが、有罪だろうが、何も関係ありません。時代はもうとっくにその先に行っています。
私もチーム岡田の別働隊として、命がけで一体改革関連法を仕上げる覚悟です。比叡山延暦寺を攻めろと言われれれば、私は攻めます。日本は戦国時代以上の国難にあります。実力ある人間は徹底的に前に出るしかありません。まっすぐにひたむきに、前へ進みましょう。どうせ人生一度きり。人生意気に感じたら、チーム岡田のみなさん、一緒に突っ込みましょう。背中を見ている人は必ずいます。
[お知らせ1]
会員制ブログで今後の政治日程とそのポイントを解説しています。
今後の政治日程 by 下町の太陽
最初の1ヶ月は無料で試し読みできます。活動資金になりますので、ぜひご協力下さい。
[お知らせ2]
「国会傍聴取材支援基金」を設けました。国会傍聴記をこのブログで伝えていきます。質素倹約に務めていますが、交通費、資料代などがかかります。既存メディアのように煽りのない情報を届けたいという希望をかなえてください。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
どうぞご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
[お知らせおわり]



























