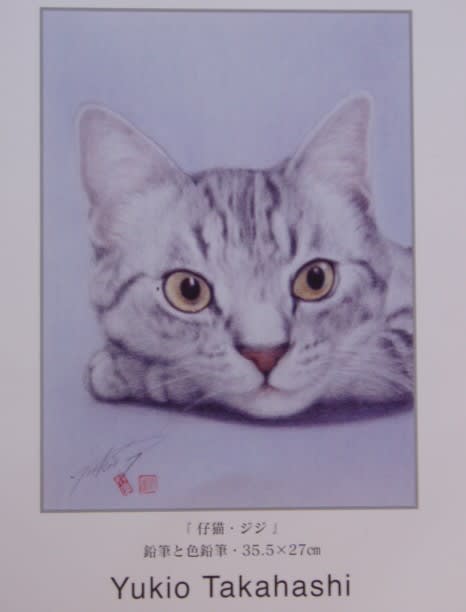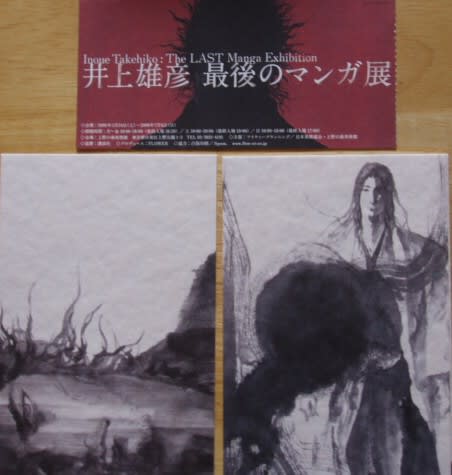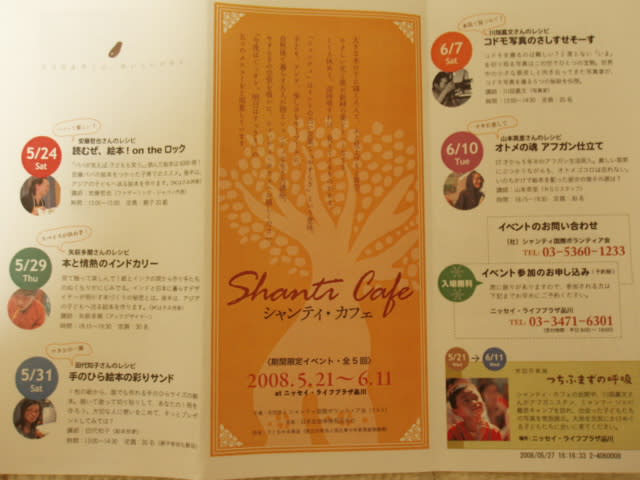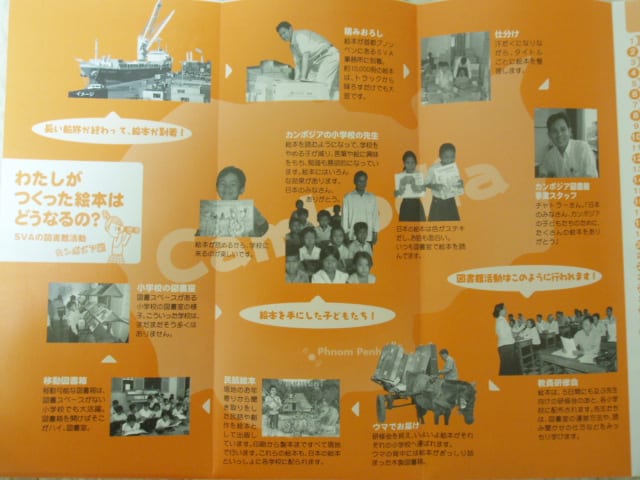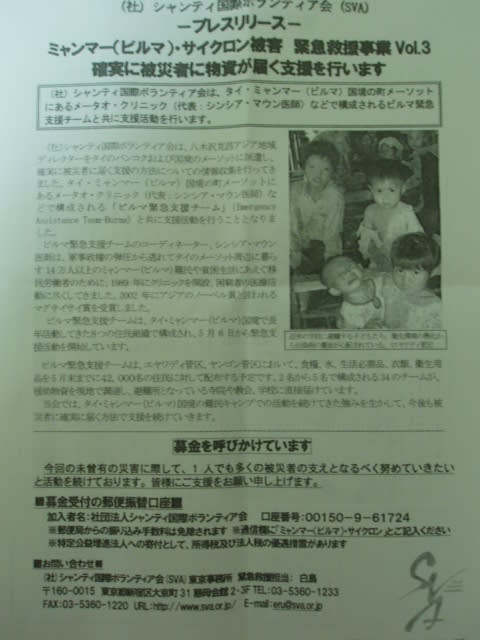8月末に金沢へ帰り、“いさら あんど・小野木 裕 展”へ、行きました。

 いさらさんは、以前行ったローラ浅田さんのライブ (写真・その時の日記 ⇒ こちら)の衣装を作られた方です。舞台にとっても映える衣装で個性的なデザイン…皆さんバッチリ着こなしてらっしゃいました。
いさらさんは、以前行ったローラ浅田さんのライブ (写真・その時の日記 ⇒ こちら)の衣装を作られた方です。舞台にとっても映える衣装で個性的なデザイン…皆さんバッチリ着こなしてらっしゃいました。
小野木さんはローラさんのお父様(90歳をこえてなお現役のアーティスト、今度、アメリカのグランドキャニオンのあたりへ行かれるとか!) 。写真はイーグルが描かれた花瓶です。色合いと絵のかわいさ・形の面白さに惹かれました。
いさらさんとも、小野木さんとも、少しだけですがお話が出来て光栄でした 。
。
そして、お楽しみイベント、ローラ浅田さんのライブがありました!クラリネット奏者のRYOさんが椅子を並べてくださり、音楽工房“ビブラソン”内での演奏がスタート。その場でピアノの方とも音のスピードを決めていらっしゃる…スゴイです。ローラさんの素晴らしい歌声♪目の前で聴いていた母は涙が自然に流れてきたそうで、それに気づいたローラさんは慌てて母を見ないようにしたとか(泣いている人を見ると自分も泣いてしまいそうになるから)。また、ローラさんは前方にいた子どもさんに向かって「退屈しない?翼をください歌おうか?」と優しく話しかけてらっしゃいました。今回も本当に素敵な歌と演奏で、良かったです。
ライブの始まる前には、虹まで出て。。。久々に見ました、キレイでした。とても充実した時間となりました。












 とりあえず自分のをチェックしてから、じっくりと皆様の絵本をみさせてもらいました。
とりあえず自分のをチェックしてから、じっくりと皆様の絵本をみさせてもらいました。