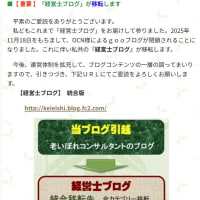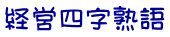
■【経営四字熟語で目から鱗が落ちる】■7-01 自育共育 仲間と共に自己研鑽 ~ 自己研鑽で成長するだけではなく、仲間と共に育つ ~

四字熟語というのは、漢字四文字で構成された熟語であることはよく知られています。お恥ずかしいながら、その四字熟語というのは、すべてが中国の故事に基づくものとばかり思っていましたが、実はそうではないことを発見しました。
経営コンサルタントという仕事をしていますが、その立場や経営という視点で四字熟語を”診る”と、今までとは異なった点で示唆を得られることが多のです。「目から鱗が落ちる」という言葉がありますが、四字熟語を講演や研修の場で用いたり、自分の仕事や日常会話に活かしたりするようにしましたら、他の人が私を尊敬といいますとオーバーですが、自分を見てくれる目が変わってきたように思えたことがあります。
四字熟語の含蓄を、またそこから得られる意味合いを噛みしめますと、示唆が多いですので、企業経営に活かせるのではないかと考えるようにもなりました。これを「目鱗経営」と勝手に造語し、命名しました。
以前にも四字熟語をご紹介していましたが、一般的な意味合いを中心にお話しました。このシリーズでは、四字熟語を経営の視点で診て、つぶやいてみます。以前の四字熟語ブログもよろしくお願いします。
■ 第7章 自育共育でプロフェッショナルに
世の中の変化、とりわけICT(IT)分野では「秒進分歩」といわれるほど技術革新のスピードが速くなっています。ビジネスの世界では、時代の変化に取り残されることは、死を意味するほどで、ビジネス関係者は必死で努力をしています。
自己研鑽という言葉がありますが、一人の力には限界があります。毎日どこかで開催されているといいましても過言ではないほど、セミナーが各処で開催されていますので、足繁く通っている人もいるでしょう。同じような志を持った仲間達が、例えば「朝会」と称して勉強しているところもあります。仲間とグループを作り、勉強会を開いているかもしれません。
「共育」は「教育」の誤変換ではなく、「共に育み合う」時代になってきているのです。自育共育のあり方を四字熟語から感じ取っていきましょう。
*
■7-01 自育共育 仲間と共に自己研鑽
~ 自己研鑽で成長するだけではなく、仲間と共に育つ ~
中国西晋の文学者である左思(さし、生没年不明、一説に252年 - 307年頃<Wikipedia>)の作品に「三都の賦」という書物があります。「賦(ふ)」とは「土地または人口に割りあてたみつぎもの。租税。年貢<広辞苑>」という意味で、「三都賦」は三国時代の社会生活を幅広く紹介した本です。当時の皇帝から庶民まで、それだけではなく後世にも、その内容である、国の統一などの問題等に言及したこともあり、評判となりました。
因みに「好評嘖嘖(こうひょうさくさく)」という「評判が非常に良い」という意味でも散られる四字熟語があります。「嘖嘖」は「人が口々に噂する」という意味です。
三国志で有名な三国時代は、中国の魏、蜀、呉の三国が鼎立した222年から263年を刺すことが多いですが、中国の時代区分としては、黄巾の乱の蜂起(184年)による漢朝の動揺から、西晋による中国再統一(280年)までを指すようです。(【Wikipedia】)このことから「三者鼎立(さんしゃていりつ)」という四字熟語があります。「三人の人や二二や組織などの勢力が三つどもえ」である状態を指します。「鼎」は、祭祀などに用いられる三本脚の器を指し、三本脚がバランス良いことからこの四字熟語が生まれたようです。
「三都賦」の話を戻しますが、その序文に、当時著名であった皇甫謐が書いたり、張載が注釈を加えたりしたこともあり、こぞってこの書物を読みました。貴族や富豪が争ってこの作品を模写したことから洛陽に紙品不足問題が発生し、値段も高騰しました。このことから「洛陽の紙、価をたからしむ」ということが言われ、「洛陽紙価(らくようのしか)」という言葉が生まれました。
すなわち、「洛陽紙価」というのは「著作物が人気を博し、盛んに読まれること」という意味です。すなわちベストセラーと言えます。
昨今、出版不況と言うことがしばしば言われますが、書籍に対する需要減退がその原因であると言われています。ところが、タブレット型電子端末機器の普及とともに、電子書籍の流通が増え、実際には需要は減退しているどころか、増えていると思います。いわゆる「紙媒体」に「印刷」された書籍が売れないということでしょう。
その一因は、電子書籍化という時代の流れですが、書籍出版業界の閉鎖性に起因している部分が大きいようです。自分達の権益を侵されないように大手出版社や印刷会社が力にモノを言わせた横暴さがあると聞いています。
「自育共育(じいくきょういく)」の「自育」は、「自分を育む」ということで「自己研鑽(じこけんさん)」という意味です。「研鑽」というのは「学問などを深くきわめること。研究(広辞苑第六版)」ということで、個人の努力で学問などを深く極めることです。
「共育」というのは、あまり使われない言葉ですが、訓読みしますと「共に育つ」という意味で、「共生」などと多少通じる意味合いを持っています。すなわち、「自育共育」というのは「個人で努力して成長するだけではなく、仲間と共に育つ」という意味の四字熟語です。
私たちが、「自己研鑽」をする時に、印刷された物であり、電子媒体であれ、書物と言われるものだけではなく、いろいろな情報が不可欠です。これらを基に自分自身を充電することにより、知識も豊富になり、人間性も豊になる物です。とりわけ洛陽紙価、すなわちベストセラーと呼ばれる、書店店頭に平積みされている本というのは、多くの人が読んで、考えている訳ですから、書いている人の意図だけではなく、読者がどの様な思いで読んでいるのかを推測することも必要です。各地で読書会というグループ活動がありますが、指定された本を参加者が読んだ上で出席し、意見や情報交換をしたり、異なった見方やとらえ方を語り合ったりして、理解を深め、記憶を定かなモノしています。
一日は二十四時間しかありません。残念ながら、一人の人間では習得できる物も限界があります。睡眠時間を削るという安易な方法もありますが、その悪影響も懸念されます。限られた時間内に、たくさんの知識や智慧を蓄え、養うためには、質を高めることです。
その方法の一つが、他人の力を借りることです。その一つとして、私は、永年セミナーと言われるような勉強会にしばしば足を運にできました。セミナーは、講師が長い時間をかけて知識や情報を収集し、整理し、わかりやすいようにまとめて受講者に提供してくれるのです。受講者は、短時間に、凝集された知識や情報を入手できます。私は、同じ人のセミナーを複数回受講することがあります。例えテーマが同じであっても、話を聞く度に、新しい発見があります。前回理解できなかったことでも二回目には理解できたり、理解度が高まったりすることがあるのです。自分と異なる考えであっても、いろいろな意見や考え方があるということを散るだけでも大いなる学びの一つといえます。
私が所属しています組織では、「知修塾」と称する勉強会があります。そこでは、上述の読書会の変形といってよいのでしょうか、定められた書籍をもとに塾員がそれを深く理解してから参加します。当番の塾員が、パワーポイントを使って、研究成果を発表します。他の塾員は、それを基に理解度を深めると共に、解釈が異なったり、重要度のウェイト付けが違っていたりした場合に、後で討議をします。経営コンサルタントの勉強会である知修塾では、単に「知識を修める」だけではなく、発表の場で講師力養成の体験ができます。また、討論を通じて、人を納得させる話術を学ぶこともできます。ベテランのコンサルタントもいれば、これから経営コンサルタント資格を取ろうという人もいます。さながら塾長を中心にした松下村塾です。
松下村塾といいますと、幕末の時代変革時の独特なやり方をする教育者でした。幕末には必ず登場するします高杉晋作や久坂玄瑞、明治時代を率いる伊藤博文やなどを育てて来ましたので、知らない人がいないほどの人物です。
松蔭は後の世に残るいろいろな言葉を発してきましたが、なかでも「草莽崛起」(そうもうくっき)」は、代表的なひとつと考えます。「草莽(そうもう)」というのは、「名もない雑草のような在野の人」を指します。「崛起(くっき)」は、「山などの高くそびえ立つこと。にわかに起こり立つこと(広辞苑第六版)」という意味です。すなわち、このことから「草莽崛起」というのは「在野の志士よ、一斉に立ち上がれ」という意味で、列強各国の外圧に対する攘夷を掲げる強烈な檄です。
自分が国のために何ができるのかを考えさせるという考えを強く訴えてきました。それは、故ケネディー大統領の就任演説の一端に通じるものを私は感じ取ります。一人ではできないことも、同じ志を持った人達が団結をすると大きな力を発揮します。群衆に埋もれることなく、きらりと光る人達を育てて来たところに松蔭の存在価値があるのでしょう。
松蔭の教えの中で、自己流に解釈しますと「志を立てよ。自分よりもすぐれた人と交われ。書物を読んで勉強しろ」ということを、二年余に短い松下村塾の教えとしてきたと言えます。その教育法は、ユニークで、十代半ばの少年を相手に激論を交わすなど、「熱く燃えるが、人間味のある人」という印象を受ける人だと考えています。そこに「自育共育」の魂を見る気がします。
【 注 】下記URLにて紹介されています。
「三都賦」http://japanese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160411.htm
「吉田松陰」http://www.yoshida-shoin.com/torajirou/soumoukukki.html
*
世の中の変化、とりわけICT(IT)分野では「秒進分歩」といわれるほど技術革新のスピードが速くなっています。ビジネスの世界では、時代の変化に取り残されることは、死を意味するほどで、ビジネス関係者は必死で努力をしています。
自己研鑽という言葉がありますが、一人の力には限界があります。毎日どこかで開催されているといいましても過言ではないほど、セミナーが各処で開催されていますので、足繁く通っている人もいるでしょう。同じような志を持った仲間達が、例えば「朝会」と称して勉強しているところもあります。仲間とグループを作り、勉強会を開いているかもしれません。
「共育」は「教育」の誤変換ではなく、「共に育み合う」時代になってきているのです。自育共育のあり方を四字熟語から感じ取っていきましょう。
*
■7-01 自育共育 仲間と共に自己研鑽
~ 自己研鑽で成長するだけではなく、仲間と共に育つ ~
中国西晋の文学者である左思(さし、生没年不明、一説に252年 - 307年頃<Wikipedia>)の作品に「三都の賦」という書物があります。「賦(ふ)」とは「土地または人口に割りあてたみつぎもの。租税。年貢<広辞苑>」という意味で、「三都賦」は三国時代の社会生活を幅広く紹介した本です。当時の皇帝から庶民まで、それだけではなく後世にも、その内容である、国の統一などの問題等に言及したこともあり、評判となりました。
因みに「好評嘖嘖(こうひょうさくさく)」という「評判が非常に良い」という意味でも散られる四字熟語があります。「嘖嘖」は「人が口々に噂する」という意味です。
三国志で有名な三国時代は、中国の魏、蜀、呉の三国が鼎立した222年から263年を刺すことが多いですが、中国の時代区分としては、黄巾の乱の蜂起(184年)による漢朝の動揺から、西晋による中国再統一(280年)までを指すようです。(【Wikipedia】)このことから「三者鼎立(さんしゃていりつ)」という四字熟語があります。「三人の人や二二や組織などの勢力が三つどもえ」である状態を指します。「鼎」は、祭祀などに用いられる三本脚の器を指し、三本脚がバランス良いことからこの四字熟語が生まれたようです。
「三都賦」の話を戻しますが、その序文に、当時著名であった皇甫謐が書いたり、張載が注釈を加えたりしたこともあり、こぞってこの書物を読みました。貴族や富豪が争ってこの作品を模写したことから洛陽に紙品不足問題が発生し、値段も高騰しました。このことから「洛陽の紙、価をたからしむ」ということが言われ、「洛陽紙価(らくようのしか)」という言葉が生まれました。
すなわち、「洛陽紙価」というのは「著作物が人気を博し、盛んに読まれること」という意味です。すなわちベストセラーと言えます。
昨今、出版不況と言うことがしばしば言われますが、書籍に対する需要減退がその原因であると言われています。ところが、タブレット型電子端末機器の普及とともに、電子書籍の流通が増え、実際には需要は減退しているどころか、増えていると思います。いわゆる「紙媒体」に「印刷」された書籍が売れないということでしょう。
その一因は、電子書籍化という時代の流れですが、書籍出版業界の閉鎖性に起因している部分が大きいようです。自分達の権益を侵されないように大手出版社や印刷会社が力にモノを言わせた横暴さがあると聞いています。
「自育共育(じいくきょういく)」の「自育」は、「自分を育む」ということで「自己研鑽(じこけんさん)」という意味です。「研鑽」というのは「学問などを深くきわめること。研究(広辞苑第六版)」ということで、個人の努力で学問などを深く極めることです。
「共育」というのは、あまり使われない言葉ですが、訓読みしますと「共に育つ」という意味で、「共生」などと多少通じる意味合いを持っています。すなわち、「自育共育」というのは「個人で努力して成長するだけではなく、仲間と共に育つ」という意味の四字熟語です。
私たちが、「自己研鑽」をする時に、印刷された物であり、電子媒体であれ、書物と言われるものだけではなく、いろいろな情報が不可欠です。これらを基に自分自身を充電することにより、知識も豊富になり、人間性も豊になる物です。とりわけ洛陽紙価、すなわちベストセラーと呼ばれる、書店店頭に平積みされている本というのは、多くの人が読んで、考えている訳ですから、書いている人の意図だけではなく、読者がどの様な思いで読んでいるのかを推測することも必要です。各地で読書会というグループ活動がありますが、指定された本を参加者が読んだ上で出席し、意見や情報交換をしたり、異なった見方やとらえ方を語り合ったりして、理解を深め、記憶を定かなモノしています。
一日は二十四時間しかありません。残念ながら、一人の人間では習得できる物も限界があります。睡眠時間を削るという安易な方法もありますが、その悪影響も懸念されます。限られた時間内に、たくさんの知識や智慧を蓄え、養うためには、質を高めることです。
その方法の一つが、他人の力を借りることです。その一つとして、私は、永年セミナーと言われるような勉強会にしばしば足を運にできました。セミナーは、講師が長い時間をかけて知識や情報を収集し、整理し、わかりやすいようにまとめて受講者に提供してくれるのです。受講者は、短時間に、凝集された知識や情報を入手できます。私は、同じ人のセミナーを複数回受講することがあります。例えテーマが同じであっても、話を聞く度に、新しい発見があります。前回理解できなかったことでも二回目には理解できたり、理解度が高まったりすることがあるのです。自分と異なる考えであっても、いろいろな意見や考え方があるということを散るだけでも大いなる学びの一つといえます。
私が所属しています組織では、「知修塾」と称する勉強会があります。そこでは、上述の読書会の変形といってよいのでしょうか、定められた書籍をもとに塾員がそれを深く理解してから参加します。当番の塾員が、パワーポイントを使って、研究成果を発表します。他の塾員は、それを基に理解度を深めると共に、解釈が異なったり、重要度のウェイト付けが違っていたりした場合に、後で討議をします。経営コンサルタントの勉強会である知修塾では、単に「知識を修める」だけではなく、発表の場で講師力養成の体験ができます。また、討論を通じて、人を納得させる話術を学ぶこともできます。ベテランのコンサルタントもいれば、これから経営コンサルタント資格を取ろうという人もいます。さながら塾長を中心にした松下村塾です。
松下村塾といいますと、幕末の時代変革時の独特なやり方をする教育者でした。幕末には必ず登場するします高杉晋作や久坂玄瑞、明治時代を率いる伊藤博文やなどを育てて来ましたので、知らない人がいないほどの人物です。
松蔭は後の世に残るいろいろな言葉を発してきましたが、なかでも「草莽崛起」(そうもうくっき)」は、代表的なひとつと考えます。「草莽(そうもう)」というのは、「名もない雑草のような在野の人」を指します。「崛起(くっき)」は、「山などの高くそびえ立つこと。にわかに起こり立つこと(広辞苑第六版)」という意味です。すなわち、このことから「草莽崛起」というのは「在野の志士よ、一斉に立ち上がれ」という意味で、列強各国の外圧に対する攘夷を掲げる強烈な檄です。
自分が国のために何ができるのかを考えさせるという考えを強く訴えてきました。それは、故ケネディー大統領の就任演説の一端に通じるものを私は感じ取ります。一人ではできないことも、同じ志を持った人達が団結をすると大きな力を発揮します。群衆に埋もれることなく、きらりと光る人達を育てて来たところに松蔭の存在価値があるのでしょう。
松蔭の教えの中で、自己流に解釈しますと「志を立てよ。自分よりもすぐれた人と交われ。書物を読んで勉強しろ」ということを、二年余に短い松下村塾の教えとしてきたと言えます。その教育法は、ユニークで、十代半ばの少年を相手に激論を交わすなど、「熱く燃えるが、人間味のある人」という印象を受ける人だと考えています。そこに「自育共育」の魂を見る気がします。
【 注 】下記URLにて紹介されています。
「三都賦」http://japanese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160411.htm
「吉田松陰」http://www.yoshida-shoin.com/torajirou/soumoukukki.html
*
【経営四字熟語】バックナンバー ←クリック
*
■ おすすめブログ コンサルタント・士業に特化したブログ
© copyrighit N. Imai All rights reserved