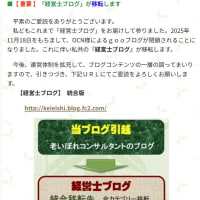■【経営四字熟語で目から鱗が落ちる】6-07 愚者一得 人の評価は難しい ~ 誰でも、たまには良いことを言ったり、思いついたりする

四字熟語というのは、漢字四文字で構成された熟語であることはよく知られています。お恥ずかしいながら、その四字熟語というのは、すべてが中国の故事に基づくものとばかり思っていましたが、実はそうではないことを発見しました。
経営コンサルタントという仕事をしていますが、その立場や経営という視点で四字熟語を”診る”と、今までとは異なった点で示唆を得られることが多のです。「目から鱗が落ちる」という言葉がありますが、四字熟語を講演や研修の場で用いたり、自分の仕事や日常会話に活かしたりするようにしましたら、他の人が私を尊敬といいますとオーバーですが、自分を見てくれる目が変わってきたように思えたことがあります。
四字熟語の含蓄を、またそこから得られる意味合いを噛みしめますと、示唆が多いですので、企業経営に活かせるのではないかと考えるようにもなりました。これを「目鱗経営」と勝手に造語し、命名しました。
以前にも四字熟語をご紹介していましたが、一般的な意味合いを中心にお話しました。このシリーズでは、四字熟語を経営の視点で診て、つぶやいてみます。以前の四字熟語ブログもよろしくお願いします。
■ 第6章 仕事上手になる法
論理思考で現状分析をキチンとし、方向性を明確にしてからPDCAサイクルを回し始めても、実際に行動に移したときに旨くいかないことがあります。やりたいという気持ちはあっても、いざ行動に移そうとしたときに、動けないこともあります。
相手の人を説得したり、納得させたりしても、必ずしも相手は期待通りに動いてくれないことがあります。日常生活においてだけではなく、経営者・管理職にとっては、社員や部下が動いてくれないというのは深刻な問題です。
人の価値観というのは、多様性に富んでいます。論理思考で相手を説得したからといって、相手は納得したわけではありません。一つの価値観だけでは、相手は納得してくれません。人は、理屈だけで動いているわけでもなく、感情もあります。
うまくいかない原因として、やろうとしていることにコツやカンというものがあったり、それを行うための技術が必要であったりして、その習得ができていないことでうまく行かないことがあります。コツの飲み込み方が上手な人もいれば、そうでない人もいます。
このような時に、役立つ四字熟語がありますので、ご紹介します。ここでは、四字熟語の中から、相手を理解し、一方、相手にその気になってもらうには、どうしたらよいのか、心に訴えるヒントを感じ取っていただきたいです。
*
■6-07 愚者一得 人の評価は難しい
~ 誰でも、たまには良いことを言ったり、思いついたりする ~
「愚者一得」というのは、史記の中に記述されていて「どのような愚かな人(愚者)であっても、たまには良いことを言ったり、思いついたりするもの」という意味です。「千慮一得(せんりょいっとく)」という言葉もありますが、ほぼ同意と言われています。
似たような四字熟語として「千慮一失(せんりょいっしつ)」という言葉があります。どのように賢い人でも、数多いアイディアの中には一つ二つの陳腐な提案もあるという意味です。熟慮の末でも、失敗をすることもあります。
われわれ経営コンサルタントも、自分の提案がうまくいったときには一人でほくそ笑んだり、乾杯したりします。一方で失敗することもあり、その時には相当落ち込みます。その代わり、大金を出してくださったクライアント・顧問先に対して申し訳けありませんので、次の機会があればさらに妙案を提供するように努力をします。私の失敗を見て、クライアントの中には、「千慮一失さ」と私の将来を見てくださったこともあり、そのようなクライアントとは長いおつきあいをさせていただいています。
別項でも触れましたが、いろいろな経営者・管理職にお会いしていますと、「うちの社員は無能揃い」「うちの役員と来たら全く役に立たん」と自分の会社の社員や部下を悪く言う経営者・管理職にお会いします。
しかし、本当にそうでしょうか?「愚者一得」というと失礼ですが、社員や部下が何も良い提案やアイディアを出さないとは思えません。むしろ、そういう経営者・管理職の方が部下の提案を正しく評価できていませんから、愚者と思えるのではないでしょうか。
このことからおわかりのように「愚者一得(ぐしゃいっとく)」というのは、愚者であっても、たまには良いことを言うという意味から、愚者と思える人であっても必ず長所はあり、自分より優れている面を持っていたり、しばしば自分が知らないことに詳しかったりします。
一方、どのように賢い人でも、それがたとえ熟慮の末のことであっても、失敗をすることもあります。数多いアイディアの中には一つ二つは陳腐であったり、効果がなかったりする提案もあるという意味です。
「愚者一得」には、「例え愚かと思える人でも、何か良い面を持っている」という意味でも使われます。幕末の賢者、吉田松陰の言葉に「人賢愚(ひとけんぐ)ありと雖(いえど)も、各々一、二の才能無きはなし」という件があります。まさに愚者一得に繋がる名言と言えます。
部下や他の人達が愚かに思えたときは、自分の驕りではないかと振り返ってみることが必要と考えます。
「一得一失(いっとくいっしつ)」という言葉があります。もともとは、「一方に益があれば、他方に損がある」という意味でした。これが転じて「良いこともあれば、悪いこともある」「長所もあれば短所もある」という意味でも用いられます。類語として「一長一短(いっちょういったん)」「一利一害(いちりいちがい)」という四字熟語もあります。
「乳母日傘(おんばひがさ)」な人だからと言って軽視することはできません。「雲蒸竜変(うんじょうりゅうへん)」という言葉がありますように、人間というのは、あることを契機として、急に成長することがあります。「雲蒸」は、雲がむくむくと湧き上がる様を言います。その雲が龍に変身して、天高く登るということから、人の急成長を表す表現でもあります。しばしば、英雄が時宜に応じた判断をして急に世の中に出現するというようなたとえで、人の成長を表現します。
人の内面がわかりにくいというのは「燕雀鴻鵠(えんじゃくこうこく)」という四字熟語にも表れています。「燕雀」というのは、燕や雀のような小さな鳥、「鴻鵠」の「鴻」は、「鳳」や「鵬」とも通じ、「大鵬」という元名横綱の名前になるような「大きな鳥」という意味です。このことから「鴻鵠」すなわち、大人物の志を、「燕雀」すなわち小人物には理解できないという、人の評価の難しさを謳っています。
世の中には、自分は人を見る目があると自負する方を時々見受けます。そのような人の中には、占い師であるがごとく、相手を的確に見抜ける人がいます。しかし、大半は、自分でそう思い込んでいるように思えます。「街談巷説(がいだんこうせつ)」という四字熟語があります。「街談」は、「街中の話」、「巷説」は「巷に聞く話」ということで、いずれも世間話とか噂ということです。
我々、経営コンサルタントも時として、ある情報を入手しますと、それが正しいこと、あるいは事実であるというとらえ方をして、失敗することがあります。別項でも触れていますが、「刑事は現場百遍」「ウラを取る」という言葉がありますが、これはわれわれ経営コンサルタントにも通ずることと考えています。われわれ経営コンサルタントは、情報は必ずウラを取ることを忘れてはいけないと考えています。
史記に登場します「鶏鳴狗盗(けいめいくとう)」はしたくないものです。「鶏鳴」は、鶏の鳴き声、「狗盗」は、犬のようにこそこそと食べ物を漁り、盗むことから、そのようなことをする卑しい人を指します。
中国・戦国時代の斉国の孟嘗君(もうしょうくん)が、鶏の鳴き真似ができる食客と、こそ泥を利用して難を逃れたという故事から来ています。このことからもとの意味から転じて「くだらないことや人でも、何かの役に立つことがある」というたとえにも使われます。
「愚者一得」神様は、公平にわれわれに天分を与えてくれているのです。
*
論理思考で現状分析をキチンとし、方向性を明確にしてからPDCAサイクルを回し始めても、実際に行動に移したときに旨くいかないことがあります。やりたいという気持ちはあっても、いざ行動に移そうとしたときに、動けないこともあります。
相手の人を説得したり、納得させたりしても、必ずしも相手は期待通りに動いてくれないことがあります。日常生活においてだけではなく、経営者・管理職にとっては、社員や部下が動いてくれないというのは深刻な問題です。
人の価値観というのは、多様性に富んでいます。論理思考で相手を説得したからといって、相手は納得したわけではありません。一つの価値観だけでは、相手は納得してくれません。人は、理屈だけで動いているわけでもなく、感情もあります。
うまくいかない原因として、やろうとしていることにコツやカンというものがあったり、それを行うための技術が必要であったりして、その習得ができていないことでうまく行かないことがあります。コツの飲み込み方が上手な人もいれば、そうでない人もいます。
このような時に、役立つ四字熟語がありますので、ご紹介します。ここでは、四字熟語の中から、相手を理解し、一方、相手にその気になってもらうには、どうしたらよいのか、心に訴えるヒントを感じ取っていただきたいです。
*
■6-07 愚者一得 人の評価は難しい
~ 誰でも、たまには良いことを言ったり、思いついたりする ~
「愚者一得」というのは、史記の中に記述されていて「どのような愚かな人(愚者)であっても、たまには良いことを言ったり、思いついたりするもの」という意味です。「千慮一得(せんりょいっとく)」という言葉もありますが、ほぼ同意と言われています。
似たような四字熟語として「千慮一失(せんりょいっしつ)」という言葉があります。どのように賢い人でも、数多いアイディアの中には一つ二つの陳腐な提案もあるという意味です。熟慮の末でも、失敗をすることもあります。
われわれ経営コンサルタントも、自分の提案がうまくいったときには一人でほくそ笑んだり、乾杯したりします。一方で失敗することもあり、その時には相当落ち込みます。その代わり、大金を出してくださったクライアント・顧問先に対して申し訳けありませんので、次の機会があればさらに妙案を提供するように努力をします。私の失敗を見て、クライアントの中には、「千慮一失さ」と私の将来を見てくださったこともあり、そのようなクライアントとは長いおつきあいをさせていただいています。
別項でも触れましたが、いろいろな経営者・管理職にお会いしていますと、「うちの社員は無能揃い」「うちの役員と来たら全く役に立たん」と自分の会社の社員や部下を悪く言う経営者・管理職にお会いします。
しかし、本当にそうでしょうか?「愚者一得」というと失礼ですが、社員や部下が何も良い提案やアイディアを出さないとは思えません。むしろ、そういう経営者・管理職の方が部下の提案を正しく評価できていませんから、愚者と思えるのではないでしょうか。
このことからおわかりのように「愚者一得(ぐしゃいっとく)」というのは、愚者であっても、たまには良いことを言うという意味から、愚者と思える人であっても必ず長所はあり、自分より優れている面を持っていたり、しばしば自分が知らないことに詳しかったりします。
一方、どのように賢い人でも、それがたとえ熟慮の末のことであっても、失敗をすることもあります。数多いアイディアの中には一つ二つは陳腐であったり、効果がなかったりする提案もあるという意味です。
「愚者一得」には、「例え愚かと思える人でも、何か良い面を持っている」という意味でも使われます。幕末の賢者、吉田松陰の言葉に「人賢愚(ひとけんぐ)ありと雖(いえど)も、各々一、二の才能無きはなし」という件があります。まさに愚者一得に繋がる名言と言えます。
部下や他の人達が愚かに思えたときは、自分の驕りではないかと振り返ってみることが必要と考えます。
「一得一失(いっとくいっしつ)」という言葉があります。もともとは、「一方に益があれば、他方に損がある」という意味でした。これが転じて「良いこともあれば、悪いこともある」「長所もあれば短所もある」という意味でも用いられます。類語として「一長一短(いっちょういったん)」「一利一害(いちりいちがい)」という四字熟語もあります。
「乳母日傘(おんばひがさ)」な人だからと言って軽視することはできません。「雲蒸竜変(うんじょうりゅうへん)」という言葉がありますように、人間というのは、あることを契機として、急に成長することがあります。「雲蒸」は、雲がむくむくと湧き上がる様を言います。その雲が龍に変身して、天高く登るということから、人の急成長を表す表現でもあります。しばしば、英雄が時宜に応じた判断をして急に世の中に出現するというようなたとえで、人の成長を表現します。
人の内面がわかりにくいというのは「燕雀鴻鵠(えんじゃくこうこく)」という四字熟語にも表れています。「燕雀」というのは、燕や雀のような小さな鳥、「鴻鵠」の「鴻」は、「鳳」や「鵬」とも通じ、「大鵬」という元名横綱の名前になるような「大きな鳥」という意味です。このことから「鴻鵠」すなわち、大人物の志を、「燕雀」すなわち小人物には理解できないという、人の評価の難しさを謳っています。
世の中には、自分は人を見る目があると自負する方を時々見受けます。そのような人の中には、占い師であるがごとく、相手を的確に見抜ける人がいます。しかし、大半は、自分でそう思い込んでいるように思えます。「街談巷説(がいだんこうせつ)」という四字熟語があります。「街談」は、「街中の話」、「巷説」は「巷に聞く話」ということで、いずれも世間話とか噂ということです。
我々、経営コンサルタントも時として、ある情報を入手しますと、それが正しいこと、あるいは事実であるというとらえ方をして、失敗することがあります。別項でも触れていますが、「刑事は現場百遍」「ウラを取る」という言葉がありますが、これはわれわれ経営コンサルタントにも通ずることと考えています。われわれ経営コンサルタントは、情報は必ずウラを取ることを忘れてはいけないと考えています。
史記に登場します「鶏鳴狗盗(けいめいくとう)」はしたくないものです。「鶏鳴」は、鶏の鳴き声、「狗盗」は、犬のようにこそこそと食べ物を漁り、盗むことから、そのようなことをする卑しい人を指します。
中国・戦国時代の斉国の孟嘗君(もうしょうくん)が、鶏の鳴き真似ができる食客と、こそ泥を利用して難を逃れたという故事から来ています。このことからもとの意味から転じて「くだらないことや人でも、何かの役に立つことがある」というたとえにも使われます。
「愚者一得」神様は、公平にわれわれに天分を与えてくれているのです。
*
【経営四字熟語】バックナンバー ←クリック
*
■ おすすめブログ コンサルタント・士業に特化したブログ
- 【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記
- 【小説風】竹根好助のコンサルタント起業
- 【経営】 成功企業・元気な会社・頑張る社長
- 【専門業】 経営コンサルタントへの道
- 【専門業】 経営コンサルタントはかくありたい
- 【専門業】 日本経営士協会をもっと知る
- 【専門業】 ユーチューブで学ぶコンサルタント成功法
- 【専門業】 プロの表現力
- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業5つの要諦
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<思考法編>
- 【経営・専門業】 ビジネス成功術
- 【経営・専門業】 経営コンサルタントのひとり言
- 【話材】 話したくなる情報源
- 【話材】 お節介焼き情報
- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業講座
- 【専門業】 経営コンサルタント情報
- 【専門業】 プロのための問題解決技法(0
- 【経営】 経営コンサルタントの本棚
- 【経営】 コンサルタントの選び方
- 【経営】 管理会計を活用する
- 【経営】 経営コンサルタントの効果的な使い方
- 【経営】 ユーチューブで学ぶ元気な経営者になる法
- 【心 de 経営】 菜根譚に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 経営四字熟語
- 【心 de 経営】 徒然草に学ぶ
- 【心 de 経営】 経営コンサルタントのあり方
- 【心 de 経営】 歴史・宗教に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 論語に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 心づかいで人間関係改善
- 【経営】 経営情報一般
- コンサルタントバンク
- 【話材】 お節介焼き情報
- 【話材】 ブログでつぶやき
- 【話材】 季節・気候
- 【話材】 健康・環境
- 【経営コンサルタントのひとり言】
- 【経営】 ICT・デジタル情報
- 【話材】 きょうの人01月
- 【話材】 きょうの人02月
- 【話材】 きょうの人03月
- 【話材】 きょうの人04月
- 【話材】 きょうの人05月
- 【話材】 きょうの人06月
- 【話材】 きょうの人07月
- 【話材】 きょうの人08月
- 【話材】 きょうの人09月
- 【話材】 きょうの人10月
- 【話材】 きょうの人11月
- 【話材】 きょうの人12月
- 【話材】 きょうの人
© copyrighit N. Imai All rights reserved