| [ブログ内検索] [漢字に関する書籍] [漢字源] [中国古典選] |
| 暗・鮭の成り立ちと参考図書について 投稿者:すう 投稿日:2008年 8月31日(日)11時51分21秒 はじめてまして。質問が3つあります。 1.「暗」は「音」の同系で、はっきりしないの意で暗いとありましたが、なぜ、へんが「日」なんでしょうか。(日があると、逆にはっきりするような気がするのですが。。。) 2.鮭はなぜ魚へんに土が二つなんでしょうか。 3.漢字の好きなドイツ人に日本語を教えていてこの手の質問が多いのですが、ドイツ在住で日本の図書館に通うこともままならず、困っております。参考図書を購入したいのですが、お薦めがあれば教えてください。突然変な質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いたします。 |
1.「暗」は、なぜ、へんが「日」?
「へん」はその字が何に関係するかを表します。
「つくり」は基本義をあらわします。
基本的な意味は、「うちにこもって、けじめが明白でない」こと。
「暗」と同じ単語家族の、「喑」や「諳」は、「へん」が「口」もしくは「言」ですので、それが言葉に関係していることがわかります。
つまり、口ごもって、「発音のけじめが明白でないこと」。これらは、「音」という字のもともとの意味を表します。
聴覚から視覚へと目を向けると、「暗」は、「日」へんで、日光に関係していることを表します。
(狭い部屋などに閉じこもって)日光が届かず「くらくて物のけじめが見分けられない」状態を表すために「日」へんをつけました。
2.鮭はなぜ魚へんに土が二つなんでしょうか?
「土+土」 ・・・ 「上の鋭く、下の方(しかく)なるを珪(ケイ)という」<荘子・馬蹄>
「圭」(ケイ)は、古代の玉器です。天子が諸候に領地を与えた印として持たせたものですが、その形は、上がとがった三角形をしていました。
どうして玉器が「三角形」をしているのかというと、もともとは「三角形の土盛り」を真似たものです。古代、諸候を封ずる儀式のおり、領有する地域の土を三角の形に盛り、土地の領有を神に告げたので、その象徴的な形を玉器にしたのです。
さて、それでは「鮭」はというと
■解字
「魚+音符圭(ケイ・△型にとがった、形がよい)」
すらりとして形がよいところに着目してつくられた漢字なのでした。
※「鮭」=「魚+圭 すらりとして形がよい魚」
※「佳」=「人+圭 すっきりと目立つ人、すっきりと形よくととのった人」(だらしないことの反対)
※「恚」=「心+圭 心をかどだてておこること」
3.参考図書のお薦めは?
参考図書については、こちらにおいでるみなさんが、それぞれお答えくださることでしょうが、このサイトでお薦めしているのは、
「藤堂明保博士著作データベース」です。
http://1st.geocities.jp/ica7ea/kanji/hakase.xls
(注:Exel用のファイルです)
外国の方に日本語を教えられるということですが、ご苦労も多いと思います。
また、よろしければ、日本語をご教授される過程でお気づきになった点など、このBBSでお知らせいただければ幸いです。
| Re^2:暗・鮭の成り立ちと参考図書について 投稿者:すう 投稿日:2008年 8月31日(日)17時15分17秒 早々のお返事ありがとうございました。私自身、大変勉強になりました。生徒がもう少し日本語ができるようになったら、ぜひこちらのサイトにお邪魔するようにと言おうと思います。本当にありがとうございました。 |
| 漢字質問箱バックナンバー |












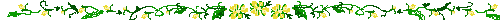

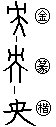 央の字は、いずれ
央の字は、いずれ