| [ブログ内検索] |
| 荘子:斉物論第二(8) 夫 言 非 吹 也 , 言 者 有 言 。 其 所 言 者 特 未 定 也 。 果 有 言 邪 ? 其 未 嘗 有 言 邪 ? 其 以 為 異 於 ? 音 , 亦 有 辯 乎 ? 其 無 辯 乎 ? 道 惡 乎 隱 而 有 眞 僞 ? 言 惡 乎 隱 而 有 是 非 ? 道 惡 乎 往 而 不 存 ? 言 惡 乎 存 而 不 可 ? 道 隱 於 小 成 , 言 隱 於 榮 華 。 故 有 儒 墨 之 是 非 , 以 是 其 所 非 而 非 其 所 是 。 欲 是 其 所 非 而 非 其 所 是 , 則 莫 若 以 明 。 |
夫(そ)れ言(ゲン)は吹(スイ)には非(あら)ざるなり。言う者には言(ことば)あり。其(そ)の言う所の者、独(ひと)り未(いま)だ定まらざれば、果たして言ありや、其れ未だ嘗(かつ)て言あらざるか。其れ以(もっ)て?(コウ)の音(ね)に異なれりと為(な)すも、亦(また)弁(ベン・けじめ)ありや、其れ弁無きや。
道は悪(なに)に隠(よ)りて真偽あるか、言は悪(なに)に隠(よ)りて是非有るか。道は悪くにか往(ゆ)きて存せざる、言は悪くにか存して不可なる。道は小成に隠(よ)り、言は栄華に隠(よ)る。
故(ゆえ)に儒墨(ジュボク)の是非有り。以て其の非とする所を是として、其の是とする所を非とす。其の非とする所を是として、其の是とする所を非とせんと欲するは、則(すなわ)ち明(メイ)を以てするに若(し)くは莫(な)し。
さて、ことばというものは、口から吹き出す単なる音ではない。ものを言った場合には言葉の意味がある。その言った言葉の意味がまだあいまいでさだかでないなら、はたしてものを言ったことになるのか、それとも何も言わなかったことになるのか。たとえ単なる雛鳥(ひなどり)のさえずりとは違うといったところで、はたして区別がつくかつかないか。
(本来、真でも偽でもない)道に、何故真と偽との区別が生ずるのか。(本来是も非もない)言語に、何故是と非の対立が生ずるのか。道はあらゆる場所に存在するし、ことばはどんな場合でもそのすべてが「可」である。道は小さな成功を求める心によって真偽の対立を生み、ことばは虚栄とはなやかな修飾によって是非の対立を生んだ。
だからこそ、そこに儒家と墨家の是非の対立が生まれる。こうして相手の非とするところを是とし、相手の是とするところを非とするようになる。相手の非とするところを是とし、相手の是とするところを非とすることを望むのは、真の明智(明明白白の理)に立脚する立場には及びもつかないのである。
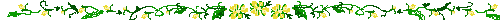
※言者有言
言葉にはすべて説明しようとする内容、すなわち意味がある。
※果有言邪, 其未嘗有言邪
二つの命題を疑問系で並べて後者を肯定する句法。
「未だ嘗て言なし」の意味。
次の「亦有辯乎, 其無辯乎」も同様。
※?
■音
【ピンイン】[kou4]
【漢音】コウ 【呉音】ク
■単語家族
句(まるく小さい)─ 狗(まるく小さい小犬)と同系。
■意味
まるく小さいひな鳥。
◆燕・雀などの子のように、親から口うつしに養われるひなを?、鶏・雉(きじ)などの子のように、自分でついばんで食するひなを雛(スウ)という。
※隱
「道惡乎隱而有眞僞」の「隠」は、あとの3つの「隠」とともに、「几(つくえ)に隠(よ)る」の隠と同じで、「よる・もたれる」と訓(よ)む。
※小成(ショウセイ)
◆「小成、謂各執所成以為道。不知道之大也」(荘子集解)
◆それぞれの立場を完全と考えて異見を立てることによって、真偽が生まれてくる。(金谷治)
◆「小(かたよ)れる成(こころ)に隠(よ)り・・・」(福永光司)
※儒墨之是非
「儒墨二学派の論争は、いずれも偏見にとらわれ、自己を誇示するところに生じたもので、彼らの議論の喧(かまびす)しさ、その見かけの華々しさにもかかわらず、その主張はなんら明確な内容と根拠を持たず、雛の鳴き声の無意味さと全く同じだというのである」(福永光司)
◆儒墨の論争については・・・
『中国思想史』(森三樹三郎・レグルス文庫)を参照。










