| 荘子:斉物論第二(2) 子 游 曰 : 「 敢 問 其 方 」、 子 ? 曰 : 「 夫 大 塊 噫 氣 , 其 名 為 風 。 是 唯 無 作 , 作 則 萬 竅 怒 ? 。 而 獨 不 聞 之 ? ? 乎? 山 林 之 畏 佳 , 大 木 而 圍 之 竅 穴 , 似 鼻 , 似 口 , 似 耳 , 似 枅 , 似 圈 , 似 臼 , 似 ? 者, 似 汚 者 。 激 者 、 ? 者 、 叱 者 、 吸 者 、 叫 者 、? 者 、 ? 者 , 咬 者 , 前 者 唱 于 而 隨 者 唱 ? , ? 風 則 小 和 , 飄 風 則 大 和 , 風 濟 則 衆 竅 為 ? 。 而 獨 不 見 之 調 調 , 之 ? ? 乎? 」 |
子游(シユウ)曰わく、「敢(あ)えて其の方(ことわり)を問う」と。
子?曰わく、夫(そ)れ、大塊(タイカイ)の噫気(アイキ・おくび)は其の名を風と為(な)す。是れ唯(ただ)作(おこ)ることなきのみ。作れば則ち萬竅怒?(バンキョウドゴウ)す。而(なんじ)は独り之の??(リュウリュウ)たるを聞かざるか。山林の畏隹(ワイサイ)たる、大木百囲の竅穴(キョウケツ)は、鼻の似(ごと)きもの、口の似(ごと)きもの、耳の似(ごと)きもの、枅(ますがた)の似(ごと)きもの、圈(さかずき)の似(ごと)きもの、臼の似(ごと)きもの、?(ア・ふかきくぼみ)の似(ごと)きもの、汚(オ・ひろきくぼみ)の似(ごと)きものあり。激(しぶき)の者(おと)あり、?(さけ)ぶ者(おと)あり、叱(しか)る者(おと)あり、吸う者(おと)あり、叫ぶ者(おと)あり、?(なきさけ)ぶ者(おと)あり、?(くぐも)れる者(おと)あり、咬(か)む者(おと)あり。前なる者は于(ウ・ふうっ)と唱え、而して隨(したがう・あとなる)者は?(ギョウ・ごうっ)と唱う。?風(レイフウ)は則ち小和し、飄風(ヒョウフウ)は則ち大和す。風(レイフウ)済(や)めば則ち衆竅(シュウキョウ)も虚と為(な)る。而(なんじ)独り之(こ)の調調(チョウチョウ)たると之の??(チョウチョウ)たるを見ざるかと。
子游が言った、「ぜひともそのことについてお教えください」と。
子?は答えて言った、「そもそも大地のあくびで吐き出された息、それを風という。この風は、吹き起こらなければそれまでだが、一たび吹き起これば、すべての穴という穴が激しく音をたてはじめる。お前は、その音を聞いたことがないか。山の木立がざわめき揺れて、百囲(かか)えもある大木の穴は、鼻の穴のような、口のような、耳の穴のような、枅(ますがた)のような、杯(さかずき)のような、臼(うす)のような、深く狭い窪地(くぼち)のような、広い窪地のような形のものに風が吹きあたれば、水のいわばしる音、高々とさけぶ音、するどい声で叱りつけるような音、吸い込むような音、金切り声で叫ぶような音、泣きさけぶような音、こもった音、咬(とおぼえ)する音がして、前のものが于(ううっ)とうなると、後のものは?(ごうっ)とこたえる。そよ風のときには小さく和(こた)え、つむじ風が舞いあがるときには大きく和(こた)える。そして大風一過して天地がもとの清寂に帰ると、もろもろの穴はひっそりと静まりかえる。お前はあの、風の中の樹々が、ざわざわ、ゆらゆらと揺れ動くさまを見たことがないか」と。
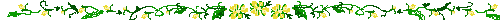
※大塊(タイカイ)
大地
※噫気(アイキ)
(1)はく息。
「夫大塊噫気、其名為風=それ大塊の噫気は、其の名を風と為す」
(2)胃にたまったガスが口から出るもの。げっぷ。おくび。《同義語》?気。
※噫
■音
【ピンイン】[ai4]
【漢音】アイ 【呉音】エ
【訓読み】ああ、おくび
■解字
会意兼形声。意は、「音(口をふさぐ)+心」の会意文字で、黙って心の中におさめたため、胸がつかえることを示す。憶の原字。
噫は「口+音符意」で、胸がつまって出る嘆声。
■意味
胸がつかえて出るげっぷ。《類義語》⇒?(アイ)。
※枅
■音
【ピンイン】[ji1]
【漢音】ケイ 【呉音】ケン
【訓読み】ますがた
■意味
ますがた。柱の上に置き、棟を支える角材。
※?
■音
【ピンイン】[liao2]
【漢音】リュウ 【呉音】ル
■解字
会意。「羽+(?-羽・まじる)」。離れる、もつれるの両方の意味をあらわす。
■意味
(1)鳥がつきつ離れつして高い空を飛ぶ。
(2)「??(リュウリュウ)」とは、風が物の間を吹きぬけるさま。
「独不聞之??乎=独りこれが??たるを聞かざるか」
※畏隹(ワイサイ)
木立のざわめき揺れる有様(郭象)
◆「即畏隹、猶隹巍」(荘子集解)
◆山陵の畏佳(イシ)たる・・・
畏佳(イシ)と読んで、「山の尾根がうねうねとめぐっているところ」(金谷治)
「畏佳(イシ)は山の高低ありて槃回(めぐ)るさま」(司馬氏)
※激(ゲキ)
【ピンイン】[ji1]
■解字
会意兼形声。右側は「白+放」の会意文字で、水が当たって白いしぶきを放つこと。
激はそれを音符とし、水印を加えてその原義を明示したもの。
■意味
(1)はげしい(はげし)。水が岩に当たってくだけるほど勢いが強いさま。
(2)はやい(はやし)。しぶきを飛ばすほどはやいさま。
◆「宣云。激、如水激聲。?如箭去聲。叱出而聲粗。吸入而聲細。叫高而聲揚。?下而聲濁。?深而聲留。咬鳴而聲清。皆状竅聲」(荘子集解)
※?(コウ)
【ピンイン】[xue4]
さけぶ。大声でさけぶ。
※叱
■音
【ピンイン】[chi4]
【漢音】シツ 【呉音】シチ
■解字
会意。七は切の原字で、鋭い刃でさっと切ること。叱は「口(くち)+七」で、しっと鋭くどなる意。
■意味
しっと鋭い声でしかりつける。
※叫
■音
【ピンイン】[jiao4]
【呉音・漢音】キョウ
【訓読み】さけぶ、さけび、よぶ
■解字
会意兼形声。右側は、糾(キュウ)の原字で、なわをよじりあわせたさまを描いた象形文字。
叫はそれを音符とし、口を加えた字で、金切り声(しぼり声)でさけぶこと。
■意味
さけぶ。さけび。のどを絞めてかん高い声でさけぶ。また、さけび。
※?
■音
【ピンイン】[hao2]
【漢音】コウ 【呉音】ゴウ
【訓読み】さけぶ
■解字
会意兼形声。「言+(音符)豪(ゴウ・大きい)」。
※?
■音
【ピンイン】[yao3]
【呉音・漢音】ヨウ
■解字
会意兼形声。「宀+(音符)夭(ヨウ)」。夭は細くかすかで、よく見えない意を含む。
■意味
(1)暗くてみえにくい、家の東南のすみ。また、一説に、東北のすみ。
「鶉生於?=鶉?に生ず」〔徐無鬼篇〕
(2)音のこもったさま。音が、かすかに響くさま。
「?者=?なる者」〔斉物論篇〕
※咬
■音
【ピンイン】[jiao3 / yao3]
【漢音】コウ 【呉音】キョウ
■解字
会意兼形声。「口+音符交(交差させる)」で、上下のあごや歯を交差させてぐっとかみしめること。
■意味
かむ。あご、または歯をかみあわせる。
※于
■音
【ピンイン】[yu2]
【呉音・漢音】ウ
■解字
指事。息がのどにつかえてわあ、ああと漏れ出るさまを示す。直進せずに曲がるの意を含む。
■意味
ああ。わあ、ああという嘆息の声をあらわすことば。
※?
■音
【ピンイン】[yong2]
【漢音】ギョウ 【呉音】グ、グウ
【訓読み】あぎとう
■解字
形声。「口+(音符)禺(グウ)」。
■意味
(1)あぎとう(あぎとふ)。魚が口を水面に出してぱくぱくと呼吸する。
(2)呼びあう声。
「前者唱于、而随者唱?=前者は于と唱へ、随者は?と唱ふ」
(3)「??(ギョウギョウ)」とは、人が仰ぎ慕うさま。また、魚が水面で呼吸するさま。
「??魚闖萍=??として魚は萍を闖ふ」〔韓愈・南山詩〕
※?風(レイフウ)
さわやかなそよ風。
「?風則小和=?風は則ち小和す」
◆「李云、?、小風也。爾雅、回風為飄。」(荘子集解)
※飄風(ヒョウフウ)
「飄」は、つむじかぜ。舞いあがる旋風。
◆「李云、?、小風也。爾雅、回風為飄。」(荘子集解)
※風(レイフウ)
(1)はげしい風。烈風。〔荘子・斉物論〕
(2)西北の風。〔呂氏春秋・有始〕
※?
■音
【ピンイン】[diao1]
【呉音・漢音】チョウ
■解字
象形。舌の揺れる鈴を描いたもの。
吊(チョウ・ぶらぶらたれさがって揺れる)と同系。
■意味
(1)ぶらぶらと舌の揺れる鈴。
(2)動揺して定まらない意から、ずるがしこい。「外頑(チョウガン・ずるいわからず屋)」
◆「郭云、調調、??、皆動揺貌」(荘子集解)










