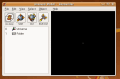ご訪問ありがとうございます。
Linux 用 BASIC (コンパイラ)言語はないものか?・・・・・
ありました。「FreeBASIC」ですね。
これは、頂きましょう!?!
「downloads」のページ

から、「Linux」用、「Windows」用、両方ダウンロードしました。
ふと、思い出しました。
以前にダウンロードしていなかったっけ?
使ったような気がする?
マイブログを検索してみました。
右上にある検索窓を使って、「このブログ内で」で検索。

見つかりました。
2008年07月03日 付「PIC(13)GCBC」で書いていましたね。

フリーの「Great Cow BASIC」も面白いと思って使ってみたが、
いろいろバグがあった。
「Great Cow BASIC」コンパイラは、実は、
Windows版「FreeBASIC」コンパイラで開発されていた。
そこで、「FreeBASIC」コンパイラを使って、
「Great Cow BASIC」コンパイラのバグを直した。

当時は、「FreeBASIC-v0.18.3b-win32.exe」とVer0.18.3b でした。
今回ダウンロードしたのは、「FreeBASIC-v0.20.0b-win32.exe」です。
2年近くが過ぎている。
もう一度、「FreeBASIC」の言語仕様を勉強しよう。
そして、Linux(Ubuntu)で使えるように!
と云うことで、頑張ります。
見ていただきありがとうございました。
お帰りに投票して頂けると嬉しいです。 ⇒
人気BlogRanking ⇒
P-NETBANKING ⇒
Linux 用 BASIC (コンパイラ)言語はないものか?・・・・・
ありました。「FreeBASIC」ですね。
これは、頂きましょう!?!
「downloads」のページ

から、「Linux」用、「Windows」用、両方ダウンロードしました。
ふと、思い出しました。
以前にダウンロードしていなかったっけ?
使ったような気がする?
マイブログを検索してみました。
右上にある検索窓を使って、「このブログ内で」で検索。

見つかりました。
2008年07月03日 付「PIC(13)GCBC」で書いていましたね。

フリーの「Great Cow BASIC」も面白いと思って使ってみたが、
いろいろバグがあった。
「Great Cow BASIC」コンパイラは、実は、
Windows版「FreeBASIC」コンパイラで開発されていた。
そこで、「FreeBASIC」コンパイラを使って、
「Great Cow BASIC」コンパイラのバグを直した。

当時は、「FreeBASIC-v0.18.3b-win32.exe」とVer0.18.3b でした。
今回ダウンロードしたのは、「FreeBASIC-v0.20.0b-win32.exe」です。
2年近くが過ぎている。
もう一度、「FreeBASIC」の言語仕様を勉強しよう。
そして、Linux(Ubuntu)で使えるように!
と云うことで、頑張ります。

見ていただきありがとうございました。
お帰りに投票して頂けると嬉しいです。 ⇒

人気BlogRanking ⇒

P-NETBANKING ⇒