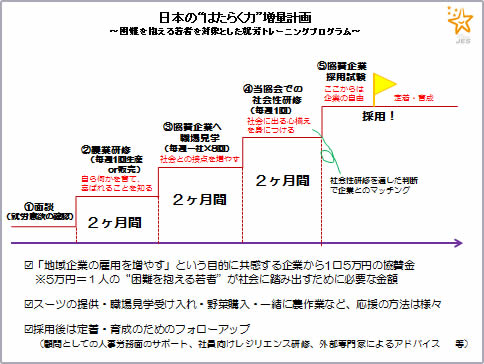今月の「もうけを生み出すビジネスモデルの作り方」セミナーに引き続き、
来月は、CSRビジネスマガジンで定評のある、オルタナさん主催のセミナーで
「ソーシャルインパクトを実現する組織・チームの作り方」のテーマをいただき講演です。

今回は、CSRのビジネスモデル設計とそれを動かしていく組織運営についてです。
前回の、ビジネスモデルの話は、お金を回す仕組についてのテーマでしたが、
今回は、CSRを念頭に置いて、価値を共創するためのビジネスモデルの作り方を解説していきます。
そのカギは、つながりです。今までの企業を評価する経営資源は、人、金、モノそして情報でした。
しかし、これからは、それに付け加えられて、「つながり」そのものが大切な経営資源になる時代です。

そんなつながりを生み出していくためには、個人は、そして組織はどうあるべきなのでしょうか?
他人事を自分事に変え、みんなごとに変える力が必要なのです。これからの時代活躍する人は、
そんな力をもった人、そして地域の課題解決のために、地域のハブとなれる組織なのです。
これからの時代は、地域の困りごとをビジネスチャンスにできる企業が伸びていく時代です。

世の中が困っていることに手を差し伸べること、それがビジネスの基本です。
本来のビジネスのありかたへと社会が気付きだしてきた時代と言えるのです。
大義なき経営は滅びる!そんな、時代なのです。
今回も、前回に引き続きそんな志の大きい人たちに出会い、私たち自身が
新たなつながりができるのを楽しみに、一生懸命講演に臨みたいとおもいます。
来月は、CSRビジネスマガジンで定評のある、オルタナさん主催のセミナーで
「ソーシャルインパクトを実現する組織・チームの作り方」のテーマをいただき講演です。

今回は、CSRのビジネスモデル設計とそれを動かしていく組織運営についてです。
前回の、ビジネスモデルの話は、お金を回す仕組についてのテーマでしたが、
今回は、CSRを念頭に置いて、価値を共創するためのビジネスモデルの作り方を解説していきます。
そのカギは、つながりです。今までの企業を評価する経営資源は、人、金、モノそして情報でした。
しかし、これからは、それに付け加えられて、「つながり」そのものが大切な経営資源になる時代です。

そんなつながりを生み出していくためには、個人は、そして組織はどうあるべきなのでしょうか?
他人事を自分事に変え、みんなごとに変える力が必要なのです。これからの時代活躍する人は、
そんな力をもった人、そして地域の課題解決のために、地域のハブとなれる組織なのです。
これからの時代は、地域の困りごとをビジネスチャンスにできる企業が伸びていく時代です。

世の中が困っていることに手を差し伸べること、それがビジネスの基本です。
本来のビジネスのありかたへと社会が気付きだしてきた時代と言えるのです。
大義なき経営は滅びる!そんな、時代なのです。
今回も、前回に引き続きそんな志の大きい人たちに出会い、私たち自身が
新たなつながりができるのを楽しみに、一生懸命講演に臨みたいとおもいます。