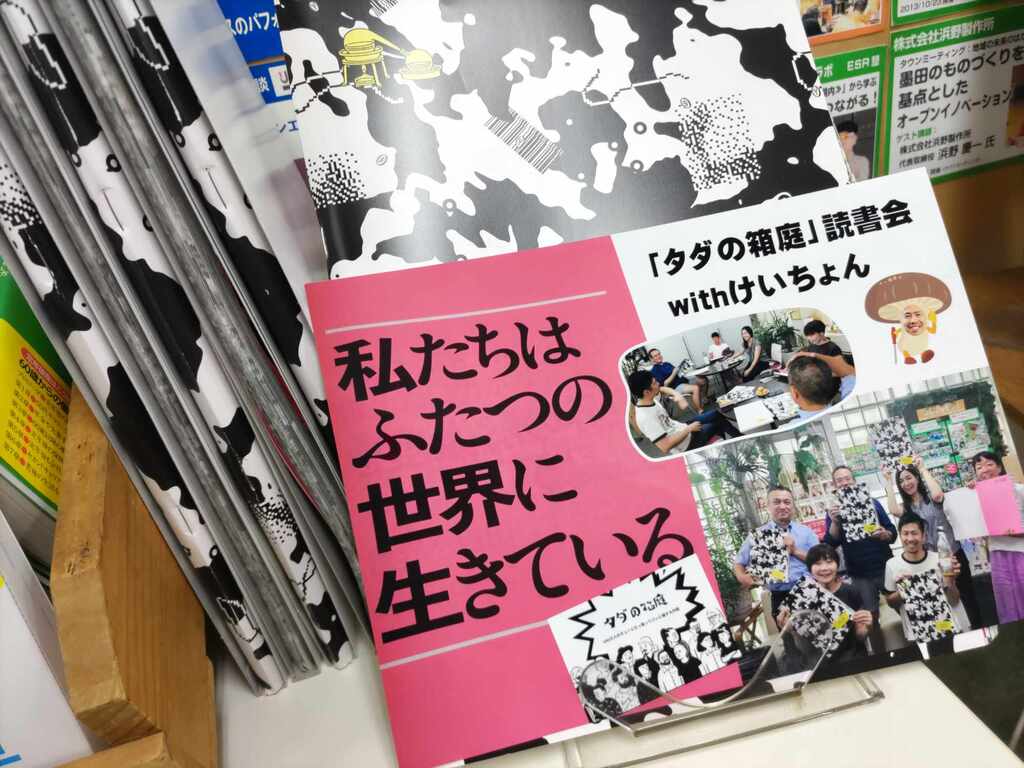皆さん、こんにちは!
今日は、日光街道沿いの「進修館」で開催された「あおぞら図書館えいが会」に参加してきました。今回のテーマは「未来のはたらくを考える」。映画を観ながら、対話を通じて、これからの働き方や自分自身のキャリアについて考える、とても充実した一日でした。

風情ある宿場町で感じた特別な時間
会場となったのは、趣のある宿場町に位置する「進修館」。歴史を感じるこの場所で、未来について考えるという、まさに「過去と未来が交わる場」での開催でした。風情ある建物に入った瞬間から、非日常感が漂い、心がリフレッシュされていくのを感じました。
映画『一葉の桐』が教えてくれた、伝統と未来
イベントのメインは、短編映画『一葉の桐』の上映でした。26分の短編ながら、春日部の桐箪笥に出会った若者が、その伝統に魅了され、奮闘する姿が描かれていました。
若者が伝統工芸の世界に飛び込むその過程は、現代の働き方における「伝統と革新」の対立を乗り越えるヒントを与えてくれました。映画を観ながら、自分自身の働き方と重ね合わせ、深く考えることができました。

飯島勤さんとのトークセッション
映画鑑賞後は、桐箪笥職人の飯島勤さんを迎えてのトークセッションが行われました。飯島さんは伝統工芸を守りながら、現代に適応した新しいビジネスモデルを築いています。飯島さんの話を聞いて感じたのは、変化を恐れずに未来に向けて進む姿勢でした。
お話の中で仰られていた仕事を継続するコツについて、「仕事をして、対価をもらって生活するが、他人に感謝され、人にありがとうと言われるような言葉があれば長続きすると思う」という言葉は、「仕事」というものに向き合っていく中で、「楽しく働く」という面において、強く印象に残っています。
また、業界全体としての課題感に関しても触れられており、後継者不足の課題を解決するために、箪笥の技法を用いた商品(傘立て等)により、若年層への認知を広げる取り組みを行われるなど、精力的に動かれているとのことでした。

まとめ:未来の「はたらく」に向けての気づき
今回の「あおぞら図書館えいが会」は、単なる映画鑑賞ではなく、自分の働き方やこれからのキャリアについて深く考える機会となりました。映画『一葉の桐』で描かれた若者の挑戦、飯島さんの伝統と革新を繋ぐ姿勢等を通じて、私自身もこれからの働き方を再定義する大切なヒントを得ることができました。

今回の飯島さんとのトークセッションの模様は、ラジオ「ここ掘れワンワンスタジオ」で放送致します。
ぜひこちらをご覧ください。