
人もまばらになったケネディスクール。今日締め切りだったFinal Paperを提出し終えて、怒涛のようだった秋学期の終わりにほっと一息。しかし、同時にこれでケネディスクール生活の4分の3が終わってしまったことを考えると、何やら早くも寂しさを覚えてしまいます。
ふと思い立って教室の扉を開けてみる。つい最近まで熱気あふれる議論が繰り広げられていたのが嘘のように静まり返る教室。普段ぎっしりと学生が詰まっているからか手狭に感じるL140教室も、こうしてたった独りで座って見ると意外に広いことに改めて気付かされます。
* * *
9月上旬に授業が始まってから、いや正確には8月下旬にクラス・アドバイザーの仕事が始まって以来、ひたすら全力で走ってきました。
基本的にいつも走っている、否、走っていないと落ち着かないという性格の自分ではありますが(ちなみにスポーツ・ジムで走るのも大好きです!)、この3か月の走りは格別でした。
というのも、自分が進んだ距離、そして駆けだす前の自分と今の自分とにポジティブな変化を確かに見ることができるという、「走ってきたという実感」をひしひしと感じることができるからです。
昨年のこの時期に綴った記事「秋学期の終わりに思うこと」を改めて読んでみると、去年の冴えない状況が蘇ってきます。初めての海外生活のスタートでもあった去年の秋学期の状態は、まるでハムスターがコロコロ回るタイヤの中で、一生懸命走っている、でも一歩も前に進んでいない・・・、そんな感じでありました。
当時は、走っても走っても前に進まず、この素晴らしい環境を思うように活用できない自分に対する焦りとフラストレーションに苛まれていましたが、今にして思うと、あの時期それでも走り続けたことが、この一年、特に夏以降のジャンプに繋がったのではないか、こう思うことができます。
* * *
今学期はブログでも度々紹介してきたLeadership、Public Private Partnership、そして修士論文であるPAE(Policy Analysis Exercise)に加え、以下の2科目をケネディスクールで履修していました。
一つは世界各国の住民参加型の政策決定のケースを通じて参加型民主主義のあり方について理解を深めるInnovations in Democratic Governance(民主主義的ガバナスの革新)。もう一つは国際経済学と金融論の基本的理論の上に立って現在の国際経済情勢について議論するInternational Captital Market(国際資本市場)。
以上5科目の授業に加え、新入生の世話役であるClass Advisorの一員としての仕事とJapan Caucus(ケネディスクールの日本人会)代表としての役割があり、さらにエズラ・ボーゲル先生の下で学ぶHarvard松下村塾で、グループで取り組んでいる「アジア経済統合に向けた展望」についての勉強会の取りまとめ役・・・と書いているだけで、まぁよくやったなぁ、という感じです(お蔭でブログの更新頻度は大分落ちてしまいましたが・・・)。
一見無秩序に見えるこれらの課題も、夏の終わりに当たって立てた3つの課題に向かって走る上で、どれも不可欠なものでありました。
一つは、自分のキャリア・プランでもあり実現したい価値でもある、官民協働(Public Private Partnership)を軸にした、現在の日本の政策の作り方の変革。これまで自分の頭のなかで、あるいは官民協働ネットワーク・Crossover21の活動を通じて、どうしても理念ばかりが先行していた官民協働というコンセプトを、世界中の様々なケースを学ぶことで、そして最後にそれを修士論文という形でまとめることで、理念を実現する上で必要な具体的なスキルと道筋を明らかにしていきたい。
この目標にダイレクトに貢献するのが、Public Private Partnership、参加型民主主義、そしてCommon Impactをクライアントに取り組んでいるPAE(修士論文)という訳です。
二つ目は国際経済の視点から日本をグローバルに見つめ直すという目標。一つ目の課題がどうしてもローカル・ミクロな視点になりがちであることを考えると、またマクロ経済政策を主要業務とする職場にスムーズに“復帰”するために、これは是非取り組んでおきたい課題です。そしてこの課題に相乗効果を発揮しながら貢献するのが、International Capital Marketの授業を通じた理論のおさらいと現在の国際経済・金融情勢へのキャッチ・アップ、そしてさらに大所高所の視点から、Harvard松下村塾で「アジア経済統合に向けた展望」をテーマにレポートを取りまとめていく作業なのです。
三つ目の目標は、ケネディスクールに自ら価値を提供するとともに、授業で得た気付きを行動に移すべく、リーダーシップを発揮して物事を実現すること。この課題に資するのは言うまでもなく、ハイフェッツ教授のLeadershipの授業、Japan Caucusの代表、そしてClass Advisorとしての役割です。
* * *
昨年の秋学期は、毎回の授業で1回発言するのがやっとでしたが、今期は発言の回数だけではなく、議論の流れを抑えた上で新しい視点を提供したり、議論の方向性自体に問題提起をするなど、質の面でも貢献度を増すことができた実感があります。
この点、「英語は引き続き厳しいけれど、自分の“満足水準”を下げることで、秋学期終了時に支配的だった焦りから解放された」という総括だった一年目終了時の5月と比較しても大きなジャンプを果たすことができ、それに最も大きく貢献したのが、やはり夏のインド・ケニアでのインターン・シップ経験だったと思います。
また、飲み会に参加するのがやっと、しかも英語の聞き取りにくさも手伝って殆ど楽しめなかった昨年の秋と比較すると、飲み会やイベントを企画し、皆を楽しませる立場になっている自分へと進化していることに気付かされます。
これに関しても、春学期の終了時の反省であった「自分がJapan Caucusの一メンバーとしてではなく、個人としてケネディスクールに付加価値をもたらすことが、残念ながら殆どできなかった」点を克服できたのではないか、と感じています。
そして何よりも大きな変化は、秋学期が終わってもまだまだ気力が満ち満ちていて、同時にやるべきこと、やりたいことが満載であること。
明日もPAE(修士論文)のクライアントであるCommon Impactへの進捗状況報告のプレゼンテーションが控えており、レポート提出直後から、そちらの準備を加速させています。
これから始まる冬休みの間は、毎週1回クライアントへの進捗状況報告を兼ねたプレゼンテーションとディスカッションがあり、さらに1月7日から18日までの2週間は朝から晩まで大学に缶詰になって戦う冬季集中講座に参加予定。
夏休みはインド、ケニア、そしてアメリカ西海岸を飛び回り、様々な人々と出会い協働する時間でしたが、この冬はじっくり腰を据えて本や文献を読み、物を書く時間となりそうです。
滞り気味だったブログの更新も頻度を上げていきますので、どうぞお楽しみに!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆ 『人気Blogランキング』に参加しています。「ケネディスクールからのメッセージ」をこれからも読みたい、と感じられた方は1クリックの応援をお願いします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆













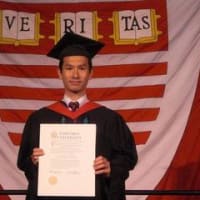






その付加価値の高いサービスについて、楽しみにしております。
また、奇をてらった感のある教授のリーダーシップ論も、まだそれだけでは終わらないだろうと期待をする一面もあります。
本年はblogではお世話になりました。
来年は何かのイベントでお目にかかれれば幸いです。
また来年もよろしくお願いいたします。
Common Impactのサービスとアメリカを初めとする各国のNPO,CSR、そして政府の関わりは冬休みを利用して取り組んでいる卒論のテーマなので、今後も綴っていこうと思っています。ハイフェッツのリーダーシップは、これは中々文章にするのがしんどいのですが、自分の学びを深める意味でも引き続き取り組んでいこうと思っています。
こちらこそ新年もよろしくお願いいたします。6月に帰国した折にお会いできるのを楽しみにしております。