
昨日に引き続き、日本をケースにしたComparative Politics(比較政治)について、今日は、実際の授業の様子を紹介したいと思います。
Culpepper教授からは以下の二つの問題提起がありました。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
① 日本の民主主義は、Corporatism(協調主義)といえるのか?
② 小泉前首相は、なぜ強力なリーダーシップを発揮しえたのか?
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
アメリカでは、多くの利益団体がロビイストを雇い、自分たちが“得をする”政策の実現を目指して政治家に活発に働きかけを行います。そうした多様なプレイヤーによる「インフォーマルな競争」を通じて政策作られるアメリカ型の民主主義を「Pluralism(多元主義)」と呼ぶのだそうです。
一方で、①で問われている「Coporatism」は「Pluralism」に対峙される概念で、オーストリアが典型例として挙げられます。具体的には、労働組合や商工会議所のような経済団体が、フォーマルに政策決定プロセスに加わり、政府との話し合いを通じて、大きな意思決定がなされます。話し合いに加わった各団体は、責任を持って政策の実施に協力することが求められ、全体的に、リーダーシップよりもConsensus(合意)やReciprocity(どちらか一方の利益ではなく、お互いの利益を重視する考え方)が求められる政策の作り方だと言えます。
さぁ、「日本はCoporatism?」と聞かれたら、なんとなく、“コンセンサス”や“お互いの利益”という言葉に惹かれて「うん・・・」と頷きたくなりますが、Culpepper教授によると、この件について、専門家の意見は大きく分かれるのだそうです・・・、とここまでいつもの超高速トークで説明した後、教授は突然、僕を指差し、
「では、それは何故か!まずは、この教室で一人しかいない日本人の君に説明してもらおう。その際、日本の政治システムの特徴として挙げられる"Patron-Client relationship(後見人と顧客の関係)"との関係も念頭に頼む。」
と、授業開始直後にいきなりCold Call(突然の名指し)をしてきました。
「Patron(=与党政治家)とClient(=利益団体)との関係を見ると、利益団体は選挙で政治家を支援する、与党政治家はその見返りとしての補助金などの優遇政策実現に向けて努力する、というReciprocity(お互いの利益)の構造が見られるので、その部分はCoporatism的な特徴が見られます。
一方で、オーストリアとは違い、日本では、そうしたプロセスはフォーマルな政策決定ではありません。また、様々な利益団体同士の関係を見ると、そこにはReciprocityというよりもCompetition(競争)が見られるため、Plurarism的な特徴も持ち合わせたシステムだといえると思います。」
と説明すると、教授は大きくうなずいて、「うまく整理されている」とコメントしてくれましたが、果たして他のクラスメートは、みな腑に落ちないような、よく分からない・・・という顔。
次に教授は、「では、何故Koizumiは日本社会のそうした風土のなかで、強いリーダーシップを発揮できたのか、まずは、日本人以外のクラスの皆から意見を聞こう!」と切り出しましたが、珍しく教室はシーンと静まり返ったまま。。。ようやく、奥さんが中国人で、アジア情勢に興味を持っているアメリカ人の友人から、
「Koizumiはこれまでの日本の首相と比べて、有権者からの支持率が圧倒的に高かったため、しがらみにとらわれず、比較的自由に自分の約束した政策を実現できたのではないか」
とあったため、教授は「重要な指摘だ。日本で最もControversial(論争的)なテーマだった、Japan Postの民営化に関する意思決定は、Koizumiへの強い支持が圧倒的な選挙結果として現れたことを背景になされた。」とコメントし、「では、他にどうだ!」と畳み掛けましたが、相変わらず教室は静まり返ったまま・・・まるでいつもと様子が違います。
教授も仕方なく、「では、君のほうから、何か追加でコメントはあるかい?」と再び唯一の日本人である僕に水を向けたので、小泉総理のパーソナリティに加え、1994年に実施された中選挙区制から小選挙区比例代表並立制への選挙制度改革により、自民党の中で派閥の力が弱まったことや、2001年の中央省庁再編により内閣府が新設され、また、内閣官房の機能が強化されたことにより、総理の権限やスタッフが充実したこと、といった制度的な要因を説明しました。
結局、日本のケーススタディでは、僕ばかり5分以上しゃべり続けることになってしまったのですが、このクラスで、こんなに議論が“盛り上がらなかった”のは最初で最後でした・・・
授業が終わった後、アフリカでNGO関係の仕事に5年間携わっていたアメリカ人の友人と食事をしたのですが、その時の会話は、教室の「沈黙」の理由を知るに十分なものでした。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
彼: 「正直、日本の政治って、よく分からないよね。Koizumiが大統領ってことくらいしか知らないなぁ。」
筆者:「イヤイヤ、小泉さんは「大統領」じゃなくて、「首相」だよ。それに、最近引退して今は「Shinzo Abe」っていう比較的若い人が首相になったんだ。」
彼: 「そうなの!知らなかった。じゃあ、Koizumiは今は何をしているんだい?」
筆者:「普通の国会議員に戻ったのさ。」
彼:「???国会議員に戻る・・・あぁ、そうか、日本では首相は国会議員の中から選ばれるんだったね。イギリスと同じか・・・」
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
要するに、総じて、日本の政治に対する知識も興味も薄いというのが現実だと思います。アメリカで最も政治色が強い大学院といわれるケネディスクールの学生ですらこの状況な訳ですから、アメリカ全体、あるいは世界の一般の人々にとっては、日本の政治って本当に興味の対象になっていないんだなぁ、ということを改めて思い知らされてしまいました。
もっとも、小泉前首相の知名度は抜群です。しかし、その理由は、「面白い髪形をしている」、「Yasukuni(靖国神社)を何度も訪問して中国と韓国を怒らせてる」、「パフォーマンスがうまい」といったところで、政策の中身にまで言及する人は、韓国人や中国人、マレーシア人の友人くらいです。
街中を歩けば、そこらじゅうにTOYOTAやHONDAのロゴマークのついた自動車。電気屋に入れば所狭しと並べられる日本の電気製品・・・日々、なんとなく誇らしい気分にさせてくれる日本製品の数々、こうした中にあって、この授業を終えたときの空しさはいったい・・・
「経済一流、政治は三流」というフレーズの持つ意味が、今更ながら実感させられたケーススタディとなってしまいました。













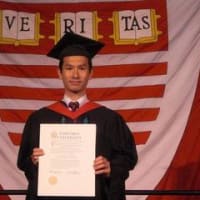






一方で、日本の大学院生が外国の内政についてどれだけ知っているかというと、これまた「?」でしょう。
そんなものじゃないですかね。
ただ、知りもしないのに「○国の政治は…」などと安易に訳知り顔で語る危険性を、せめて認識しておくことだと思いますが。
ご指摘のとおり、自分も含め、日本人学生が諸外国の政治制度について「知識」があるかというと疑問ですし、自分の生半可な知識を一般化して人に語ることほど、危険な、しかし陥りやすい失敗はないですよね。
ただ、前者について、僕の言葉がやや足りなかったのですが、今回のテーマの中で強調したかったのは、「Comparative Politics」で一緒だった同級生たちの、日本政治に対する「知識」の少なさではなく、「関心」の薄さです。
ご指摘のとおり「知識」が少ないのは、ある意味でお互い様であり、だからこそケネディスクールで学んでいるのですが、僕はこの2ヶ月間を通じて、ケネディスクールの学生達は知識欲が極めて旺盛で、未知の分野であってもリーディング等を通じて知識の習得に努め、「稚拙だ」と思われることを恐れることなく、積極的に仮説を展開し、分からないことは何でも質問できる「勇気」と、他人の意見にしっかりと耳を傾けることのできる「謙虚さ」を持って、授業に臨み、自らの限られた知識を最大限深めるために努力をしていると感じています。
また、satsukiさんもご存知のとおり、日本の大学院生と異なり、ケネディスクールの学生は、ビジネスマン、行政官、NGO職員など、それぞれの分野で平均で5年くらいプロとしてのキャリアを持っており、比較政治のクラスでも外交官出身の友人も数人います。
こうした学生の持つ特徴によってか、あるテーマで議論で紛糾することはあっても、教授の質問や問題提起に対して、教室中が「沈黙」で支配されてしまうということは、少なくともこの2ヶ月間の僕の経験ではこの授業に限らず、他のどの授業でも(合計5つ授業をとっていますが)、この時が最初で最後でした。
特にこれまで比較政治の授業では、クラスメートから活発に出される持論や仮説、質問に対し、ケースとして取り上げられた国から来ている学生と教授が、経験や知識を持って応じるという流れができていたため、僕自身、今回の授業に臨むに当たり、色々準備してきたこともあり、「失望感」が殊更強かったのかもしれません。
ハーバードビジネススクールに通っている友人の話では、TOYOTAなど、日本企業がケースとして取り上げられることは多く、そのときの議論は相当活発なものとなるようです。こうした話を聞いていたこともあり、日本の経済分野におけるプレゼンスと、それに対応した諸外国の人々の関心の高さ(知識の高さでは必ずしもない)に比して、政治分野のプレゼンスが低いことを感じさせられたできことだったというわけです。
長くなってしまってごめんなさい。これからもよろしくお願いします。お仕事頑張って下さい。
失礼しました。