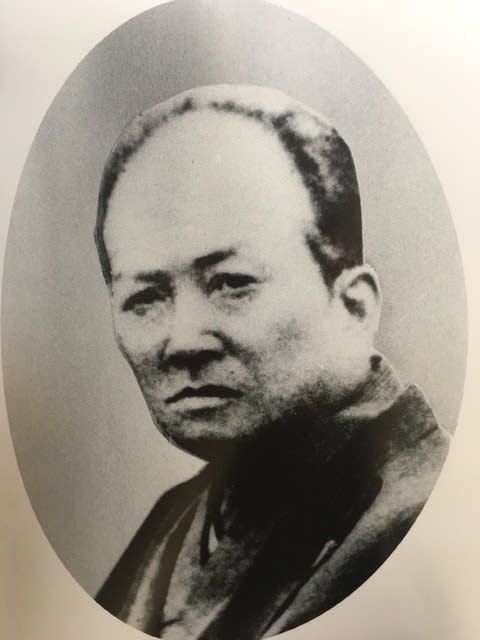スポーツ新聞を読んでいると「原田龍二、自宅で怪奇現象続々!」という記事が目に留まりました。
TV「世界の何だコレ、ミステリー」で座敷わらし調査始めてから、頻繁に不思議な現象が起こるとのこと。
近年の人々が妖怪や怪異への関心は異常に強くなっています!
このミステリーチェイサー原田龍二さんが探索する妖怪・座敷わらしシリーズもTVの人気コーナーです。
そんなご時世ですが、私の地元亀岡と西京区の境に位置する大枝山の頂上には、
つい先日まで日本妖怪研究の第一人者・小松和彦先生が大将を務めた
国際日本文化研究センターがあるのも何かの因縁でしょうか?
そう、この大枝山の老ノ坂峠には、昼でも不気味な霊気が漂う「首塚大明神」が祀られています。
ここに祀られているのが、日本三大妖怪と呼ばれる「酒呑童子」です。
平安時代に丹波大枝山を棲み家としていた伝わる酒呑童子。
夜な夜な都に現れては金銀財宝を強奪し、婦女子をかどわかすなどの
悪行三昧で、当時の都人を恐怖に陥れていました。
そこで武勇に長けた源頼光率いる四天王に酒呑童子討伐の命が天皇から発せられ、
源頼光らは大江山千丈ヶ嶽に攻め上り、苦心の末、酒呑童子とその一派を征伐しましたとさ。
平安の世の都人は日本海に繋がる西の方角に対して、神経質なほど恐れを抱いていたといわれてます。
妖怪伝説も多く伝承されているのです。そういえば保津川の流れも西から都へ注がれていますね。
「最先端の技術や情報も、邪悪なものも、西から訪れる~」
今度は原田龍二さんと一緒に、京都や丹波の妖怪ミステリーを探訪する企画をしたい~
これまで見えなかった‘何か’が見えるてきたりして・・・
TV「世界の何だコレ、ミステリー」で座敷わらし調査始めてから、頻繁に不思議な現象が起こるとのこと。
近年の人々が妖怪や怪異への関心は異常に強くなっています!
このミステリーチェイサー原田龍二さんが探索する妖怪・座敷わらしシリーズもTVの人気コーナーです。
そんなご時世ですが、私の地元亀岡と西京区の境に位置する大枝山の頂上には、
つい先日まで日本妖怪研究の第一人者・小松和彦先生が大将を務めた
国際日本文化研究センターがあるのも何かの因縁でしょうか?
そう、この大枝山の老ノ坂峠には、昼でも不気味な霊気が漂う「首塚大明神」が祀られています。
ここに祀られているのが、日本三大妖怪と呼ばれる「酒呑童子」です。
平安時代に丹波大枝山を棲み家としていた伝わる酒呑童子。
夜な夜な都に現れては金銀財宝を強奪し、婦女子をかどわかすなどの
悪行三昧で、当時の都人を恐怖に陥れていました。
そこで武勇に長けた源頼光率いる四天王に酒呑童子討伐の命が天皇から発せられ、
源頼光らは大江山千丈ヶ嶽に攻め上り、苦心の末、酒呑童子とその一派を征伐しましたとさ。
平安の世の都人は日本海に繋がる西の方角に対して、神経質なほど恐れを抱いていたといわれてます。
妖怪伝説も多く伝承されているのです。そういえば保津川の流れも西から都へ注がれていますね。
「最先端の技術や情報も、邪悪なものも、西から訪れる~」
今度は原田龍二さんと一緒に、京都や丹波の妖怪ミステリーを探訪する企画をしたい~
これまで見えなかった‘何か’が見えるてきたりして・・・