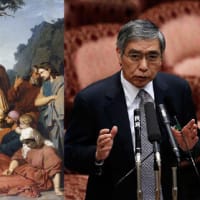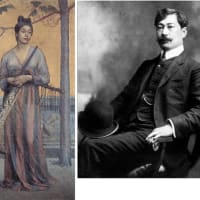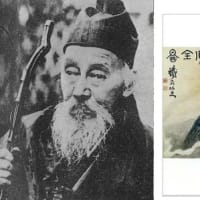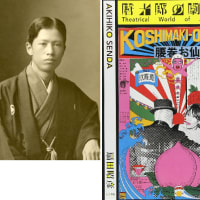A.老獪な偽善者
「文豪」という言葉があるが、いわゆる明治以降の小説家の中で、誰もが知っている人気・実力ともに傑出した作家を指す、と一般に考えられる。しかし、ちゃんとした定義はないだろう。少なくとも高い評価を受け後世まで読まれ語られる作品を、ある程度長い期間に書き続けたこと、ということはある程度長生きした人、したがって晩年に著作集がまとめられ、社会的にも名士として名声を高めた人、ということになるだろう。瀧澤馬琴とか井原西鶴や十返舎一九など、江戸時代の文筆家は「文豪」とは呼ばれないし、30代で自殺した芥川龍之介や太宰治も「文豪」にはなじまない。尾崎紅葉や国木田独歩はやはり30代なかばで世を去っているように、明治の人たちはなかなか長生きはできず、良い小説を書いても「文豪」とは呼ばれない。
明治日本の近代小説家で「文豪」と呼ばれる人は幾人かいるが、森鷗外(文久2生~大正11年没)や夏目漱石(慶応3生~大正5没)は、いわゆる「文壇」の主流に君臨したわけではないし、軍医だったり大学の英文学者だったりして、小説を書きはじめたのは中年以降だし、小説でその作風を直に受け継ぐ弟子というのも見当たらない。そう考えると、「文豪」と呼ばれるにふさわしいのは、島崎藤村(明治5生~昭和18年没)と永井荷風(明治12生~昭和34没)、志賀直哉(明治16生~昭和46没)、谷崎潤一郎(明治19生~昭和40没)、川端康成(明治32生~昭和47没)あたりまでかと思われる。戦後の三島由紀夫や大江健三郎も「文豪」になるんじゃないか、という声はあるが、ぼくは個人的に「文豪」という称号は、この橋本治『失われた近代を求めて』が問い直している日本語の言文一致という文体で、小説を確立した明治生まれの世代に奉るもの、という感じなので、戦後の三島や大江は「文豪」たちの成果を別の意味で普及させた「小説家」と呼ぶ方がいいと思う。
もし日本語で書かれた小説が、国民的に愛され大衆に広く影響を与えたという意味ならば、松本清張と司馬遼太郎を「文豪」と呼びたいなら、それはそれでよいと思う。それで、ここは島崎藤村『新生』のお話である。
「前編と後編に分かれる『新生』は、そのどちらもが『春』以上の長さを持つが、この調子で島崎藤村は「我が身を責め続け苦悶し続ける岸本捨吉の胸の内」を書いて、前編が終わった段階でも、捨吉はまだパリで苦悶している。ともかくもう、岸本捨吉は自分自身の胸の内を過去にまで遡って延々と語り続けるのだが、一向に事態収拾のめどはつかない。ただもうひたすらにグルグル回りを続けるのだが、そうなってしまうのも当然で、その苦悩の発端となった「節子との関係」がいつどのように始まったのかが、この小説の中ではまったく触れられていないのだ。
「ある夜、寝静まっている節子の部屋に忍び込んだ」とか、「急にムラムラッと来て、人がいないのをいいことにして節子を押し倒した」とか、「節子に誘うような表情が見えたのでつい――」とか、そういう「始まり」がない。それは、ある時なんらかの形で始まったはずなのだから、「始まり」があってしかるべきなのに、その記述がない。検閲というものが存在する当時だからあけすけに書けないのも分かるが、姪との関係をもつ以前の岸本捨吉のあり方がなにも書かれていないから、その関係がどうして始まったのかは分からない。あってしかるべき「始まり」がないまま、岸本捨吉は苦悩し続けている――「だから、彼が苦悩していることだけは分かるが、「なんでこんなに苦悩をしているんだろう?その苦悩の質は何だろう?」ということが分からない。その初めの「彼の心理」や「状況」が欠落しているから、グルグル回りの苦悩を収束させる方向が見つからない。『破戒』の瀬川丑松が、猪子蓮太郎に自分の出自を打ち明けようとして言えない――「言えない理由」を一生懸命に説明しようとして出来ずに、「言えない、言えない、ただ言えない」になってしまうのと同じで、『春』の岸本捨吉に「放浪の旅に出る前の話」がないのと同じである。島崎藤村の自己分析は、「分析されてしかるべき自分の中枢」を棚上げにしたまま行われる不思議なものだから、延々と続く空回りになってしまうのも仕方がない。
三十六歳で自殺した芥川龍之介は、その遺作『或阿呆の一生』の《四十六 嘘》という項で《彼は『新生』の主人公ほど老獪な偽善者に出会ったことはなかった。》と言っているが、その十年前のまだ新進のスター作家だった頃、前編が刊行され後編の新聞連載が始まったばかりの『新生』に対しては、もう少し違うことを言っている。
《藤村氏が「新生」の第二巻を書いてますね。しかしいくら裸になろうとしても藤村氏は裸になれない人ですね。丸で玉葱みたいな人です。が、それでいて中味みたいな顔をしているのだから妙です。》(『芥川龍之介氏縦横談』)
まことに『新生』の主人公の苦悩はグルグル回りの玉葱の皮剥きみたいで、芥川龍之介が『新生』を嫌いこれを書く島崎藤村をバカにしているのは確かだが、しかしもしかしたら、玉葱の皮剥きをしている島崎藤村の方が一枚上手かもしれない。どうしてかと言えば、玉葱の皮剥きをする藤村は、そこに「皮」ばかりではない「中身」があることを知っているからである。
これは『新生』に書かれない藤村自身の年譜的事実だが、節子の妊娠が発覚する三年前、藤村の妻の園子は産褥で死亡する。煩雑になるのを避けるため、藤村以外の人名は『新生』のそれを流用するが、妻の園子は『春』の勝子と同様、藤村の教え子である。そして、妻を亡くした藤村を助けるために、節子の姉である姪の輝子がやって来て、節子がその後でやって来る。輝子は二年後に結婚して、節子一人が藤村の許に残る。彼女の妊娠が発覚するのが翌大正二年(1913)の正月過ぎだから、輝子がいなくなると間もなく藤村と節子の関係が生まれたのは間違いがないはずだが、その妊娠がある発覚する直前とも言える時期に、藤村は新しい長編小説の筆を執って、一月から雑誌連載を始めている。岸本捨吉を主人公とする二作目の『桜の実の熟する時』である。
『桜の実の熟する時』は、『春』の前段を語る作品で、十代の終りから二十二歳になった藤村が失意の旅に出るところまでが書かれている。もちろん、この連載小説は二回目で中絶されてしまうのだが、その理由は二回目の原稿を読めばなんとなく分かる――。
《それらの目上の人達からまだ子供のように思われて居る間に、彼の内部(なか)に萌やした若い生命(いのち)の芽は早筍のように頭を持ち上げて来た。自分を責めて、責めて、責め抜いた残酷(むご)たらしさ――沈黙を守ろうと思い立つように成った心の悶え――狂(きちがい)じみた真似――同窓の学友にすら話もせずにある其日までの心の戦いを自分の目上の人達が奈何(どう)して知ろう、繁子や玉子のような基督教主義の学校を出た夫人があって青年男女の交際を結んだ時があったなぞとは奈何して知ろうと思って見た。》(『桜の実の熟する時』)
同じ部分が《草稿》として、微妙に違った形で『新生』にも引かれている。なぜ藤村は『桜の実の熟する時』を書こうと思ったのか?藤村の自伝的小説で、そのゴールとなるところが「失意の旅」だから、『桜の実の熟する時』は暗い話である。《若い生命の芽は早筍のように頭を持ち上げて来た》とは、あまりにもストレートに性的である。「師範学校を卒業して後、快活だった瀬川丑松は変わってしまった」という、『破戒』で保留にされていた部分に該当するのが『桜の実の熟する時』である。その小説を、大正二年に至らんとする時、島崎藤村はなぜ書こうとしたのか?
大正二年になる前、藤村の心は《若い生命の芽は早筍のように》云々であるような「過去」へと向っていた。性的飢餓の始まりで女への渇仰の始まりであるような時期をさまよって、節子との関係は(おそらく)そこから生まれた。「妻を亡くした」という前段があって、そこに節子がいたればこそ、藤村の心は現実を離れて、二十年以上前の過去へと飛んで行った。その時に節子は、若い藤村を翻弄した女達と同じ年頃のニ十歳だった。
かくして『桜の実の熟する時』が始められるが、すぐに節子の妊娠が知らされて、四十二歳の島崎藤村は現実へと引き戻される。『桜の実の熟する時』を書く藤村は『新生』的現実の中にいて、姪の節子は「過去の藤村」と「現実の藤村」を一つに結びつける役割を持っている。だから、『新生』という小説は「姪との関係を持ってしまった藤村の苦悩」を書くように見えて、それでは終わらない。「その先の局面」を踏まえて、この作品『新生』は出来上がっているのだ。
フランスへ逃げた藤村は、一年後の大正三年五月から、中絶した『桜の実の熟する時』の連載を再開する。ところがそこに第一次世界大戦が勃発し、通信事情の悪化で、日本に送っていた原稿が行方不明になるというアクシデントが起こり、日本でのこの連載は一年もたたぬ前に中絶されてしまう。藤村はその後もフランスにいて、やっと帰国した大正五年(1916)の更に翌年の十一月になって連載が再開され、大正七年の六月に完結する。
『桜の実の熟する時』が大正六年の十一月に再開され、これが目出度く完結に至る理由は、おそらく明確である。『新生』の後編によれば、大正六年の九月に近い頃には、藤村の中に「姪との関係の一切を告白したい」という衝動が生まれてしまっていたからである。
《彼の言うこと為すこと考えることは過去の行為に束縛せられて、何時でも最後に暗い秘密に行って衝き当った。彼は過去の罪過を償おうが為に苦しんでも、自分の虚偽を取除こうが為には今迄何事も努めなかったことに気がついた。(中略)
「一切を皆の前に白状したら。」
岸本は今まで聞いたことの無い声を自分の耳の底で聞きつけた。》(『新生』後編九十二)
藤村は、自分の頭の中がぐるぐる回りをしていたことに気づいたのだが、どうしてそれが大正六年の九月に近い頃なのかというと、その時期になって藤村が「姪の節子と一緒にいることが幸福だ」ということに気づき、これを認めて揺るぎなくなってしまったからである。右の引用の「中略」の部分には、《暗い秘密を隠そう〽隠そうとしたことは自分のためばかりでなく、一つは節子のためだと考えたのも》云々と書いてある。だからこそ、「皆の前に白状したい一切=最後に衝き当たる暗い秘密」が「節子との関係」と思われもして、実際に藤村もそのように考えるしかないと思っているフシもあるが、藤村の思考を衝き当らせてグルグル回りをさせているものは、そう簡単に一口で言えるようなものではない。「節子との関係がどういうものでありえたのか」を実感することによって生まれ出た幸福感――そいれが藤村の人生に欠落していたということこそが、《暗い秘密》なのだ。
『新生』の初めの方には不思議な記述がある。節子から妊娠を知らされた捨吉が愕然として、どういうわけか、妻と共にあった日のことをやがて思い出す。そこにこう書いてある――。
《長いこと妻を導こう〽とのみ焦心した彼は、その頃に成って、初めて何が園子の心を悦ばせるかを知った。彼は自分の妻も亦、下手に礼儀深く尊敬されるよりは、荒く抱擁されることを願う女の一人であることを知った。
それから岸本の身体は目を覚ますように成って行った。髪も眼が覚めた。耳も目が覚めた。皮膚も眼が覚めた。眼も眼が覚めた。其他身体のあらゆる部分が目を覚ました。彼は今迄知らなかった自分の妻の傍に居ることを知るように成った。》(『新生』前編十四)
『新生』は、岸本捨吉が感じる不幸の記述に満ち満ちている。妻の園子は、決して捨吉に幸福感を与えるような存在ではなく、『新生』では詳しく書かれないが、結婚前の男との関係を夫から猜疑の目で凝視されているような不幸な女だ。
《「父さん、私を信じて下さい‥‥‥私を信じて下さい‥‥‥」
左様言って、園子が彼の腕に顔を埋めて泣いた時の声は、まだ彼の耳の底にあり〽と残って居た。》(同前八)
だからこそ彼はこう思うーー。
《妻の園子を失った後二度と同じような結婚生活を繰り返すまいと思って居た彼は、出来ることなら全く新規な生涯を始めたいと願って居た彼は、独身そのものを異性に対する一種の復讐とまで考えて居た彼は、日頃煩わしく思う女のために――しかも一人の小さな姪のために、斯うした暗いところへ落ちて行く自分の運命を実に心外にも腹立たしくも思った。》(同前二十四)
岸本捨吉=島崎藤村がとんでもないエゴイストだということを知らせる部分で、これなら「することをすればどうなるか」の自覚もなにもないまま姪に手を出して、「いつからその関係が始まったのか」という記憶も欠落させたままにしてはおけるだろうが、「妻の死後、女への復讐のために独身を貫いている」は、『新生』の中で何度も繰り返されることである。つまり『新生』は、女性に対して頑ななまでに心を鎖した男の不幸感に満ち満ちている作品なのだが、《それから岸本の身体は目を覚ますように成って行った。》の部分は、例外的に存在する「幸福」なのだ――しかもそれが「節子の妊娠の発覚」のすぐ後に置かれている。
《髪も眼が覚めた。》から始まる《眼が覚めた》のオンパレードは、生理的な快感と心理的な至福感が一体となった性的な陶酔感をついに知ったというようなものだが、それが「姪の妊娠」という不幸の始まりと一つになって登場するのはおかしい。がしかし、『新生』がどの時点で「書こう」と思い立たれたのかを考えると、これが、そうへんでもない。『新生』は、ある意味で「周到に仕組まれた作品」なのだ。
この長くグルグル回りをする男の苦悩ばかりを書き綴る作品を読んでいると、いつの間にかこれが大正二年の正月を起点とする現在進行形の小説」のように思えて来る。グルグル回りで先が見えないから、「この作品は先の見えない現実を漂う男の胸の内を描くものなのか」などと思われたりもするのだが、しかしこの作品が「いつ書き始められたのか、いつ“書こう”と思われたのか」を考えると、これを書く作者の「別の意図」も見えて来る。
大正二年の四月、姪の妊娠を知った岸本捨吉=島崎藤村はフランスへ逃げ、大正五年の七月に日本へ帰って来る。叔父に置き去りにされた節子はその間ずっと不安定な状態でいるのだが、「なにもなかった」のままにしていた捨吉=藤村は、やがてその関係を復活させてしまう。事態は大正二年の主国前の段階に戻って、長々と続いたパリでの前編の苦悩はなんだったのかということになってしまうが、このとめどなく「我が身の苦悩」を語る作品の眼目は、「語られる苦悩」の方にはなくて、「帰国した捨吉=藤村が事態をどのようなものであるかと理解し、終息させたか」というところにある。後編まで読んだ後の芥川龍之介が《『新生』の主人公ほど老獪な偽善者に出会ったことはなかった。》と言うのも、そこを衝いてのことかもしれない。早い話、帰国した捨吉=藤村は、節子と共にあることに「幸福」を見出すのだ。《一切を皆の前に白状したら》という彼の胸の奥の声は、「罪を償うために告白しなければならない」という義務感から生まれたものではなくて、「もう幸福だから白状してもつらくはない」と藤村が思ってしまったことの結果なのである。
姪との関係に降伏を見出すことが出来たからこそ、島崎藤村は『新生』の執筆を思いついたのだ。であればこそ、「私は不幸だ、だめだだめだ、ただだめだ」が延々と続く小説の初めに「幸福のなんたるか」が唐突に登場してしまうのも、不思議なことではない。」橋本治『失われた近代を求めて』上巻、朝日選書、2019朝日新聞出版、pp.81-89.
『妊娠小説』という画期的な文芸評論を書いた斎藤美奈子は、男が女性を妊娠させて巻き起こるドラマをテーマとする近代日本文学における諸作品の源流に位置する2作品、森鷗外の『舞姫』と島崎藤村の『新生』をあげ、『舞姫』を「妊娠小説の父」、『新生』を「妊娠小説の母」と呼んだ。そこで『新生』はこんなふうにやり玉に挙がっている。
「ぎんぎんの私小説。のっけから妊娠。しかも近親相姦ときてはワイドショー的興味も高まるが、期待してはいけない。みごと読み終えた暁には(読み終えられれば)、文庫本を力いっぱい床にたたきつけて叫ぶことになるだろう。なんなんだよ、この男は。それでこの小説はっ!『新生』とは、まあだいたいそんなような作品だ。」斎藤美奈子『妊娠小説』筑摩書房、1994年、pp.19-20.

B.連合赤軍あさま山荘事件から50年
*連合赤軍事件:全共闘運動の退潮を背景に、武力革命を目指したメンバーが栃木県真岡市で猟銃を強奪。追い詰められて山中を移動し、1972年2月19~28日、5人が長野県軽井沢町の「あさま山荘」に立てこもり、警察と銃撃戦を繰り広げた。警察官2人を含む3人が死亡。その後,「総括」と称して群馬県内で仲間12人を殺害し、遺体を埋めていたことが発覚した。
「インタビュー:連合赤軍事件と私 弁護士 古畑 恒雄 さん
12人のリンチ自白 異常な集団心理が 純粋な学生変えた
連合赤軍事件から50年になる。1972年2月、「共産主義革命」を目指した若者たちが「あさま山荘」に立てこもり、同士のリンチ殺人も発覚した。弁護士の古畑恒雄さんは当時、検事としてメンバーを取り調べ、いまも無期懲役が確定した元幹部の身元引受人を務める。連合赤軍事件とは何だったのか。古畑さんに聞いた。
――50年前、あさま山荘事件の現場に行かれていますね。
「1972年2月19日の午後でした。当時、私は長野地検で交安担当の検事をしていました。その日は土曜で、スキーに出かけようと板を車に積み込んでいると、妻から『検察庁から電話』と呼ばれました。『怪しい男女4人が軽井沢駅で捕まった。連合赤軍かもしれない』という連絡でした」
「軽井沢所に到着後、連合赤軍のメンバー5人があさま山荘にライフルを持って立てこもっていると聞かされ、真っ暗な中を車で山荘の近くまで生きました。現場ではヒューンというライフル銃の音がしていました」
「翌20日、私は駅で逮捕された4人に、直後の言い分を聞く弁解録取をすることになりました。最初に向き合った男性に職業を尋ねると、彼は私をじっと見て『革命戦士です』と答えました。事実関係は『黙秘します』でしたが、落ち着いていて、礼儀正しかった。その後、私はこの男性の担当になり、拘留期間の20日間、取り調べをすることになります」
――取り調べはどのようなものだったのですか。
「当初はリンチ殺人をしているとは、想像もしていませんでした。医学部の大学生で、父親が田舎から面会に来たときも、『お父さん、(行方不明だった息子さんの行方がわかって)よかったですね。遠からず帰っていくので大学に戻してください』と言ったぐらいです」
「男性と私は少しずつ話すようになりました。男性からドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を読んだことがあるかと問われ、途中で投げ出したと答えると、『一度読んでください』と言われました。被疑者から読書を進められたのはこのときだけです。取り調べの合間に人生論議もするようになり、互に通じ合うものが生まれて言ったように感じました」
――その後、事態が変わるのですね。
「2月28日にあさま山荘が落城した後、男性が山岳ベースでのリンチ殺人のことを自白しました。最初に『12人』と聞いたときには、私は12人が1人を殺したのかと思ったのですが、『総括』の名の下に12人が殺害されていました。驚きました。彼が一連の犯行を語り、私が調書を作りました」
「この男性には、ひたむきにものを考える誠実さがありました。しかし、残念ながら、当時は視野が狭かった。私が『君らが思うようなことにはならない』と言うと、彼は『わかりました』と答えるようになりました。彼になぜ自白をしたのかと聞いたことがあるのですが、私から『総括』の誤りを指摘され、一切を清算する気持になったと話してくれました」
- *
――連合赤軍がとんでもない輩だという印象は持っていなかったのでしょうか。
「私は学生運動にあまり偏見をもっていませんでした。治安維持を目的に制定された破壊活動防止法に反対する闘争デモには、早稲田の学生だった私も参加していました。彼らの心情はよくわかりました。安保闘争があり、ベトナム戦争で日本が米国を支援して巻き込まれていく時代、為政者への批判を強めた若者たちの思いは理解できました」
「私が取り調べた男性は真面目で純真でした。ふとした弾みで過激派に加わり、真っ直ぐに進んでしまったのだと感じました。異常な集団心理の下で異端の行動を取ることは起こりうることです」
「私は男性を死刑にしたくないと思いました。数だけで言えば死刑です。しかし彼の人間性や事件の背景を考えると、いつかは社会復帰してもらいたい。それで、いつだれがリンチの標的になるかわからない異常な集団心理の中で、生き残るためにリンチする側に加わらざるをえなかったという彼の心理を調書に書き込みました」
- *
――それ以降も連合赤軍事件を調べられたのですか?
「72年4月に東京地検に転勤になり、その後は関係していません。91年に法務省保護局長になり、翌年に、調書を書いた男性の仮釈放の許可決定の報告書を目にしました。懲役20年の判決を受けたのですが、模範囚として過ごし、18年弱で社会復帰した。心からよかったと思いました」
――退官後、受刑者の「寄り添い弁護士」の活動をされています。その中で、連合赤軍の元幹部に関わっています。
「寄り添い弁護士の活動は20年ほど前からですが、実刑判決を受けた人について知人から相談があったのがきっかけです。孤独感や絶望感の高まる受刑者と手紙をやりとりし、面会もします。刑務所への上申書も書きます。50人余のお世話をしてきました」
「あさま山荘事件で逮捕され、無期懲役が確定した吉野雅邦受刑者(73)もそのうちの一人です。10年ほど前、私が取り調べたあの男性と再会したのですが、そのつながりで吉野受刑者に力を貸して欲しいと頼まれました。ほぼ毎週手紙を書き、2カ月に一回は面会をしてきました。受刑して39年、逮捕から50年。完全に改悛し、模範囚として服役を続けています」
「私自身は彼をどう励ましていけばいいのか、彼の心のケアに悩んでいます。仮釈放の門戸があまりにも狭いのです」
――無期刑受刑者の仮釈放はどのぐらい狭き門なのでしょうか。
「法務省によると、2020年中の新規仮釈放者は8人。その年の無期刑受刑者は1744人ですから、たったの0.4%です。新規仮釈放者の平均受刑期間は37年6カ月。私が法務省保護局総務課長だった1981年は1年で67人が仮釈放されました」
- *
――なぜ、仮釈放者の数が激減したのでしょうか。
「刑法28条には『無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる』という文言があります。80年代までは模範囚であれば18年ほどで多くが仮釈放されましたが、90年代以降は、社会の厳罰化志向が強まります」
( 中 略 )
――とはいえ、無期刑受刑者の社会復帰には被害者や遺族は納得しない部分もあるのでは。どう乗り越えればいいのでしょうか。
「いま私は2人の無期刑受刑者をお世話しています。彼らは自らの犯した罪の重大さからして被害者家族が納得せず、社会も冷たいことは当然であると十分に理解しています。その『気づき』が人間性の改善のしるしです。被害者遺族や社会の人々が赦していなくても、それを当然として受け入れ、被害者遺族や社会の人々を思いやり、可能な限り物心両面での慰謝の手立てを考えたいという強い気持でいます。私自身は、そういう彼らの良き伴走者でありたい」
「どんな罪を犯した人でも、やがては本人の気づきと周囲の支えによって、変わり得る。罪を十分に反省して再起しようと努力しているのであれば、更生保護の支援をするべきです。適切な見守りと支えによって人間性を回復させるべきだと考えます」 (聞き手 編集委員・大久保真紀)」朝日新聞2022年2月26日朝刊15面オピニオン欄。
あさま山荘に立てこもった5人のうち、最年少の高校生で兄弟で連合赤軍に加わり、リンチで兄を殺され逮捕服役していま農業をやっているという遠藤氏が、別の記事で言っていたことが心に残る。自分たちがやったことが、その後の若い人たちに、政府や国家のやることに異議を唱え、批判することが罪悪であり、タブーだと思わせるようになったとすれば、実に残念なことだと。