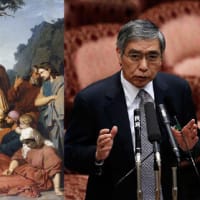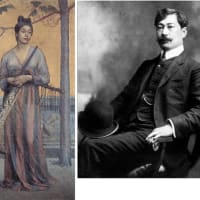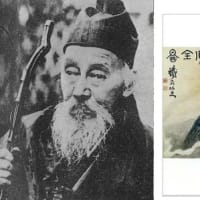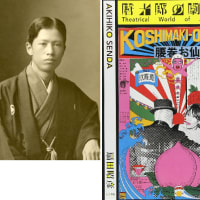A.「日本人であること」にこだわるわけ?
ネットを見ていると、いわゆる「ネトウヨ」と呼ばれる人たちが、非常に熱心にある話題にだけ強く反応して、攻撃的な言辞を書き込んでいるのを目にする。たとえばNHKが夜のニュースで、国立市議会が「在日コリアンへのヘイトスピーチを法規制することを求めた意見書を可決した」という報道をしたことに対し、ツウィッターに「ぜってぇ住まねえ、国立はサヨクの巣だ!こいつらは反日のゴミだ」みたいな罵詈雑言が、山のように寄せられている。ぼくは言論の自由は認めるべきだと思うので、そのような発言をすること自体は構わないと思う。しかし、このような書き込みをしている人たちの頭の中を占領している言説の、拠って来たる所を知りたいと思う。ヘイトスピーチ・デモをしている在特会の参加者だけではなく、自分は街頭の行動をするわけではなくても、彼ら(彼女らもいるのだろうが)はそういう発言を書き込むことで一種の熱い連帯感を確認しているんだろうな、ということはよくわかる。
それはたぶん「サヨク」の側も似たようなところがあって、先頃の「朝日新聞謝罪」をめぐる従軍慰安婦問題などは、格好のバトルになっている。「ウヨク」がこのさい国際世論に訴えて日本が悪い国だったというにっくき韓国朝鮮に同調する「反日」言説をひっくり返す運動を繰り広げようというのに対して、挑発に乗ったように「ウヨク」の言い分に反論する攻撃を内輪で頷きあうためネットで繰り返そうとしている。安倍政権の登場で、排外主義がある種の人々に全能感を与えて言いたい放題な状況があるのだとしても、在特会的なヘイトスピーチが国際世論を動かすとはとても思えない、どころか偏狂奇妙なネオナチと同一視されて「国辱」をもたらすぐらいのことは、従来もまともな政治家や外交官なら知っているはずだろう。
日本の大学教育は、若者にそんな常識的なことも教えていないとしたらこの国の未来はないし、歴史を知ってものを考える訓練を怠っているといわれても仕方がない。だからもう少し理性的な次元でこの「ネトウヨ」言説を考える必要はあると思う。そのアイディアのもとは、たぶん要約してしまえば、コリアや支那が憎悪をこめて流布したウソを信じた「バカな反日サヨクが捏造によって作り上げた」歴史観によって、戦後の日本は「日本人としての誇り」を傷つけられてきたので、もういい加減やめよう、反日サヨクは叩き出そう!というスローガンになるのだろう。どうしてそんなふうに考えるのか?社会科学的には、興味のあるテーマである。
これまで出ている解釈は、かつての「豊かな社会」が収縮する日本で、個人としての充足感や自己肯定感のもてない人たちが、無限に肯定的な「日本人」「日本という国」という観念を掲げることでいわば心理的な大逆転を図る、あるいはそのような「気分」を共有する仮想の仲間がいると思うことで、自分を肯定するという動機がある、という説明がひとつ。ただ、それだけではごく一部のマイノリティの問題になってしまい、社会的に大きな運動にはならないはずなのに、今の日本では少なくとも、かつての右翼のように社会の片隅で異様な街宣車の絶叫で顰蹙を買うような運動の質とは違った側面が出てきているとは思う。ヘイトスピーチ・デモは今のところ旧型の右翼運動を引きずっているようにも思えるが、それが不特定の匿名的ネット社会になったから、というだけでは説明としてちょっと足りない。
ぼくなりに考えてみると、ひとつは80年代から抬頭した意識的なrevisionist歴史修正主義の言説が、教科書問題を契機にアカデミックなレベルにおいても、ある勢力をなしてきたこと。もうひとつは、東アジアの国際政治的な勢力関係power balanceが、アメリカに依存した日本の覇権が衰え、韓国と中国が力を増してきたこと、が影響していると思う。「日本人のプライド」という観念がそこで急速に、社会的マイノリティ以外の人々にも共有される状況が出現した。ナショナリズムはいつの時代、どこの国でも国民統合の核になるイデオロギーだが、それが国民を鼓舞するか沈静するかは、ときどきの国際関係の関数として現れる。いまの日本はまさに、グローバリズムの進展ゆえにナショナリズムが表に出てくる状況にある。「日本人」のマジョリティが今までの既得権や財産を脅かされ、漠然とした不安を感じているとすれば、過去の歴史に真摯に学ぶのではなく、歴史を捏造してでも自分が所属する国家を褒めたい心情に陥るのは、それこそ過去の歴史の至るところで見出される事実である。
それこそが戦争というナショナリズムの祭りを呼び込む誘惑なのであり、昭和戦前期の日本が突き進んだ道だと思う。明治維新は外圧による混沌のなかでこの国が活路を開こうとした歴史であり、それ自体奇跡的な成功だと思うが、19世紀という時点で革命を達成した国が次に追求すべき道は、隣国への軍事的侵略に繋がるのはなかば必然だった。その結果辿り着いた場所は、日本の歴史にかつてなかった敗戦と外国の占領統治だった。このことを直視しない日本史はありえないし、それを教えない教育は教育とはいえない。いまの従軍慰安婦問題にしろ南京虐殺問題にしろ、ぼくは歴史的事実の科学的検証は必要だけれども、もっとも肝心な問題はそこにはなく、日本という国家が何をしようとし何を実際にやってきたかの本質を考えるべきだと思う。歴史修正主義者たちは、それが輝かしい正義の道であったと思いたいのだろう。
でも、それは水戸学的ロマンチシズムに過ぎない。明治維新史を正確に読めば、そんな結論は夢想に過ぎなかったし、当の維新の志士、明治の指導者たちも試行錯誤の連続だったと思う。そのもっとも意識的な指導者は大久保利通と伊藤博文だったと思うが、彼らにしてもこの日本という幼い国家が、朝鮮半島や中国大陸を占領支配して巨大帝国を形成するなどと考えていたわけではない。「ネトウヨ」の準拠点が、日露戦争に勝利した栄光の大日本帝国に置かれているのは、一番うまくいった自分を褒めるというゴーマンな思想であり、それはほとんど失敗する運命にある。実際それは「近代の超克」などとほざいているうちに、これ以上ないほど無残に挫折した。戦争に敗け、多くの人が死んだという事実を、謙虚に冷静に捉えるとき、じつは人間は賢くなる可能性が高いのだ。そこで日本人は体験的に多くの智恵を得たと思う。
だから、この国を卑下自虐するのではなく、と同時に過大尊大に栄光を讃えるのでもなく、もっと広い視野で賢く隣人に信頼される人間になるには、何をすればよいかを考えるべきだ。

B.明治の美術界
日本は長い歴史のある国なので、明治の御一新によってはじめは江戸時代の伝統の中に生きていた人々も、気分をガラッと変えて西洋に目標を定めた。工学的技術、鉄道、機械、造船、鉱山、化学、薬学、そういう分野は10年もすれば優秀な若者が勉強して、次々とその成果を日本で実現するようになった。その次は、経済(当時は理財とも呼んだ)や法律の知識を導入した。ヨーロッパの社会科学も次々持ち込まれて、帝国大学では優秀な行政官僚を送りだしていた。でも、それをやっていけば、今度は西洋の芸術、音楽や文学や演劇、そして美術も国家の要請にしたがって学校を造り、次世代の若者に西洋の美の基準を教え込んだ。それは国の使命として欧米の技術や道具で学んだ若者に、ヨーロッパでは何が役に立ち、何が美しい作品として大勢の市民が見たがるのか、という問いになってくる。
日本の美術教育という点で、まずは岡倉天心というリーダーがいた。英語で日本の美術を紹介した彼は、「茶の本」を書いて、日本画という伝統的な技術をなんとか明治の新しい時代に適応させ、生き延びさせようとした。しかし、西洋の美術こそこれから日本の画家が追求すべきスタンダードだと信じる若い教師や画学生たちは、伝統絵画にこだわる天心と対立したのも仕方がないことだった。
「1898年(明治三十一年)岡倉天心が東京美術学校を辞めざるをえなくなったのは、若くして校長になった彼に対する誹謗があったからであるが、その私怨の原因は伝統的な木彫に洋風の彫塑を加えようとした大村西崖らが、国粋保存派の天心一派と対立したからである。辞任後、彼を慕う美術家たちと日本美術院を結成した。
ここでは一見、洋風派と和風派の対立のように見えるが、果たしてそうであろうか。日本美術院には橋本雅邦を中心として横山大観(一八六八~一九五八)、下村観山(一八七三~一九三〇)、菱田春草(一八七四~一九一一)らがいた。彼らは「朦朧体(線抜きの色彩画)」をもってひとつの主張をしたといってよい。この画法は岡倉天心が画家たちに、「空気を描く工夫はないか」と問うたことから発したと言われているが、これは黒田清輝ら西洋画がもたらした「外光派」の応用であった。これはまさに陰影法をいかに日本画の伝統の中に組み入れようとしたか、その努力の一端といってよい。一九〇四年天心は大観、春草を伴って渡米するが、そこで見出したのはホイスラーの「トーナリスム」という輪郭抜きの描法であった。あるいはターナーにおける雰囲気描写であった。その「朦朧体」に琳派の技法を加えて日本風に工夫をこらしているが、それは西洋風の大気表現の導入の一部であった、と捉えることが出来る。つまり彼らの対立は結局同じ洋風化に他ならなかった。
大観の『屈原』(一八九八年、厳島神社)の中の色没骨の草叢の描き方はまさに西洋画的な雰囲気描写であったのである。するとこの荒涼たる野を歩む屈原こと天心の姿は、やはり洋風を追った姿であったのである。観山の代表作のひとつである『木の間の秋』(一九〇七、東京国立近代美術館)が、琳派風の装飾的な樹木の配置でありながら、そこには西洋風の遠近法、明暗法がはっきり使われ、これが西洋風の日本画であることを示している。また春草の同じ林をあつかった『落葉』(一九〇九年、永青文庫)も、その樹木の肌の犀利な表現と空気遠近法は、西洋画の写実を取りこんだもの、といえるのである。これは京都の竹内栖鳳(一八六四~一九四二)も異なるものではない。一九〇〇年栖鳳が欧州旅行したときターナーとコローに注目し、そkに「本当の風景画」を見出したのも、日本画と西洋画は異なるものではないことを感じていたからである。東京は色彩を、京都は筆法を重んじていると区別していても、内実はともに西洋絵画の摂取と吸収であった。栖鳳が帰国後、西洋の「写意」を重んじ、その基礎に《実物を知悉》しようとする徹底した写実精神がある、と感じ、日本画家の「写意」を《習慣的に古風を習得し、約束に許り拘泥して》いる、と批判するとき、日本画はまさに西洋画となったし、ひとつのものであるといったことに等しい。しかし栖鳳が『アレ夕立に』(一九〇九年、高島屋資料館)とか『絵になる最初』(一九一三年、京都市美術館)のように人物を主題にするとき、風景を、動物画で用いた陰影法や写実を捨てて装飾風の二次元的に描くのは、まだ日本画を信じている証拠である。画家たちの多くは、相変わらず日本画は西洋画と異なるものと思う不可思議な現象が続いている。
彫刻の方でも同じことが言える。一九七六年(明治九年)に工部美術学校に彫刻科が置かれ、イタリア人ヴィンチェンツォ・ラグーザ(一八四一~一九二八)が招かれ、六年間塑像・大理石などの彫刻を教えた。その生徒の一人長沼守敬(一八五七~一九四二)は、六年にわたってヴェネツィア美術学校で学び、一八八七年(明治二十年)に帰国したが、それは『老父』に示されるように写実そのものであり、一方では高村光雲(一八五二~一九三四)などが伝統的な木彫を受け継いでいたが、『老猿』などで見えるのは、たはり同じ写実に基くモニュメンタリティである。
しかし単に写実だけでなく、そこにロダン風の生命観を付与しようとしたのは荻原守衛(一八七九~一九一〇)で、彼ははじめ絵画の方に意を注いでいたが、一九〇一年に渡米、一九〇三年には渡欧しロダンの『考える人』に感銘を受け彫刻に転じた。そのブロンズ像の『女』(東京国立近代美術館)にあるような動作に見える、ひとつの理想性の追求がある。このロダンの影響は日本の彫刻家に大きかったが、とくに高村光太郎(一八八三~一九五六)はその生命力を受け継ごうとした。『手』(東京国立近代美術館)はその代表作とされるが、彼が《構造無きところに存在無し》(『彫刻十箇条』)といった言葉と裏腹にロダンと比べると、しっかりとした骨組みを欠いていることを感じさせる。これも結局模倣が招来するオリジナリティの欠如が存在していることに他ならない。」田中英道『日本美術全史』講談社学術文庫、2012.pp.526-529.
昭和戦前、日本の洋画家のことを考えていくと、ある種の明るい克服とまたある種の悲哀を感じざるをえない。