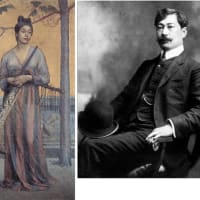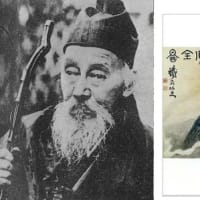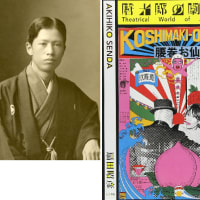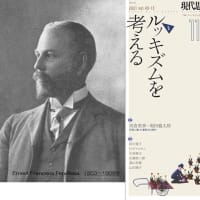A.宇沢弘文追悼
ぼくの学生時代までは、大学で習う経済学というものは、ざっくり分けて「マル経」と「近経」というふたつがあって、どっちを学ぶかによって学問上の立場だけでなく、現実社会に対する見方、基本的なスタンスが違ってくるといわれていた。「マル経」つまり「マルクス経済学」ではカール・マルクスの『資本論』が必読で、そこからさまざまな経済理論が導かれるとされるから、「交換価値」と「使用価値」とか、「原始的蓄積」とか下部構造と上部構造とか、主要な用語はすべてマルクスの原典に拠って、経済現象は説明されるはずだった。そういうものを少し囓っていくと、「マル経」のなかにもいろいろ立場があって、たとえば日本では「宇野派の三段階論」とか「構造改革派の修正理論」だとか、「講座派」とか「労農派」だとかかなりややこしくなる。当時は戦後の学生運動の名残があって、社会主義革命が必要だと叫ぶ左翼的な学生は、『資本論』の講読会などをやって、にわか勉強の「マル経」の用語を口にするとなんだか世界がわかっているような気がしてきて、得意になる。
一方、「近経」つまり「近代経済学」の方は、英米の科学としての経済学を追究する立場だから、マルクスなんか無視して、ハイエクとかサミュエルソンとかピグーとか、あるいはケインズを読むことから始める。こっちの方は、数学を使うので頭の良さを競って数式に馴染まないとやっていけない。だから頭の悪い学生はついていけない。「マル経」学生には、何をいっているのか解らないので、「近経」などやる連中は資本主義を肯定し、資本家の手先になって労働者を搾取する片棒を担ぐ御用学者に洗脳された「反動」の側にいる、と攻撃していた。
でも、そんな対立はまもなく日本が高度成長の恩恵を身に浴びて、革命など夢物語だと思う時代になって、じわじわと消えていった。経済学は、社会の変革や東側の社会主義圏の謳う計画経済ではなく、これに勝る市場資本主義の現代化を遂げ、それを分析し処方箋を提供する技術として大学で教えられるようになった。
宇沢弘文という名前は、「近経」の世界の中心で成功を遂げた日本人経済学者のヒーローだった。宇沢さんの価値は、「マル経」の凡百の経済学者が滅びていったことと比べて、輝きを増していった。そして経済学という学問の真価が問われる今の日本では、宇沢さんの言っていたことの意味が重い価値をもつと思うのだが、どうもそれは理解されていない。
「国が子どもたちへの金融教育に力を入れ始めたころ、時の日銀総裁が講演で、こんなことを話した。「自分の持っている大切なものを手放してお金に換えても、そのお金は価値をきちんと保全し、次に必要なものを手に入れる時に役立ってくれる」▼先日、八十六歳で逝去した経済学者・宇沢弘文さんはその言葉に怒りを感じたそうだ。「大切なものは決してお金に換えてはいけない。人生で一番大きな悲劇は、大切なものを国家権力に奪い取られたり、あるいは追い詰められてお金に換えなければならなくなった時です」▼宇沢さんは十七歳で終戦を迎えた。貧困と失業、経済混乱に苦しむ人々の姿を見て経済学の道を歩みはじめた。もともとは医師志望。「経済学は社会を癒やす学問」と考えてのことだ▼数理経済学でノーベル経済学賞候補に選ばれるほどの成果を挙げた頭脳は、社会・経済の病理に苦しむ人に向けられた。その深い洞察力が認められ、ローマ法王の助言役を務めたこともある▼生活の糧の海を大企業の利益のため汚され、健康と命を「換金」させられた水俣の人々や、国策による開発で先祖伝来の地を「換金」させられた人々……。そういう人たちの心が救われるまで「日本経済の貧困は解決できない」と言っていたそうだ▼経済とは、経世済民。世をおさめ、民をすくう。言葉の本来の意味の経済学者だった。2014.9.27」筆洗『東京新聞』9月27日朝刊。
ノーベル経済学賞を受賞していたら、宇沢弘文の本はもっと読まれたかもしれないが、そういう金メダルでしか評価しないマスメディアなど、しょせんはど~でもいいのである。問題は、経済学の最先端と現実とがどう関わるか、一流の学者がそれにどういう見解を提示していたか、なのだ。
「評伝:18日86歳で死去した宇沢弘文東大名誉教授は、得意の数学を生かした先駆的な成長理論をつくり上げる一方、環境問題など社会・経済問題にも積極的に関わった。
東大理学部数学科を卒業後、1956年に渡米。シカゴ大学教授などを務めた十年余りの米国滞在中、消費財と投資財の二部門による成長のメカニズムを示す成長理論をまとめた。同理論はその後も米国の研究者に大きな影響を与え続け、ノーベル経済学賞の候補に何度も挙げられた。
68年に帰国した背景には、ベトナム戦争への批判があったとされる。宮川努学習院大教授は、東大二年の春、休講続きの講義に出てきた宇沢氏が「サイゴンが落ちた」と、唐突に語りだしたのを覚えている。
日本に戻った宇沢氏は、「自動車の社会的費用」(74年)で、排ガス公害など自動車社会のコストを世に問い、地球温暖化にも警鐘を鳴らし続けた。2011年には環太平洋連携協定(TPP)に慎重な国会議員らでつくる「TPPを考える国民会議」の代表世話人に就任するなど、成長の「負の側面」にも厳しい目を注いだ。
中央官庁に勤める宇沢ゼミOBは「論文指導も厳しかったが、谷川岳合宿の登山がきつかった」と振り返る。健脚で学生を驚かせた宇沢氏は、大学にもたびたびランニング出勤し、二酸化炭素(CO2)排出を抑制する研究者でもあった。」『東京新聞』9月27日30面。
ぼくが宇沢弘文という名前を強く記憶したのは、70年代半ば、「自動車の社会的費用」を読んだ時からだった。「近経」のチャンピオンのような人が、日本経済の成功のチャンピオンのような自動車産業を根元から批判していた。「へえ!」と驚いた。当時の日本人は日本製自動車が世界市場を席巻し、次々発売される高性能の自動車に喜んで乗り、高速道路を走り回るのに誇りさえ感じていた。だから宇沢氏の自動車の経済に対する、そして文明に対するマイナスのコストについてなんか誰も考えていなかった。しかし、それは確実に犠牲を伴うと指摘されて、目を覚まされた気がした。それは今の原発につながる。

B.絵画の価値について
昔、1967年に始まった『季刊藝術』という雑誌があって、これは文学評論の江藤淳、音楽評論の遠山一行、美術評論の高階秀爾、そして編集人として作家の古山高麗雄によって年4回発行されていた。ぼくはその頃、江藤淳の書くものには全部目を通したいと思っていたので、この『季刊藝術』を買って書棚に並べていた。この雑誌にはいろんな人が書いていたのだが、とりわけ音楽についての遠山一行の論考と美術についての高階秀爾の書くものには、いつも多くを教えられていた。高階先生は、美術の分野ではとびぬけた存在で、当時は東大にいて美学美術史を講じるほか、マスメディアにも盛んに登場して、古典から現代美術まで多くの作品を解説していた。後に近代美術館や大原美術館の館長などを勤められる一方、今も美術の分野で多くの著作を書かれている。久々に文庫になっている『20世紀美術』を読んでみた。
「実物にはいっこう感心しない。ところがこの実物がひとたび絵になると、人は実物に似ているといって関心する。世に絵画ほど空しいものはない。
一七世紀のフランスの哲学者パスカルの言葉である。
なるほど、言われてみればたしかにその通りに違いないという気がする。
一七世紀においては、――いや二十世紀の今日においてすら多くの人びとにとって――絵画とは現実の世界を何らかのかたちで反映し、写し出すものであった。それはかならずしもいわゆる「美しいもの」である必要はなかった。無骨な将軍の肖像でも、ありふれた台所の一隅でもかまわない。ただそれが「実物」を髣髴させるように描かれてあれば、それで人びとは満足し、感嘆すらしたのである。だが人は、いったい何に満足し、何に感嘆したのだろうか。
同じ将軍の顔を描き出した肖像画が何枚もあるとする。おそらく当時の人びとは、描き出された姿が本物の将軍に似ていればいるほど、喜びもすれば、感嘆もしたに相違ない。現在でも多くの人びとがそのような反応を示す。では、それほどまで本物に似ている方がよいというのなら、紛れもない本物の将軍に出会ったら感嘆のあまり卒倒でもしなければならないところだが、事実はしかし逆であって、本物の将軍に「美的感動」を覚える人はまずないであろう。とすれば、誰からも感心されない将軍の姿のいわば「影」にすぎないその肖像画を、それもそれが本物に似ているからという理由で讃美するとは、何とおかしなことではないか、というのがパスカルの言い分である。
だが人びとが「実物」よりも「影」の方にいっそう惹かれたということは、それなりに理由があったはずである。その理由を探るためには、「実物」と「影」とのあいだに、どのような本質的な差異があるのか、もっと具体的に言えば、「実物」から「影」へと移行する過程において、いったいなにが失われてなにがつけ加えられたのか、それを明確にしなければならない。
失われたものはあきらかである。それは、将軍というひとりの人間の持っている物質性、その重み、その実体、現実の世界のなかに生きていて、呼吸し、喋舌り、動き回る存在としての将軍である。もっとも素朴な、もっとも平凡な意味における「もの」としての将軍の存在である。絵画の世界においては、三次元の空間に存在する「もの」としての将軍の実体はかんぜんに失われる。描かれた将軍の姿は、重さも、厚みも、物質性も持たない。「影」はあくまでも二次元の世界にのみ属しているからである。
絵画が、比喩的な意味でなしに現実の「もの」の影であるということは、絵画の誕生についてプリニウスがその『博物誌』の中で語っているあの美しい伝説によっても明らかであろう。プリニウスの語るところではこうである。ギリシャのコリントスの陶工ブータデスの娘は、自分の恋人が立ち去ろうとする時、何とかして彼の面影を自分のそばにとどめておきたいと思った。そこで娘は、炭を手に持つと、燈火に照らし出された若者の顔が壁の上に落とす影をずっと線でなぞって、その相貌を描き出したという。それが世界の最初の「肖像画」であった。それは文字通り「影」の世界であり、「実物」の不在を補い、「実物」の代わりを勤めるためのものであった。
同じような考えは、レオナルド・ダ・ヴィンチにも指摘することができる。彼はその「手記」の中で、
最初の絵画は、太陽によって壁の上に作られた人間の影の輪郭をたどった線にすぎなかった・・・・・・。
と書き残しているからである。
ギリシャの伝説の娘が壁の上に描きとどめたという若者の肖像は、単なる一本の線にすぎなかった。だが、それが、「実物」の世界の「代り」であり、実物を思い出させるためのものであるとしたら、単なる輪郭線だけではなく、本物の世界に見られるさまざまの性質を備えていた方がいっそう効果的であるあることはいうまでもない。眼や、鼻や、唇などの細部の描写、柔らかい肌の色合いやかすかにそれと認められる頬の翳り、豊かな髪の毛のうねりなどをそれらしく描き出せば、「影」はそれだけ「実物」に近くなる。レオナルドは、「影」を「実物」に似せて描き出す技術において、もっとも卓越した腕の持主のひとりであった。しかしそのレオナルドの《モナ・リザ》でさえ、実体のない「影」の存在であるという点では、ギリシャの伝説の娘とたどたどしい炭の線の跡と何ら変わりはなかった。ただ《モナ・リザ》の画面には、いっそう多くの現実の部分が入り込んでいるだけである。だがいずれの場合においても、「実物」の世界だけが持っている三次元の空間存在としての「もの」の実体は失われてしまっている。
肖像画が、「実物」の世界から何ものかが失われただけのものであったなら、パスカルならずとも「空しい」と思わずにはいられないだろう。「実物」が少しも面白くないのに、それからさらに何かが失われたものが興味を呼び得るはずがない。しかし、《モナ・リザ》は、いやあのギリシャの娘のたどたどしい線ですら、「実物」の世界の持たない別のものを持っている。それは、娘が恋人の面影を描き出したという壁そのものと共通の特質、すなわち二次元の平面としての特質がそれである。
十七世紀の将軍の肖像にも、《モナ・リザ》にも、ギリシャの娘の壁の線にも共通して見られるなにものかがあるとすれば、それはまさに、平面における形と色の世界というこのことであろう。そしてこの特質こそが、三次元の空間の中の存在である「実物」と絵画とを決定的に分けるものなのである。
現実の世界と深いかかわり合いは持ちながら、現実の世界とはまったく別の、いわば実体を持たない「影」の世界としての絵画の特性、それをわれわれは「イマージュ」の世界と呼ぶことにしたい。それに対し、先ほどから「実物」という言葉であらわして来た現実のものの世界、それは「オブジェ」の世界と呼んでもよいものであろう。」高階秀爾『20世紀美術』ちくま学芸文庫1993.pp.30-34.
絵とは何であるか?「イマージュ」と「オブジェ」について、パスカルから始めたこの文章の密度は高い。
ぼくの学生時代までは、大学で習う経済学というものは、ざっくり分けて「マル経」と「近経」というふたつがあって、どっちを学ぶかによって学問上の立場だけでなく、現実社会に対する見方、基本的なスタンスが違ってくるといわれていた。「マル経」つまり「マルクス経済学」ではカール・マルクスの『資本論』が必読で、そこからさまざまな経済理論が導かれるとされるから、「交換価値」と「使用価値」とか、「原始的蓄積」とか下部構造と上部構造とか、主要な用語はすべてマルクスの原典に拠って、経済現象は説明されるはずだった。そういうものを少し囓っていくと、「マル経」のなかにもいろいろ立場があって、たとえば日本では「宇野派の三段階論」とか「構造改革派の修正理論」だとか、「講座派」とか「労農派」だとかかなりややこしくなる。当時は戦後の学生運動の名残があって、社会主義革命が必要だと叫ぶ左翼的な学生は、『資本論』の講読会などをやって、にわか勉強の「マル経」の用語を口にするとなんだか世界がわかっているような気がしてきて、得意になる。
一方、「近経」つまり「近代経済学」の方は、英米の科学としての経済学を追究する立場だから、マルクスなんか無視して、ハイエクとかサミュエルソンとかピグーとか、あるいはケインズを読むことから始める。こっちの方は、数学を使うので頭の良さを競って数式に馴染まないとやっていけない。だから頭の悪い学生はついていけない。「マル経」学生には、何をいっているのか解らないので、「近経」などやる連中は資本主義を肯定し、資本家の手先になって労働者を搾取する片棒を担ぐ御用学者に洗脳された「反動」の側にいる、と攻撃していた。
でも、そんな対立はまもなく日本が高度成長の恩恵を身に浴びて、革命など夢物語だと思う時代になって、じわじわと消えていった。経済学は、社会の変革や東側の社会主義圏の謳う計画経済ではなく、これに勝る市場資本主義の現代化を遂げ、それを分析し処方箋を提供する技術として大学で教えられるようになった。
宇沢弘文という名前は、「近経」の世界の中心で成功を遂げた日本人経済学者のヒーローだった。宇沢さんの価値は、「マル経」の凡百の経済学者が滅びていったことと比べて、輝きを増していった。そして経済学という学問の真価が問われる今の日本では、宇沢さんの言っていたことの意味が重い価値をもつと思うのだが、どうもそれは理解されていない。
「国が子どもたちへの金融教育に力を入れ始めたころ、時の日銀総裁が講演で、こんなことを話した。「自分の持っている大切なものを手放してお金に換えても、そのお金は価値をきちんと保全し、次に必要なものを手に入れる時に役立ってくれる」▼先日、八十六歳で逝去した経済学者・宇沢弘文さんはその言葉に怒りを感じたそうだ。「大切なものは決してお金に換えてはいけない。人生で一番大きな悲劇は、大切なものを国家権力に奪い取られたり、あるいは追い詰められてお金に換えなければならなくなった時です」▼宇沢さんは十七歳で終戦を迎えた。貧困と失業、経済混乱に苦しむ人々の姿を見て経済学の道を歩みはじめた。もともとは医師志望。「経済学は社会を癒やす学問」と考えてのことだ▼数理経済学でノーベル経済学賞候補に選ばれるほどの成果を挙げた頭脳は、社会・経済の病理に苦しむ人に向けられた。その深い洞察力が認められ、ローマ法王の助言役を務めたこともある▼生活の糧の海を大企業の利益のため汚され、健康と命を「換金」させられた水俣の人々や、国策による開発で先祖伝来の地を「換金」させられた人々……。そういう人たちの心が救われるまで「日本経済の貧困は解決できない」と言っていたそうだ▼経済とは、経世済民。世をおさめ、民をすくう。言葉の本来の意味の経済学者だった。2014.9.27」筆洗『東京新聞』9月27日朝刊。
ノーベル経済学賞を受賞していたら、宇沢弘文の本はもっと読まれたかもしれないが、そういう金メダルでしか評価しないマスメディアなど、しょせんはど~でもいいのである。問題は、経済学の最先端と現実とがどう関わるか、一流の学者がそれにどういう見解を提示していたか、なのだ。
「評伝:18日86歳で死去した宇沢弘文東大名誉教授は、得意の数学を生かした先駆的な成長理論をつくり上げる一方、環境問題など社会・経済問題にも積極的に関わった。
東大理学部数学科を卒業後、1956年に渡米。シカゴ大学教授などを務めた十年余りの米国滞在中、消費財と投資財の二部門による成長のメカニズムを示す成長理論をまとめた。同理論はその後も米国の研究者に大きな影響を与え続け、ノーベル経済学賞の候補に何度も挙げられた。
68年に帰国した背景には、ベトナム戦争への批判があったとされる。宮川努学習院大教授は、東大二年の春、休講続きの講義に出てきた宇沢氏が「サイゴンが落ちた」と、唐突に語りだしたのを覚えている。
日本に戻った宇沢氏は、「自動車の社会的費用」(74年)で、排ガス公害など自動車社会のコストを世に問い、地球温暖化にも警鐘を鳴らし続けた。2011年には環太平洋連携協定(TPP)に慎重な国会議員らでつくる「TPPを考える国民会議」の代表世話人に就任するなど、成長の「負の側面」にも厳しい目を注いだ。
中央官庁に勤める宇沢ゼミOBは「論文指導も厳しかったが、谷川岳合宿の登山がきつかった」と振り返る。健脚で学生を驚かせた宇沢氏は、大学にもたびたびランニング出勤し、二酸化炭素(CO2)排出を抑制する研究者でもあった。」『東京新聞』9月27日30面。
ぼくが宇沢弘文という名前を強く記憶したのは、70年代半ば、「自動車の社会的費用」を読んだ時からだった。「近経」のチャンピオンのような人が、日本経済の成功のチャンピオンのような自動車産業を根元から批判していた。「へえ!」と驚いた。当時の日本人は日本製自動車が世界市場を席巻し、次々発売される高性能の自動車に喜んで乗り、高速道路を走り回るのに誇りさえ感じていた。だから宇沢氏の自動車の経済に対する、そして文明に対するマイナスのコストについてなんか誰も考えていなかった。しかし、それは確実に犠牲を伴うと指摘されて、目を覚まされた気がした。それは今の原発につながる。

B.絵画の価値について
昔、1967年に始まった『季刊藝術』という雑誌があって、これは文学評論の江藤淳、音楽評論の遠山一行、美術評論の高階秀爾、そして編集人として作家の古山高麗雄によって年4回発行されていた。ぼくはその頃、江藤淳の書くものには全部目を通したいと思っていたので、この『季刊藝術』を買って書棚に並べていた。この雑誌にはいろんな人が書いていたのだが、とりわけ音楽についての遠山一行の論考と美術についての高階秀爾の書くものには、いつも多くを教えられていた。高階先生は、美術の分野ではとびぬけた存在で、当時は東大にいて美学美術史を講じるほか、マスメディアにも盛んに登場して、古典から現代美術まで多くの作品を解説していた。後に近代美術館や大原美術館の館長などを勤められる一方、今も美術の分野で多くの著作を書かれている。久々に文庫になっている『20世紀美術』を読んでみた。
「実物にはいっこう感心しない。ところがこの実物がひとたび絵になると、人は実物に似ているといって関心する。世に絵画ほど空しいものはない。
一七世紀のフランスの哲学者パスカルの言葉である。
なるほど、言われてみればたしかにその通りに違いないという気がする。
一七世紀においては、――いや二十世紀の今日においてすら多くの人びとにとって――絵画とは現実の世界を何らかのかたちで反映し、写し出すものであった。それはかならずしもいわゆる「美しいもの」である必要はなかった。無骨な将軍の肖像でも、ありふれた台所の一隅でもかまわない。ただそれが「実物」を髣髴させるように描かれてあれば、それで人びとは満足し、感嘆すらしたのである。だが人は、いったい何に満足し、何に感嘆したのだろうか。
同じ将軍の顔を描き出した肖像画が何枚もあるとする。おそらく当時の人びとは、描き出された姿が本物の将軍に似ていればいるほど、喜びもすれば、感嘆もしたに相違ない。現在でも多くの人びとがそのような反応を示す。では、それほどまで本物に似ている方がよいというのなら、紛れもない本物の将軍に出会ったら感嘆のあまり卒倒でもしなければならないところだが、事実はしかし逆であって、本物の将軍に「美的感動」を覚える人はまずないであろう。とすれば、誰からも感心されない将軍の姿のいわば「影」にすぎないその肖像画を、それもそれが本物に似ているからという理由で讃美するとは、何とおかしなことではないか、というのがパスカルの言い分である。
だが人びとが「実物」よりも「影」の方にいっそう惹かれたということは、それなりに理由があったはずである。その理由を探るためには、「実物」と「影」とのあいだに、どのような本質的な差異があるのか、もっと具体的に言えば、「実物」から「影」へと移行する過程において、いったいなにが失われてなにがつけ加えられたのか、それを明確にしなければならない。
失われたものはあきらかである。それは、将軍というひとりの人間の持っている物質性、その重み、その実体、現実の世界のなかに生きていて、呼吸し、喋舌り、動き回る存在としての将軍である。もっとも素朴な、もっとも平凡な意味における「もの」としての将軍の存在である。絵画の世界においては、三次元の空間に存在する「もの」としての将軍の実体はかんぜんに失われる。描かれた将軍の姿は、重さも、厚みも、物質性も持たない。「影」はあくまでも二次元の世界にのみ属しているからである。
絵画が、比喩的な意味でなしに現実の「もの」の影であるということは、絵画の誕生についてプリニウスがその『博物誌』の中で語っているあの美しい伝説によっても明らかであろう。プリニウスの語るところではこうである。ギリシャのコリントスの陶工ブータデスの娘は、自分の恋人が立ち去ろうとする時、何とかして彼の面影を自分のそばにとどめておきたいと思った。そこで娘は、炭を手に持つと、燈火に照らし出された若者の顔が壁の上に落とす影をずっと線でなぞって、その相貌を描き出したという。それが世界の最初の「肖像画」であった。それは文字通り「影」の世界であり、「実物」の不在を補い、「実物」の代わりを勤めるためのものであった。
同じような考えは、レオナルド・ダ・ヴィンチにも指摘することができる。彼はその「手記」の中で、
最初の絵画は、太陽によって壁の上に作られた人間の影の輪郭をたどった線にすぎなかった・・・・・・。
と書き残しているからである。
ギリシャの伝説の娘が壁の上に描きとどめたという若者の肖像は、単なる一本の線にすぎなかった。だが、それが、「実物」の世界の「代り」であり、実物を思い出させるためのものであるとしたら、単なる輪郭線だけではなく、本物の世界に見られるさまざまの性質を備えていた方がいっそう効果的であるあることはいうまでもない。眼や、鼻や、唇などの細部の描写、柔らかい肌の色合いやかすかにそれと認められる頬の翳り、豊かな髪の毛のうねりなどをそれらしく描き出せば、「影」はそれだけ「実物」に近くなる。レオナルドは、「影」を「実物」に似せて描き出す技術において、もっとも卓越した腕の持主のひとりであった。しかしそのレオナルドの《モナ・リザ》でさえ、実体のない「影」の存在であるという点では、ギリシャの伝説の娘とたどたどしい炭の線の跡と何ら変わりはなかった。ただ《モナ・リザ》の画面には、いっそう多くの現実の部分が入り込んでいるだけである。だがいずれの場合においても、「実物」の世界だけが持っている三次元の空間存在としての「もの」の実体は失われてしまっている。
肖像画が、「実物」の世界から何ものかが失われただけのものであったなら、パスカルならずとも「空しい」と思わずにはいられないだろう。「実物」が少しも面白くないのに、それからさらに何かが失われたものが興味を呼び得るはずがない。しかし、《モナ・リザ》は、いやあのギリシャの娘のたどたどしい線ですら、「実物」の世界の持たない別のものを持っている。それは、娘が恋人の面影を描き出したという壁そのものと共通の特質、すなわち二次元の平面としての特質がそれである。
十七世紀の将軍の肖像にも、《モナ・リザ》にも、ギリシャの娘の壁の線にも共通して見られるなにものかがあるとすれば、それはまさに、平面における形と色の世界というこのことであろう。そしてこの特質こそが、三次元の空間の中の存在である「実物」と絵画とを決定的に分けるものなのである。
現実の世界と深いかかわり合いは持ちながら、現実の世界とはまったく別の、いわば実体を持たない「影」の世界としての絵画の特性、それをわれわれは「イマージュ」の世界と呼ぶことにしたい。それに対し、先ほどから「実物」という言葉であらわして来た現実のものの世界、それは「オブジェ」の世界と呼んでもよいものであろう。」高階秀爾『20世紀美術』ちくま学芸文庫1993.pp.30-34.
絵とは何であるか?「イマージュ」と「オブジェ」について、パスカルから始めたこの文章の密度は高い。