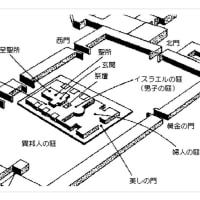「さて、~御霊の賜物についてですが」と、コリントの教会の人たちの質問にパウロは答えようとする。御霊を巡って、種々の混乱があったからである。古代世界では、神々と特別に深いかかわりを持つ人たちは、特別な霊的な賜物を持っていると考えられていた。しかし実際には、そこには本物の経験があると同時に、異常に興奮しただけの自己満足的な経験もありうることだろう。そこでパウロは、恍惚的な熱狂ぶりが、そのしるしであると見なす、教会の雰囲気に対して、本物の霊の賜物のしるしがどういうものであるかを語ろうとする。
その第一は、イエスの主権を認めることにある(3節)。どうやら、コリントの教会には「イエスはのろわれよ」と語る者がいたらしい。それは、回心する以前のパウロ的なユダヤ人であったのだろう(使徒26:11)。あるいは、私たちのためにのろわれたイエス・キリストを(ガラテヤ3:13)覚えて、陶酔と熱狂の最中でそのようにキリスト者が口走ったのかもしれない。しかし、パウロは、本当の霊性は、「イエスは主です」と告白するところに現れるのだ、それが正しいことである、と指摘する。
次に、御霊を与える主は一つであるが、御霊の現われ方は様々である、という(6、7節)。しかし、多様ではあるが、それは一つになり成熟するための分配である、という(12節)。パウロは、この考え方を他の書簡においても繰り返している。たとえば、ローマ人への手紙においては、一致(12:1-5)、多様性(12:6-8)、成熟(12:9-21)という形で、またエペソ人への手紙においても、一致(4:1-6)、多様性(4:7-12)、成熟(4:13-16)という形で、繰り返している。教会は、多様な賜物を持った人々の集まりであるが、それは、キリストにあって一致し、成熟しつつ神のみこころを実現していく場なのである。
人間にはそれぞれ親譲りの才能がある。蛙の子は蛙と言うが、スポーツや音楽、芸術、など、親譲りの才能が子どもに開花することがある。同じように、神を信じた時に、私たちは神の子とされるのだから、神譲りのもの、つまり御霊の賜物があって当然だろう。大切なのは、人はしばしば、才能を自己満足、自己顕示のために用いようとする。しかし、神によって与えられる賜物は、7節「みなの益となるために」とあるように、教会全体の益と喜びのために与えられ、用いるべきものだ、ということだ。御霊の賜物は、それぞれの霊的な成熟に役立つように神から与えられているのである。だからそれは神に奉仕するために用いられなければならない。
ところで勘違いしてはいけない。私たちは一致するが一様になるのではない(12:14-31)。異なった者でありながら一致していくのである。多様性のない一致は画一化に過ぎない。パウロは、人間の体を例に、キリストの体である教会の多様性について説明する。一つは、多様性は固有性であるという(14節)。キリスト教会は賜物をあまりにも狭く考え来た嫌いがある。それは、教会音楽であったり、説教であったりといわば非常に目立つ類のものに限られて考えられ、だから私には賜物がない、という議論もなされたりするところがある。しかし、物事を綺麗に整理したり、壊れたものを修理したり、いつも通りの環境を整えるいわば営繕の働きが苦なくできることも賜物であるし、俳優の世界には名わき役というものがあるように、人を支えることもまた賜物であるし、そう考えると、目立たないが、重要な賜物のある人はたくさんいるのであり、固有性ということの意味は、それぞれが違っている状況のままに、用いられるということでもあるのだ。確かに信者それぞれはキリストの体において固有の器官であり、まったく異なる存在である。一人一人の感じ方、性質、振る舞いのみならず、能力や技術もそれぞれが違う。違うからこそ互いに互いを必要とする。誰も皆、この箇所をよく読みながら、自分の教会における役割の重要さ、必要性を再認識すべきである。
そういうわけであるから多様性は必然的に協力を求める(21-26)。神の業は、互いに手を取り、互いに協力し合う共同体の中に表されるのである。賜物に優劣はない。そして最後に多様性は、単なる個性ではない、神に与えられる多様性である(27-31)。つまり神に起源を発しているのであるから、神の目的に沿って自分の役割を考え、他人の役割をサポートし、神の目的を実現するものである。だから、賜物にも秩序がある。使徒、預言者、教師、…とあるが、それは序列ではない。教会が神の目的に沿って機能するために、それぞれの立ち位置がある、ということだろう。そういう意味で、信仰を持ったら自己実現だけを考える人生から早く脱却しなくてはいけない。信仰者には、神の大目的を果たす使命が与えられている。クリスチャン一人ひとりが、自分の役割に目覚めていくならば、一つ一つの教会が祝福されるのである。