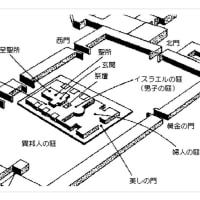「主よ。私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで、聞いてくださらないのですか」(1節)ハバククは、自らを預言者と語る。しかし、開口一番、神のことばを民に伝えようとするのではなく、逆に、神に訴えを起こしている。つまり、これまでの預言者と異なるのは、自らの祈りをメッセージとしているところである。
ハバクク書の歴史的な背景はあまりはっきりとしていない。1:6のカルデヤ人という表現は、おそらく、弱体化したアッシリヤ帝国を滅ぼした新バビロニヤ帝国ではないか、と考えられている。BC612年、バビロニヤとメディアの連合軍はアッシリヤ帝国の首都ニネベを陥落させ、アッシリヤ帝国はハランで滅亡した(BC609年)。その数年後(BC605年)には、二大大国エジプトと新バビロニヤがカルケミシュで戦い、新バビロニヤが勝利を収め、やがてネブカデネザル2世が登場することになる。イスラエルでは、偶像を排除し、宗教改革が行われたヨシヤ王の死後、つまりエホヤキム王の治世で、預言者エレミヤが活動した時代である。すでに、エレミヤは20年間の長きにわたって「主の言葉」を語り伝えていたが、民は主の言葉に「聞かなかった」(エレ25:3)のであり、その背教と堕落の故に、神はイスラエルをカルデヤ人によって処罰されたのである。
しかし、なぜカルデヤ人なのか。ハバククの祈りと疑問はそこに発せられている。カルデヤ人は、勢いがあるだけではない。彼らは「自分自身で裁きを行い、威厳を現す」つまり、自分の力を礼賛し、自分を掟とし、あらゆる権威を侮る高ぶった者たちである。自分を神とする者ではないか。自己の野蛮な力におごり高ぶっている者を、どうして、「あまりきよくて、悪を見ず」というはずの神は、用いられているのか。まるで人間を「海の魚」のようにきまぐれに釣り針で釣り上げ、網で引きずり上げ、楽しむ、そういう残酷なことを許されるのか、という訴えである。
これまでの預言者はどちらかといえば、神の裁きをそのまま語り伝えており、神の裁きの手法について異議を唱える者はいなかった。神がカルデヤ人を用いられるのは当然のことであった。ユダが悪い。その一言であった。しかしハバクク書は、たとえ裁きがやむを得ないものとしても、その裁きにおいて神が用いられる器についての率直な疑問を寄せている。もし神に裁かれるのならば納得できる方法で裁かれたいというわけだ。どうしてあんなやつに、懲らしめられることが裁きになるのか、ということだろう。2章以降は、ハバククの疑問に対する答えとなっている。
ともあれ、聖書は、悪を正す、正義を語る、こうした事柄を単純に扱っていないところに、安心感を得る思いがする。神は人間の様々な感情、ある意味では寄り道的な感情すら無視されることはない。そういう神であればこそ、素直に、神の声に耳を傾ける思いにもなることだろう。
私たちの思いの中にあることを、素直に神に申し述べることが大切である。神に訴え、神に叫び、神の答えを得ることが人間の特権でもある。自らの思いを、余すところ無く神に語りつつ、歩ませていただこう。
ハバクク書の歴史的な背景はあまりはっきりとしていない。1:6のカルデヤ人という表現は、おそらく、弱体化したアッシリヤ帝国を滅ぼした新バビロニヤ帝国ではないか、と考えられている。BC612年、バビロニヤとメディアの連合軍はアッシリヤ帝国の首都ニネベを陥落させ、アッシリヤ帝国はハランで滅亡した(BC609年)。その数年後(BC605年)には、二大大国エジプトと新バビロニヤがカルケミシュで戦い、新バビロニヤが勝利を収め、やがてネブカデネザル2世が登場することになる。イスラエルでは、偶像を排除し、宗教改革が行われたヨシヤ王の死後、つまりエホヤキム王の治世で、預言者エレミヤが活動した時代である。すでに、エレミヤは20年間の長きにわたって「主の言葉」を語り伝えていたが、民は主の言葉に「聞かなかった」(エレ25:3)のであり、その背教と堕落の故に、神はイスラエルをカルデヤ人によって処罰されたのである。
しかし、なぜカルデヤ人なのか。ハバククの祈りと疑問はそこに発せられている。カルデヤ人は、勢いがあるだけではない。彼らは「自分自身で裁きを行い、威厳を現す」つまり、自分の力を礼賛し、自分を掟とし、あらゆる権威を侮る高ぶった者たちである。自分を神とする者ではないか。自己の野蛮な力におごり高ぶっている者を、どうして、「あまりきよくて、悪を見ず」というはずの神は、用いられているのか。まるで人間を「海の魚」のようにきまぐれに釣り針で釣り上げ、網で引きずり上げ、楽しむ、そういう残酷なことを許されるのか、という訴えである。
これまでの預言者はどちらかといえば、神の裁きをそのまま語り伝えており、神の裁きの手法について異議を唱える者はいなかった。神がカルデヤ人を用いられるのは当然のことであった。ユダが悪い。その一言であった。しかしハバクク書は、たとえ裁きがやむを得ないものとしても、その裁きにおいて神が用いられる器についての率直な疑問を寄せている。もし神に裁かれるのならば納得できる方法で裁かれたいというわけだ。どうしてあんなやつに、懲らしめられることが裁きになるのか、ということだろう。2章以降は、ハバククの疑問に対する答えとなっている。
ともあれ、聖書は、悪を正す、正義を語る、こうした事柄を単純に扱っていないところに、安心感を得る思いがする。神は人間の様々な感情、ある意味では寄り道的な感情すら無視されることはない。そういう神であればこそ、素直に、神の声に耳を傾ける思いにもなることだろう。
私たちの思いの中にあることを、素直に神に申し述べることが大切である。神に訴え、神に叫び、神の答えを得ることが人間の特権でもある。自らの思いを、余すところ無く神に語りつつ、歩ませていただこう。