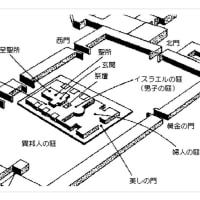既にパウロは、私たちが神の奴隷ではない、神の子なのだ、と語った。私たちは奴隷の子ではなく自由の子なのである。1,2章においては、自由の子とされたパウロの個人的な事情が語られた、3,4章においては、自由の子とされたパウロが持っている自由の福音が語られた。5章からは、自由の子とされた福音の実践について語ろうとする。
パウロは言う。「あなたがたは堅く立って、再び奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい」と。そしてその自由の実践を語る前に、3,4章を要約する信仰理解を明確にする。つまり、キリスト教信仰にキリスト以外の何も要求されない。もし、割礼をプラスアルファの行為として受けようとするなら、キリストは何の意味もない(2節)。割礼を受けるなら、他のものだって、つまり律法全体をきっちり行うべきだ(3節)、いや、律法で神の愛顧を受けようとするなら、結局はキリストの十字架の恵みを無駄にするのだ(4節)。キリストにある信仰者は、敬虔な生活に必要な一切を信仰によって、上から得るのだ(5節)。大事なのはキリストといのちある関係を持つこと、信仰によってつながっていることだ、というわけである(6節)。
そして再び、パウロは、ガラテヤ人の現実に思いを寄せている。一体どうしてこんな問題が起こってしまったのか。どうして、真理から脱線してしまったのか。あなた方を惑わしたものは裁きを受けるであろう。いや、いっそう割礼だ、などと言っていないで「切除」したらいいのだ。パウロの感情の高ぶりもここまでか、という表現である。ガラテヤの読者は、異教の女神キュベレの祭司たちが、自らを去勢していたことを知っていた。パウロは、おそらくその知識に訴えたのであろう。あなたがたが言っていることやっていること、異教の女神キュベレの信仰者と変わらない。あなたがたが、霊的な無知蒙昧と見る異教信者と同じだ、と。
注意すべきところではないか。私たちが、キリスト教の十字架の恵みを語りながら、キリスト以外のものを付け加えて、神の愛顧を得ようとし、さらに敬虔な信仰生活を完成させようとするならば、それは、仏教徒、イスラム教徒と何ら変わらないのである。
続いてパウロは第二の主題に移る。13節、兄弟たちよ。あなたがたは自由を与えられるために召された。しかし、それは、アンティノミニズム(反律法主義)ではない。神に受け入れられる基礎として律法とその奴隷状態から自由にされたといっても、放縦を許しているわけではない。自由気ままに、好むままの生活ができることを言っているわけではない。神の子は、愛に生きるのだ。キリスト者の自由は、愛を基調とする。つまり、キリストの愛によって解放された私たちは、そのキリストの愛に生きるように召されているのである。愛という観点から自分の生き方を統制することである。父を愛する、母を愛する、子を愛する、教師を愛する、生徒を愛する、同僚を愛する、部下を愛する、上司を愛する、夫を愛する、妻を愛する、そして神を愛する、そういう観点から自分の行動を決定していくことである。しかもその愛は、上から与えられる愛である。御霊の実として与えられる。もっと人間的なサイドから言えば、信仰によって結ぶ実である。
パウロは言う、「あなたがたは自由を与えられるために召されたのです」(13節)ギリシア語原文の直訳は「あなたがたは、自由へと召されている」である。つまり、私たちは自由へと向かっているのであって、まだ自由を掴んでいない。確かに、キリスト者になっても、私たちの心には依然として自己中心な性質が巣食っている。神に与えられている時間も、財産も、才能も、ただひたすら自分のためにだけ使いたいという深い罪の思いに縛られている。罪の性質は習慣化され、フロイト的に言うならば、無意識のレベルにまで根付いている。だから、罪がわかった。じゃ、その罪を捨てようと言っても、そう簡単には行かない。私たちは救われた、と過去形で自分の救いを表現するが、実際には肉の思いは深く、ローマ7章にあるように、その肉の心を満足させようとして生きている現実にぶちあたるものだ。しかし、大切なのはその現状認識であり、そういう現実から、キリストの御霊により頼む、信仰による自由へ召されていることを理解することだ。
私たちの力ではどうにもならないからこそ、キリストの御霊に頼るのである。私たちが自分のしたいことが何一つできないのは、肉の欲に心を委ねているからである。だから、むしろ、キリストの御霊にこそ、心を向け、御霊の導きを受けて歩むことに、集中することが救いであり、解放である、とパウロは言う(18節)。
19、20節と、22、23節は、肉の行いと御霊の実が対比されている。肉の行いは、四つの領域で語られる。性、宗教、人間関係、そして飲酒である。一方御霊に導かれて結ぶ実は、三つの領域で語られる。一つは、神に対する愛、喜び、平安、人に対する寛容、親切、善意、そして最後に、自分に対する誠実、柔和、自制である。こうした実は、まさに御霊に生きることによって結ばれる。大切なのは、キリストが与えられるいのちに対する信頼である。私たちは、しらけたキリスト者になってはいけない。神が自分の祈りに答えてくださるという確信を失った、中途半端なキリスト者になってはいけない。私たちの罪の心は全力で、人を愛する力を阻止しようとするが、神様が愛しなさいと言う以上、私たちにはそれが出来ることを信じなくてはならない。神が自分の内になしてくださることを、静かに見守る信仰が必要とされている。神は、確かに罪の深みから、私たちを救ってくださるお方である。神の御霊の導きに従い、御霊の業に期待する歩みをさせていただこう。
パウロは言う。「あなたがたは堅く立って、再び奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい」と。そしてその自由の実践を語る前に、3,4章を要約する信仰理解を明確にする。つまり、キリスト教信仰にキリスト以外の何も要求されない。もし、割礼をプラスアルファの行為として受けようとするなら、キリストは何の意味もない(2節)。割礼を受けるなら、他のものだって、つまり律法全体をきっちり行うべきだ(3節)、いや、律法で神の愛顧を受けようとするなら、結局はキリストの十字架の恵みを無駄にするのだ(4節)。キリストにある信仰者は、敬虔な生活に必要な一切を信仰によって、上から得るのだ(5節)。大事なのはキリストといのちある関係を持つこと、信仰によってつながっていることだ、というわけである(6節)。
そして再び、パウロは、ガラテヤ人の現実に思いを寄せている。一体どうしてこんな問題が起こってしまったのか。どうして、真理から脱線してしまったのか。あなた方を惑わしたものは裁きを受けるであろう。いや、いっそう割礼だ、などと言っていないで「切除」したらいいのだ。パウロの感情の高ぶりもここまでか、という表現である。ガラテヤの読者は、異教の女神キュベレの祭司たちが、自らを去勢していたことを知っていた。パウロは、おそらくその知識に訴えたのであろう。あなたがたが言っていることやっていること、異教の女神キュベレの信仰者と変わらない。あなたがたが、霊的な無知蒙昧と見る異教信者と同じだ、と。
注意すべきところではないか。私たちが、キリスト教の十字架の恵みを語りながら、キリスト以外のものを付け加えて、神の愛顧を得ようとし、さらに敬虔な信仰生活を完成させようとするならば、それは、仏教徒、イスラム教徒と何ら変わらないのである。
続いてパウロは第二の主題に移る。13節、兄弟たちよ。あなたがたは自由を与えられるために召された。しかし、それは、アンティノミニズム(反律法主義)ではない。神に受け入れられる基礎として律法とその奴隷状態から自由にされたといっても、放縦を許しているわけではない。自由気ままに、好むままの生活ができることを言っているわけではない。神の子は、愛に生きるのだ。キリスト者の自由は、愛を基調とする。つまり、キリストの愛によって解放された私たちは、そのキリストの愛に生きるように召されているのである。愛という観点から自分の生き方を統制することである。父を愛する、母を愛する、子を愛する、教師を愛する、生徒を愛する、同僚を愛する、部下を愛する、上司を愛する、夫を愛する、妻を愛する、そして神を愛する、そういう観点から自分の行動を決定していくことである。しかもその愛は、上から与えられる愛である。御霊の実として与えられる。もっと人間的なサイドから言えば、信仰によって結ぶ実である。
パウロは言う、「あなたがたは自由を与えられるために召されたのです」(13節)ギリシア語原文の直訳は「あなたがたは、自由へと召されている」である。つまり、私たちは自由へと向かっているのであって、まだ自由を掴んでいない。確かに、キリスト者になっても、私たちの心には依然として自己中心な性質が巣食っている。神に与えられている時間も、財産も、才能も、ただひたすら自分のためにだけ使いたいという深い罪の思いに縛られている。罪の性質は習慣化され、フロイト的に言うならば、無意識のレベルにまで根付いている。だから、罪がわかった。じゃ、その罪を捨てようと言っても、そう簡単には行かない。私たちは救われた、と過去形で自分の救いを表現するが、実際には肉の思いは深く、ローマ7章にあるように、その肉の心を満足させようとして生きている現実にぶちあたるものだ。しかし、大切なのはその現状認識であり、そういう現実から、キリストの御霊により頼む、信仰による自由へ召されていることを理解することだ。
私たちの力ではどうにもならないからこそ、キリストの御霊に頼るのである。私たちが自分のしたいことが何一つできないのは、肉の欲に心を委ねているからである。だから、むしろ、キリストの御霊にこそ、心を向け、御霊の導きを受けて歩むことに、集中することが救いであり、解放である、とパウロは言う(18節)。
19、20節と、22、23節は、肉の行いと御霊の実が対比されている。肉の行いは、四つの領域で語られる。性、宗教、人間関係、そして飲酒である。一方御霊に導かれて結ぶ実は、三つの領域で語られる。一つは、神に対する愛、喜び、平安、人に対する寛容、親切、善意、そして最後に、自分に対する誠実、柔和、自制である。こうした実は、まさに御霊に生きることによって結ばれる。大切なのは、キリストが与えられるいのちに対する信頼である。私たちは、しらけたキリスト者になってはいけない。神が自分の祈りに答えてくださるという確信を失った、中途半端なキリスト者になってはいけない。私たちの罪の心は全力で、人を愛する力を阻止しようとするが、神様が愛しなさいと言う以上、私たちにはそれが出来ることを信じなくてはならない。神が自分の内になしてくださることを、静かに見守る信仰が必要とされている。神は、確かに罪の深みから、私たちを救ってくださるお方である。神の御霊の導きに従い、御霊の業に期待する歩みをさせていただこう。