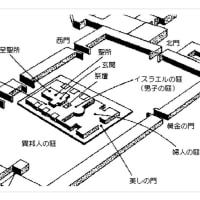<朝のディボーション>
「やみの中を歩んでいた民は、大きな光を見た」(2節)。人が辿る闇は、しばしば一瞬ではない。それは、何年も、いや何十年も、このまま人生が終わってしまうのではないか、と思うほどに、長く深い闇であったりする。そういう中で人は人生を諦めかけてしまうし、諦めてはいけない、と自分に語りかけることにも疲れてしまうことがある。
「ゼブルンの地とナフタリの地」は、ガリラヤ湖北方の領域で、まずアッシリヤの侵攻を受けた土地である。しかしその同じガリラヤに、今度は、神の恵みが真っ先に下される、と言う。アッシリヤに蹂躙され、苦しめられたその土地に、今度は、キリスト降誕の恵みがもたらされる。それは、これから起こる近い未来と遠い未来の二重預言となっている。
その神の恵みは、「ひとりのみどりごが、私たちのために生まれ」、私たちの重荷をその肩に担ってくださることによって現されるのである。その人物は、「不思議な助言者」である。意味的には人間的なものを遙かに超えた超自然的な知恵の提供者ということだろう。人間的な知恵によって国家を滅びに至らせたアハズ王のようではない。むしろ「力ある神」つまり、神そのものである。そして「永遠の父」。人間の支配は断続的であるが、この王は、永続する統治権を行使する。しかも父としての配慮と訓練を示す王である。「平和の君」完全な統治を実現する王が、私たちに与えられる意だろう。それは、万軍の主の熱心によって実現することである。神が不動の決意を持って、何事にも妨げられず実現することであるという。これはキリストにおいて実現したと理解すべきなのだろう。
<夜のディボーション>
さて8節以降11章6節までは、イザヤ書特有の書き方で、7章1節から9章7節までを別の観点から繰り返し印象づけようとするものである。先にイザヤはユダのために語ったが、今度はイスラエルに対して語っている。エフライムは北王国で最も重要な部族なので北イスラエル王国の代名詞として用いられる事が多い。エフライムは高ぶり、神を信頼しようとせず、むしろ自分達の力に拠り頼んだ。彼らは、れんがが駄目になったらもっと高価な切石で、いちじく桑が駄目になったらもっと高価な杉の木で、と立て直せると(10節)自信のほどを示している。ただ、すべてを握るのは神である。神は、「レツィンに仇する者たち」つまりアッシリヤの王を敵とし、これを裁くと言う。
しかしそれでも、イスラエルは悔い改めない。本来ならば悔い改めへと導かれるところであるが、それが人間の愚かさである。人間は神の裁きを受けて、苦しい目にあっても、悔い改めることができずにいる。謙虚になれず、神を尋ね求めることができない。こうして神の御怒りは、私たちの上に留まり続けることになる。神の裁きを感じる時に、私たちがしなければならないことは、その裁きに腐り果てることでも、弱ってしまうことでもなく、素直に悔い改めることである。裁き主である神に素直に心を開き、神を心から尋ね求めることであろう。確かに私たちにみどりごを与えてくださり、私たちの生活に平和を取り戻し、それを永遠のものとしてくださる神を信頼することである。
「やみの中を歩んでいた民は、大きな光を見た」(2節)。人が辿る闇は、しばしば一瞬ではない。それは、何年も、いや何十年も、このまま人生が終わってしまうのではないか、と思うほどに、長く深い闇であったりする。そういう中で人は人生を諦めかけてしまうし、諦めてはいけない、と自分に語りかけることにも疲れてしまうことがある。
「ゼブルンの地とナフタリの地」は、ガリラヤ湖北方の領域で、まずアッシリヤの侵攻を受けた土地である。しかしその同じガリラヤに、今度は、神の恵みが真っ先に下される、と言う。アッシリヤに蹂躙され、苦しめられたその土地に、今度は、キリスト降誕の恵みがもたらされる。それは、これから起こる近い未来と遠い未来の二重預言となっている。
その神の恵みは、「ひとりのみどりごが、私たちのために生まれ」、私たちの重荷をその肩に担ってくださることによって現されるのである。その人物は、「不思議な助言者」である。意味的には人間的なものを遙かに超えた超自然的な知恵の提供者ということだろう。人間的な知恵によって国家を滅びに至らせたアハズ王のようではない。むしろ「力ある神」つまり、神そのものである。そして「永遠の父」。人間の支配は断続的であるが、この王は、永続する統治権を行使する。しかも父としての配慮と訓練を示す王である。「平和の君」完全な統治を実現する王が、私たちに与えられる意だろう。それは、万軍の主の熱心によって実現することである。神が不動の決意を持って、何事にも妨げられず実現することであるという。これはキリストにおいて実現したと理解すべきなのだろう。
<夜のディボーション>
さて8節以降11章6節までは、イザヤ書特有の書き方で、7章1節から9章7節までを別の観点から繰り返し印象づけようとするものである。先にイザヤはユダのために語ったが、今度はイスラエルに対して語っている。エフライムは北王国で最も重要な部族なので北イスラエル王国の代名詞として用いられる事が多い。エフライムは高ぶり、神を信頼しようとせず、むしろ自分達の力に拠り頼んだ。彼らは、れんがが駄目になったらもっと高価な切石で、いちじく桑が駄目になったらもっと高価な杉の木で、と立て直せると(10節)自信のほどを示している。ただ、すべてを握るのは神である。神は、「レツィンに仇する者たち」つまりアッシリヤの王を敵とし、これを裁くと言う。
しかしそれでも、イスラエルは悔い改めない。本来ならば悔い改めへと導かれるところであるが、それが人間の愚かさである。人間は神の裁きを受けて、苦しい目にあっても、悔い改めることができずにいる。謙虚になれず、神を尋ね求めることができない。こうして神の御怒りは、私たちの上に留まり続けることになる。神の裁きを感じる時に、私たちがしなければならないことは、その裁きに腐り果てることでも、弱ってしまうことでもなく、素直に悔い改めることである。裁き主である神に素直に心を開き、神を心から尋ね求めることであろう。確かに私たちにみどりごを与えてくださり、私たちの生活に平和を取り戻し、それを永遠のものとしてくださる神を信頼することである。