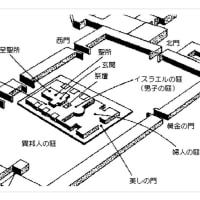3章 遣わされるエゼキエル(3:12-27)
おはようございます。神の召命に立っていくエゼキエル、彼と神の対話に、神の誠実さ、救いの計画に対する責任感の深さを私は感じます。このお方について行って大丈夫だと。今日も、主の恵みを信頼し、支えられる豊かな一日であるように祈ります。主の平安
1.神も冗談を言われる
神がエゼキエルを遣わそうとする民は、難しい外国語を話す民ではない、同胞である、ただ鉄面皮の同朋だと言うわけです。いくら語り掛けても、耳を傾けようとしない人々に、彼は語らなくてはならなかったのです。なんとも大変な使命ではないでしょうか。そこで神は言います。ユダヤ人は鉄面皮だから、あなたの面の皮も厚くしよう、と(8節)。「堅く」するはヘブル語でハーザーク、そう語りかけられたエゼキエル自身の名は「神が堅くする」を意味します。ですからここには意味の語呂合わせがあるわけです。昔、平安時代の平家一門の武将に、平忠度(ただのり)薩摩守という人がいました。そこで「無賃乗車する人」のことは「薩摩守」と言われることがあります。「音」ではない「意味」の語呂合わせですが、神は、ここで困難な宣教に向かうエゼキエルに冗談を交わしているのです。
しかしエゼキエルは「笑えない」のです(14節)。心は神の霊に燃やされても、やはり心頑なな民に語る現実を考えるなら、心の負担は大きかったと言うべきでしょう。ただ、14節で「苦々しい」と訳されたヘブル語は激しい気質あるいは怒り、子を奪われた雌グマのような(2サムエル17:8)殺気立った状態を意味しています。新共同訳では、「怒りに燃える心を持って」と訳しています。つまり、明らかに失敗するとわかりきった宣教の働きを委ねられて、エゼキエルは冗談じゃないよ、と腹を立てているわけではなく、むしろ、神の義なる怒りに巻き込まれたと言うべきです。冗談交じりで言う神の心の奥深い思いに共感し、神の義なる憤りを共有した、というわけです。
2.宣教に備えるエゼキエル
エゼキエルは、テル・アビブの捕囚の民の所へ戻りました。彼はそこで七日間茫然自失であったと言います。改めて目いっぱいハードルの高いチャレンジに、決意を固める重要な時間であったのでしょう。神の民の礼拝の再建を成し遂げたエズラも、その働きの前に同じような経験をしています(エズラ9:4)、また異邦人伝道に召された使徒パウロも、ダマスコへの途上、復活の主と出会いただ静められる時を持ったのに似ています(使徒9:9)。それはまさに預言者としての困難な働きに、備えられる時でした。
3.鉄面皮であってはならない
主はエゼキエルを「イスラエルの家の見張り人」(17節)として召されました。「見張り人」は主の預言者として、迫ってくる危険を見て警告する任務を負います(17b)。大切なのは、聞こうが聞くまいが、語り続けることです。それは、聞く意思を持たない人々に対する任務であり、全く割に合わない働きであることは確かなことですが、だからといって、手加減もサボリも許されないのです(18-21節)。結果の良し悪しは問われていません。ただ彼は語り続けなくてはなりませんでした。しかも、神は、働きを委ねて後はよろしく、と言うような方ではありません。「語る時に、あなたの口を開く」(27節)とあるように、その働きを一緒に担ってくださる、と言うのです。このようなところに、神の誠実さ、神の救いの計画に対する責任感の強さを私は感じます。
こうしてエゼキエルは魂の見張り人として立ちましたが、これは現代の牧会者も同じでしょう(ヘブル13:17)。牧会者が神のことばを語るのは、たましいの見張り人としてです。その働きの前に、信徒は「鉄面皮」と「神に」言われる者であってはなりません。自ら進んで心を開き神のことばに向かいたいところです。