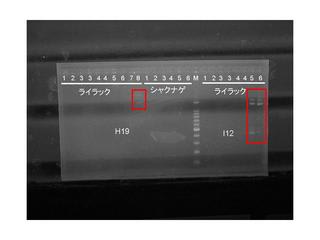・学会最終日。本日は育種関連の研究会が二つ。当方はバイテク林木育種研究会の世話人になっているため,最後まで気が抜けない。前半の育種研究談話会では,精英樹をテーマにした発表で,歴史的な経緯が詳細に分かり,大変勉強になった。また,Mくんによる地域差検定林の話は分かりやすい上に,結構インパクトがあった。今度の講義では,早速,仕入れたネタを元に林木育種の話をするとしよう。
・バイテク林木育種研究会では,「品種登録」というおよそバイテクとは関係なさそうなネタであったが,想像以上にたくさんの人が集まってくれた。いつも,昼時に人が少なくなった後,午後から人が集まるのか不安になるのがこの研究会の辛いところだ。品種登録というのは,育種に携わった人ならば「一度はやってみたい」というイベントである。しかし,「なんか大変そう」というので、つい尻込みしてしまうわけだが,これを少しでも軽減したい、というのが研究会の趣旨である。
・最初に,全体的な種苗法の話や登録の要件の話題提供を頂いた後,それぞれの立場で登録をした人たちによる体験談(苦労話)を伺うという流れ。しかし,実際にやってみると,色んな準備が想像以上に大変だった上にトラブルが発生することもある、という話で,「キミにもできる品種登録」というよりは,「キミにもできる?品種登録」という感じ・・・。それでも,具体的に何を準備しておけばよいかとか,どのくらいの期間配布しない方がよいかとか,どうすれば登録できる可能性があるか(どのくらいの特性で既存品種と違いが認められればよいか),など具体的な情報が聞けて、参加者には非常に参考になったのではないだろうか。
・全体を通して,実際には大変な作業になりそうだけど,やっぱり一度は品種登録をしてみたい。本当は「売れる」べき商品を登録すべきところだろうけど,まずは特異な性質を持ったクローンでもいいから挑戦してみたい課題である。しかし,それには実行体制の整備と準備(特に,比較する既存品種と次世代ラメット)を着実にやっておくべきだと肝に銘じておくとしよう。お忙しい中,話題提供してくれた皆さんに感謝!である。
・バイテク林木育種研究会では,「品種登録」というおよそバイテクとは関係なさそうなネタであったが,想像以上にたくさんの人が集まってくれた。いつも,昼時に人が少なくなった後,午後から人が集まるのか不安になるのがこの研究会の辛いところだ。品種登録というのは,育種に携わった人ならば「一度はやってみたい」というイベントである。しかし,「なんか大変そう」というので、つい尻込みしてしまうわけだが,これを少しでも軽減したい、というのが研究会の趣旨である。
・最初に,全体的な種苗法の話や登録の要件の話題提供を頂いた後,それぞれの立場で登録をした人たちによる体験談(苦労話)を伺うという流れ。しかし,実際にやってみると,色んな準備が想像以上に大変だった上にトラブルが発生することもある、という話で,「キミにもできる品種登録」というよりは,「キミにもできる?品種登録」という感じ・・・。それでも,具体的に何を準備しておけばよいかとか,どのくらいの期間配布しない方がよいかとか,どうすれば登録できる可能性があるか(どのくらいの特性で既存品種と違いが認められればよいか),など具体的な情報が聞けて、参加者には非常に参考になったのではないだろうか。
・全体を通して,実際には大変な作業になりそうだけど,やっぱり一度は品種登録をしてみたい。本当は「売れる」べき商品を登録すべきところだろうけど,まずは特異な性質を持ったクローンでもいいから挑戦してみたい課題である。しかし,それには実行体制の整備と準備(特に,比較する既存品種と次世代ラメット)を着実にやっておくべきだと肝に銘じておくとしよう。お忙しい中,話題提供してくれた皆さんに感謝!である。