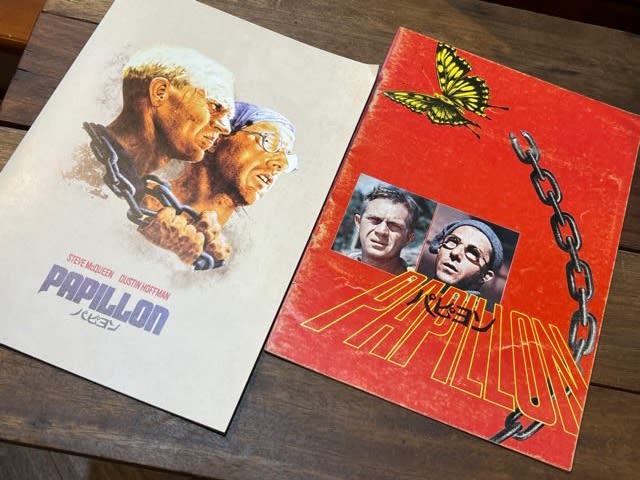もしもカーツ大佐(もしくはウィーラード大尉)をスティーヴ・マックィーンが演じていたら...コレ、あながち妄想ではなくて実際話があったそうです。

※芳賀書店刊「マックィーン・ザ・ヒーロー」より
ウィーラード役だとハマらないし、カーツ役はマーロン・ブランドさんの重厚過ぎる姿を見ているから、それを師匠が演じる姿も想像できないかな。でも観てみたかった気もします。出演していれば間違いなく晩年の代表作になりましたよね。
https://cinemakadokawa.sakura.ne.jp/anfc/
今回一瞬(一週間。一日一回のみ)だけ公開されたのは、デジタル修復が施された『ファイナル・カット』版のIMAX上映。オープニング、ヤシ林がナパームで焼かれるカットに右から左からヘリコプターの音が被り、ドアーズの「ジ・エンド」(初公開時、観てすぐにシングル盤買いました)が流れるシーンから全くの別物でした。
ヘリコプターがホントに劇場内を飛び回っているかのような立体音像。司令部に呼び出されたウィーラード大尉が豪華な食卓を囲むシーン(僕は初公開時このシーンで初めて”ローストビーフ”というものを知りました)で食器がカチャカチャ鳴るところの、どうでも良い生々しいリアル感。
そして何といっても今回のIMAX化の恩恵を一番受けたのは、キルゴア中佐率いる”空の騎兵隊”の奇襲攻撃シーンです。全身トリハダで画面にクギ付けで身動き一つとれませんでした。
映像の鮮明度は言うに及ばず、音の迫力が凄まじかった。ヘリコプターからの映像ではまるで自分も攻撃に参加しているような感覚になり、地上からの映像ではまるで攻撃を受けているような恐怖を感じました。ヴィットリオ・ストラーロさんによるヨーロッパ映画っぽいしっとりとした映像(特にフランス人の農園でのシーン)も美しくて、劇中の惨劇との対比が一層浮かび上がります。
他にも随所の銃撃戦(ジャングルから飛んでくる槍や弓矢の風切り音が耳元をかすめます)やプレイメイトのショウの臨場感(観衆の欲望が塊となって押し寄せる)、任務に飽きてドラムスティックで船体を叩きみんなを一層イラつかせるクリーンのドラミングの耳障りな響き、地元民の運搬船を密輸船だと決めつけて物色する際の全員の息遣いやピリピリする緊張感(これは音がリアルに響くから)。さらにカーツの王国の群衆のザワザワ感やカオスな様子、ずっとハエの羽音がしている(至る所に死体が転がっているんだから当然か)のも初めて気づきました。カーツが暗がりから顔を出し(でも表情は確認できない)、洗面器の水で顔や頭をゆっくりと洗うシーンでの水のパシャパシャって音がとてもキレイ。これもクリアーになった映像もあって良く理解できました。
初めてこの作品を観たのは初公開時(1980年2月)は中学生になる直前でした。オリジナル版の難解さに加え、スクリーンも映写機も古いから、カーツ王国のシーンは暗すぎて何が映っているのかすら分かりませんでした。それ以前に王国での会話やらがあまりにも哲学的すぎて(カーツ曰く「カタツムリが剃刀の刃の上を歩く」云々で、カタツムリは刃の上を歩けるんだってことは知れました)、12歳の少年には酷な作品でした。
その後2001年の「特別完全版」を観て話はようやく理解はできたけど、長すぎて辛かったのも事実。最近上映時間の長い映画が多いけど、せめて2時間30分以内にして欲しいですね。
それが今回の「ファイナル・カット」のIMAX版で、もっと分かり易く(画も音も)なったバージョンが観れたのは幸せでした。やっぱり好きな作品ランキングの上位に入り続けている映画です。
6/13(金)再上映!映画『地獄の黙示録 ファイナル・カット』WEB用予告編
そして奇しくも同じ週に「午前10時の映画祭」で特別上映されていた『ゴッドファーザー』も観ることができました。
https://asa10.eiga.com/2025/cinema/1407/

毎年数回はシリーズを通して観る大好きな作品。きっとこの先も同じように何回も何回も観るんだろうな。何度観ても全く飽きずに毎回新鮮な気持ちで観れる稀有な映画です。今回はマイケルがダークサイドに堕ちていく過程をじっくりと楽しませて頂きました。
『ゴッドファーザー』と言えば、よく年末とかにテレビ洋画劇場で放映されていたときの思い出です。イタリア系の長い名前の登場人物と相関図が良く分からず、ノート片手に名前を書きだしながら観ていました。そのおかげで誰が誰の手下で、誰と誰が仲良しで、誰が裏切ってどうたらこうたら...ていうのが未だに覚えていられるのがプチ自慢です。若い頃に刻まれた記憶ってなかなか消えないもんですね。一昨日の夜ご飯忘れるくせに笑
もう一つ『ゴッドファーザー』の思い出を。
「ぴあ」の上映スケジュールで映画のタイトルを眺めるだけでもオカズになっていた高校生の頃、どうしても映画館で観たくて、わざわざ(各停の鈍行に乗って)東京まで観に行きました。しかもPART1とPART2の同時上映!合わせて375分(6時間半!)。それも早稲田の二番館か三番館の硬い椅子での修行。若さゆえの行動ですね。確か入場料も700円くらいだったはず。40年以上前の話だから当然フィルムでの上映だから、映写室には山のようにフィルムが積んであったんでしょうね。一時期イベントなんかで映写機を回す仕事(16㎜も35㎜も)をしていたので技師さんのご苦労も良く分かります。殆どお客さんも入ってなかった中、ご苦労様でした。
仙台には二番館がありません。できればこんなバカができる二番館があったらなぁ。今なら三部作連続上映も夢じゃないし、そこにいる自分も容易にイメージできます。サブスク全盛の現代だけど、誰か二番館作ってください!