産経新聞の社説「不当な競争制限許されぬ」を読んだが、一面的な考察では?と疑問に感じた。
社説は、「企業向け電力を巡る関西・中国・中部・九州電力がカルテルを結んで自由競争を妨害したことは、自由化に逆行し契約者の利益を損なう行為」と断罪している。
電力については、
・2000年 「特別高圧(大規模工場、デパート、オフィスビル)」部分を自由化
・2004年~ 自由化の範囲を「高圧(中小規模工場・中小ビル)」部分に順次拡大
・ 2016年 家庭用を含む「低圧」部まで全面自由化
となっており、地域の電力(発電)会社からしか購入できなかった電気を、どこの電力会社からでも購入できることになった。
東電地域に住む自分の例でも、ガス会社が仲介した中部電力の電気を使用するという形態であるので、「中部電力(卸問屋)~ガス会社(小売業)~自分」という図式で電気を使用している。
当然に小売業主同士の競争は熾烈で安売り合戦に発展するとともに、卸業となった大手電力会社も卸価格の競争を余儀なくされた結果、電気の安定供給には不可欠の余剰電力と送電網の維持費の全額を卸価格に上乗せできない状態になっている。
電力の完全自由化が末端の利用者にとってバラ色一色かと云えば、そうとも云えない一面を持っているように思える。
平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電の原因は、一部発電所の停止によって電力使用量が発電能力を大きく超えたために周波数が低下したこととされているが、ここにも金にならない余剰電力を局限するために北海道電力が一部発電所を完全停止していたという側面もあると思っている。
電力の小売り業者は、発電能力・送電網の全てを卸会社等に依存する「抱き着きお化け」状態で、停電に対する責任も負えない。もし、地域以外の電力を使用している医療機関で停電に起因する医療事故が発生した場合、責任は発電業者か、送電業者か、小売業者かという曖昧な状態に陥ることは避けられないように思える。
今回の闇カルテルの背景には、従来、地域の電力会社に寡占的に認めていた特権を、発送電の全てに根本的な見直しをすることなく自由化したことが挙げられると思う。自然エネルギーの拡大・原発問題・送電網整備をも含めた総合的な電力行政と電力の在り方を改めて見直す必要があるように思う。
「規制緩和」の名の下に公共事業を含む多くの入札が、受注者の能力・体力を勘案した「随意契約」・「指名競争入札」から、誰でも応札できる「一般競争入札」とされた結果、役務を完遂できない・納期を守れない事案が飛躍的に増加しているとされる。今になっては詮無いことながら、発電能力を持たない小売業者が電気を売ることは適当なのだろうか。自分の契約している卸業者(中部電力)の発電能力を超えて小売業者が販売しているようなことはないだろうか。勧誘に来たセールスマンは、「その時は、東電などから購入します」と云ったが、はてサテ。











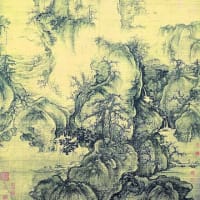








ぼんやりと、同じようなことを考えておりました。規制緩和が全て善という風潮には、??を感じている私です。
これからも警鐘を、期待しております。
コメントを有難うございます。
全般的に商道徳が低下している現状では、性善を前提する規制緩和は再考すべき時期にあるようにも思います。