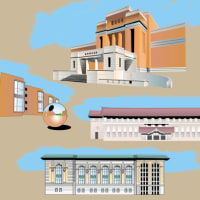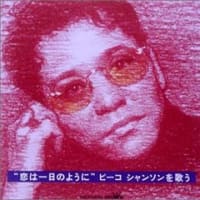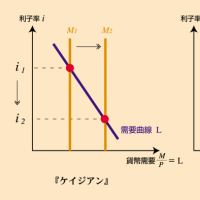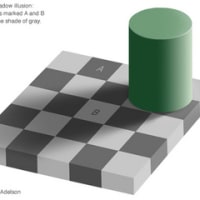今日は上野の国立科学博物館においてイカ・タコ類の研究者であり、昨年に世界で初めて生きている大王イカの撮影に成功した(この大王イカの映像は来週の4月16日にNHK「ダーウィンが来た」でも放送される。)窪寺恒己氏のディスカバリートークが行われた。
大王イカ好きの私としては是非ともこれを聞きかなくてはいけない。
というわけで、今日私は上野に行ってきたのである。
そこで今日はトークで印象に残ったことを以下に書きたいと思う。
属名「大王イカ」、英語名ではGiant Squid、学名はArchiteuthis。
記録に残る最大の個体は、体長13メートル、獲物を捕らえるための触腕を含めた全長が18.7メートルもあったという。
彼らはマッコウクジラの重要な餌でもある。
マッコウクジラの食事内容の調査によると、この大王イカが食糧の重量のかなり大きな割合いを占めていることが分かっている。
マッコウクジラが水深1000メートルまで潜るのはこの大王イカなどの深海生物を補食するためであり、マッコウクジラの顔に時おり巨大な吸盤による傷が残されているのは有名な話である。
深海という秘境に生息する大王イカの生態は謎に包まれている。
だからこそ生きている姿が映像に取られたのは快挙であった。
そんな謎の生物であるから、その総数を正確に知ることは難しい。だが簡単な見積もりならば行うことができる。
まず世界中にマッコウクジラは20万頭いる。
そのマッコウクジラが最低一日に一匹大王イカを食べるとしよう。あの巨体を維持するにはそれくらいは食べなくてはいけない。
すると最低でも7000万匹の大王イカはこの世に存在しており、毎年クジラの胃袋に納まっていることになる。
この時点で既に驚くべき数なのだが、話はこれでは終わらない。
大王イカの全てが餌になるわけはないから、単純にその10倍の数が生息しているとみなしてみる。これは自然界一般に見られる捕食者と獲物のピラミッドを考えれば非現実的な数字ではないであろう。
よってこの計算では少なくとも20万×365×10=7億3000万の大王イカが深海に泳いでいるとみなすことができるのだ。幼体の大王イカも含めるとどれだけの数になるか見当もつかない。
深海に潜む10億のクラーケン共!!
素晴らしきモンスターの群れである。
そんな大王イカは日本近海にも生息している。
昨年撮影に成功したのも小笠原諸島の深海に住む大王イカだ。
日本近海に生息している個体は、先の記録ほど大きくはないが、それでも足を除く胴体部分(外套長)の長さが2メートル、足を含めた体長が5メートル、そして全長が10メートルにもなる。
発見される大王イカはほぼ全てが死体として漂着したものだ。日本では37年間に20匹が漂着している。
その場所は鳥取などの中国地方の沿岸部が多く、冬場、特に2月に集中する。
これは大王イカが寒さで衰弱するためだそうだ。
日本においての最初の大王イカの報告例は江戸時代に行われた展覧会に巨大なイカがあったと外国人の手紙に書かれていたものがある。しかしこれは文字だけの報告で学術的にはあまり意味がない。
より正確な報告としては明治時代初期に生物学者の箕作・池田が東京魚市場に水揚げされた大王イカを調べて論文にしたものがある。それは後に別の外国人研究者により新しい種と認められJaponicaという学名が与えられた。
さて、一般人は大王イカを見ても「うわー、おーきいー、すごーい、これ刺身にすると何人分?」とでも言っていれば済むが、生物学者は「分類」というとても重要な作業をしなくてはいけない。
発見されたArchiteuthis Japonicaには複数の外見の違いが認められる。
それは腕の長短と精嚢の受け渡しをする交接腕の有無で分類できる。
(二列目は外套長と腕の比率、三列目は第四椀が交接腕化するかしないか)
長腕型 1:1.5~1.7 しない
中腕型 1:1.2~1.3 する
短腕型 1:1 する
窪寺氏はこれら3つの型をそれぞれ別の3つの種と考えている。
それに対して別の研究者はこれらを多型的な同一種とみなし1科1種と報告した。
そこで窪寺氏はミトコンドリアのDNAを解析してみたところ、この3つの型の大王イカの塩基配列には3箇所だけしか違いが認められず、ほぼ同一種とみなせてしまうという結論を得た。
自説とは反対の結果である。
だがこの分析したのがDNA全体のごく短い範囲であることや、調査対象である個体数が少なすぎることから最終的な結論を出すことはできない。
窪寺氏は今後も3種説を主張していくつもりのようだ。
(余談)
時おり「学者は中立的であるべきだ」と言い、自説に固持する学者をいけないものと考える人がいるが、むしろ学問の発展の為には各自が自説に固執して、それらの意見同士をぶつけあい競争させた方が効率的である。
なぜなら完璧な学説などというものは存在せず、どんな理論にも問題点や矛盾はあるものだからだ。
それらは実験技術や理論体系の不備ゆえに満足に説明できないだけものもあれば、本質的に間違っているという場合もある。
遺伝の法則を発見したメンデルや微生物の存在を立証したパスツゥールの実験も実は欠点の多いものであったし、ニュートンの古典力学は光速の世界では矛盾だらけの学問である。
しかし遺伝や微生物の存在自体はより正確な実験で確かめられているし、今は光速の世界も正しく記述できる相対論というものがあり古典力学は低速度領域の近似法則としてならば正しいものである。
このように科学の世界では欠点や矛盾がただちにその説を放棄する理由にはならないことがある。
だからもし自説の欠点を指摘されたとしても、学者はすぐに自説を放り出すべきではない。
むしろ誤りを指摘されたのならば、まずは自説に固執し、より精密な実験や理論の不備を修正する努力をするべきである。
それは学者個人には「誤った説に執着して学者人生を棒にふった」という悪夢をもたらすかもしれないが、学問全体から見れば一つの説を十分に検証したという利益をもたらす。
それに中立的な立場というのは、ある意味とても楽なのである。
何故ならそれは何の判断も思考もしなくていいからだ。どの意見にも「もっともだ、もっともだ」と言ってさえいればいいのだから。自分の立場を選択するということは、とても気苦労が多いものなのだ。
しかも中立的立場というのは、ともすると単なる主流派や最大勢力に偏る傾向があり、実は中立でも何でもなくなり、少数派の無視という結果さえ招く。
私が思うに学問でも日常でも大事なことは偏見を持たないことではなく、自分がどのような偏見を持っているのかを自覚し、かつ他人の偏見の存在も認めることなのではないだろうか。
大王イカ好きの私としては是非ともこれを聞きかなくてはいけない。
というわけで、今日私は上野に行ってきたのである。
そこで今日はトークで印象に残ったことを以下に書きたいと思う。
属名「大王イカ」、英語名ではGiant Squid、学名はArchiteuthis。
記録に残る最大の個体は、体長13メートル、獲物を捕らえるための触腕を含めた全長が18.7メートルもあったという。
彼らはマッコウクジラの重要な餌でもある。
マッコウクジラの食事内容の調査によると、この大王イカが食糧の重量のかなり大きな割合いを占めていることが分かっている。
マッコウクジラが水深1000メートルまで潜るのはこの大王イカなどの深海生物を補食するためであり、マッコウクジラの顔に時おり巨大な吸盤による傷が残されているのは有名な話である。
深海という秘境に生息する大王イカの生態は謎に包まれている。
だからこそ生きている姿が映像に取られたのは快挙であった。
そんな謎の生物であるから、その総数を正確に知ることは難しい。だが簡単な見積もりならば行うことができる。
まず世界中にマッコウクジラは20万頭いる。
そのマッコウクジラが最低一日に一匹大王イカを食べるとしよう。あの巨体を維持するにはそれくらいは食べなくてはいけない。
すると最低でも7000万匹の大王イカはこの世に存在しており、毎年クジラの胃袋に納まっていることになる。
この時点で既に驚くべき数なのだが、話はこれでは終わらない。
大王イカの全てが餌になるわけはないから、単純にその10倍の数が生息しているとみなしてみる。これは自然界一般に見られる捕食者と獲物のピラミッドを考えれば非現実的な数字ではないであろう。
よってこの計算では少なくとも20万×365×10=7億3000万の大王イカが深海に泳いでいるとみなすことができるのだ。幼体の大王イカも含めるとどれだけの数になるか見当もつかない。
深海に潜む10億のクラーケン共!!
素晴らしきモンスターの群れである。
そんな大王イカは日本近海にも生息している。
昨年撮影に成功したのも小笠原諸島の深海に住む大王イカだ。
日本近海に生息している個体は、先の記録ほど大きくはないが、それでも足を除く胴体部分(外套長)の長さが2メートル、足を含めた体長が5メートル、そして全長が10メートルにもなる。
発見される大王イカはほぼ全てが死体として漂着したものだ。日本では37年間に20匹が漂着している。
その場所は鳥取などの中国地方の沿岸部が多く、冬場、特に2月に集中する。
これは大王イカが寒さで衰弱するためだそうだ。
日本においての最初の大王イカの報告例は江戸時代に行われた展覧会に巨大なイカがあったと外国人の手紙に書かれていたものがある。しかしこれは文字だけの報告で学術的にはあまり意味がない。
より正確な報告としては明治時代初期に生物学者の箕作・池田が東京魚市場に水揚げされた大王イカを調べて論文にしたものがある。それは後に別の外国人研究者により新しい種と認められJaponicaという学名が与えられた。
さて、一般人は大王イカを見ても「うわー、おーきいー、すごーい、これ刺身にすると何人分?」とでも言っていれば済むが、生物学者は「分類」というとても重要な作業をしなくてはいけない。
発見されたArchiteuthis Japonicaには複数の外見の違いが認められる。
それは腕の長短と精嚢の受け渡しをする交接腕の有無で分類できる。
(二列目は外套長と腕の比率、三列目は第四椀が交接腕化するかしないか)
長腕型 1:1.5~1.7 しない
中腕型 1:1.2~1.3 する
短腕型 1:1 する
窪寺氏はこれら3つの型をそれぞれ別の3つの種と考えている。
それに対して別の研究者はこれらを多型的な同一種とみなし1科1種と報告した。
そこで窪寺氏はミトコンドリアのDNAを解析してみたところ、この3つの型の大王イカの塩基配列には3箇所だけしか違いが認められず、ほぼ同一種とみなせてしまうという結論を得た。
自説とは反対の結果である。
だがこの分析したのがDNA全体のごく短い範囲であることや、調査対象である個体数が少なすぎることから最終的な結論を出すことはできない。
窪寺氏は今後も3種説を主張していくつもりのようだ。
(余談)
時おり「学者は中立的であるべきだ」と言い、自説に固持する学者をいけないものと考える人がいるが、むしろ学問の発展の為には各自が自説に固執して、それらの意見同士をぶつけあい競争させた方が効率的である。
なぜなら完璧な学説などというものは存在せず、どんな理論にも問題点や矛盾はあるものだからだ。
それらは実験技術や理論体系の不備ゆえに満足に説明できないだけものもあれば、本質的に間違っているという場合もある。
遺伝の法則を発見したメンデルや微生物の存在を立証したパスツゥールの実験も実は欠点の多いものであったし、ニュートンの古典力学は光速の世界では矛盾だらけの学問である。
しかし遺伝や微生物の存在自体はより正確な実験で確かめられているし、今は光速の世界も正しく記述できる相対論というものがあり古典力学は低速度領域の近似法則としてならば正しいものである。
このように科学の世界では欠点や矛盾がただちにその説を放棄する理由にはならないことがある。
だからもし自説の欠点を指摘されたとしても、学者はすぐに自説を放り出すべきではない。
むしろ誤りを指摘されたのならば、まずは自説に固執し、より精密な実験や理論の不備を修正する努力をするべきである。
それは学者個人には「誤った説に執着して学者人生を棒にふった」という悪夢をもたらすかもしれないが、学問全体から見れば一つの説を十分に検証したという利益をもたらす。
それに中立的な立場というのは、ある意味とても楽なのである。
何故ならそれは何の判断も思考もしなくていいからだ。どの意見にも「もっともだ、もっともだ」と言ってさえいればいいのだから。自分の立場を選択するということは、とても気苦労が多いものなのだ。
しかも中立的立場というのは、ともすると単なる主流派や最大勢力に偏る傾向があり、実は中立でも何でもなくなり、少数派の無視という結果さえ招く。
私が思うに学問でも日常でも大事なことは偏見を持たないことではなく、自分がどのような偏見を持っているのかを自覚し、かつ他人の偏見の存在も認めることなのではないだろうか。