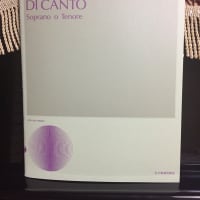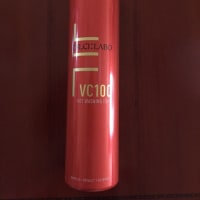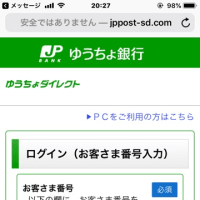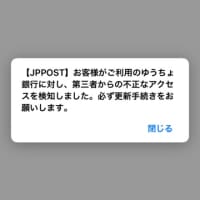「初秋の月」に入りました。
「漁火」の間奏部分、なんとか弾けるようになりましたが
これを作曲した人の気持ちにまではとてもとても辿りつけない・・・
「手事」というのか「合いの手」というのか、一絃琴のみの演奏部分が
邦楽の基礎的なもの?というのか、その素地が自分にないため
曲のリズムや雰囲気がいまいちわからない。。。
わからなくても悩まず弾いてればいいんだか、、、
一絃琴が流行った頃、曲作りに影響を及ぼした音楽はなんだったのでしょう?
三味線や筝ですよね。どんなジャンルのものでしょうか?
幕末の京阪神が中心ですから、上方の邦楽ですね。
三味線ならば、地唄でしょうか?
一絃琴の曲で、ここは三味線ならすらすら弾けるだろう、とか
筝でなら美しい旋律になるだろう、とか予測はしても確信がない。
筝や三味線を本格的には知らないから。
邦楽の基礎的なものをなにか習えば、また一絃琴についても
新しい発見があるかもしれません。
小唄や長唄習ったら、その唄い方になってしまい
一絃琴らしさが損なわれる、と先生から言われていますが
いま自分はそんなふうには考えられない、むしろ、知ったほうが
この琴の流行した頃の有り様に近づくように思うのでした。

「漁火」の間奏部分、なんとか弾けるようになりましたが
これを作曲した人の気持ちにまではとてもとても辿りつけない・・・
「手事」というのか「合いの手」というのか、一絃琴のみの演奏部分が
邦楽の基礎的なもの?というのか、その素地が自分にないため
曲のリズムや雰囲気がいまいちわからない。。。
わからなくても悩まず弾いてればいいんだか、、、
一絃琴が流行った頃、曲作りに影響を及ぼした音楽はなんだったのでしょう?
三味線や筝ですよね。どんなジャンルのものでしょうか?
幕末の京阪神が中心ですから、上方の邦楽ですね。
三味線ならば、地唄でしょうか?
一絃琴の曲で、ここは三味線ならすらすら弾けるだろう、とか
筝でなら美しい旋律になるだろう、とか予測はしても確信がない。
筝や三味線を本格的には知らないから。
邦楽の基礎的なものをなにか習えば、また一絃琴についても
新しい発見があるかもしれません。
小唄や長唄習ったら、その唄い方になってしまい
一絃琴らしさが損なわれる、と先生から言われていますが
いま自分はそんなふうには考えられない、むしろ、知ったほうが
この琴の流行した頃の有り様に近づくように思うのでした。