


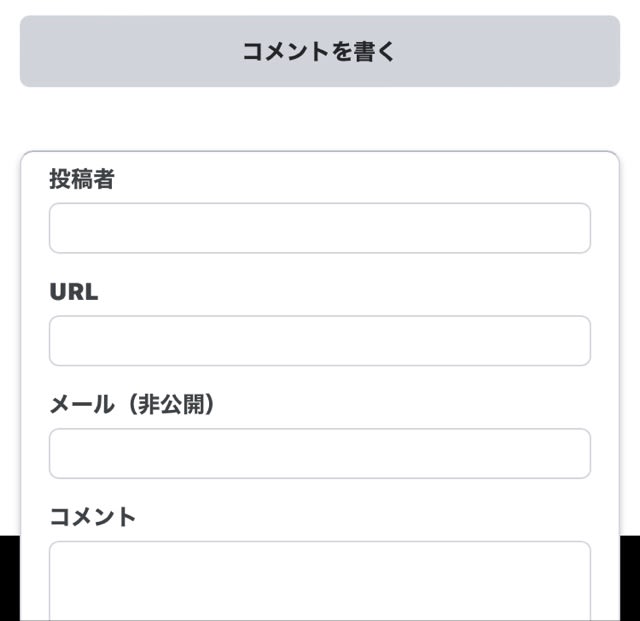




失敗したかもしれない。
金曜の夕方に市役所へ急いだのが原因だった。
所得税の確定申告は不要というメッセージが出たので、医療費控除などは市役所の住民税で申告する必要があった。
控除対象は、医療費、生命保険料、地震保険料、ふるさと納税の寄付控除の4つだけ。
昨年と異なるのは、新たに生命保険を契約したことだった。
問題なのは、従来の生命保険に加え、新たな生命保険に加入したため、控除額が不明な点だ。
平成24年の税制改正で生命保険料の控除額計算方式が変更され、旧生命保険と新生命保険(平成24年以降)の支払い控除額が別々に存在する。
1 国税庁のHP
国税庁のHPでは、問い合わせに答えるように、以下のように記されていた。
両方の生命保険料を支払った場合、新契約と旧契約の控除額を算出し、金額の大きい方を控除額とすることができるというものだ。
控除額が大きくなれば課税対象の所得が少なくなり、税金が少なくなる。納税者の立場に立っている。

2 市役所のHP
住民税はどうなのか。
所得税より控除額が少ないが新旧控除額の合計を適用とされ、喜んだのもつかの間、控除上限額は28,000円ときびしい。
控除額が旧契約35,000円、新契約28,000円の場合、控除上限が28,000円だと控除額が減ってしまいオカシナことになる。
所得税が控除額の大きい方を使っていいと納税者の立場なのに対し、住民税は控除額の小さい方しか認めないという税金徴収者の立場。
どーゆーこと?

3 市役所の申告会場
国と市で保険料控除の考え方が違うのはオカシイ。市役所へ行けば親切に教えてくれるはずだと思っていた。
市役所から送られてきた用紙に、新契約と旧契約の支払額を記入し、証明書を添付して提出した。
旧契約の方が控除額が大きいから、新契約の提出は取り下げてもいいのかなと考えていた。
受付で書類を確認した女性の担当者は「受理しました」と日付印を押して申告受付書をくれた。
私:「ここではなく、会場の奥に座ってる係の人に説明したいのですが。」
受付:「書類は記入されているし、添付書類もあるので、これで終了です。」
私:「生命保険料の支払いが新契約と旧契約の2種類があり、どのように計算されるか知りたいのです。」
受付:「提出された書類の通りになります。金額は今はわかりません。6月には計算されます。」
なんてこったい。
控除額を減らす新契約の支払証明書をわざわざ提出して、税金を増やす人などいるのかい?
よけいなことをしちまった。
市役所に申告書類の取り下げを電話しようか迷っている。
4 市役所に電話 (追記)
月曜日に市役所に電話した。
私:今まで旧制度の保険料を申告していたが、昨年新制度の保険契約をした。控除額が分からなかったが両方記入して金曜日に提出した。でも旧制度の方が控除額が大きく、新制度の提出は損してしまう。
市民税係:有利な旧制度の方を採用します。
私:市のHPでは両方記入した場合は低い新制度とありますが、大丈夫なんですか?
市民税係:はい。大丈夫です。
制度改正が生んだ矛盾で課税への不信感を招く問題だが、現場では混乱を防ぐため現実的対応をしていることがわかった。
最近火災が多いので、気になっていたコンセントを掃除しました。
私:「今日は4年に一度の電気設備点検です!」
妻:「おお、それオリンピックみたいに言わんでええわ!」
私:「関東電気保安協会の人が来てくれて、ブレーカーの点検してくれるんやけど、今まで全部任せてたから、今日は初めて立ち会うねん。」
妻:「ほんまや。いつも私が平日に頑張ってるんやから、感謝しぃや!」

私:「で、点検のついでに相談したんよ。『キッチンの食器棚のコンセントが漏電しそうで怖い』って。」
妻:「そこ、確かに見えへんから不安やな。」
私:「そしたら保安協会の人が『埃が積もると漏電火災の原因になりますよ』って教えてくれて。」
妻:「埃!?それ聞いて掃除したことないのバレたんちゃう?」
私:「いやいや、それは言わへん!」
私:「で、さっそく報告したら、何か冷蔵庫がガタガタ音立てて動いてるやん!」
妻:「そら私や。聞いて放っとくわけないやろ!」
私:「その対応力、ちょっと感動するわ。で、一緒に作業し始めたんやけど、冷蔵庫の裏見た瞬間、びっくりやで!」
妻:「埃がモフモフやったな!」
私:「まるで冷蔵庫が冬支度してるみたいな厚みや!」
妻:「あんたの驚き方がおもろいわ。さっさと掃除しよ!」
私:「掃除機、クイックルワイパーに雑巾。粘着ローラー駆使して、めっちゃキレイにしたで!」
私:「で、いざ問題の食器棚の裏のコンセントや。見えたと思ったら、3口タップの上にまたモフモフ!」
妻:「そのタップ、埃に埋もれてたな!」
私:「これは危ない思て、掃除機で吸い取ったけど、またすぐ積もるやろなぁ。」

妻:「そしたらもう抜いてしまえばええやん!」
私:「いやいや、簡単に言うけど、食器棚が全然動かへんのよ!」
妻:「ほんなら傾けたらええやん?」
私:「え、天才?」

妻:「まぁな!上の食器を取り出して、ちょっと傾けたら隙間できるやん!」
私:「ほんまや、できた!で、一瞬でタップ抜いた!」
妻:「火災の心配ひとつ減ったな!」

私:「これで安心して暮らせるわ。ありがとうな。」
妻:「ええけど、次はちゃんと自分で気付いて掃除しぃや!」
私:「はい、次回も4年後やな!」
妻:「それ忘れてるやつのセリフやん!」
意外と時間がかかるのが断捨離。
今日こそと思うが、終わらない。
ハリー・ポッター
通勤電車の中で、時間をかけて苦労して読んだハリー・ポッター。
子供用の本で、会話も多いからなんとかストーリーはわかるけど、魔法や怪物の描写は難しい。
映画を観たときに感じた違和感。原作との違いについて感じたことを整理した記事「ハリー・ポッター原作と映画の違い」は、テレビ放送があると今でもアクセス数が増える。

訳本や映画の字幕のオカシナところ
第1巻「ハリー・ポッターと賢者の石」の冒頭で、ポッター夫人(リリー)とダーズリー夫人(ペチュニア)が出てくる。
松岡佑子さんの翻訳(2003年11月)では「ポッター夫人はダーズリー夫人の実の姉」と訳されていた。
原作ではsisterとあるだけで、リリーが姉か妹かはわからない状態だった。
そして、その後発刊された続編で、リリーが妹なのが明らかになり、誤訳が判明した。
Philosopher's stone「賢者の石」の訳もオカシイ。
ヴォルデモートは不老不死を求めていたのだから、「ハリー・ポッターと不老不死の石」のタイトルにすべきだった。
4階の廊下
入学式でダンブルドア校長が「the thrird-floor corridor は立ち入り禁止」と話す。
この階を、松岡さんは4階と訳したが、映画の字幕は「3階」と誤訳だった。
英国では、地上階をground floor、2階を1st floor、3階を2nd floor、4階は 3nd floorと呼ぶ。
米国やカナダは日本と同じ数え方だが英国は違う。
こんなややこしい数え方は英国だけかと思っていたが、先日行ったイタリアでも地上階はpiano terra 、2階をprimo poano、3階をsekondo pianoと呼んでおり、英国と同じだった。
理由を調べると、歴史的に建物の1階には商業施設があり、2階から上が住居になる。そのため、住居として数えると2階が1階になるとのこと。
ダンブルドアのプリーズ Please
スネイプSnapeに対し、ダンブルドアが”Please.”と言う重要なシーンがある。
Pleaseは、「頼む」と「どうぞ」とがあって、「頼む」だと”Please, help me”。
「どうぞ」だと ”Please, kill me”のニュアンスが感じられる。
原作ではどちらなのかよくわからなかったが、映画の演技を見ていると「どうぞ」のように感じられたが、日本語字幕や松岡さんの図書翻訳では「頼む」になっていた。
最終作を読むと、「どうぞ」が妥当だと思う。
*********ハリーポッターの記事一覧***********
第7話ハリーポッター原作と映画の違い「死の秘宝 PART2」
第7話ハリーポッター原作と映画の違い「死の秘宝 PART1」

ということで、ハリー・ポッターともお別れです。
意外と時間がかかるのが断捨離。
今日こそと思うが、終わらない。
5000人とお別れ
仕事で出会ったときに行うのが名刺交換。
名刺を納めたフォルダーファイルは12冊。
そのうち2冊に集約して残し、約5000枚の名刺とはお別れ。

写真と同じように、名刺の肩書きや名前を見ると一人一人当時の様子が思い出される。
お世話になった人の顔、苦労したことなど…。
捨ててしまうと、もう思い出すこともできなくなるのかな。
若い頃は、名刺の印刷は自腹だった。1ケース100枚で千円くらい。
お金がないので、カラー用紙に印刷し、カッターで切断して名刺を作っていた時期もあった。
もらった人も驚くペラペラの薄さが特徴だった。
そのうち、パソコンで名刺をデザインしプリントできる用紙が市販された。用紙には切り取り線と適度な厚みがあり便利だった。
カレンダーや広告の裏面を利用して、手作りの名刺にしていた人がいたね。(右側)
そのうち、名刺の裏に勤務先の広告を入れるようになり、会社負担で名刺が作れるようになった。
ビューティフル・ウインドウズ運動のPR、県内の主要都市への公共交通のアクセスをPR。(左側)
いただいた名刺の裏面

不要になった名刺フォルダーファイルは、診察券やポイントカードを入れる使い道。
名刺フォルダーファイルって、結構なお値段がしたことを覚えてる。
それに、購入時期がそれぞれ異なるから、収納ポケットも異なる。
縦書きから横書きに、背景の紙を省いて透明化、加除式を省いて薄さを追求など、変化していった。
















新しい日本銀行券に両替してもらった。








【介護が必要になる】 #備える
今は健康でも、年を重ねるとどこか調子が悪くなり、やがて日常生活を一人では難しくなってくる。
突然やってくる転倒事故の骨折や脳卒中。健康だった人でも、退院後は介護が必要になることも。
すなわち、健康の時こそ、介護される立場になったことを考えておく必要がある。
誰が自分を介護してくれるか、その人の負担を考えると、介護施設への入所を考えることも大切だ。
【介護費用はいくらかかるか】
要介護3から入所できる特別養護老人ホーム(特養)の利用料金は、地域で差があるようだ。
手元の資料を見ると、
介護施設利用料(介護保険1割負担の場合):月額26,000円(多床:いわゆる相部屋)
保険対象外の食事や日常生活費など :月額62,400円
合 計 :月額88,400円
短期間の入院手術なら相部屋でよいが、長期間ではプライバシーなどから個室が推奨される。
月額5万~10万円が加算され、医療費や理髪などは別なので、月額20万円はかかると思われる。
一人暮らしをしても、そのくらいはかかる。光熱費が高いしね。
【高齢者世帯の可処分所得の実態は】
総務省の2023年度の家計調査報告書をみると、65歳以上の無職夫婦のみの世帯では、
月額で実収入は244,580円、税金や社会保険料を控除した可処分所得は213,042円。
65歳以上の無職単身世帯では、実収入は126,905円、可処分所得は114,663円。

【介護費用の不足をどうするか】
可処分所得と介護費用の差は、一人当り月額10万円。
不足分の毎月10万円を貯蓄から取り崩すと年間120万円。10年で1200万円にもなる。
これでは、先行き不安である。
【米国債の為替リスクはヘッジできるか】
米国の高金利を活かした外貨保険は、今は円安なので将来円高になった場合、リスクがある。
日米の為替レート(赤)は、国債の金利差(青)に連動しており、円安が続いていることが読み取れる。
しかし、約5%の高金利を活かした保険商品なら、為替リスクをヘッジできるのではないか。

【どんな保険があるの】
例えば、ニッセイ・ウェルス生命保険(株)。日本生命保険相互会社の完全子会社。
保険財務力格付け A+(上から3番目のAに+が付いてる)
指定通貨建終身保険(認知症・介護保険金特則有り)
要介護2以上に認定された場合や認知症に該当すると判断された場合、死亡保険金と同額の介護保険金を受け取れる。
90歳まで加入でき、被保険者が受け取る介護保険金は、非課税。これは大きいね。
【無告知コース】
加入時に告知をしないタイプ。積立利率は4.85%。
第一保険期間(3年)は保険金が一時払い保険料と同程度だが、それを過ぎると急速に増加する。
一時払い保険料に対する介護保険金の割合(3年後)
契約年齢 女性 男性
50歳 388% 320%
60歳 261% 225%
70歳 183% 168%
50歳の女性が3年後に要介護2になったら、一時払い保険料の3.88倍を受け取れる。
結構大きいね。1年刻みで率が変わるが、60歳、70歳を抜粋してみました。
生存中にこれだけ大きな介護保険金が受け取れる。3年間は大丈夫という方は、いいのではないか。
【告知コースも】
いやいや、契約後に直ぐにもらいたい人のために「告知コース」も用意してある。
70歳だと介護保険金の割合が12%程度低くなり、年齢が若くなると30%くらい低くなる。
それでも、倍率が大きいね。
【為替リスク】
今、1ドル160円として、受け取るときにA130円、B110円になった場合は、どうなるか。
A 1ドル130円の場合
130/160=81.25%
契約年齢 女性 男性
50歳 315% 260%
60歳 212% 183%
70歳 149% 137%
B 1ドル110円の場合
110/160=0.6875
契約年齢 女性 男性
50歳 267% 220%
60歳 179% 155%
70歳 126% 112%
契約時の年齢と男女差で異なるが、今のままよりは良いね。
【損益分岐点 円/ドル】
要介護2になった時の為替レート(円/ドル)が、次の数字よりも大きければ(円安なら)メリットがある。
契約年齢 女性 男性
50歳 41.2 50.0
60歳 61.3 71.1
70歳 87.4 95.2
と言う結果になりました。
日米の金利差が為替レートに影響を与えて、大幅な円安となっているけど、米国の5%近い金利を活かした保険商品を上手く活用すると、為替リスクをヘッジできるね。
米国の金利が下がらないうちに、検討してもよいかも。
【生命保険の役目は終わったか】#残す
マイホームのローン返済や子供の教育資金や家族の生活を考え、万が一の場合に備え、生命保険に加入する。
ローン返済が終わり子供も独立したら、役割を終えた生命保険は、縮小や解約するのが一般的だと思う。
しかし、年金生活になり、やがて訪れる相続に際して、生命保険が有効かも。
【すみやかな現金化】
死亡すると、故人の預金口座などは凍結されてしまう。口座引落しできず困ることも想定しないといけない。
故人の相続財産は、遺産分割協議が整わないと、名義変更できず、現金化もできない。
しかし、生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産で、遺産分割協議の対象外で直ぐに現金化できる。
【納税資金の確保】
長年苦労して手に入れたマイホームの相続税はいくらか。建物は固定資産税の評価額。土地は国税庁の路線価で概算が分かる。それに預金や金融商品を加え計算。
相続税は、死亡後10ヶ月以内に現金一括納付なので、予め税額を計算し納税資金を準備しておくといざという時に慌てない。
現金が無ければマイホーム売却もありうるが、短期間に思い通りの値段で売れるかリスクがある。
死亡保険金は、納税資金に充当でき、500万円×法定相続人の数が非課税となるため、預金より有利。
【米国の高金利を活かした生命保険】
預金の一部を外貨建ての生命保険に充当し、上記の問題を解決するとともに、願わくば資産を増やせないか。
5%前後の高い金利が続いている米国の債券を活かした生命保険で、いいものはないか探してみました。
【どんな保険があるの】
例えば、第一フロンティア生命保険(株)。第一生命ホールディングスの100%子会社。
保険金支払能力の格付けは AA(保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある)
積立利率変動型終身保険(通貨指定型)
積立利率は毎月2回変動するが、契約後は30年間固定。
【がんと診断されたけど加入できるか】
「医療告知無し」なので、がんになった人も加入できる。
現在、入院中や余命宣告された人は入れません。
【計算例】
仮に、定期預金1000万円を解約すると、63,279ドル(1ドル158円)。
米国債など5%の債券を活用し、積立利率は4.68%。実質利回り(30年)は2.39%。
メリット
損益分岐点の為替レート
死亡時の為替レートをB円/ドルとすると、130,457ドル × B円/ドル >=10,000,000円
損益分岐点Bは、76.6ドル/円。
対応方針
死亡時、受取人は銀行で外貨預金口座を1100円で作成後、死亡保険金を請求。相続税は死亡日の為替レート。外貨で保有し、円安になった際に両替。
2000万円に到達時点で、円建て終身保険に移行する特約を選択(円で受領)。生存中に円安が進んだタイミングを逃さず利益確定。死亡時の円高に備える。
ただし、死亡時のレートがさらに円安になり1ドル200円だったら609万円が逸失利益になる可能性もある(計算上の話だが)。
為替レートと利益・資産増加率

評価
円高になって、1ドル120円でも、資産は1.57倍。566万円増やせる。
外貨で受け取るので、為替レートが気に入らなければ、ドルのまま保有する限り、損は発生しない。
円換算で2倍になったら円建て終身保険に移行する特約があり、コレを使えば、仮に生存中に為替レートが円安になって2倍を超えた時に死亡保証金は円になり、外貨で受け取ることは無くなる。(2.5倍や3倍にも変更可能)
こうした対策でいいのかな。
【資産の減少】#使う
物価が3%上がる(過去3年平均)一方で、定期預金や国債の利率が低いままでは、せっかく貯めた資産が減る一方。
0.97×0.97×0.97×0.97×0.97×0.97×0.97=0.81 何もしなければ、7年後には資産が19%も減ってしまう。
【配当が無い】
株価が購入時価格に長期間戻らない経験をしたので株を売却したものの、配当が無く、年金生活者にはさみしい。
【何か対策は】
金融機関を2つ回って、詳しくお話を聞いた。年金生活者には時間は十分ある(^0^)
【外貨建て生命保険】
いいのではないかと思うのが一つありました。
メットライフ生命って、CMの生命と似てるからパクった?と思ったら、世界3位、米国1位だった。
例えば、銀行の定期800万円(0.002%)を解約して購入すると
8,000,000円÷157.81円/ドル=50,693ドル 手数料50銭加算済みレート
(メリット)
(10年間の受取総額)
50,693+2310×10=73,793ドル (50,693ドルを3.83%で10年)
(損益分岐点の為替レート)
10年後の為替レートをA円/ドルとすると、
(50,693+2310×10)ドル× A円/ドル >= 8,000,000円
損益分岐点Aは、108.41円/ドル。
(対応方針)
10年後の利率改定期で解約する。
(為替リスクのヘッジ)
為替レートが108円より円安ならば、損はしない。
円高の場合は外貨預金でドルのまま保有し、円安になった際に両替する。(契約時にドルで受取りを選択しなければならない)
死亡時は、その日のレートで相続税の評価をするが、実際に両替する必要は無い。
円だけでなく、外貨で資産を持つことはリスク分散にもなる。
仮に、1ドル100円の時に100万円をドルに替えて1万ドルを外貨預金しておけば、1ドル150円になった際は150万円になる(為替差益50万円は申告必要)。
(為替レートと利益・資産増加率)

(評価)
3%の物価上昇が10年続くと仮定すると、財産は1.34倍になってほしい。
10年後に、為替レートが145円より円安ならば、資産運用として上出来だね。
もし為替レートが120円で両替したら10年で1.11倍。これは為替リスクの無い「円建ての一時払い保険の商品」の運用と同程度になるが、円建て保険は一時所得に所得税がかかり、さらに住民税や介護保険料も1年間上がってしまう。しかし、毎年支払金を受け取る外貨建て保険なら申告不要の20万円以内で済む。
10年後の解約時に為替レートが悪ければ、50693ドルのまま保有し、円安になるまで待つ。