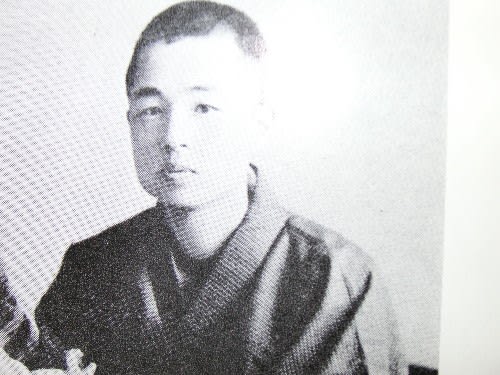寺山修司が出現する一九五四年までの歌壇は、「沈滞を進化と勘違いするほどに長老が絶対権を持ったであった。」と言う中井英夫が見いだした寺山修司の出現は「まさに青春の香気とはこれだといわんばかりにアフロディテめく奇蹟の生誕であった」といわしめている。それからの四十七才でこの世を去るまでは、まるで約束されたような病身でありながらの孤独のランナーとして、俳句、短歌、現代詩をはじめ、映画、演劇、ときに競馬、ボクシング、そして「天井桟敷」とあらゆる文化芸術を網羅するようにサブカルの世界もつきぬけていった一瞬の偉大な旋風であったといいかえてもいいだろうか。
十二、三歳で俳句を作りその後、短歌へとすすんだ寺山修司の才能の開花はそれを発掘したという中井英夫の力ばかりとはいえない気がしてくるだろう。

森駆けてきてほてりたるわが?をうずめんとするに紫陽花くらし
空豆の殻一せいに鳴る夕母につながる我のソネット
夏川に木皿しずめて洗いいし少女はすでにわが内に棲む
国土を蹴って駆けりしラクビー群のひとりのためにシャツを編む母
蛮声をあげて九月の森に入れりハイネのために学をあざむき
雲雀のすこしにじみそわがシャツに時経てもなおさみしき凱歌
失いし言葉かえさん青空のつめたき小鳥打ち落とすごと
わがカヌーさみしからずや幾たびも他人の夢を川ぎしとして
これらは高校生のころの作品だが、無心の美しさが心を打つ。同時に読者である私たちの少年時代をも仄かに照らす夢淡きランプである、と選者の中井英夫を賞賛させた投稿作品の一部である。この作品からは五月の風にはにかみながらも聡明で感受性豊かな少年の颯爽とした姿が確実にこのむねにとどく。いまにおもえば当時はパソコンなどのまだ無い時代、どのように溢れる思いの言葉をノートなどに書きつづっていたのだろうか。
これまで刊行された歌集は次のとおりである。
『われに五月を』 昭和三十二年一月・作品社刊。(短歌の外、詩、俳句等収録)
『空には本』 昭和三十三年六月・的場書房刊。(第一歌集)
『血と麦』 昭和三十七年七月・白玉書房刊。
『田園に死す』 昭和四十年八月・白玉書房刊。
『寺山修司全歌集』昭和四十六年一月・風土社・刊。(前期の作品すべてと、未完詩集 「テーブルの上の荒野』を収録)
いま、寺山修司の第一歌集『空には本』(五八年発行)を久しぶりにめくりながら発行の当時は気がつかなかったが、麦藁帽子がモチーフとなっている短歌には不思議とふるさとのにおいがした。
今でこそ「私」を仮装する寺山の手法を通して短歌を詠むことができるが、当時はその短歌に寺山の少年時代をにょにつな事実として読んでいた気がする。たぶん虚構によって触れる真実の深さを知るにはあまりにも稚拙な世界にとりまかれていたのかもしれない。
海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり
夏帽のへこみやしきを膝にのせてわが放浪はバスになじみき
わが夏をあこがれのみが駆け去れり麦藁帽子被りて眠る
麦藁帽子を野に忘れきし夏美ゆえ平らに胸に手をのせ眠る
列車にて遠く見ている向日葵は少年の振る帽子のごとし
ころがりしカンカン帽を追うごとくふるさとの道駆けて帰らん
麦藁帽子が少年時代の郷愁を呼び込む世代はもう少ないだろう。戦後の少年たちもすっかり年齢をとったけれど、唄は永遠に年を取らないからだろうか、古い詩や小説の中へ引き戻されることがある。
堀辰雄の短編小説「麦藁帽子」(淡い恋の物語)や芥川龍之介の「麦わら帽子」(「侏儒の言葉」の文章)もあるが、一番心に残っているのは西条八十の「帽子」と立原道造の「麦藁帽子」がある。中でも西条八十の詩は角川映画『人間の証明』の重要なモチーフになっていて、その主題歌を歌ったジョー中山が一躍脚光をあびた。
母さん、ぼくのあの帽子どうしたでしょうね?
ええ、夏の碓氷から霧積(きりづみ)へゆくみちで、
渓谷へ落としたあの麦藁帽子ですよ。
母さん、あれは好きな帽子でしたよ
ぼくはあのときずいぶんくやしかった
だけどいきなり風がふいてきたもんだから、
(略)
母さん、本当にあの帽子どうなったんでせう?
そのとき傍に咲いていた車百合の花は、もう枯れちゃったですね
そして、秋には灰色の霧が丘をこめ
あの帽子の下で毎晩きりぎりすが啼いたかもしれませんよ。
(略) ( 西条八十「帽子」)
主演は岡田茉莉子と松田優作であったが、後に松田優作の追悼のために歌ったジョー山中も二〇一一年八月には永眠、享年六四才であった。この映画は二〇〇一年には渡辺謙、二〇〇四年に竹野内豊によってそれぞれリメークされている。