本業で余裕が無くなると、ブログはそれに反比例するかのように暇人的な内容になる。しかし表題にある『情報サービス産業における監査上の諸問題について』が日本公認会計士協会より3月中旬に公表されており、やはり忘れぬうちに書き留めておかなくては。このレポートは、ここ最近のIT業界の不正会計処理を受けて「IT業界における特殊な取引検討プロジェクトチーム」が取り纏めたものである。
東葛人的視点ブログでは、「全体的に会計士の“逃げ”を感じる内容」という厳しい指摘もあるが、今回のレポートでは、明らかな不正に対する監査指針は出されているものの、情報サービス業の会計慣行をどうすべきかについては米国の手法を紹介するに留まっている。そして、レポートは日本においても明確な会計基準を設定すべきことを提言して締め括られる。
情報サービス産業の更なる成長のためにも、会計基準が早期に検討されることが望まれるが、今回のレポートが情報サービス産業の特性を解明しようとしていることは評価したい。例えば、当レポートは、情報サービス産業における会計環境の特質として下記の3点を挙げている。
1)ソフトウェア開発における収益認識基準のあいまいさ
2)受注金額確定の遅延による仕掛品の資産性への疑義
3) 商社的な取引慣行とその問題点
その上で、以下のそれぞれのビジネス形態における監査上の留意点を解説している。中でも商社的取引慣行については、不正の温床となり易いことから、別の章立てでスルー取引、Uターン取引、クロス取引などへの注意を喚起している。
1) 開発型
2) コンサルティング型
3) 商社的取引型
会計手法については、以下の3つの論点につき、米国の基準を紹介している。
1) 売上の総額計上/純額計上の指標
2) 収益の認識時点の問題
3) 複数の要素のある取引
売上の総額計上と純額計上は先のIBMの売上高修正でも話題となった。ちなみに、総額計上の指標のひとつとして、「取引において主たる債務者(ユーザーに対してサービス責任を負う者)」というのが挙げられているが、主たる債務者でありながらも、その下請業者に債務を転嫁するような契約形態が取られていたらどうなるか、など日本の下請構造からは気になる点もある。
また、複数要素のある取引については、今後サブスクリプション型など、ライセンスと保守が一体となった取引形態の増加も予想されるため、会計基準の早期検討が必要となる。米国基準だと契約高が資産計上され、契約遂行に伴ってそれが利益に計上されていくような方法であるらしい。つまり、それによってサブスクリプション契約の動きが投資家からも把握可能となるわけである。
いろいろ課題はありそうだが、こうした問題は公認会計士協会に指摘される前に、情報サービス業の業界団体である情報サービス産業協会のようなところが主導して公認会計士協会のアドバイスのもとに自主ルールを定めるような動きが望ましいのではないか。
【参考】
「IT業界における特殊な取引検討プロジェクトチーム報告」
東葛人的視点ブログでは、「全体的に会計士の“逃げ”を感じる内容」という厳しい指摘もあるが、今回のレポートでは、明らかな不正に対する監査指針は出されているものの、情報サービス業の会計慣行をどうすべきかについては米国の手法を紹介するに留まっている。そして、レポートは日本においても明確な会計基準を設定すべきことを提言して締め括られる。
情報サービス産業の更なる成長のためにも、会計基準が早期に検討されることが望まれるが、今回のレポートが情報サービス産業の特性を解明しようとしていることは評価したい。例えば、当レポートは、情報サービス産業における会計環境の特質として下記の3点を挙げている。
1)ソフトウェア開発における収益認識基準のあいまいさ
2)受注金額確定の遅延による仕掛品の資産性への疑義
3) 商社的な取引慣行とその問題点
その上で、以下のそれぞれのビジネス形態における監査上の留意点を解説している。中でも商社的取引慣行については、不正の温床となり易いことから、別の章立てでスルー取引、Uターン取引、クロス取引などへの注意を喚起している。
1) 開発型
2) コンサルティング型
3) 商社的取引型
会計手法については、以下の3つの論点につき、米国の基準を紹介している。
1) 売上の総額計上/純額計上の指標
2) 収益の認識時点の問題
3) 複数の要素のある取引
売上の総額計上と純額計上は先のIBMの売上高修正でも話題となった。ちなみに、総額計上の指標のひとつとして、「取引において主たる債務者(ユーザーに対してサービス責任を負う者)」というのが挙げられているが、主たる債務者でありながらも、その下請業者に債務を転嫁するような契約形態が取られていたらどうなるか、など日本の下請構造からは気になる点もある。
また、複数要素のある取引については、今後サブスクリプション型など、ライセンスと保守が一体となった取引形態の増加も予想されるため、会計基準の早期検討が必要となる。米国基準だと契約高が資産計上され、契約遂行に伴ってそれが利益に計上されていくような方法であるらしい。つまり、それによってサブスクリプション契約の動きが投資家からも把握可能となるわけである。
いろいろ課題はありそうだが、こうした問題は公認会計士協会に指摘される前に、情報サービス業の業界団体である情報サービス産業協会のようなところが主導して公認会計士協会のアドバイスのもとに自主ルールを定めるような動きが望ましいのではないか。
【参考】
「IT業界における特殊な取引検討プロジェクトチーム報告」











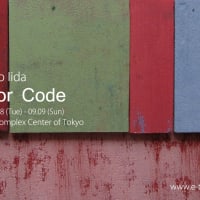
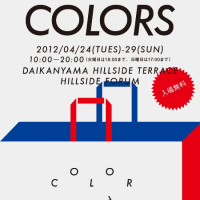

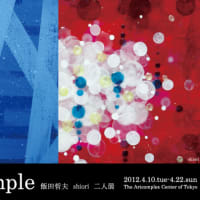



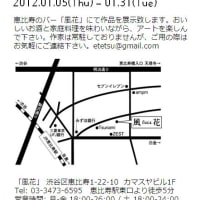

契約が確定していないのにプロジェクトが始まっちゃうんですね(もしかして終わりまで?)。
これを会計士の先生方に裁いてもらうのも妙な話ですね。
やはり業界側で取引慣行を整理する方が重要な部分も多いのではないでしょうか。
記事の引用ありがとうございます。“逃げ”を感じると書きましたが、『情報サービス産業における監査上の諸問題について』はITサービス業界の問題点を俯瞰するのに、よい資料だと思います。
多くの会計士さんにとって、ITサービス会社の監査はできればやりたくない仕事のようです。この前、会計士の方と話をしていて、この話題になり、私が「こんなことでは、ITサービス会社を監査してくれる人はいなくなってしまいますね」とつぶやくと、「ほんと、そうです」とおっしゃっていました。