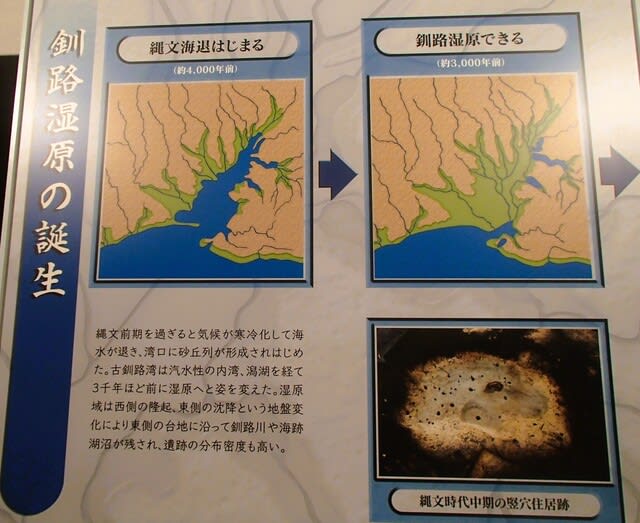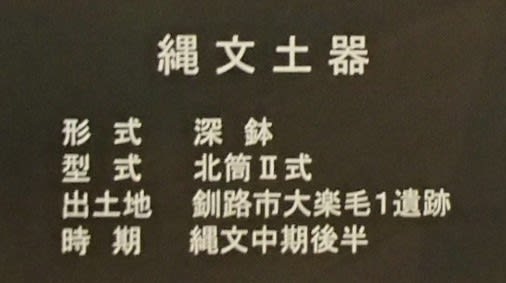静岡で着工遅れ、岐阜の水源に悪影響…多難リニアの行方は?
2024年7月1日 中日新聞
リニア中央新幹線は、静岡県内での着工が計画より大幅に遅れていたが、知事選後に工事開始に向けた協議が進み始めた。しかし、工事が進む岐阜県瑞浪市で水源に悪影響が出るなど、多難な様相だ。開業予定が大幅に遅れ、取り巻く社会状況も変化しつつあるリニアの行方を考える。
リニア中央新幹線 東京-大阪間438キロを超電導磁気浮上方式の走行で67分で結ぶ計画。うち東京-名古屋間286キロの所要時間は40分で、この区間の建設費だけで約7兆円と見込まれる。JR東海は「東海道新幹線の将来の経年劣化と南海トラフ巨大地震など大規模災害への備え」と意義を説明。当初は東京-名古屋間の開業を2027年としていたが、同社は静岡県の同意が得られない状況が続いたとして27年開業の断念を表明。開業は早くとも34年とみられる。
リスク管理の共有が重要 静岡市長・難波喬司さん

難波喬司さん
なぜ静岡は、そんなに過剰な環境影響評価をしているのか? 言いがかりをつけているだけではないのか? リニア事業に対する静岡県や静岡市の態度に対して、そういう疑問や批判があります。
リニアのトンネル掘削工事が進む岐阜県瑞浪市で井戸やため池などの水位低下が起きて問題となっていますが、まさにこのような事態が起きることを恐れ、こういう事態が起こることを防ぐための仕組みづくりを、私たちは進めてきました。
JR東海と議論と交渉を重ねてつくった枠組みでは、施工前に影響の予測・分析・評価を共有しておきます。工事は、施工計画と環境保全措置の実施計画に基づいて行われ、モニタリングの実施計画に基づいて湧水量などさまざまな項目を綿密に観測する。観測結果を評価し、状況に順応して適切な行動を選択していく。たとえばトンネル工事で予想外の湧水が生じた場合などは、すぐ工事を止めて対策を考える。場合によっては施工計画自体を見直す。これらの観測・評価・行動はすべて公表していきます。
ですから、瑞浪で起きたような事態であれば、予測外の湧水が起きた時点で情報が共有され、早期に対処できたはずです。事態を悪化させないためには「早期検知、初動全力」が何より大切です。
そもそもJR東海は、工事の水への影響を甘く見ていたと思います。静岡では南アルプスを貫くトンネルが大井川などにどう影響するかが大きな問題でしたが、JRが影響予測に使っていた解析手法は精度が低いものでした。
それを県や専門家から繰り返し指摘されても、自分たちのやり方が正しいと言い張っていた。県が求めた資料も、何度催促してもなかなか提供しませんでした。
想定外のことが起こりうることや解析結果には不確実性があることへの意識が希薄で、ゼロリスクなど科学的・技術的にありえないのに、それを口にするようなこともあって、工学者らを驚かせました。
そういうことが重なって、リスク管理・回避のための仕組みづくりに何年間も費やさざるを得なかった。そういう静岡での経験が、どれだけ他自治体での工事にいかされているのか。瑞浪の例を見ると、いささか不安です。
工事が各地で進めば、私たちが続けてきたことへの理解や共感が広がり、深まっていくのではないかと思っています。 (聞き手・星浩)
なんば・たかし 1956年、岡山県生まれ。名古屋大大学院工学研究科修了。工学博士。1981年に旧運輸省入省。国土交通省技術総括審議官を経て、2014年に静岡県副知事、23年に静岡市長に。
不誠実な住民説明に疑問 ジャーナリスト・樫田秀樹さん

樫田秀樹さん
私自身はリニア建設に賛成でも反対でもない立場で事実のみを伝える姿勢で取材を続けてきましたが、JR東海の住民への対応は非常に問題があると考えています。東京都品川区や長野県大鹿村など各地の住民説明会を取材しましたが、住民の質問は、同時に三つと決められている。質問数を限定するのはまだ仕方ないにしても、再質問ができないというルールでは事業への理解はなかなか深まりません。
住民の手が挙がっていても延長は30分程度。反対の声が圧倒的だった説明会の後でも、JRは「住民の理解を得ました」と言います。説明会に住民が来るのは、この事業に関心があるからで理解が進んでいるという解釈です。説明会イコール理解が進んだとするJRの姿勢はあってはならないと思っています。
今年になってやっとJRは開業は2034年以降になると認めましたが、27年開業は無理だということはとうの昔に分かっていたことで、リニア駅建設に伴う住民の立ち退きについても、もっと時間をかけて話し合うことができたはずです。長野県飯田市の駅開発で実際立ち退いた方々に話を聴こうとしても、「27年にできると信じて出て行ったのに、後悔が強すぎて今は話したくない」という住民が多くて取材に苦労しています。
JRから説明がないというだけで、開業遅れを自ら調べようとしない周辺自治体の責任も大きいです。例えば、神奈川県に建設される車両基地は、JRの資料に工期が11年と明記されています。仮に今年着工できても完成は35年、電気調整試験と走行試験に必要な期間を2年とすると、開業は37年になります。JRは工期の短縮を図ると言っていますが、これまで同社の説明をうのみにして住民の立場で動かなかった自治体の罪は重い。「静岡県が着工許可を出さない」という開業遅れに対するJRの主張を無批判に伝えてきたメディアにも責任があると思います。
ウクライナ戦争による資材の高騰などで、3兆円の財政投融資があっても、JR東海に品川-名古屋間と名古屋-大阪間の工事を同時に進める体力はないでしょう。むしろ、自社の経済基盤が強固になるまで、名古屋-大阪間の工事は遅れても仕方ないと考えているのではないかと推察します。これから完成に何十年もかかるであろう鉄道事業の意義を突き詰めて考えるときだと思います。 (聞き手・中山敬三)
かしだ・ひでき 1959年、北海道生まれ。『“悪夢の超特急”リニア中央新幹線』で日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞受賞。他の著書に『リニア新幹線が不可能な7つの理由』ほか。
スピードは至上価値なのか 政治学者・原武史さん

原武史さん
リニアの背景にはナショナリズムが見え隠れします。リニア開業が宿願だったJR東海の故葛西敬之(よしゆき)名誉会長の仮想敵国は中国でした。世界最速鉄道の座を奪われたくないという思いがあった。
戦前の満州を走った「あじあ号」。日本の技術の粋を集め、最高時速は130キロ。当時、世界最速レベルの超特急列車でした。その満鉄で理事だった十河信二(そごうしんじ)が国鉄総裁となり1964年に東海道新幹線ができる。国鉄の民営化後、JR東海は新幹線をひたすらスピードアップさせた。
ところが21世紀に入ると中国が高速鉄道網を整え、北京-上海間のスピードで新幹線の東京-博多間を上回る。そうなると、中国に勝つにはリニアしかないと。葛西氏の中には、満鉄以来の栄光の歴史があって、鉄道において常に世界をリードしてきた誇りを失いたくないという自負があった。そうした成功物語に呪縛されたとも言えます。
葛西氏は明治の元勲、山県有朋(やまがたありとも)を尊敬し、日本という国家を第一に考えた。山県のようにこの国をけん引し、正しく導こうとしたのでしょう。故安倍晋三元首相が葛西氏を「国士」と呼んだのも、そういう意味からでした。
葛西氏は、鉄道のもっている諸価値をスピードに一元化した。山県にとっての民衆が客体にすぎなかったように、葛西氏にとっての乗客もまたどこかからどこかまで速く移動する列車の客体にすぎなかったのではないか。
しかし世界的に見ると、鉄道は別の価値がいま注目されている。例えば、環境への負荷が少ない。飛行機よりもCO2の排出が少ないので、欧州では夜行列車がどんどん復活している。スピードではなく、移動する時間そのものの価値が見直されているわけです。バリアフリー化した路面電車もまた高齢者や障害者の目線に立った乗り物として注目されていますよね。
スピードを追求した新幹線でも、とりわけ外国人はただ運ばれるのではなく、富士山に向かってシャッターを切ろうとする。リニアではそれすらも不可能になります。
葛西氏は政府とまさに一体となってリニア建設にまい進し、政府もまた3兆円もの財政投融資で支援してきた。しかし時代が変化し、鉄道も含めて別の価値基準が人々の広い了解事項になってくれば、ナショナリズムの遺物と言うべきリニアにいつまで巨額の金をつぎ込むのかという話にならないとも限らないと思います。 (聞き手・辻渕智之)
はら・たけし 1962年、東京都生まれ。明治学院大名誉教授、放送大客員教授。専攻は日本政治思想史。著書に『大正天皇』『昭和天皇』『最終列車』『歴史のダイヤグラム』『戦後政治と温泉』など。