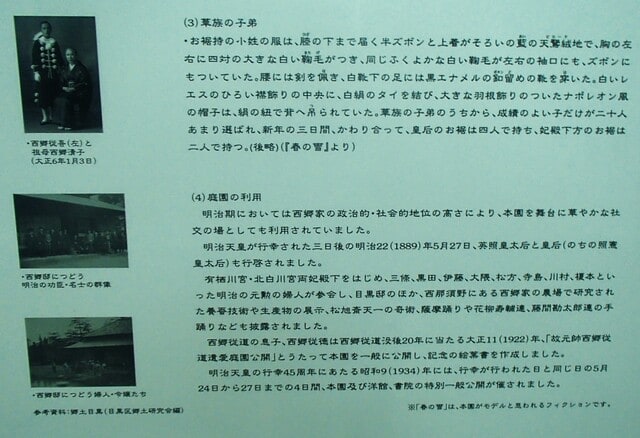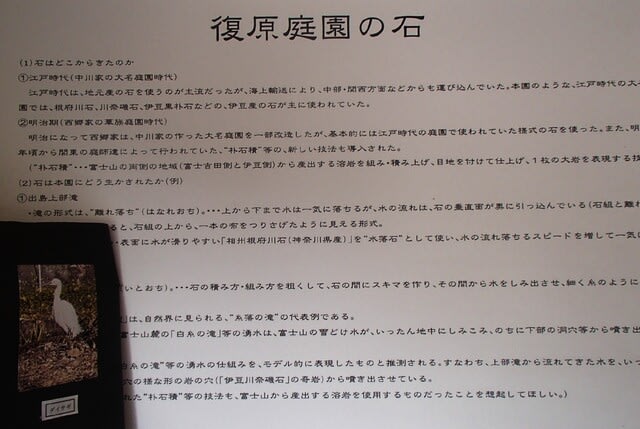2025年6月23日(月)から7月1日(火)まで9日間、横浜・東京などを旅行した。目的は、乗り鉄、史跡見学、グルメなどである。
費用は、基本運賃が、JR名古屋から横浜まで障害者割引で2860円。京急横浜から浅草まで619円。東京から名古屋まで3190円。 宿泊費が、横浜5泊、東京3泊で19073円。平均1泊2384円。以上で基本的な旅費は25742円。
6/23( 月)。名古屋の自宅からJR東海道線に乗車。静岡で途中下車して、静岡鉄道に乗ろうとしたが、トラックが橋桁に衝突した事故により浜松で1時間半ほど足止めされた。藤沢で途中下車して14時過ぎに大和で老人ホームにいる兄に面会。

その後、北鎌倉の明月院へ16時過ぎに入苑してあじさいを鑑賞。大船に戻って東海道線横浜駅経由で石川町で下車し、宿へ。なお、大船から根岸線経由で石川町にすると運賃が高くなる。
6/24(火)。横浜市営バス・地下鉄共通1日乗車券420円を地下鉄伊勢崎長者町駅で購入し、8時に弘明寺を見学。京急に乗り換え金沢文庫駅で下車し、金沢文庫で「徒然草展」を鑑賞し、称名寺へ。地下鉄上大岡駅から桜木町駅で下車。市バスに乗り替えて山下公園まで行き、


ホテルニューグランドで日本初の「シーフード・ドリア」と「プリンアラモード」を食べた。5313円。地下鉄でセンター北駅まで行き、弥生遺跡の大塚・歳勝土遺跡を見学後、隣接する横浜市歴史博物館を見学。
16時ごろになり、雨が降りそうな天候になったので、伊勢崎長者町で下車して宿に帰った。
6/25(水)。横浜駅へ行き、東急横浜駅の改札で東急線ワンデーパス(半額)370円の使用方法を尋ねて、スマホでチケットを購入。渋谷駅まで行き、折り返し旧朝倉家住宅を見学しようと、代官山で下車しようとしたら雨が激しく降ってきたので電車に戻って、池上線で池上本門寺を見学。自由が丘に戻って、

喫茶店モンブランでモンブランを食べた。祐天寺で下車して祐天寺を見学。15時ごろ代官山に着き、

旧朝倉家住宅を見学。
16時ごろ不動前駅で下車、5分ほど雨に降られて目黒不動尊を見学。目黒駅で下車し、「とんかつとんき」に着くと、臨時休業だったので、横浜に帰った。
6/26(木)。東急線ワンデーパス370円利用。東横線多摩川駅で下車し、多摩川台公園へ。古墳展示室、亀甲山古墳、多摩川台古墳群を見学。

九品仏駅で下車し、九品仏を見学。

洗足池駅で下車し、洗足池と勝海舟記念館を見学。戸越銀座駅で下車し、後藤蒲鉾店でおでんを食べ、

15時過ぎに戸越銀座温泉に入浴。目黒駅へ行き、「とんかつとんき」でロースかつ定食2500円を食べたのち横浜へ帰った。
6/27(金)。東急線ワンデーパス370円利用。三軒茶屋駅で下車したのち、世田谷線に乗り、終点下高井戸で京王線に乗り換えて芦花公園駅で下車。友人と喫茶店へ。11時30分頃下高井戸駅から宮の坂駅へ。

豪徳寺で猫招きと外人を見る。上町駅で下車し、世田谷区立郷土資料館を見学。

等々力駅で下車、御岳山古墳、等々力不動から等々力渓谷の一部を歩いて、国史跡・野毛大塚古墳を見学して、横浜へ帰った。

6/28(土)。石川町駅付近の高台にある山手イタリア山庭園へ。ガーディナー設計の「外交官の家」とブラフ18番館を見学。京急横浜駅から浅草駅へ。東武浅草駅で「台東・墨田東京下町周遊きっぷ」2日券700円を購入。「東西めぐりん」に乗車。谷中霊園下で下車。

朝倉彫塑館を見学。谷中銀座の「肉のサトー」でメンチを食べる。

千駄木まで歩き、旧安田楠男邸庭園を見学。

日本医科大学まで歩き夏目漱石旧居を見学。北めぐりん(浅草回り)を利用して清川にある宿へ。
6/29(日)。東武下町きっぷ2日目。浅草駅からスカイツリー駅で下車。噴水の出ていない広場を見学。北千住駅から折り返して鐘ヶ淵駅で下車。すみだ百景北西部ルートに乗車。鳩の街通り商店街入口で下車。

幸田露伴旧居蝸牛庵跡を見学。見番通り入口で下車。


長命寺桜餅と言問団子を喫食。1280円。押上駅から曳舟・亀戸駅を折り返して押上駅へ。すみだ百景南部ルートに乗車。刀剣博物館で下車。


旧安田庭園、東京都慰霊堂、東京都復興記念館を見学。押上駅へ戻り、浅草駅へ。待乳山聖天を見学。16時過ぎ、新橋の宿へ向かう。
6/30(月)。東武浅草駅から伊勢崎線に乗車。館林、太田経由で相老駅へ。障害者割引で620円。

わたらせ渓谷鉄道で間藤駅へ。障害者割引で540円。間藤駅から13時32分発の日光市営バスで東武日光駅へ。障害者割引で580円。東武日光駅から浅草駅まで。障害者割引で700円。運賃合計、2440円。新橋の宿へ。
7/1(火)。6時10分頃新橋駅からJR東海道線経由で名古屋駅へ向かう。沼津駅で3分の乗換えに間に合わなかった。清水駅で下車、新清水駅から静岡鉄道で新静岡駅へ。障害者割引で180円。静岡駅で乗車し、掛川駅で下車。

天竜浜名湖鉄道に乗り換えて、新所原駅まで。障害者割引で810円。新所原駅から豊橋駅乗換えで金山駅に15時45分頃着いて大曽根駅へ向かった。