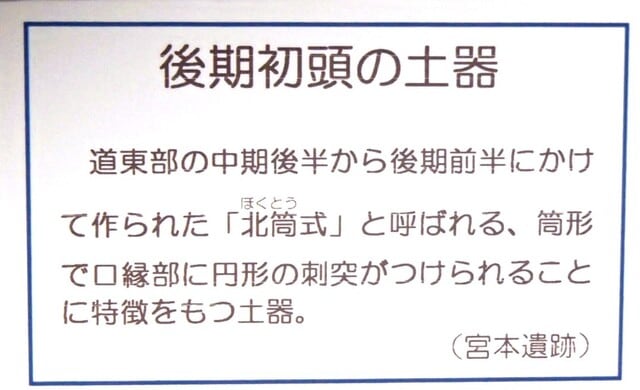観世寺。二本松市安達ケ原。
2024年5月27日(月)。
二本松城跡を見学後、安達ヶ原の鬼婆伝説の地(黒塚・岩屋)へ向かった。

黒塚は、安達ヶ原(阿武隈川東岸の称)に棲み、人を喰らっていたという鬼婆の墓のことである。

近くの観世寺(入場料が必要)には鬼婆が住んでいたという岩屋がある。
黒塚付近には堤防があるため、近くのふるさと村の駐車場から徒歩で見学することが推奨されている。
16時50分ごろ、観世寺裏の駐車場に着いて、寺正面の受付に行くと、16時閉門、入場料400円、と書いてあった。16時閉門は早すぎるし、岩屋を見るために400円は高すぎる。一帯は丘になっているので、坂道から境内を覗いてみたりした。

横の家の人に尋ねても要領を得ない。周囲の環境さえ分かればいいので、諦めた。黒塚は川の方向へ行けば見学できるようだが、すっかり忘れてしまった。
能の『黒塚』、長唄・歌舞伎舞踊の『安達ヶ原』、歌舞伎・浄瑠璃の『奥州安達原』もこの黒塚の鬼婆伝説に基づく。
昔、京都の公卿屋敷に「岩手」という名の乳母がいて、姫を手塩にかけて育てていました。その姫が重い病気にかかったので易者にきいてみると「妊婦の生き肝をのませれば治る」ということでした。そこで岩手は生き肝を求めて旅に出て、安達ケ原の岩屋まで足をのばしました。
木枯らしの吹く晩秋の夕暮れ時、岩手が住まいにしていた岩屋に、生駒之助・恋衣(こいぎぬ)と名のる旅の若夫婦が宿を求めてきました。その夜ふけ、恋衣が急に産気づき、生駒之助は産婆を探しに外に走りました。 この時とばかりに岩手は出刃包丁をふるい、苦しむ恋衣の腹を割き生き肝を取りましたが、恋衣は苦しい息の下から「幼い時京都で別れた母を探して旅をしてきたのに、とうとう会えなかった・・・」と語り息をひきとりました。ふとみると、恋衣はお守り袋を携えていました。それは見覚えのあるお守り袋でした。なんと、恋衣は昔別れた岩手の娘だったのです。気付いた岩手はあまりの驚きに気が狂い鬼と化しました。
以来、宿を求めた旅人を殺し、生き血を吸い、いつとはなしに「安達ケ原の鬼婆」として広く知れわたりました。
このあと、道の駅「安達」へ向かった。

安積山(あさかやま)。郡山市日和田町安積山。安積山公園。
2024年5月28日(火)。
道の駅「安達」で起床。本日は、郡山市・三春町方面の見学である。午後まで雨だった。歌枕の安積山を見学するため、安積山公園へ。安積山は比高差20mほどの丘である。頂上には東屋がある。
安積山は、万葉集や古今和歌集に記された歌の歌枕として知られてきた。万葉集にその影が映ると詠まれた「山ノ井清水」、松尾芭蕉ゆかりの「奥の細道の碑」などがあり、子供用の遊具や散策路、野球場などと併せて公園として整備されている。


万葉集(巻16ー3807)「安積香山 影さへ見ゆる山の井の 浅き心を 吾が思はなくに」(前の安積采女)
現代語訳 「安積山の影までも映す山の泉、それほどに浅い心を私はもたないものを。」
伝えて言うには「葛城王が陸奧国に派遣された時に、国司の接待が甚しくなおざりであった。そこで王には不快な憤懣の表情があった。酒宴の席を設けてもけっして楽しまなかった。その時、采女(うねめ)を務めてさがって来た女性がいた。風流な娘であった。彼女が左の手に盃を持ち右手に水を執って王の膝を叩き、この歌を口ずさんだところ、王の心も和らいで一日中酒宴を楽しんだ」という。
8世紀前半のことという。
郡山の歴史(2014年10月郡山市発行)
わが国最古の和歌集とされる『万葉集』に、この安積山の歌が収められている。同書によれば、葛城王が陸奥国に下向した折、国司のもてなしが不十分であったために王が不機嫌となったが、前采女(さきのうねめ)が機転を利かせてこの歌を詠み、その場を和ませたという。後に『古今和歌集』の序文が、難波津(なにわづ)の歌とともに安積山の歌を取り上げ、「うたのちゝはゝ」と絶賛したため、和歌の中で特別な存在となる。
安積山の歌が詠まれたのは、葛城王が陸奥国へ下向した年である。『万葉集』はその具体的な年次を語らないが、七二四(神亀元)年に陸奥国府の多賀城が完成した際、その「オープニングセレモニー」へ出席のため、葛城王は陸奥国に下向したとの見解がある。歌が詠まれた場所も明記されないが、多賀城と安積郡という二つの考え方がある。また、前采女は歌の作者ではなく、詠者として登場しており、安積山の歌そのものは、これ以前から存在していたとの推定もある。その場合、安積山は都周辺に存在した可能性が高い。大阪府堺市には「浅香山」の地名があり、その候補である。
このように、安積山の歌については不明確な点が少なからずあったが、二〇〇八(平成二十)年五月に公表された滋賀県甲賀市の宮町遺跡出土の木簡は、安積山の歌について多くのことを明らかにした。問題の木簡には、安積山の歌と難波津の歌が、木簡の両面に一首ずつ墨書されており、その年代は七四四~七四五(天平十六~十七)年以前と考えられている。十世紀初頭に成立した『古今和歌集』のはるか以前から、二つの歌はセットで認識されていたのである。このような状況は、安積山の歌が、葛城王の陸奥国下向以前から存在していたとする推定とも符合する。都でよく知られていた和歌を鄙の陸奥国で聞いたからこそ、都人である葛城王は、機嫌を直したのだと考えられる。
歌が詠まれた場所は、葛城王をもてなしたのが陸奥国司であったとすると、陸奥国府の多賀城と考えるのが自然である。しかし、歌の詠まれたのが七二四年とすると、多少の問題が生じる。この年は、石背国(いわせのくに)(中通り・会津地方)と石城国(いわきのくに)(浜通り地方)が、陸奥国へ併合される年である。葛城王をもてなしたのが、廃止される石背もしくは石城国司であった可能性も否定できないからである。安積郡は石背国の管轄であり、石背国府が安積郡に存在していたとすれば、アサカの音の通じる場所で歌が詠まれたことに、葛城王が興を感じたとも想像できる。

「山ノ井清水」。散策路奥の案内標識から下へ降りて、すぐ左の山際にある。
古今和歌集「みちのくの あさかのぬまの花かつみ かつみる人に 恋ひやわたらん」
第十四「恋歌四」、詠み人しらず。
意味。「みちのくの安積の沼の花かつみの名の、かつみというように、かつがつに不満足ながら、ともかくも、ちょっと逢ったばかりの人なのに、心に恋しく思って、永く月日を暮らすことであろうか」
この歌により、「花かつみ」は陸奥国の安積の沼の名物となり、多くの歌が読まれるようになった。
元禄2年5月1日(1689年6月17日)松尾芭蕉と曾良は、「奥の細道」紀行でここ安積山を訪れた。
「安積山」は、「万葉集」や「古今和歌集」に詠まれている歌枕として有名で、芭蕉はここで「「花かつみ」を尋ね歩いたが、残念ながら見つけることはできなかった。
「奥の細道」には、次のように記されている。
「等窮が宅を出て五里斗、檜皮(ひはだ)の宿を離れてあさか山有。路より近し。此あたり沼多し。かつみ刈比もやゝ近うなれば、いづれの草を花かつみとは云ぞと、人々に尋侍れども更知人なし。沼を尋、人にとひ、かつみかつみと尋ねありきて、日は山の端にかゝりぬ。…」

奥の細道の碑
明治9年6月、明治天皇が東北をおとずれたとき、日和田の安積山のふもと・横森新田のご休息所で、「菖蒲(しょうぶ)に似て最(いと)些小(ちいさ)き花」なるヒメシャガを花かつみとして鑑賞した。以後、ヒメシャガが「花かつみ」とされ、昭和49年、郡山市の花に制定された。
このあと、三春町の三春城跡へ向かった。