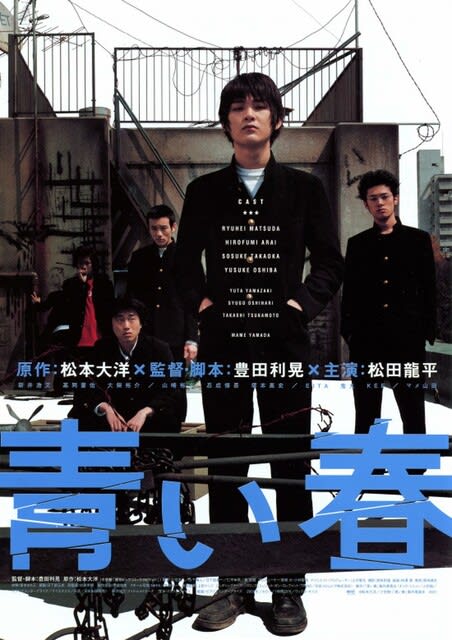関東に梅雨明け宣言が出た次の日から、灼熱。
なんて色気がないんだ。
スイッチをぱちっと押して季節が切り替わったかのような、そっけない感じ。
2013年にオリンピック招致が決まった時から懸念されていた日本の夏の暑さは、
ここ8年でさらに深刻なものとなっている。
私の中で未来というのは決まってブレードランナー的なサイバーパンクの世界か、
Dr.STONEのような森に覆われた世界、あるいは『A.I』みたいに海に沈む世界だったけれど、
最近思うのは全部砂漠になってしまうんじゃないかということ。
地球温暖化がここまで深刻だとは、知らなかった。
ある一定層には周知の事実として共有されている常識だ。
最近読んだSF小説でもやはり未来は砂漠化していた。
先日夏クールの『sonny boy』というアニメが始まった。
キャラクターデザイン江口寿史に主題歌は銀杏ボーイズ。
今の3、40代にとって青春ど真ん中の組み合わせ。
しかも監督は『ワンパンマン』第1期の夏目慎吾監督。
第1話をみたが文学的なSFアニメという印象ですごく好きな感じだ。
最後に銀杏ボーイズの『少年少女』がかかるとみぞおちのあたりがぎゅーっとしまる。
その哀愁はありもしない夏の思い出をかき集める。
暑いのは嫌だけど夏は好きだ。
セミの鳴き声が心のふるさとに潤いを与える。
どこ由来なのかわからない、ありもしない夏の思い出。
でもそれは確かにあるんだな。
なんて色気がないんだ。
スイッチをぱちっと押して季節が切り替わったかのような、そっけない感じ。
2013年にオリンピック招致が決まった時から懸念されていた日本の夏の暑さは、
ここ8年でさらに深刻なものとなっている。
私の中で未来というのは決まってブレードランナー的なサイバーパンクの世界か、
Dr.STONEのような森に覆われた世界、あるいは『A.I』みたいに海に沈む世界だったけれど、
最近思うのは全部砂漠になってしまうんじゃないかということ。
地球温暖化がここまで深刻だとは、知らなかった。
ある一定層には周知の事実として共有されている常識だ。
最近読んだSF小説でもやはり未来は砂漠化していた。
先日夏クールの『sonny boy』というアニメが始まった。
キャラクターデザイン江口寿史に主題歌は銀杏ボーイズ。
今の3、40代にとって青春ど真ん中の組み合わせ。
しかも監督は『ワンパンマン』第1期の夏目慎吾監督。
第1話をみたが文学的なSFアニメという印象ですごく好きな感じだ。
最後に銀杏ボーイズの『少年少女』がかかるとみぞおちのあたりがぎゅーっとしまる。
その哀愁はありもしない夏の思い出をかき集める。
暑いのは嫌だけど夏は好きだ。
セミの鳴き声が心のふるさとに潤いを与える。
どこ由来なのかわからない、ありもしない夏の思い出。
でもそれは確かにあるんだな。