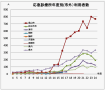昨日、京都府亀岡市議会で、議会が取り組む事業仕分けを調査しました。
理由は、先だって江島カルチャーセンターで開催した事業仕分けの勉強会で講師をして頂いた構想日本の伊藤伸さんが、フェイスブックでも案内して頂いたことがひとつ。また、勉強会に参加頂いた方の声の中に、鈴鹿市議会でも事業仕分けに取り組んで欲しいという話があったからです。ですので、せっかくの機会でもあり、時間の都合もついたことから、急遽傍聴に参加した次第です。

これは資料の一部、取り組みは決算特別委員会の勉強会として行われ、全議員の方々が出席されていました。構想日本からは伊藤さんと、永久寿夫氏、川嶋幸夫氏の3名の方々が参考人として出席されていました。
会場の写真がないのは、亀岡市議会さんの傍聴規定に写真撮影や録音・録画は禁止という項目があったからです。写真が撮れないのは残念でした。
決算委員会ではまず、議会だよりの発行時行を対象にした模擬事務事業評価が行われました。
傍聴の感想ですが、模擬とは言え、議会だより発行事業をいろいろな角度から議論されていたことは、鈴鹿市議会の議会だよりについて考えるヒントがたくさんあったと感じました。
・・・と、これは本題ではありません(^_^;)

議会だより発行事業の説明は議会事務局が行い、事業について議論するのは、事業にも直接携わっている議員の方々ということで、いろいろ微妙かな・・・と思っていましたが、やはり、第三者としての伊藤さんたちの視点や意見が入ることにより、事業について整理の方向が感じられる議論になっていました。議論が深まったことは、予定されていた時間よりも、話の時間が延びていたことが物語っていると思います
後半の論点勉強会では、ごみの減量化・資源化推進事業と、商店街等活性化推進事業が取り上げられていました。このように論点について、まず議員間で話をする取り組みがあれば、議会の審議の質が上がると感じました。
鈴鹿市で取り組むとすればと考えたのですが、やはり、議会に関係する事業についてをまず整理するところからではないかと思います。そこで事業仕分けの観点や、それに基づく論点整理や議論を経験してから、他の一般事務事業に取り組むことがよいと考えます。
いきなり取り組むことは難しいかもしれないので、まず自分の審議から行動を変えてみたいと思います。
理由は、先だって江島カルチャーセンターで開催した事業仕分けの勉強会で講師をして頂いた構想日本の伊藤伸さんが、フェイスブックでも案内して頂いたことがひとつ。また、勉強会に参加頂いた方の声の中に、鈴鹿市議会でも事業仕分けに取り組んで欲しいという話があったからです。ですので、せっかくの機会でもあり、時間の都合もついたことから、急遽傍聴に参加した次第です。

これは資料の一部、取り組みは決算特別委員会の勉強会として行われ、全議員の方々が出席されていました。構想日本からは伊藤さんと、永久寿夫氏、川嶋幸夫氏の3名の方々が参考人として出席されていました。
会場の写真がないのは、亀岡市議会さんの傍聴規定に写真撮影や録音・録画は禁止という項目があったからです。写真が撮れないのは残念でした。
決算委員会ではまず、議会だよりの発行時行を対象にした模擬事務事業評価が行われました。
傍聴の感想ですが、模擬とは言え、議会だより発行事業をいろいろな角度から議論されていたことは、鈴鹿市議会の議会だよりについて考えるヒントがたくさんあったと感じました。
・・・と、これは本題ではありません(^_^;)

議会だより発行事業の説明は議会事務局が行い、事業について議論するのは、事業にも直接携わっている議員の方々ということで、いろいろ微妙かな・・・と思っていましたが、やはり、第三者としての伊藤さんたちの視点や意見が入ることにより、事業について整理の方向が感じられる議論になっていました。議論が深まったことは、予定されていた時間よりも、話の時間が延びていたことが物語っていると思います
後半の論点勉強会では、ごみの減量化・資源化推進事業と、商店街等活性化推進事業が取り上げられていました。このように論点について、まず議員間で話をする取り組みがあれば、議会の審議の質が上がると感じました。
鈴鹿市で取り組むとすればと考えたのですが、やはり、議会に関係する事業についてをまず整理するところからではないかと思います。そこで事業仕分けの観点や、それに基づく論点整理や議論を経験してから、他の一般事務事業に取り組むことがよいと考えます。
いきなり取り組むことは難しいかもしれないので、まず自分の審議から行動を変えてみたいと思います。