【議論に向いてない人】
『批判』を『否定』だと思い込んでいる。
『論証』を『説得』だと勘違いしている。
『反論』を『中傷』と一緒くたにしている。
『意見』を『人格』と結び付けている。
『好き嫌い』を『善悪』に置き換えている。
『向いてない』を『するな』と取り違える。
以上にひとつでも当てはまらないという人を、わたしは見たことも聞いたこともない(笑)
艦娘モデルでモリヤステップ (4:16) nico.ms/sm22212879 #sm22212879 壮観である。・・・と、それはさておき、すでにたいていの艦娘のMMDモデルが作られているということを、この動画で知った。そのうち艦これカテゴリとかもできそうだな
【画像】女子中学生誘拐犯の顔が狂気に満ちていると話題に(アルファルファモザイク) alfalfalfa.com/archives/69168… 右側の画像はVisualStudio2008のインストール画面に出てくるこの人だよなw pic.twitter.com/uqzuhYShF4
仕事やってた頃はマシンが新しくなるたんびにVS2008のインストールをやり直したりしていたわけだが、そうすると毎度この人が出てくるわけで、この思いっきり作り笑いしてる顔がいつ見ても不気味で仕方がなかった
アメリカではこういう不気味な作り笑いのできるやつが優秀なプログラマだとかエンジニアだとかのイメージなのだとすると、とにかく俺は絶対こんなのにはなりたくないと、毎度心に誓わされたものだったw
機能主義とか機能主義批判とかについてすこし視野を広げてみようと思って、さしあたりアンソニー・ギデンスについて調べ(直し)たり読んだりしてみている(社会学の系統に沿って調べたら最初に出てきたというだけで、特にギデンスが重要だと思っているわけでは、現時点ではない)
調べているうちに初めて気づいたことだが、「機能主義」という言葉自体、じつに多様な分野で、まったく多様な意味で用いられている。なんでこれが機能主義なんだと思ってしまうような用法もある
たぶん、わたしのような素人哲学は、最終的には「機能主義」という言葉は(批判のためにであれ)使わない方がいいだろうという気がしはじめている。特定の分野に絞ってみても、その分野の歴史とか内ゲバ(笑)とかの事情が複雑に絡んでいて、それは、素人にはどうでもいいことだからである(笑)
米雇用統計で円相場99円台に(NHKニュース) nhk.jp/N4AM6gIU NY株価も最高値を更新したらしい。いずれにせよ雇用統計を受けて「アメリカの景気が本格的に回復することへの期待が高まっ」たということのようである
ネットに長くいて、しみじみ思うのだけど、憎悪のエネルギーが幻影を産んでいること。人は具体的ではない憎悪をなぜもち得るのか? たぶん、それが自我と密着してるからなのだろう。
前と全然違うことを言うのだが(笑)、いまふと思いついたままを言うと、普通に性的欲求不満だったりするのかもしれない
「なぜ東電が起こした原発事故を東電管内の受益者以外を含めた全国民の税金で救済するんだ!」と気が付いた人は、是非とも「なぜ事故を起こしたのは東電なのに、北海道、東北、北陸、関西、中部、中国、四国、九州が電力不足と値上げに苦しんでツケを払わにゃならんのだ?」とも考えて下さいな。
3DプリンタでブローニングM1911 米企業(CNN) cnn.co.jp/tech/35039669.… ”同社は、この技術は、3Dプリンタが単にホビーストたちがプラスチック製品を大量生産するための物ではなく、まじめな商業利用も可能であることを証明したかったとしている”
そう言えばずっと昔、「バイオ」というカタカナ語がまだ珍しかったくらいの時代に、将来はバイオ技術を駆使して任意の化合物を自由自在に合成するシステムとか作れるんじゃないかと「妄想」したことがあった。デスクトップPCくらいのサイズと価格で、その名も「パーソナル・ケミカル・プラント」と
もちろん容易な話であるはずはないが、それこそ「原理的にはまったく自在」であるように思われた(笑)
現実の装置としてはほとんど妄想ではあるにしても、遠い未来にそんな技術が実用化される可能性はあるわけで、逆にそうした技術が実現された未来の方から現在を考えてみるのは愉快なことではあった。そうした技術が実現したら「化学物質に関する表現の自由」ということが真面目に問題になるだろうなと
実際、その萌芽的には現実に一度問題になったことがあったわけである。個人用ではないし、合成できるのも少量だが、化学物質をある程度の自在さで合成する装置ならすでにあって、オウム真理教の連中がそれを使って合成麻薬やら毒ガスやらを作っていたということがあったわけである
サリン事件の後に吉本隆明が「教祖麻原を宗教家として評価する」と言っ(て物議を醸し)たことの方は必ずしもよく理解できなかったのだが、「殺傷の次元を新しくしてしまった」という指摘の方は、わたしにとっては上述の文脈と合わせた上で重要な注目すべき指摘だと思われたことだった
科学とか科学技術とかの進歩は、どういう経路をたどるにせよ、また、どれだけの時間がかかるにせよ、いずれはそういうことが「いつでも誰でもどこででも」(笑)実行可能だというような水準まで人類を導いて行くことは間違いない
そういう未来が個人や小集団のどうしようもない狂気のテロリストだらけの、まるっきり悪夢の世界ではないとすれば、あと何が考えられ、実行されるべきだということになるのか。これは途方もない難問で、しかも科学や科学技術のそれ自身の手にはまったく負えない難問だと思われた
逆に言えば現代の未熟で粗末な技術の段階で、萌芽的な無差別大量殺傷事件を引き起こすことを小集団の規模において可能にしてしまった宗教理念とか教義というのはどういうものであるのか、それは考察と解明に値するものだという意味でなら、吉本の「評価する」云々は十分了解可能な主張だと思った
思ったけど、吉本が本当にそういう文脈で言っているのかどうかは、必ずしもはっきりしなかった(笑)また当時はわたし自身やっと出戻り学部生を卒業できるかどうかの状態で、どう考えても科学の外にあるとしか思えない領域の難問を、その時点で自分で本気で考えてみる気にはならなかった
それで大学院に進んでぼやぼやと研究などやっているうちに起きたのが911だった。集団の規模はやや大きいとしても、これもまた技術的解放と特異な宗教的理念の組み合わせによって生じた事件だ
ある種の特異な宗教的理念に導かれた中小規模の集団(この場合は「アルカイダ」だ)が、その気になればジェット旅客機を超高層ビルに狙って正面衝突させる程度のことは、いつでも可能だというくらいまでは、すでに技術的解放は進んできてしまったということだ










 性・恋愛に関する雑学 @seerged0
性・恋愛に関する雑学 @seerged0 celsius220 @celsius220
celsius220 @celsius220
 finalvent @finalvent
finalvent @finalvent 菊池雅志 @MasashiKikuchi
菊池雅志 @MasashiKikuchi 小谷野敦 @tonton1965
小谷野敦 @tonton1965 美脚コレクション @bikyakukore
美脚コレクション @bikyakukore


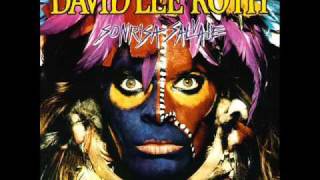
 池田信夫 @ikedanob
池田信夫 @ikedanob ブラック版ワロスwwwBOT @wwww_bot
ブラック版ワロスwwwBOT @wwww_bot ワロスwwwBOT @wwww__BOT_
ワロスwwwBOT @wwww__BOT_
 mollichane2 @mollichane
mollichane2 @mollichane 47NEWS @47news
47NEWS @47news 芦田宏直 @jai_an
芦田宏直 @jai_an *。゜ふわふわtime?♪*゜ @Gazou_bot_
*。゜ふわふわtime?♪*゜ @Gazou_bot_
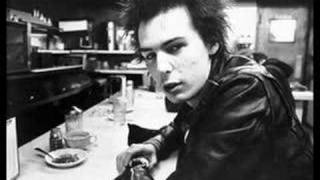
 西原理恵子 @riezo0608
西原理恵子 @riezo0608
 大妖精さんの衝撃セリフ集 @dietyan_bot
大妖精さんの衝撃セリフ集 @dietyan_bot
 ぢゃいける @jaikel
ぢゃいける @jaikel


 ミシェル・フーコー @M_Foucault_jp
ミシェル・フーコー @M_Foucault_jp サルトルbot @jpsartre_bot
サルトルbot @jpsartre_bot 有村悠%C84新刊とらのあなで販売中 @y_arim
有村悠%C84新刊とらのあなで販売中 @y_arim ショーペンハウエルbot @Schopen_bot
ショーペンハウエルbot @Schopen_bot 浄土真宗法語 @18vow
浄土真宗法語 @18vow kamS @kamS_XXX
kamS @kamS_XXX 中西大輔 @daihiko
中西大輔 @daihiko 渡邊芳之 @ynabe39
渡邊芳之 @ynabe39 間違いやすい漢字bot @kanjimiss1st
間違いやすい漢字bot @kanjimiss1st エピクロスbot @Epikouros_bot
エピクロスbot @Epikouros_bot 笑ったら寝ろbot @omorooo_bot1
笑ったら寝ろbot @omorooo_bot1 こかだじぇい @kokada_jnet
こかだじぇい @kokada_jnet


 新稲法子 @niina_noriko
新稲法子 @niina_noriko 抹茶@あやちLOVE♯26 @mattya_314
抹茶@あやちLOVE♯26 @mattya_314
 2chニュース @2chnews_j
2chニュース @2chnews_j Fairy @Fairy46151263
Fairy @Fairy46151263 般若心経 @N_hannyashinkyo
般若心経 @N_hannyashinkyo 積極社交な高等遊民u|v @Lito_tweet
積極社交な高等遊民u|v @Lito_tweet cozi @cozi_roop
cozi @cozi_roop
 レブます @MintTakuma
レブます @MintTakuma


