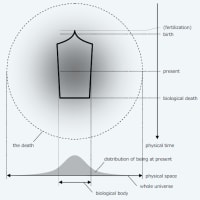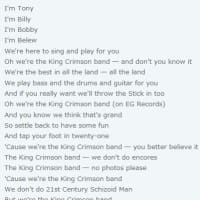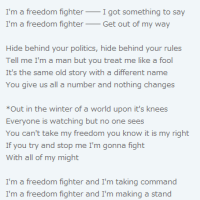4-07 結論(承前)
いやちょっと待て、「非常に精緻な反省は我々にほとんど、あるいはまったく影響しない」とは何事か。とんでもない言い草ではないか。わたしの現在の感じと経験によれば、この考えはほとんど引っ込めざるを得ないというか、棄却せざるを得ない。どうやらわたしは(上述のような)人間理性の多種多様な矛盾と不完璧さから強烈にアテられて取り乱し、アツくなってしまったようである。ためにわたしは、信念と推理のすべてをあっさり退けようとし、どんな意見も確からしさ(probable)やもっともらしさ(likely)において何ら変わるところがないと見るようになってしまったのである。わたしはどこにいるのか。何者なのか。わたしがわたしの存在を導き出すことを引き起こすものは何か。わたしはどんな状態へと還ってゆくのか。わたしは誰の歓心を買おうとするのか。誰の怒りに怯えなければならないのか。わたしを取り囲んでいるものは何か。わたしは誰にどんな影響を及ぼすのか。誰からどんな影響をこうむるのか。すべての問いはわたしを狼狽させる。わたしは自分自身が想像できる限り最もひどい状態にあって、漆黒の闇に四方を囲まれ、金縛りにあってまったく身動きもならなくなっているのだ、などと(中二病さながらに)妄想を始めてしまうのである。
(だが)ここでまったく幸運なことに、理性がこうした(迷いの)雲を吹き払うことができなくなると、(人間本性の)自然それ自体の方からその目的を満たし、かのごときわたしの哲学的な憂鬱やら錯乱やらを癒してくれる。心の緊張(bent)を緩めることによって、つまりあれこれの怪物をことごとく消し去るような気晴らし(avocation)、わたしの感覚の活気ある印象によって、わたしは癒されるのである。わたしは食事をとり、友達とバックギャモン(西洋双六)をやって遊んだり、世間話をしたりする。そうやって何時間かくつろいだ後にさっきの考察に戻ろうとしてみると、(今や)それらはまったくつまらない(cold)、こじつけの(strained)、バカバカしい(ridiculous)へ理屈だと思える。要はすっかりその気が失せてしまっているわけである。
となるとつまり、わたしは日常茶飯のことごとにおいて他の人々とおんなじように生き、語り、行うように、絶対的かつ必然的に決定されている。そういうことなのである。わたしの自然的な傾向、神経やら感情のあれこれのいたるところ、それは世間の一般常識についての怠惰な信念である、しかしそうは言っても、以前の(哲学に向かう)気質の残り火のようなものも感じはする。だったら今すぐあらゆる書物と紙片を火にくべて、哲学的考察のために人生の愉しみを放棄するようなことはもはやすまい、そう決意したいところである。それが現在のわたしを支配する脾臓っぽい状態(splenetic humour※)の中での、わたしのキモチである。わたしは感覚と知ることに服従し、その自然の流れに身を任せてよいのである。いな、任せなければならない。わたしはわたしの懐疑的な気質と原理を、この盲目的な服従において最も完璧に示すのである。(それはひどい話だと言われるかもしれない、)だがそうだからと言って、怠惰や快楽の方へわたしを導く自然の流れに逆らおうとしなければならないものであろうか。人や社会と交わること、それはとっても素敵なことではないのか。あるところから先では身を引かなければならないのだろうか。また、苦痛を覚えながらも努力を怠らないという、そうした分別のありよう(reasonableness)などで満足するわけにはいかないとか、そうこうするうちに真理と確実性とにたどりつけるのだという、その、まずまずそれらしい見通しさえ立たないというときに、それでもわたしは重箱の隅の突き合いやら詭弁やらのためにこの頭脳を苛まなければならないのであろうか。いったいどんな責務があってわたしはこんなことに時間を浪費しなければならないのか。人類への奉仕のためか。私利私欲のためか。どっちにしろこんなことが何の役に立つというのか。何もない。何の役にも立ちはしない。あるものが本当は何であるか、そんなことの推理だ信念だなどというのは、つまりわたしのことだが(笑)、そんな奴は愚か者に決まっている。ただ、わたしはわたしの愚かしさが少なくとも自然で快適な愚かしさであってもらいたいのである。わたしはわたしの心の傾きに逆らおうとする、その抵抗にもそれ相応の理由はあるのであろう。だがもうやめよう。これまでほっつき歩いてきたクソ面白くもない僻地だの、ケモノ道だの、そんなところにさまよい入って行くのは、もうたくさんである。
(つづく)
いやちょっと待て、「非常に精緻な反省は我々にほとんど、あるいはまったく影響しない」とは何事か。とんでもない言い草ではないか。わたしの現在の感じと経験によれば、この考えはほとんど引っ込めざるを得ないというか、棄却せざるを得ない。どうやらわたしは(上述のような)人間理性の多種多様な矛盾と不完璧さから強烈にアテられて取り乱し、アツくなってしまったようである。ためにわたしは、信念と推理のすべてをあっさり退けようとし、どんな意見も確からしさ(probable)やもっともらしさ(likely)において何ら変わるところがないと見るようになってしまったのである。わたしはどこにいるのか。何者なのか。わたしがわたしの存在を導き出すことを引き起こすものは何か。わたしはどんな状態へと還ってゆくのか。わたしは誰の歓心を買おうとするのか。誰の怒りに怯えなければならないのか。わたしを取り囲んでいるものは何か。わたしは誰にどんな影響を及ぼすのか。誰からどんな影響をこうむるのか。すべての問いはわたしを狼狽させる。わたしは自分自身が想像できる限り最もひどい状態にあって、漆黒の闇に四方を囲まれ、金縛りにあってまったく身動きもならなくなっているのだ、などと(中二病さながらに)妄想を始めてしまうのである。
(だが)ここでまったく幸運なことに、理性がこうした(迷いの)雲を吹き払うことができなくなると、(人間本性の)自然それ自体の方からその目的を満たし、かのごときわたしの哲学的な憂鬱やら錯乱やらを癒してくれる。心の緊張(bent)を緩めることによって、つまりあれこれの怪物をことごとく消し去るような気晴らし(avocation)、わたしの感覚の活気ある印象によって、わたしは癒されるのである。わたしは食事をとり、友達とバックギャモン(西洋双六)をやって遊んだり、世間話をしたりする。そうやって何時間かくつろいだ後にさっきの考察に戻ろうとしてみると、(今や)それらはまったくつまらない(cold)、こじつけの(strained)、バカバカしい(ridiculous)へ理屈だと思える。要はすっかりその気が失せてしまっているわけである。
となるとつまり、わたしは日常茶飯のことごとにおいて他の人々とおんなじように生き、語り、行うように、絶対的かつ必然的に決定されている。そういうことなのである。わたしの自然的な傾向、神経やら感情のあれこれのいたるところ、それは世間の一般常識についての怠惰な信念である、しかしそうは言っても、以前の(哲学に向かう)気質の残り火のようなものも感じはする。だったら今すぐあらゆる書物と紙片を火にくべて、哲学的考察のために人生の愉しみを放棄するようなことはもはやすまい、そう決意したいところである。それが現在のわたしを支配する脾臓っぽい状態(splenetic humour※)の中での、わたしのキモチである。わたしは感覚と知ることに服従し、その自然の流れに身を任せてよいのである。いな、任せなければならない。わたしはわたしの懐疑的な気質と原理を、この盲目的な服従において最も完璧に示すのである。(それはひどい話だと言われるかもしれない、)だがそうだからと言って、怠惰や快楽の方へわたしを導く自然の流れに逆らおうとしなければならないものであろうか。人や社会と交わること、それはとっても素敵なことではないのか。あるところから先では身を引かなければならないのだろうか。また、苦痛を覚えながらも努力を怠らないという、そうした分別のありよう(reasonableness)などで満足するわけにはいかないとか、そうこうするうちに真理と確実性とにたどりつけるのだという、その、まずまずそれらしい見通しさえ立たないというときに、それでもわたしは重箱の隅の突き合いやら詭弁やらのためにこの頭脳を苛まなければならないのであろうか。いったいどんな責務があってわたしはこんなことに時間を浪費しなければならないのか。人類への奉仕のためか。私利私欲のためか。どっちにしろこんなことが何の役に立つというのか。何もない。何の役にも立ちはしない。あるものが本当は何であるか、そんなことの推理だ信念だなどというのは、つまりわたしのことだが(笑)、そんな奴は愚か者に決まっている。ただ、わたしはわたしの愚かしさが少なくとも自然で快適な愚かしさであってもらいたいのである。わたしはわたしの心の傾きに逆らおうとする、その抵抗にもそれ相応の理由はあるのであろう。だがもうやめよう。これまでほっつき歩いてきたクソ面白くもない僻地だの、ケモノ道だの、そんなところにさまよい入って行くのは、もうたくさんである。
| ※ | 「脾臓っぽい」というのはこの場合「気難しい」「怒りっぽい」「意地悪」というような意味だと辞書にはあるが、よくわからない。この時代の、特にイギリスでは性格や心理状態についての神秘的な体液説が広く信じられていたというか、そもそもhumourという語は、もともとはその体液説でいう「体液」のことだったわけである。生き物の性格とか心理状態は体内諸器官のそれぞれが固有のもとして分泌している体液(humour)の、その多寡や比率や増減に支配されている、たとえば機知に富んだ冗談を飛ばすことも、それに対応する体液(humour)の配分があるのだ、などと考えられていたわけで、その意味だけが現在の「ユーモア」の語に名残りをとどめているわけである。炭素化合物の化学を有機化学(organic chemistry)と呼ぶのが神秘的な生気論の名残りであることと同じである。何にせよ体液説そのものは全体として血液型占いと一向に変わらぬバカ話にすぎない(ついでに言うと、有機化学だけを例外として、「有機」なんちゃらというのはほぼすべてその種の非科学的迷信を根拠としたバカ話である)。ここのところは要するに「あまり思わしくない心理状態」だという程度にとっておいて構わないことであろう。 |
(つづく)