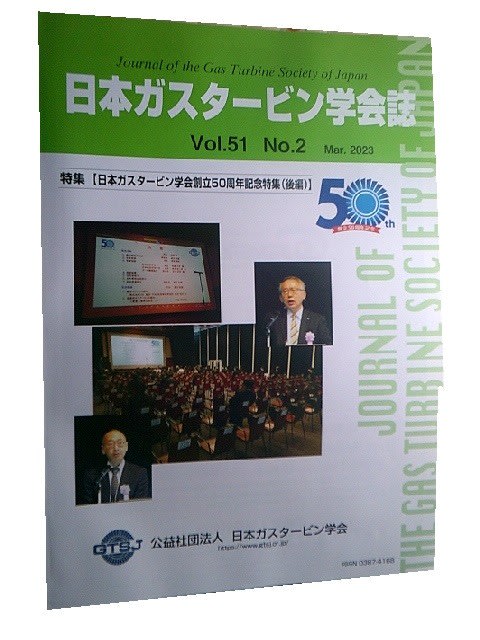調理したりお風呂を沸かしたりするときに使うガスには、都市ガスとLPガスの2種類があるでつ。
そのうち、ガス管を通じて供給される都市ガスの普及率は東京や大阪で高く、80%を超えているでつ。
都市ガスの原料は、メタンを主成分とした天然ガスとLNGが多くを占めているでつ。
いずれのガスも貴重なエネルギー資源でつが、天然ガスに含まれるメタンは、
メタネーションという技術により人工的に合成でき、近年注目を集めているでつ。

メタネーションとは、水素と二酸化炭素を反応させてメタンを合成・製造する技術のこと。
合成したメタンは、空調やキッチン、給湯などの燃料として天然ガスの代わりに利用できるでつ。
その際、二酸化炭素が発生するでつが、これをメタネーションの原料に使用することで、
再び合成メタンを製造できるというメリットがあるでつ。
メタンを合成・製造する技術を開発したのは、フランスの化学者ポール・サバティエ氏。
1911年、水素と二酸化炭素を高温高圧の状態に置いた上でニッケルの触媒を用いると、メタンと水が生成できることを発見。
この化学反応は「サバティエ反応」と呼ばれているでつ。
サバティエ氏はこの功績により、1912年にノーベル化学賞を受賞。
サバティエ氏により製造技術は開発されていたものの、実際にメタンの製造に成功したのは1995年のこと。
メタンをつくる実証プラントを建設。太陽光発電の電力を使い、水を電気分解して取り出した水素を用いて、
世界初の合成メタンを製造。
メタンが燃焼した際に発生した二酸化炭素を装置に戻せば、再生成できる仕組みになっているでつ。
二酸化炭素を回収してから合成メタンの生成、排出されるまでの流れを見ていくと、2つのメリットがあるでつ。
メリット①二酸化炭素の量が増加しない。
メタネーションにおける二酸化炭素に注目して見ると、
発電所や工場から回収された量と、住宅やビル、工場から排出された量が相殺。
その結果、合成メタンを利用しても、全体の二酸化炭素は増加しないでつ。
メリット②環境への負担がない。
メタネーションの原料となる水素は、二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーなどを使って製造できるでつ。
この方法で水素を生成すれば、環境に負担をかけないクリーンなエネルギー生産が可能。
これらの仕組みとメリットから、メタネーションは次世代のエネルギーとして大きな注目を集めているでつ。
メタネーションが必要とされている理由は、日本をはじめ世界において二酸化炭素の排出量をゼロにする「脱炭素化」が
進められていることにあるでつ。
ガスの脱炭素化は比較的実現しやすいと考えられていることが1つ目の理由。
脱炭素化を実現するためには、日本における消費エネルギーの約6割を占める工場や家庭、
業務などから排出される二酸化炭素を抑える必要があるでつ。
工場などでは蒸気加熱、家庭や業務などでは給湯や暖房による排出量が主でつが、これらの場面で多く利用されているのは天然ガス。
そして天然ガスは、石炭や石油に比べて燃焼した際の二酸化炭素の排出量が少ないという特徴があるでつ。
石炭を100とした場合の天然ガスの二酸化炭素排出量は57と、約6割程度…
そのため、工場や家庭、業務などで利用する天然ガスをメタネーションにより供給すれば、
より早く低炭素を実現できるという利点があるでつ。
2つ目は、天然ガスの代わりに合成メタンを利用しても、経済的な負担が少ないこと。
合成・製造したメタンを供給する際には、都市ガスの導管やガス消費機器などの既存のインフラ設備を利用できるでつ。
そのため、費用をかけることなく合成メタンに移行できるメリットがあり、脱炭素化が推進しやすいとされているでつ。
さらに、都市ガスの導管は地下に埋設されていることから、災害時にも安定的な供給が可能。
このことから、メタネーションは「環境適合(Environment)」のほか、「経済効率(Economic Efficiency)」「安定供給(Energy Security)」の
要素があるでつ。
これらは、日本のエネルギー政策の基本方針「3E」に当てはまるでつ。
資源の少ない日本において、メタネーションは有望なエネルギー供給源となるでつ。
3つ目は、メタネーションが地球規模の課題である気候変動問題を解決する手段として期待されていること。
メタネーションは、装置をつくるメーカーやガス業界などで研究開発が積極的に行われているほか、実用化に向けた実証実験も進められているでつ。
2021年度より横浜テクノステーションにてメタネーション実証試験を実施。
再生可能エネルギーから得た電力により水素を製造し、合成メタンの製造・利用を行っているでつ。
CO2ネット・ゼロへの挑戦」を経営ビジョンに掲げ、水素を製造する際のコストを低減するなどの開発を強化。
鉱場内から回収した二酸化炭素を使用して合成メタンを製造する実証実験を、2024年度後半から2025年度にかけて実施すると発表。
製造した合成メタンは、INPEXの都市ガスパイプラインを利用して供給。
この設備の合成メタンの製造能力は、計画段階で約400 Nm3/hであり、現時点では大規模な部類。
基盤技術開発や省エネルギーで合成メタンを製造する触媒技術などを駆使して、本実験を行う予定。
メタネーションは将来有望なエネルギー供給源ですが、デメリットや課題もあるでつ。
1つ目は、メタン製造設備を大型化する必要があること。
メタネーションを商用化するためには、1~6万Nm3/hの製造能力が必要でつが、現時点で世界最大級といわれる装置でも500 Nm3/h。
将来的には、20~100倍の規模に拡大する必要があるでつ。
2つ目は、水素と二酸化炭素を低価格で調達すること。
メタネーションには、設備や運営、生産においてコストがかかるでつ。
現在使われているLNGと同水準の価格にするためには、特に原材料コストを抑える必要があるでつ。
これらの課題の解決に向けて、関係各社や研究機関、学識者、政府が参加する「メタネーション推進官民協議会」が開催。
この協議会では、メタネーションの実現に向けた活発な取り組みが行われているでつ。
政府は2021年、経済と環境の好循環を生み出す産業政策「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の改訂を行ったでつ。
その中でメタネーションは、次世代熱エネルギー産業として成長が期待される重要分野に位置づけられているでつ。
また、メタネーションの年間導入量と供給コストの目標も定められたでつ。
都市ガスの90%が合成メタンに置き換わるという目標が達成されると、2050年には年間約8,000万トンの二酸化炭素が削減できると試算されているでつ。
これは、日本で排出される二酸化炭素の量の約1割に当たり、脱炭素化への大きな一歩となるでつ。
メタネーションとSDGsの関係。
メタネーションは、これら17の目標のうち、目標7エネルギーをみんなにそしてクリーンにと関係があるでつ。
目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」は、すべての人々が、手頃な価格で信頼性が高く、持続可能且つ現代的なエネルギーを
利用できるようにすることが目標。
またこの目標には、クリーンなエネルギーの研究や技術、投資を促進していくことも含まれているでつ。
メタネーションには、製造能力の規模が小さく、コストがかかるなどの課題があるでつ。
それらが解決できれば、二酸化炭素の排出量を増やさないクリーンなエネルギーとして有効。
また、既存の都市ガスのインフラを利用できるので、より効率的なエネルギー供給が実現。
このことから、メタネーションを推進していくことは、持続可能な社会の実現に貢献できるでつ。
メタネーションは、水素と二酸化炭素を反応させてメタンを合成・製造する技術。
合成されたメタンはエネルギーとして使用できるほか、工場などから排出される二酸化炭素を利用して製造できるメリットがあるでつ。
一方で、設備の規模やコストの面での課題もあるでつ。
今は実証実験の段階でつが、これらの課題を解決できれば、メタネーションの本格的な運用も実現するでつ。
脱炭素やカーボンニュートラルの取り組みが世界的に行われている中、日本においても具体的な目標を定めてメタネーションを導入していく考え。
それは同時に、SDGsの目標エネルギーをみんなにそしてクリーンにへの貢献にもつながるでつ。
メタネーションが新しいエネルギーとして、今後普及していくことが期待されるでつ。