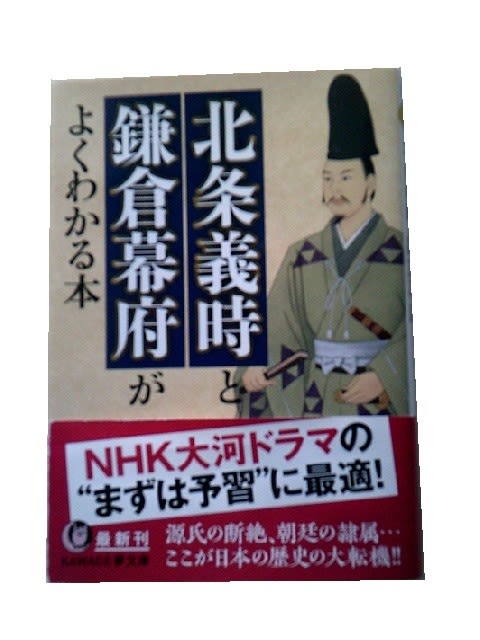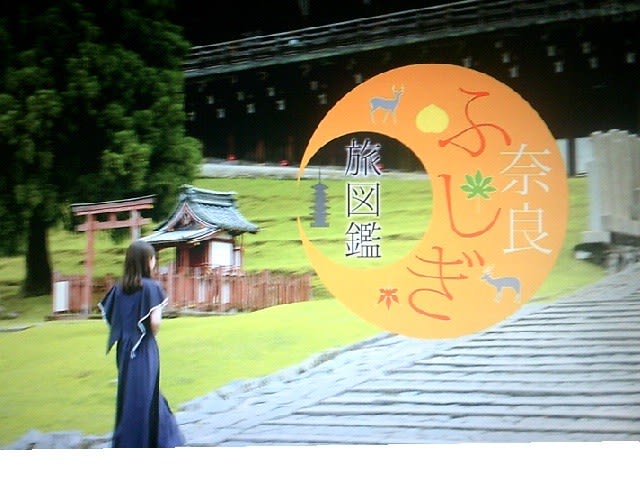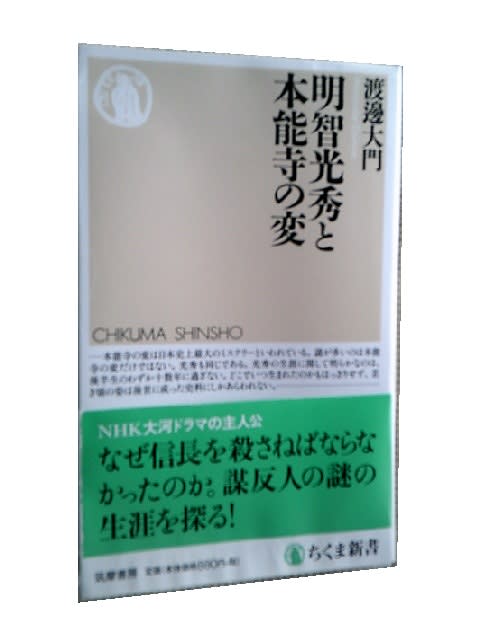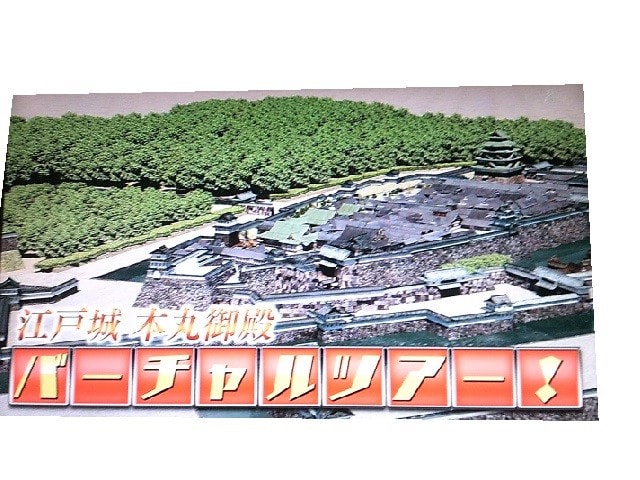なぜ羽柴秀吉は「信長の後継者」になれたのか。
本来であれば後継者に近いのは織田家の筆頭家老だった柴田勝家。
だけど、情報不足などの理由で、光秀討伐に出遅れたのが響いたでつ。
こりが…
この『空白の10日間』が勝家と秀吉の命運を分けることになったでつ。
本能寺の変から明智光秀が討たれた山崎の戦いの時期のこととして注目されてきたのが、
羽柴秀吉による奇跡の「中国大返し」。
秀吉は、本能寺の変の翌日にあたる天正十年(一五八二)六月三日深夜から四日朝までに、
その正確な情報を得ていたでつ。
ただちに対戦していた毛利氏との講和を結ぶや、上方めざして全力で進軍し、
六月十三日の山崎の戦いで快勝したでつ。
この行軍が「奇跡」といわれるのには理由があるでつ。
第一が、変の情報をきわめて早く確保したこと。
光秀の使者が誤って陣所に迷い込んだ、というのはありえないことでつ。
それは、備中高松の古戦場に行けば氷解するでつ。
毛利方の陣所は遥か遠いところにあるため、そのような初歩的なミスを犯すとは
考えがたいからでつ。
もしかりに事実だったとしても、その情報がインテリジェンスであることを、
即座に確信することはできない。
第二が、進軍しながら光秀方勢力の動きを正確に把握して、丹後宮津城の細川藤孝を説得したり、
淡路洲本城の長宗我部方の水軍菅達長を攻撃したりしたことでつ。
細川氏には、親しい家臣を本隊に先行して派遣して秀吉に協力するように説いたでつ。
また淡路の味方勢力に菅氏攻撃を命じたのは、長宗我部氏が摂津に渡って秀吉軍の背後を
襲わないようにするため。
このように、あたかも変以前から光秀の行動を見抜いていたかのような完璧な対応。
光秀は、このような秀吉の動きに関してはほとんどノーマーク。
変以前に毛利氏が推戴していた将軍足利義昭と連携していたからでつ。
副将軍だった毛利氏が、備中高松合戦における形勢逆転のチャンスを無駄にするはずがないと
確信していたでつ。
秀吉方は動くことができないどころか、毛利方に揉み潰されるとみていたのではないか。
光秀が警戒していたのは、大坂城に籠城した織田信孝と副将丹羽長秀でもないでつ。
なぜなら、本能寺の変の情報を得た彼らの軍隊が、その衝撃から雑兵を中心に
逃げ去ってしまったからでつ。
信孝のもとにあった伊勢・伊賀出身の兵士たちは、一目散に逃げ帰ったと言われるでつ。
結局、二人は籠城するしかなかったでつ。
光秀がマークしていたのは、越中出陣中の柴田勝家。
光秀が戦略上抑えておかねばならないのは信長の本拠安土城と近江一国。
天下人の本城を確保することは当然であるでつが、近江には自らの居城坂本城や、
秀吉の長浜城と長秀の佐和山城もあったでつ。
織田家を支える重臣たちの居城を接収しておくことは、戦略上きわめて重要。
勝家は、近江の北隣越前の北庄城に配置されていたでつ。
もし彼が越中から無事に帰還すれば、もっとも至近の強敵になるでつ。
光秀は、それを想定して変前から勝家シフトを敷いていたでつ。
なお上杉氏関係史料には、光秀が本能寺の変の情報をあらかじめ越中魚津城で
知らせていたことを示す書状があるでつ。
六月三日の魚津落城後から山崎の戦いまでの十日間の勝家の動向については、
これまで関係史料がないことからわかなかったでつ。
ところが、近年個人蔵ではあるが関係史料群が発見され勝家の動向が判明したでつ。
新史料からは、勝家の率いた北国軍が魚津城を陥落させ、さらに越中宮崎城を落として越後に侵入し、
上杉景勝の春日山城をめざしていたことが確認されたでつ。
勝家は、六月六日に変の情報を得て退却を開始。
あわせて春日山城に迫っていた信濃の森長可や関東の滝川一益の軍隊も退却することで、
上杉氏は危機を避けることができ、反転攻勢の動きをみせたでつ。
勝家は、与力の越中の佐々成政や能登の前田利家をそれぞれの居城に帰還させ領内を固めさせ、
彼自身は六月九日に北庄に帰城したことが確認されたでつ。
情報を得てからわずか三日間で、直線距離にして約一七〇キロメートルもの道のりを無事に
全軍を帰還させるのに成功したでつ。
これを勝家の「北国大返し」と呼んで、その見事な手腕を評価してもよいでつ。
帰城直後から、勝家は光秀を討つための作戦にとりかかったでつ。
ここに、大問題が浮上。
若狭守護家武田氏と北近江の京極氏とその麾下の国人たちが蜂起して、佐和山城や長浜城を落城させて、
北近江を占拠していたでつ。
当時の若狭は、丹羽長秀が国主となっていたでつが、先述したように彼が家臣たちとともに大坂に籠城したため、
信長に抑圧されていた勢力が息を吹き返したでつ。
しかも当主の武田元明の母は足利義昭の姉であり、正室竜子は京極高次の妹だったでつ。
彼らの迅速で効果的な軍事行動は、やはり光秀あるいは義昭サイドとの接触なしにはありえなかったでつ。
武田・京極両氏の出陣によって、北庄と大坂を結ぶ動脈北国街道が不通になったでつ。
勝家は、長秀重臣溝口氏の若狭高浜城(福井県高浜町)を経由して、大坂城の長秀と家臣の若狭衆に
対する書状を届けようとしたでつ。
だけど、山崎の戦いがあった六月十三日まで、情報不足と背後から武田牢人衆に襲われることを懸念して、
勝家は近江に向けて出陣することができなかったでつ。
光秀方勢力による北近江路の封鎖は、成功していたでつ。
大坂方も勝家方の情報が入らないことには、容易には動けなかったでつ。
膠着こうちゃく状態を打ち破ったのが、秀吉の京都をめざす爆発的な進軍だったでつ。
したがって秀吉の「中国大返し」さえなかったら、上杉氏の反転攻勢や近江で展開していた若狭武田氏や
京極氏の光秀への協力、長宗我部氏の摂津進軍とそれを支える菅氏ら淡路水軍の蠢動、
さらには将軍足利義昭の帰洛への動きも予想され、光秀による室町幕府再興の可能性もあったでつ。
勝家が上方に向けて出陣を開始したのは、結局のところ山崎の戦いが終結した後のことであったでつ。
信長の弔い合戦に間に合わなかったことが、結果的に勝家の政治的な地位をおとしめ、
翌年の賤ヶ岳の戦いにおける敗戦につながったでつ。
新史料によると、勝家は大坂城にいる織田信孝を推戴して、畿内諸地域に散在する織田家臣団が
包囲網を形成して光秀を討ち取ることを構想している。
天正十年六月十日付勝家書状があったでつ。
他の史料では、光秀が近江にいるので、大坂籠城衆をはじめとする反光秀方勢力が相互に連携・協力して、
一刻も早く討ち果たしたい。
そのうえで、信長在世時のように戻したいと語っている勝家書状があるでつ。
このような勝家の意志を、書状で長秀に伝えていたのだが、きわめて常識的な戦略を主張していたでつ。
これに対して秀吉は広く情報を収集したばかりか、情報操作まで試みたでつ。
摂津茨木城主中川清秀に宛てた書状の内容を紹介しよう。信長様と信忠様は、無事切り抜けられました。
近江の膳所に退かれていますと天正十年六月五日付秀吉書状を送っていたでつ。
毛利氏と講和を締結し備中高松から撤退している時期に認めたもので、信長父子の無事を伝えたものであるが、
明らかに虚偽内容でつ。
京都に近く情報を得やすい立場の中川氏に堂々と知らせたのは、日頃から情報通として知られる秀吉の言うことであるから、
あるいはそうなのかもしれないと思わせるためだったでつ。
当時、秀吉は摂津高槻城の高山氏とも交信していたから、情報を攪乱して畿内の大名たちが光秀方に
ならないようにするための作戦だったでつ。
既にこの時期に、秀吉は長浜城までのルートを確保し、使者を往復させていたこともわかっているから、
正確な情報を得たうえでの作戦あることは確実。
なお、柴田勝家が越中方面を平定して、急ぎ上方に向けて進軍しようとしている由、丹羽長秀からの書状で
拝見しました。天正十年六月十日付秀吉書状。
勝家が北庄に帰城した翌日にあたるでつが、この頃明石に到着し、淡路の長宗我部方への軍事対応を
すませた秀吉は、光秀の居場所と軍事行動に関するかなり正確な情報を記しているでつ。
引用はその追伸部分であるが、秀吉が長秀と交信し、勝家の情報も得ていることがわかるでつ。
秀吉の情報収集力と対応能力のすさまじさを感じる書状。
この時期の反光秀陣営のキーマンは、織田信孝。
勝家も秀吉も光秀攻撃の首将として大坂城の信孝をみなしていたからであり、彼の副将として一緒にいる実力者長秀の存在も
クローズアップされたでつ。
だれがこの二人を掌握するのかが、次の天下人の行方を決めたでつ。
この解答は、六月十三日の山崎の戦いの直前に、秀吉と長秀が合流し、信孝の命令を奉じる連署副状を
発給することで出た(六月十三日付筒井順慶宛秀吉・長秀連署副状)でつ。
一時は光秀方を表明した大和郡山城の筒井氏に対して、正式の軍事命令を伝えたでつ。
これまでわからなかった勝家の動きが判明した結果、北近江に展開した武田・京極両氏の軍事行動が効いており、
光秀の勝家シフトが有効だったことが判明。
本能寺の変は完璧だったでつが、その後の動きの拙劣さが長らく指摘されてきた光秀。
だけど、それはあくまでも結果からみた誤解。
まったく予想外の秀吉の「中国大返し」さえなければ、帰洛を遂げた足利義昭を、
光秀や藤孝といった幕府衆はもとより、毛利氏をはじめ上杉氏や長宗我部氏ら諸大名が
支える室町幕府体制の復活もありえたでつ。
本能寺の変から山崎の戦いに至る歴史の流れは、結果的に五十歳以上の光秀や勝家といった
老齢の宿老層が敗れた」でつ。
秀吉に代表される、室町時代以来の古い権威を相対化するかわりに、正確な情報を収集し、
より合理的な判断にもとづく意志決定ができる武将のみが生き残る段階へと突入するでつ。
信長、秀吉が天下を取れたのは、情報戦を制したからでつ。
本来であれば後継者に近いのは織田家の筆頭家老だった柴田勝家。
だけど、情報不足などの理由で、光秀討伐に出遅れたのが響いたでつ。
こりが…
この『空白の10日間』が勝家と秀吉の命運を分けることになったでつ。
本能寺の変から明智光秀が討たれた山崎の戦いの時期のこととして注目されてきたのが、
羽柴秀吉による奇跡の「中国大返し」。
秀吉は、本能寺の変の翌日にあたる天正十年(一五八二)六月三日深夜から四日朝までに、
その正確な情報を得ていたでつ。
ただちに対戦していた毛利氏との講和を結ぶや、上方めざして全力で進軍し、
六月十三日の山崎の戦いで快勝したでつ。
この行軍が「奇跡」といわれるのには理由があるでつ。
第一が、変の情報をきわめて早く確保したこと。
光秀の使者が誤って陣所に迷い込んだ、というのはありえないことでつ。
それは、備中高松の古戦場に行けば氷解するでつ。
毛利方の陣所は遥か遠いところにあるため、そのような初歩的なミスを犯すとは
考えがたいからでつ。
もしかりに事実だったとしても、その情報がインテリジェンスであることを、
即座に確信することはできない。
第二が、進軍しながら光秀方勢力の動きを正確に把握して、丹後宮津城の細川藤孝を説得したり、
淡路洲本城の長宗我部方の水軍菅達長を攻撃したりしたことでつ。
細川氏には、親しい家臣を本隊に先行して派遣して秀吉に協力するように説いたでつ。
また淡路の味方勢力に菅氏攻撃を命じたのは、長宗我部氏が摂津に渡って秀吉軍の背後を
襲わないようにするため。
このように、あたかも変以前から光秀の行動を見抜いていたかのような完璧な対応。
光秀は、このような秀吉の動きに関してはほとんどノーマーク。
変以前に毛利氏が推戴していた将軍足利義昭と連携していたからでつ。
副将軍だった毛利氏が、備中高松合戦における形勢逆転のチャンスを無駄にするはずがないと
確信していたでつ。
秀吉方は動くことができないどころか、毛利方に揉み潰されるとみていたのではないか。
光秀が警戒していたのは、大坂城に籠城した織田信孝と副将丹羽長秀でもないでつ。
なぜなら、本能寺の変の情報を得た彼らの軍隊が、その衝撃から雑兵を中心に
逃げ去ってしまったからでつ。
信孝のもとにあった伊勢・伊賀出身の兵士たちは、一目散に逃げ帰ったと言われるでつ。
結局、二人は籠城するしかなかったでつ。
光秀がマークしていたのは、越中出陣中の柴田勝家。
光秀が戦略上抑えておかねばならないのは信長の本拠安土城と近江一国。
天下人の本城を確保することは当然であるでつが、近江には自らの居城坂本城や、
秀吉の長浜城と長秀の佐和山城もあったでつ。
織田家を支える重臣たちの居城を接収しておくことは、戦略上きわめて重要。
勝家は、近江の北隣越前の北庄城に配置されていたでつ。
もし彼が越中から無事に帰還すれば、もっとも至近の強敵になるでつ。
光秀は、それを想定して変前から勝家シフトを敷いていたでつ。
なお上杉氏関係史料には、光秀が本能寺の変の情報をあらかじめ越中魚津城で
知らせていたことを示す書状があるでつ。
六月三日の魚津落城後から山崎の戦いまでの十日間の勝家の動向については、
これまで関係史料がないことからわかなかったでつ。
ところが、近年個人蔵ではあるが関係史料群が発見され勝家の動向が判明したでつ。
新史料からは、勝家の率いた北国軍が魚津城を陥落させ、さらに越中宮崎城を落として越後に侵入し、
上杉景勝の春日山城をめざしていたことが確認されたでつ。
勝家は、六月六日に変の情報を得て退却を開始。
あわせて春日山城に迫っていた信濃の森長可や関東の滝川一益の軍隊も退却することで、
上杉氏は危機を避けることができ、反転攻勢の動きをみせたでつ。
勝家は、与力の越中の佐々成政や能登の前田利家をそれぞれの居城に帰還させ領内を固めさせ、
彼自身は六月九日に北庄に帰城したことが確認されたでつ。
情報を得てからわずか三日間で、直線距離にして約一七〇キロメートルもの道のりを無事に
全軍を帰還させるのに成功したでつ。
これを勝家の「北国大返し」と呼んで、その見事な手腕を評価してもよいでつ。
帰城直後から、勝家は光秀を討つための作戦にとりかかったでつ。
ここに、大問題が浮上。
若狭守護家武田氏と北近江の京極氏とその麾下の国人たちが蜂起して、佐和山城や長浜城を落城させて、
北近江を占拠していたでつ。
当時の若狭は、丹羽長秀が国主となっていたでつが、先述したように彼が家臣たちとともに大坂に籠城したため、
信長に抑圧されていた勢力が息を吹き返したでつ。
しかも当主の武田元明の母は足利義昭の姉であり、正室竜子は京極高次の妹だったでつ。
彼らの迅速で効果的な軍事行動は、やはり光秀あるいは義昭サイドとの接触なしにはありえなかったでつ。
武田・京極両氏の出陣によって、北庄と大坂を結ぶ動脈北国街道が不通になったでつ。
勝家は、長秀重臣溝口氏の若狭高浜城(福井県高浜町)を経由して、大坂城の長秀と家臣の若狭衆に
対する書状を届けようとしたでつ。
だけど、山崎の戦いがあった六月十三日まで、情報不足と背後から武田牢人衆に襲われることを懸念して、
勝家は近江に向けて出陣することができなかったでつ。
光秀方勢力による北近江路の封鎖は、成功していたでつ。
大坂方も勝家方の情報が入らないことには、容易には動けなかったでつ。
膠着こうちゃく状態を打ち破ったのが、秀吉の京都をめざす爆発的な進軍だったでつ。
したがって秀吉の「中国大返し」さえなかったら、上杉氏の反転攻勢や近江で展開していた若狭武田氏や
京極氏の光秀への協力、長宗我部氏の摂津進軍とそれを支える菅氏ら淡路水軍の蠢動、
さらには将軍足利義昭の帰洛への動きも予想され、光秀による室町幕府再興の可能性もあったでつ。
勝家が上方に向けて出陣を開始したのは、結局のところ山崎の戦いが終結した後のことであったでつ。
信長の弔い合戦に間に合わなかったことが、結果的に勝家の政治的な地位をおとしめ、
翌年の賤ヶ岳の戦いにおける敗戦につながったでつ。
新史料によると、勝家は大坂城にいる織田信孝を推戴して、畿内諸地域に散在する織田家臣団が
包囲網を形成して光秀を討ち取ることを構想している。
天正十年六月十日付勝家書状があったでつ。
他の史料では、光秀が近江にいるので、大坂籠城衆をはじめとする反光秀方勢力が相互に連携・協力して、
一刻も早く討ち果たしたい。
そのうえで、信長在世時のように戻したいと語っている勝家書状があるでつ。
このような勝家の意志を、書状で長秀に伝えていたのだが、きわめて常識的な戦略を主張していたでつ。
これに対して秀吉は広く情報を収集したばかりか、情報操作まで試みたでつ。
摂津茨木城主中川清秀に宛てた書状の内容を紹介しよう。信長様と信忠様は、無事切り抜けられました。
近江の膳所に退かれていますと天正十年六月五日付秀吉書状を送っていたでつ。
毛利氏と講和を締結し備中高松から撤退している時期に認めたもので、信長父子の無事を伝えたものであるが、
明らかに虚偽内容でつ。
京都に近く情報を得やすい立場の中川氏に堂々と知らせたのは、日頃から情報通として知られる秀吉の言うことであるから、
あるいはそうなのかもしれないと思わせるためだったでつ。
当時、秀吉は摂津高槻城の高山氏とも交信していたから、情報を攪乱して畿内の大名たちが光秀方に
ならないようにするための作戦だったでつ。
既にこの時期に、秀吉は長浜城までのルートを確保し、使者を往復させていたこともわかっているから、
正確な情報を得たうえでの作戦あることは確実。
なお、柴田勝家が越中方面を平定して、急ぎ上方に向けて進軍しようとしている由、丹羽長秀からの書状で
拝見しました。天正十年六月十日付秀吉書状。
勝家が北庄に帰城した翌日にあたるでつが、この頃明石に到着し、淡路の長宗我部方への軍事対応を
すませた秀吉は、光秀の居場所と軍事行動に関するかなり正確な情報を記しているでつ。
引用はその追伸部分であるが、秀吉が長秀と交信し、勝家の情報も得ていることがわかるでつ。
秀吉の情報収集力と対応能力のすさまじさを感じる書状。
この時期の反光秀陣営のキーマンは、織田信孝。
勝家も秀吉も光秀攻撃の首将として大坂城の信孝をみなしていたからであり、彼の副将として一緒にいる実力者長秀の存在も
クローズアップされたでつ。
だれがこの二人を掌握するのかが、次の天下人の行方を決めたでつ。
この解答は、六月十三日の山崎の戦いの直前に、秀吉と長秀が合流し、信孝の命令を奉じる連署副状を
発給することで出た(六月十三日付筒井順慶宛秀吉・長秀連署副状)でつ。
一時は光秀方を表明した大和郡山城の筒井氏に対して、正式の軍事命令を伝えたでつ。
これまでわからなかった勝家の動きが判明した結果、北近江に展開した武田・京極両氏の軍事行動が効いており、
光秀の勝家シフトが有効だったことが判明。
本能寺の変は完璧だったでつが、その後の動きの拙劣さが長らく指摘されてきた光秀。
だけど、それはあくまでも結果からみた誤解。
まったく予想外の秀吉の「中国大返し」さえなければ、帰洛を遂げた足利義昭を、
光秀や藤孝といった幕府衆はもとより、毛利氏をはじめ上杉氏や長宗我部氏ら諸大名が
支える室町幕府体制の復活もありえたでつ。
本能寺の変から山崎の戦いに至る歴史の流れは、結果的に五十歳以上の光秀や勝家といった
老齢の宿老層が敗れた」でつ。
秀吉に代表される、室町時代以来の古い権威を相対化するかわりに、正確な情報を収集し、
より合理的な判断にもとづく意志決定ができる武将のみが生き残る段階へと突入するでつ。
信長、秀吉が天下を取れたのは、情報戦を制したからでつ。